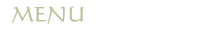NEW ENTRY
[PR]
141 DATE③
時刻は18:30を少し回ったところ
まだまだ話し足りない4人だったが、夕食の時間を考慮し、ユイと菱和は店を出ることにした
帰り際、店先で我妻と苑樹が並んで二人の見送りをする
「君たちに会うの、ほんとに楽しみにしてたんだ。会えて良かった。わざわざ時間作ってくれて、有難うございました」
「いえ、こちらこそ有難うございました!超楽しかったです!また演りたいなぁ、なんて‥へへ」
「勿論。機会があったら、是非また」
「‥やった!」
ユイと苑樹は握手を交わし、互いに感謝の意を表した
「アズサちゃん、真吏ちゃんに宜しくねー」
「へいへい。‥‥有難うございました。連絡します」
「お待ちしてます。気を付けて」
二時間ほどの間に起きた強烈な驚きと感動、興奮、快感を胸に、silvitを後にするユイと菱和
我妻と苑樹の見送りに、ユイは名残惜しそうに何度も後ろを振り返っては手を振った
二人の姿が見えなくなると、我妻と苑樹は店に戻った
「‥‥涼ちゃん。セッティングしてくれてほんとにありがとね。直接彼等と会って話せて良かった」
「いいえー。なまら良いコたちでしょ?」
「うん。若くて、真っ直ぐで、逞しくて‥‥‥腕もセンスもあるし、将来が楽しみだ。他のメンバーにも、早く会いたい」
「ふふ。取材、出来ると良いねぇ」
「うん。‥‥‥‥‥ユイくんてさ、‥‥“OH”に似てるね」
「あ、やっぱそう思う?俺も、出会ったときからずっとそう思ってたんだよねー。あの天然で溌剌とした感じが“OH”そっくりだよね」
「うん。見てて楽しいし、なんか、可愛い」
「駄目駄目そんなこと云っちゃ。ユイくんはアズサちゃんのなんだから」
「‥‥え‥?」
「‥さっきね、アズサちゃんが教えてくれた。あの2人、“そういう”仲なんだってさ」
「そう、か‥‥‥って、別に他意はないよ!フツーに『可愛いな』って思っただけで‥」
「わぁかってるって!‥‥‥‥時に、“ゆきっちゃん”元気してる?」
「‥‥うん。今、ツアー回ってる」
「相変わらず忙しそうだなぁ。‥‥さ、俺らも飯食いに行こっか。その辺の話も訊きたいし」
「うん。ちょっと、呑みたいね」
「おやおや。そんなこと云ってると、ガチでしこたま呑ませちゃうよー?」
「いや、ほんとにちょっとだけ‥‥明日電車乗り遅れたらヤバいし」
「ふふ。っていうか俺も明日は店開けるから呑兵衛んなってる場合じゃないや」
「じゃあ‥ほどほどに、ね」
「そうね。そんじゃま、明日に向けてなんか力つくもん食いますか!」
***
「はー‥‥びっくりしたねー‥」
「ん。かなり想定外だった」
「ほんとね!でも、来て良かった!超楽しかった!ギター弾けたし、ENさんにも会えたし!てか、ENさん俺らの曲完全にコピーしてたね!ゾクゾクしちゃった!」
「しかも“DIG-IN”とか‥‥なまらアツかった。プロに叩いてもらえるなんて光栄だな」
「ほんと!夢みたい!連れてきてくれて、アリガトね!」
「どういたしまして。‥‥さぁて、飯食いに行くか」
「うん!あー、なんか腹減ってきたぁ‥‥うはは、グラタンだぁー!」
菱和の母が作るグラタンを待ち焦がれ、無邪気にはしゃぐユイ
菱和はふ、と口角を上げる
“デート中”に馴染みの店に顔を出した、ただそれだけの話
我妻が今のユイとの関係を予感していたとは、菱和にとってはこちらも想定外だった
別にわざわざ打ち明けることでもないと思っていた
だが、我妻ならば拓真やアタルのように引きはしない───そんな自信も、確実に菱和の心の何処かにはあった
我妻の話だと、以前、ユイの『菱和に対する気持ちを聞いた』とのこと
我妻はその時のユイの感情が“恋”だと断定したわけではないが、菱和から直接話を聞き、『やはり“そう”だったのか』と納得した
“そう”なったと告白しても、何の疑問も抱かなかった
寧ろ喜び、祝福してくれた
いつ、どんなときでも、どんなことがあっても───“男同士の恋愛”すら、“師”は“弟子”を受け入れ、歓迎する
少し年の離れた“友達”の幸せを、心から願っている
ただ、それだけの話だった
「───‥‥‥‥‥」
吐く息が白い
陽はすっかり落ち、行き交う人はほぼ居ない時刻
睦月の風が二人を近付ける
菱和は徐に、ユイに差し出すように手を伸ばした
「‥‥ん、?」
「‥繋ぎたくなった」
「‥‥‥、うん‥‥‥‥、!」
握られた手は、菱和の上着のポケットに仕舞われた
温いポケットの中
重なった手に、ぎゅ、と、力が籠る
早鐘が打ち付けるも、暖かさに頬が綻ぶ
───‥‥‥あったかい
小さな手は無骨で大きな手に包まれ、幸せを感じていた
菱和の実家がある、“あけぼの”と呼ばれる地区の高台
手を繋いだままゆっくりと坂道を上がっていくと、目の前に豪邸が姿を現した
去年の秋頃、この場所で
ユイや拓真をわざと遠ざける為、菱和は嘘を吐いた
ユイと、ユイを取り巻く全てのものを護ることが出来るならばと思い吐いた嘘だったが、その思惑とは裏腹に、深く傷付けてしまった
そのことに、自身も心を傷めた
そして、自分の中にあるユイの存在の大きさに気付かされた
ふと見上げた自宅
“過ち”を思い出し、胸がちくりとする
あのときは、こんな風に過ごせるなんて思っても見なかった
もう、触れることも、会うことも、自分の想いなど届くことはないのだと思っていたから
だけど今、自分の手を握っている小さな手
隣にいる、大切な人
もう、あんな哀しそうな顔はさせない
───二度と、絶対に
「‥‥またあとで」
菱和は名残惜しそうに、ゆるりと手を離した
人気のないところでなければ堂々と手を繋ぐことも出来ない
何とも歯痒いこと
大好きな人、大好きな手
大きくて、優しくて、あったかくて
本当は、ずっと握っていたい
でも、だけど、そんなことは叶わない
自分達は、同性同士
皆が皆、拓真やあっちゃんやリサみたいに受け入れてくれるとは限らない
アズは、ほんとに俺で良いのかな
俺が男でも、良かったのかな
時々、不安になる
アズは優しい、一緒に居られて嬉しい
だけど、でも、俺は───
『またあとで』
ユイは菱和の温もりが逃げないよう、小さな掌をきゅ、と手を握った
140 喫煙所にて
「ね、アズサちゃん」
「‥‥んだよ」
「今日、ユイくんと『デート』って云ってたよね?」
「ああ」
「それってさ、どういう意味合いのもの?」
「‥何が」
「だから、恋人同士がするような、ほんとに“デート”って呼べるものなのか、それともただ単に友達同士で遊び歩くだけのものなのか、どっちなのかなって」
「‥‥‥‥、‥前者」
「‥‥てことは、ユイくんとは“そういう関係”ってこと?」
「‥‥‥‥ん」
「‥あ、そう!そうなの!へぇー‥ふーん‥‥」
「‥‥何だよ」
「別に。仲睦まじいなーと思っただけ。そっかそっか‥‥うんうん」
「‥‥‥、引いたり、しねぇの」
「何で?男同士だから?」
「‥‥‥‥」
「‥‥今更何も驚かないよ。『いつか“そう”なるんじゃないかな』って思ってたから」
「‥は?」
「ほら、いつだったか君ら喧嘩してたときあったでしょ。あのとき、ユイくんがアズサちゃんに対する気持ちを沢山話してくれたんだ。『ああ、これ“恋っぽい”なー』って感じしたの。もしそうだったとしたら『上手くいけば良いな』って、密かに思っちゃったよね。ユイくんはイイ子だし、アズサちゃんもイイ男だもん」
「‥‥‥‥」
「‥‥中には引く人もいるかもしれないけど、俺は引いたりなんてしないよ。アズサちゃんが誰を好きになろうと、俺アズサちゃんのこと大好きだからね。‥あ、勿論“like”の方だよ」
「たりめーだろ、バカ野郎」
「んふふ。‥‥2人がお互いに納得してそういう関係にあるんなら、それはもうとても素敵なことじゃない。大事な“友達”が幸せなら、俺はすごく嬉しい。ただそれだけのことだよ」
「‥‥‥‥」
「‥‥、一つ訊いて良い?」
「‥何」
「何でほんとのこと話してくれたの?幾らでも誤魔化せた筈だよね?」
「‥‥逆に、誤魔化して何の意味があんだよ」
「まぁ、そりゃそうだけど」
「‥‥‥‥‥、相手がお前だから、としか云いようがねぇ」
「おやまぁ。それは嬉しいねぇ」
「‥‥‥‥正直なとこ、“そう”なったことで“ここ”に来づらくなんのだけは避けたいと思ってた。‥‥今思えば杞憂だけど」
「なーに云ってんだか。ほんとに杞憂だね。俺、絶ーーーっ対そんな風にさせない自信、あるよ?」
「‥‥なーに云ってんだか」
「あら、人の台詞パクんないでよ。‥‥でも、“ここ”をそういう風に思ってくれてるんだね」
「‥‥、俺がっていうより、あいつが来られなくなるのが嫌なだけだ。あいつ、“ここ”もお前のことも気に入ってるし。バンドとしても“ここ”使えなくなったら不便だし」
「またまた。アズサちゃんもそうでしょー?」
「‥‥暇潰しと一服と、タダでコーヒー飲める場所」
「もぉ‥‥素直じゃないんだから。『バンドとしても』ってことは、アズサちゃん自身も入ってるでしょ。だから、絶対『来づらい』思いなんてさせない。ってか、そんなこと考えないでよ。アズサちゃんと俺の仲でしょ」
「‥どんな仲だよ」
「アズサちゃんは俺の愛弟子でしょー!?ほんと可愛くないんだからー!も少し可愛げ持った方が良いよアズサちゃんは!」
「るせ」
「‥‥‥、話してくれて、有難うね」
「‥別に。‥‥っつーか、野次馬根性丸出しだな」
「まぁ‥‥正直なとこはね」
「‥‥やっぱ性格悪りぃ」
「‥嘘嘘!今の嘘!」
「云ってろ」
「‥‥‥‥これからも、気兼ねなく来てよ。バンドとしても、個人的にも‥デートの途中でも。いつでも待ってるから」
「‥‥ん」
139 “Ruby gemstones”
熱を帯びた快楽と興奮の余韻が立ち籠めるBスタ
たった一曲演奏しただけで全員が肩で息をするほどの疲労感に支配され、暫し休憩の時を求める
「───‥‥‥‥涼ちゃん‥‥」
「‥‥はー‥い‥‥‥」
「やっぱり‥‥涼ちゃんの目に狂いはない。サイコーだね」
「で、しょう‥‥ふふふ‥‥」
楽器隊に負けじと全力で喉を酷使しへろへろになっている我妻は、額から汗を垂らす苑樹の言葉に項垂れながらもしたり顔をした
「‥凄いね、君たち‥‥イントロとアウトロ、ソロ、勿論リフも‥‥ポールとビリーみたいに、コンビネーションばっちりだった。とても高校生とは思えない」
「‥はー‥‥有難う、ございます‥」
「‥‥恐縮、です」
苑樹の称賛に応えたくとも、今は言葉が出てこない
天を仰いだり座り込んだりして、身体の震えが治まるのを待つ
2人が落ち着くのを見計らい、苑樹は感想を求めた
「如何でしたでしょうか、お二方?」
「すっっっげぇ楽しかったです!ENさんのドラム、生きてるうちに生で聴けて良かったー!有難うございました!」
「‥‥悶えました。暫くシャッフルが頭から離れなさそうす。‥まだこの辺に残ってる」
ユイは漸く、溌剌と返事をした
菱和も、胸元に触れながら心境を吐露した
“元”とはいえ、巧みの技は未だ健在───アマチュアの自分達とは別次元の、圧倒的なオーラを放つ苑樹のドラム
演奏中、一打一打が確実に心臓を射抜いてくるような、そんな感覚がしていた
その身をもってプロの凄みを肌で感じた2人は、自分達と『演りたい』と申し出てくれたことに謝恩の念を抱き、深く頭を下げた
若さ故か、2人とも然程回復に時間を要さなかった
菱和はともかく、ユイは輪をかけて疲れ知らずだ
未だ興奮冷めやらぬユイと澄まし顔の菱和を見遣り、我妻もニコニコしながら会話に混ざる
「イイ演奏だったね。俺も悶えたよ。苑樹もまだまだ衰えてないな」
「いやー、あんまり気分イイもんだからついつい気合い入っちゃった。暫く叩いてなかったからなぁ‥‥仕事に響きそうだ」
「選曲ミスだったかね?ごめんねー」
「‥‥何を今更」
「アズサちゃあん!ごめんねってば!2人が『MR.BIG好き』だって話したら『どうせ演るなら激しいのにしようか』ってつい盛り上がっちゃってさー」
「全然!ほんと、楽しかったです!ソロんとこなんか超ヤバかった!店長のヴォーカルも、サイコーだったね!」
「いやいや!本職には程遠いレベルで‥‥俺がヴォーカルで何だか逆に申し訳なくなっちゃった」
「‥そんなん云うくらいなら最初からてめぇがベース弾いてりゃ良かったじゃねぇか」
「あら、そんなことしたらアズサちゃんが歌うことになっちゃうじゃーん?それでも良かったの?」
「何でそうなんだよ、ざけんな」
「俺はそれでも良かったなー、アズもイイ声だもん!」
「‥‥、あんなん高くて出ねぇ」
菱和はユイと我妻を横目で睨みつつ、被っていたニット帽を脱ぎ捨て髪を掻き上げた
演奏の技術、音、“元プロと演る”というプレッシャーをものともせず、堂々とした態度
ユイは“クソ度胸”と云われるほど肝が座っており、何より愉しむことを最優先にしている
菱和も、我妻に悪態をつくだけの余裕と“愛弟子”と讃えられるほどの技量を兼ね備えている
どれほどの場数を、練習量を重ねてきたのか定かではない
きっと気の遠くなるような時間を費やしてきたのだろうと、苑樹は思った
「やっぱり、生音は良いね。‥‥演ったばっかだけど、もう一曲リクエストしても良いかな」
「マジですか!?嬉しい!!何演りますか!?」
ユイはまた気持ちが昂り、待ち切れないという様子で楽器を構えた
やれやれ、と云わんばかりに、菱和も徐に立ち上がる
苑樹はにこりと笑み、ある曲の一部分を叩いて見せた
散々耳に馴染んだ一節のリズムパターン
その曲を、自分達は誰よりもよく知っている
打ち付けたシンバルを手で押さえて音を消した苑樹が、悠然とした笑みを浮かべた
「───“Haze”の“DIG-IN”を」
「──────‥‥‥‥え‥‥」
先程度肝を抜かれたばかりのユイと菱和は、自分達のレパートリー曲を悠々と叩いた苑樹に更に圧倒された
***
「───苑樹は、ROCK-ON BEATの『Ruby gemstones』っていうコーナーを担当しててね」
「え!マジですか!俺、“ルビジェム”大好きなんです!あれに紹介された動画とかめっちゃ観てます!」
「ほんとに?嬉しいな」
「“アマチュアバンド応援し隊”、ってやつすよね」
「“隊”って云っても、俺一人なんだけど‥‥自分の足で全国各地を回って、“ルビーの原石を発掘する”‥っていうコンセプトでやらせてもらってます」
「‥‥だからロゴが鶴嘴なんすね」
「! そんなとこまで気付いてくれてたんだ。ほんと、有難いなぁ」
「アマチュアでも良いバンドは沢山あるからねー。苑樹はちょっとこだわりがあって、全国津々浦々、小さい箱ばっかり巡ってるんだ。しかも、自費で」
「‥自費!?すげー!!」
「会社から近場の箱だけね。遠方の交通費は経費で行ってる。チケット代分くらいは貢献したくてさ‥‥‥これだけ情報が錯綜してるご時世なのに‥‥だからなのかな、埋もれてしまってる良いバンドがほんとに沢山あるんだ。なかなか芽が出なくてデビュー諦めかけてるとか。それって、何だか凄く『勿体無い』と思ってね。ちゃんと自分の耳で聴いて、老若男女関係なく沢山の人に知って欲しいと思うバンドを記事にしてます」
「そうだったんだ‥‥なんか、感動しちゃった!」
「‥俺の独断と偏見で、だけどね」
スタジオから事務所に場所を移した4人は、苑樹の職業について談笑に耽る
“ルビジェム”の愛称で親しまれているコーナーの由来やコンセプト、想いの丈を担当者から直々に聞き、ユイと菱和は興味深そうな顔で頻りに頷いていた
「‥‥それでね、是非Hazeをルビジェムで紹介させて欲しいと思ってるんだ」
今日は、何という日なのだろう
silvitに来てからというもの、驚きの連続ばかりだ
苑樹の言葉の意味をいまいち飲み込めない
ユイと菱和はぽかんとし、何度か目を瞬かせた
「──────‥‥‥‥‥‥」
「ちょっと、お2人さん。固まっちゃってるけど、大丈夫?」
我妻の呼び掛けに漸く我に返るも、ユイは怪訝そうに菱和の服の袖を引っ張った
「‥‥‥‥だって‥ねぇ‥‥」
「‥‥すいません。俺らを『雑誌に掲載させてくれる』、ってことで合ってますか」
「うん。合ってる。是非、お願いしたいです」
不安げな2人を他所に、苑樹はにこりと笑った
「ちょうど3日くらい前に『この辺の箱回る予定』って連絡受けててね、わざわざウチに顔出してくれたんだ」
我妻は追加の飲み物を持ってきて、デスクに置いた
「‥‥元々、ネタ集めの為に涼ちゃんにはちょいちょい探り入れてて、君たちのことは結構前から教えてもらってたんだ。でも、なかなか時間取れなくて‥‥いつか絶対会える機会を作ろうと思って、せめてそれまでは送ってもらった音源聴いてよう、って。ほんと、覚えちゃうくらい沢山聴きました」
「だから“DIG-IN”も難なく叩けちゃった、ってワケ。‥‥で、どうせ会うならセッションしちゃえーー!‥ってなノリでね」
「すいません、折角2人で遊んでるところ水差しちゃって‥‥」
「‥いえ、それは全然。どうせこいつの悪乗りすよね」
「そんなこと云ってー。楽しかったでしょー?」
「‥‥あのベース、マジでどうにかしちまうぞ」
「ぁああ、それはもう、勘弁、して‥‥」
『あの2人なら、きっと断らない。例えアズサちゃんが嫌がっても、ユイくんは乗ってくれる筈』
そんな風にでも伝えていたのだろうか
話の後半はほぼ我妻の悪乗りなのだろうと思い、菱和は睨みをきかせた
そんな態度をとってみても、何だかんだと云いつつ菱和もベースを弾き通した
それも見越した上での悪乗りだったのだろう、そこはかとなく師弟愛を感じた苑樹はくすくす笑った
「涼ちゃんの云う通り、『会えるなら生で聴きたい』と思ってたから。付き合ってくれてほんとに有難う。実際の音聴いて、益々記事にしたくなりました。‥‥ルビジェムの件、是非前向きに考えて欲しいです」
向き直り、改めて雑誌掲載の意向を2人に問う
ユイは、目を丸くしたままだった
毎月楽しみにしている、お気に入りの雑誌のお気に入りのコーナー
そこに自分達が掲載されるという、俄には信じ難い現実
「‥‥俺らが、雑誌に載る‥‥‥‥全然、実感が、ない‥‥」
「‥奇想天外過ぎる話だな‥‥」
「うん‥‥‥‥それに、あの‥‥俺ら、全然ルビジェムに載るようなレベルじゃ‥」
「そんなことないです」
苑樹は首を横に振り、ユイの言葉を打ち消した
「何度も聴いたけど、君たちのバンドは、曲の雰囲気も演奏の技術もとても素晴らしいと思う。君たちは、まさに“原石”。磨き抜けば絶対に“光る”。もっと自信を持ってください」
元プロから賜ったその一言が、ユイの心にずしりと響く
まだまだ技術は荒削り、音作りも研究中
愉しむ気持ちだけは常に持ち続けているが、そこに実力と自信が伴っているかと云われればそれはまた別の話だった
だが、自分が積み重ねてきたものを評価してくれる人物がいる
沢山の原石を発掘してきた人物のお眼鏡に敵った───それだけでも、音楽に向き合ってきた時間と自分の腕が報われるような気がした
「ふふ‥‥ほーんと、ユイくんは素直でイイ子だね。俺も、もっと自信持って良いと思うな。あれだけ堂々と演奏出来るんだし、もっと胸張って欲しい。勿論、アズサちゃんもね」
我妻と苑樹の称賛と督励が、胸に沁みる
ユイは堪らず、はにかんだ
菱和はユイの様子を見て、その頭をぐしゃぐしゃと撫でた
軽く息を吐き、苑樹を見据える
「‥‥凄げぇ有難いお話ですけど‥‥‥他のメンバーに相談してからで良いですか。俺らの一存じゃ決めらんないす」
「そうだよね‥‥こんな大事な話‥皆で話し合わなきゃ」
「勿論。バンドで話し合って決めてください。結論は急がないから‥‥‥‥名刺の裏に携帯の番号書いてあるので、話がまとまり次第、いつでも連絡ください」
物柔らかに笑んだ苑樹
先程ドラムをドカドカしばき倒していた人間と同一人物とは思えないほど、穏和な笑みだった
138 「Bottoms up, down the hatch! It's time to start all over again!」
「暫く弾いてないから、ちょっと緊張してきた」
「んなこと云ってる割に、めっちゃ愉しそうな顔してっけど」
「あ、そう?バレた?」
「なまら顔に出てる」
「へへ‥‥や、楽しみだよ。今、すげぇワクワクしてる」
「‥‥だろうな」
「嫌じゃなか、った?」
「あいつの無茶振りには慣れてる。‥‥それに、ENさんのドラム聴いてみたいしな」
「ふふ、だよね!‥‥取り敢えず、イントロだね」
「だな。暫く弾いてねぇからグダるかもしんねぇけど、勘弁な」
「“アレ”をグダらずに弾ける方がおかしいよ。ポールもビリーも『弾くのしんどい』って云ってたって、なんかの記事で読んだことある。‥あ、でも確かポールは2日3日で弾けるようになったって‥‥2テイクでOK出たとか」
「俺もなんかで読んだことあるわ、それ。ほんと、あのバンド全員バケモンだよな」
「ほんとね!」
「‥‥どんな味すんの?」
「“Colorado Bulldog”の味?コーラだよ。炭酸キツめのやつで、ブッシャアァーーって!」
「『ぶっしゃあぁーー』ね‥‥ま、そんな感じで演りますか」
***
ポール・ギルバート
“光速ギタリスト”の異名をとる彼のギターは超絶テクニカルで、その速弾きは世界最速と謳われる程の実力を誇るプレイヤー
世界中のギターキッズ達を魅了し、苦しめてきた───ユイが最も敬愛するギタリストの一人だ
ポールの光速ギターとも対等に渡り合うスリーフィンガー・ピッキングやライトハンド奏法を駆使した速弾きを始め、多彩なテクニックを擁するベーシスト、ビリー・シーン
齢50を越えた今もなお世界中のベーシストたちの羨望の的であり、菱和も尊敬するプレイヤーだ
ポールとビリー
ロック界における神───或いは“バケモノ”が2名在籍する世界屈指のモンスターバンド、MR.BIG
少しでも彼に近付きたくて、何度も何度も彼らのプレイを観、弾いてきた
無論、“Colorado Bulldog”もそのうちの一つ
ジャズ要素とハードロックが絶妙に組み合わさったゴリゴリのファストナンバーで、とあるギターの解説サイトでは「練習の際には腱鞘炎に十分注意を」と喚起するほど
それもその筈、テンポは驚異の270で初っ端から高速3連のフレーズがあり、シャッフルと共に雪崩のように展開していく
ジャジーなベースと軽快でテクニカルなスティックワークのドラムで構成されるAメロから息つく暇も与えず激しいBメロへと流れ、そのままサビへと続く
ソロパートにはギターとベースのユニゾンと、それぞれの限界すら超越した瞬速のフレーズ
その後ろで刻むドラムは、右足で瞬間的な4連打を叩き出しながら左足でハットペダルを操作するという妙技を繰り出す
最早、全てのパートが超人的───というよりも変態的だ
畏れ多くも“RIOTのドラマー・EN”のドラムで大好きな曲を演奏出来るというまさかの展開
非常に昂ったユイは、武者震いがした
我妻はユイと菱和の愛機に近い機材を選び、既にBスタに楽器をセッティングしていた
「お!店長、用意良いね!」
───あんにゃろう‥‥もし俺らが断ってたらどうする気でいたんだかな
如何にも、我妻の目論見通りに事が運んでいるシチュエーション
感心しギターを手に取るユイに対し、用意周到な“師”に苛ついた菱和は目を細める
2人は楽器を構え、軽く指を慣らしてからイントロやユニゾン部分を合わせ始めた
オリジナルのイントロのギターはレガートとピッキングの組み合わせで、フィンガリングストレッチは常軌を逸するレベルであり、手の小さいユイにとっては至難の業だ
一音一音を正確に弾くことを念頭に置きながら、徐々にスピードを速めていく
続いて、フルピッキングのパターンでも弾いてみるが、視覚的には捉え易くもとにかく速い上に運指は意外と複雑で、何度か躓いてしまう
それでも、めげずに練習を重ねる
菱和もユイのギターに重なるように、高速3連の部分を弾いた
細く長い指先がしなやかに指板の上を滑り、ダイナミックなポジション移動を繰り返す
手の大きさや指の長さは関係ないのだが、やはり大きければ、長ければそれだけ有利ではある
菱和の大きな手を、羨ましく思う
あともう少しだけ手が大きければ───何度もそう思った
でも
『手の大きさなんて関係ねぇんだよ。んなことより、大事なのは“上手くなりてぇ”って気持ちがどんだけでかいかってことだ。手の小さいギタリストなんか、世界中にごまんといるぞ。だから、指の所為にしてねぇで沢山弾きまくれ。んな小せぇ手でも、十分“戦”えんぞ』
嘗て、伸び悩んでいた時期にアタルから掛けられた言葉を思い出す
この身体に生まれついた以上、願っても大きくならないものは仕方がない
指が短くて届かないなら押さえ方を工夫し、その分速くポジション移動すれば良い───手が小さいというハンデは、技術で補うしかないのだ
アタルの言葉は挫折しそうになった心を何度も奮い起たせ、“変態”と揶揄されるほど尋常ではない練習量で培った技術で幾つもの壁を乗り越えてきた
───これが、俺の“武器”
“戦闘態勢”宛ら、何かに取り憑かれたように夢中でピッキングに没頭するユイ
華奢な指先が紡ぎ出す音に付随する底知れぬ“想い” “情熱” “気迫” が、菱和にも伝わっていた
「‥‥なんか、良いね。“若い”なって感じ」
「そうね。全力で、我武者羅だよね」
「‥‥‥‥‥昔を思い出すね」
「‥‥ん」
我妻と苑樹は、スタジオの外で2人の様子を静観していた
爆音を奏でるユイと菱和を、バカみたいに音楽に向き合っていた当時の自分達と重ね合わせる
バカみたいな申し出をバカ素直に聞き入れた2人に恥じぬよう、『バカになって演奏する』と誓い、頃合いを見計らってスタジオの扉を開けた
「俺も少し音出して良いかな」
苑樹はドラムセットの椅子に座り、ミディアムテンポでシャッフルビートを刻み出した
見た目からは“あの”ドラムを叩いていたとは想像もつかないほど、穏やかで温厚そうな相貌の苑樹
シャッフルも、この程度ならば拓真でも余裕で叩けるであろうレベルのものだったが、彼が本気を出すのはきっと“これから”───ユイと菱和は、そう思った
苑樹が身体を慣らしている間、我妻はマイクのスイッチを入れ、咳払いをしつつ声を出す
「ぅんんっ‥あー、あー、あー、あーーー。‥ん。‥‥苑樹、大丈夫?」
「うん。良いよ。お2人は?」
「おっけー!宜しくお願いします!」
「‥‥グダったら責任取れよ」
「そんな怖い顔止めてよ、アズサちゃんもユイくんみたいに笑顔!ね!」
にべも無い態度や表情はいつものこと
それを理解した上で『笑顔』とは、悪乗り以外の何物でもない
我妻のしたり顔に苛ついた菱和は、親指を思い切り弦に叩きつけた
ガシ、という音と同時に、震動を捉えた咆哮がアンプから轟と飛び出てきた
普段は無口で無表情な菱和の、楽器による感情表現───怒りに満ち満ちた重低音に、他の3人は肩を竦ませる
「あ、ちょっと‥一応、そのベース売り物‥‥展示品だから」
「んなもん用意したてめぇが悪りぃんだろ」
「アズサちゃん、もうその辺で止めて。マジで」
「るせぇ」
我妻の言葉を無視し、当て付けたように容赦なく弦をガンガン叩きまくる
その手を止めようとしない様子に我妻は若干青い顔をし始めたが、菱和とて“本気”でやっているわけではなかった
ただの悪ふざけ───『互いに遠慮しない間柄』だということを物語る、菱和と我妻ならではの“戯れ”
無論、それはユイにも苑樹にも伝わっており、微笑ましく感じた2人は堪らずくすくす笑った
「ふふ。そんだけインパクトあるベースなら安心だ。テンポ、これくらいで良いかな」
苑樹はハイハットを踏み、テンポを確認した
恐らくは、原曲の270より少し遅い程度
それでも十分速いが、楽器隊としては有難いこと
3人が頷くと、苑樹は全員に目配せした後にこりと笑み、カウントを取った
ギター、ベース、ドラムの、怒濤の唸りが流れる
どっと押し寄せる音の波に悪寒が走った我妻は、思わず口角を上げた
出だしの高速3連は、一先ずキマった
文字通り、束の間のブレイク
ギターとベースのリフとドラムのシャッフルによるイントロ8小節を見送ると、マイクを構えた我妻が大きく息を吸った
『 ポーカーで絶好調、オンザロックで意気揚々
誰だい、あのいい女?3時に連れ込んでやったぜ、何で1時や2時に送らなかったんだ?
その次に覚えているのは、部屋中を這いずり回ってた記憶
彼女はテーブルの上で踊り、血走った目で月に咆えるぜ
もうフラフラ、完全にコントロール失ってる
そういや俺…ずっと独りじゃねぇか
最後の呼び出し、酒は自宅だ
その次に覚えているのは、地獄のような気分
最後の女の愛撫の感触が残ってる
まるで悪夢だ』
ほぼギターの音がないAメロを、リムの軽快な金属音とジャジーなベースラインが作り出す
菱和と苑樹は目配せしつつリズムをキープし続け、我妻は悠々と歌う
Bメロから激しいノリに変わり、我妻の声にも力が入る
苑樹はトラディショナルグリップに替えてシャッフルを刻み、菱和のベースと並走する
ほぼ出番のなかったAメロへの鬱積をぶちまけるようにユイはギター掻き鳴らし、サビ直前のチョーキングで、無意識に、十二分に一同を煽った
『 野蛮なコロラドブルドッグ
今宵も飲むぜ
首輪を引っ掛けて、鬼のように疾り回れ 』
サビは掛け合いのようになっており、ユイと苑樹も我妻に負けじと声を張り上げる
愈々、ソロのパート
我妻のヴォーカルが途切れると、ユイは一つの高速フレーズを弾き、一オクターブ高音で同じフレーズを弾く
これをもう一度繰り返すのだが、そこでベースが加わりユニゾンとなる
2人は互いに顔を見合わせユニゾンを弾き切った後、すぐに顔を逸らした
限界すら凌駕したソロを迎える、それが合図だった
菱和はイントロからずっと踵でリズムを刻み続けていた
頭も指も身体も脚も、全てがそのリズムに乗り、苑樹のドラムに食らい付く
ギターソロの後半は更に複雑な運指になるも、それぞれのソロが絶妙に重なる
そこには、“変態的”なドラムも存在していた
ドカドカと撃ち抜いてくるバスドラの4連打が、2人のソロに食い込む
がなるシンバルに煽られ、指も気持ちもハイポジションまで一気に昇り詰める
───やべぇ!!指が止まんない!!
気が狂いそうになるほど気持ち良い
瞳の奥に快感が滾る
幾度となく味わってきたそれは、ここにいる全員が感じている
マジでどうにかなっちまいそうだ
身体中の血管が沸騰して爆ぜてしまうような気がする
散々振ったコーラの缶から中身が一気に弾けて泡が噴き出すような───
───『ぶっしゃあぁーー』か。云い得て妙だ
菱和は、ユイの共感覚に共鳴出来ているような気分になった
楽器隊の凄まじいパフォーマンスを無事に聴き終えた我妻は、再びマイクを構える
『 俺の愛しいロリータ
男を食い物にするあの娘は、俺をモーテルNo.6に置き去りにした
…どうだったかって?
骨まで脱がされて、俺の心はバッチリ盗まれたぜ 』
漸く、再び訪れたAメロで昂りは一旦治まったかに思えた
だが、僅かに音が途切れた瞬間に全員が息を吸い込み、Bメロと大サビを迎え撃つべく一気に熱を吐き出した
野蛮で粗暴なコロラドブルドッグは今宵も女漁りに精を出し、月夜に吼える
止まらない
止められない
このまま快楽の絶頂へと
───皆で一緒に、イこう
137 DATE②
たまたま目に入ったコンビニの前で菱和の一服に付き合った後、2人は近くのカフェに入った
時刻はあと15分ほどで15:00になるところであり、“おやつタイム”にちょうど良い時間だった
ユイはマーブルパウンドケーキとミルクティーを、菱和はニューヨークチーズケーキとコーヒーをそれぞれ注文した
会計は1人800円ほど
先程たこ焼き代を出してもらったことをすかさず思い出したユイは財布を取り出そうとしたが、菱和に先手を取られた
「あっちと会計一緒で」
「‥あ!ここは俺が出す!」
「良いから」
「駄目!!」
「良いって。それより席取っといて。結構混んでっから」
菱和の云う通り、2人のように“おやつタイム”を過ごそうと入店する客が多く、店内はそこそこ混み合っていた
「むー‥‥‥‥!」
ユイは納得いかない様子だったが、席を捜しに渋々会計から離れた
菱和は注文した商品を一つのトレーにまとめてもらい、ユイが座る席に向かった
先に座って待っていたユイの表情は、明らかにむくれていた
何がそんなに気に入らないのだろうかと、だが可愛らしくも見え、思わず笑いが込み上げてきた
「‥‥そんなに奢られんの嫌?」
向かい側に座った菱和は、口角を上げつつ早速コーヒーに口をつけた
「‥‥‥‥何で出さしてくんないのさ」
「良いじゃん、別に」
「良くない!だって、2回も奢ってもらった‥!お金使わしてばっかで、申し訳なくて‥ほんと」
「そんなん気にしなくて良いから」
「‥でもさ!なんか、それって、平等じゃないじゃん!」
その言葉が、菱和の胸に引っ掛かった
今日のデートにおける金銭的な負担のウェイトは、明らかに菱和の方が高い
改めて振り返ってみると、確かに平等ではない
菱和は奢るという行為に対して損得勘定などを一切考えず『当たり前のこと』と思っていたが、ユイがむくれる理由がすとんと落ちていった
───ああ、そっか
いつだって対等でありたいと思う、それは互いに同じこと
「───‥‥ん。そうだな。平等じゃねぇな」
「もぉ、次からは絶っっっ対割り勘ね!!」
わざと頬を膨らませ不機嫌モードを続けるユイ
菱和はその頬を、指先でつん、と触った
「‥‥‥‥‥“次”も、あんの」
「‥、へ‥‥」
「‥‥これからも、こうやってデート出来る?」
「!‥‥あ、アズが良ければ、だけど‥‥うん‥」
「‥‥ごめんな、今日んとこは奢られといてくれる?」
「ん‥‥‥。‥ありがと、ね」
「どういたしまして。‥‥これ、一口食う?」
「‥良いの?てか、じゃあ、俺のも」
2人は自分が注文したケーキをフォークで一口分に切り、互いに一口ずつ頂戴した
ケーキの皿が空になり、飲み物もそろそろなくなってくるかという頃
菱和は母親に今晩の献立をリクエストすべく、携帯を取り出した
「そだ。夜、何食うか決めちまうか。何が良い?」
「あ、うん。そだね。えーと‥‥‥」
尋ねられたユイは、“おやつ”で満たされたばかりの胃と相談をする
───和洋中‥‥今までアズは全部作ってくれたよな。パスタはいっつも美味いし、肉じゃがも炒飯も美味かった。あ、あとカレーも。アズの母さんが作るパスタも食べてみたいけど‥‥んーーー‥‥‥‥なんか、ちょっとこってりしたもの食いたいな。チーズがどっさり乗ってる感じの‥‥
「───‥‥じゃあ、グラタン」
「ふーん‥‥‥そっちいったか」
「え、予想外?」
「てっきり和食いくんかなって」
「ってか、和食もめっちゃ捨てがたいんだけどさ。良い、かな」
「ん。連絡入れとくわ」
「ほんとにお邪魔して大丈夫‥?」
「ちゃんと話してあるから心配すんな。‥‥そろそろ我妻んとこ行ってみっか」
「うん!あー、ケーキも紅茶も美味しかったー!ご馳走さまでした!」
今からsilvitに向かえば、16:00には着くという頃合い
2人はカフェを後しに、silvitを目指して歩き出した
***
silvitの看板は“CLOSE”になっていた
2人は店舗の裏に回り、裏口から入店した
「こんにちはー!店長ー!」
ユイの声が響くや否や、我妻が事務所からひょっこりと顔を覗かせた
「お、来た来たぁ。お待ちしてました。どうぞ、こっちこっち」
我妻は手招きをし、2人を事務所の奥へと促した
促されるまま3帖ほどの小さな事務所へ入ると、見慣れない男性の姿があった
どうやら2人が来るまで我妻と談笑していたらしく、デスクの上に缶コーヒーが2つ並んでいた
「じゃーん!早速だけど、彼が会わせたい人!俺の“元バンドメンバー”の‥‥」
「初めまして。折田 苑樹といいます」
そう名乗ると、男性はぺこりと頭を下げた
ユイも菱和も、目を丸くした
我妻の元バンドメンバー、ということは───
「‥‥、‥“RIOT”の、メンバー‥‥!?」
「はい。“RIOT”の元ドラムです。今は、こういう仕事をしてます」
苑樹は、2人に名刺を手渡した
肩書きは2人もよく知っている音楽雑誌の編集記者で、名前の部分に“ORITA SONOKI”とルビが振られていた
思わぬ先客に、ユイと菱和は改めて目を丸くする
「‥“月刊ROCK-ON BEAT 編集部”。‥‥マジで」
「この雑誌‥!俺ら、よく読んでます!」
「そうなんだ。どうも有難う」
苑樹はにこりと笑い、軽く頭を下げた
その後ろから、我妻が肩を抱く
「えーとね、彼のことは“EN”って呼んであげてね」
「“えん”‥‥?」
「ああ、プロ時代の名前なんだ。下の名前の、苑樹の“苑”っていう字が音読みで“エン”だから」
「ふーん‥‥」
菱和は頷き、苑樹と名刺を交互に見遣った
「‥ね、店長のプロのときの名前は?」
「俺?“ZOO”だよ。“アズマ”の“ズ”を『ズー』って伸ばして、“ZOO”」
「‥‥動物園かよ」
「ふふっ、面白い!」
菱和の呆れた溜め息と、ユイの笑いが響く
「んーとね‥‥前から話してた、俺の愛弟子のアズサちゃん。それと、うちの店のお得意さんのユイくん」
「菱和です。断じて“愛弟子”じゃねぇっす」
「店長にはいつもお世話になってます!」
「ふふ。宜しくね」
苑樹はまた、にこりと笑った
我妻は、予め用意しておいた梅サイダーとコーヒーをユイと菱和に手渡す
促された2人は、その辺の椅子に腰掛けた
「菱和くんがベースで、ユイくんがギターだよね。音源は涼ちゃんから聴かして貰いました。ほんと、凄く良いバンドだよね」
「“りょーちゃん”?」
「‥‥こいつの下の名前」
「あ、そっか!そうだったね!」
「うん‥‥でね、苑樹が是非一度『生で音聴きたい』って云うもんだからさ。早速だけど、ちょっとスタジオ行こっか」
「──────は??」
面食らうユイと菱和に対し、のほほんとにこやかにしている我妻と苑樹
「‥‥あの、マジですか?」
「うん。大マジ」
「‥‥‥‥‥」
───ええええええ!!!
───何だそれ
第一線で活躍していた元プロが、アマチュアである自分達の音を聴きたがっている
まさかの申し出に、「一体何の冗談か」と思ってしまう
元とはいえプロ
自分達の演奏が確かな耳を持つ人間の琴線に触れたという、それはとても喜ばしいことだが───
ユイと菱和は互いに顔を見合わせると、黙りこくってしまった
その心中を察したかどうか定かではないが、我妻は2人の表情を窺うと軽く噴き出した
「もう、そんな不安そうな顔しなくても大丈夫だってば!歌は俺が歌うから!ね!」
「‥‥そういう問題じゃねぇ」
───こいつ、何もわかってねぇな‥‥このスカポンタン
菱和は下唇を軽く噛んだ
「ま、肩の力抜いてさ。楽しく演ろうよ。楽曲は、さっき話してたんだけど‥‥“Colorado Bulldog”とかどうかな?」
“Colorado Bulldog”はユイも菱和もお気に入りのバンドの一つ、MR.BIGの楽曲
全てのパートがイントロからガンガン攻めてくる、かなり難易度の高い曲だ
「‥‥‥てめぇ」
「もぉ、そんな睨まないでよ!アズサちゃん、弾けるでしょー?」
「‥‥ムカつく」
菱和には、我妻を睨む気力すら失せ始めていた
反面、ユイは少々乗り気になってきたようで、突然すく、と立ち上がった
「───アズ」
「‥‥ん」
「‥‥‥‥、やって、みない?」
真ん丸の瞳の奥に、一筋の輝きが見えた気がした
こういう状況であっても、只管愉しむ───ユイは、そういう性分だ
───“クソ度胸”、か
ユイに一瞥された菱和は大きな溜め息を吐き、観念したように椅子から立ち上がった
「ちょっと、練習しても良いですか」
「うん、どうぞ。Bスタ、開けてあるから」
ユイはこくりと頷き、菱和と共に事務所を出た
「じゃ、俺らも行こうか」
我妻と苑樹も、2人の後に続いた
136 DATE①
たこ焼きを一パックも食べれば、胃は十分満たされた
たこ焼き屋の店主から貰った駄菓子を食しつつ、二人は繁華街へと戻り、再びぶらつき始めた
「あ」
ふと、ユイが歩みを止める
菱和は振り返り、ユイの視線の先を追った
「‥靴屋?」
「う、うん。ほら‥一足失くなっちゃったから、さ。見てっても良い?」
冬休み前、お気に入りのスニーカーは工藤の手により所在がわからないままになっていた
今履いている靴もお気に入りのうちの一つなのだが、いちばんのお気に入りを失くしてしまったショックはなかなか拭えぬままでいた
言葉尻からも、その様子が窺える
思い出したくはない、重い過去になってしまった───それを上書きし、またお気に入りの一足を捜す腹積もりでいるユイ
───ほんと、健気なやっちゃな
そう思い、菱和はユイの頭を軽くぽん、と叩いた
「気に入ったの、見つかると良いな」
「‥‥うん」
二人は靴屋に入店し、物色を始めた
様々なメーカーを取り扱っている店舗のようで、店内は比較的賑わっていた
素通りしようとしたある一角で、ユイは立ち止まった
つんとした本革の匂いが、鼻を擽った
「あ、これあっちゃんがよく履いてるやつに似てる」
「“REDWING”か。云われてみればあっちゃんっぽいな」
「有名なメーカー、なの?」
「まぁ、そこそこ有名なんじゃね」
「アズはさ、どういうの好き?」
「‥靴?」
「靴、は、ブーツが多いよね?」
「そうだな、ブーツばっか履いてるわ。服はあんまこだわりねぇんだけど、靴はマーチン。今履いてんのも、マーチン」
「マーチン?」
「“Dr.Martens”。あとは、“CHIPPEWA”。‥‥‥あった、これだ。こんなやつ」
件のメーカーのものも店内に並んでおり、菱和は手に取りユイに見せた
「どくたぁ、まーちん‥‥ち、ぺわ‥?‥‥わ、めっちゃアズっぽい!ゴツくてカッコイイなー!」
「‥‥ゴツいのは良いんだけど、重てぇんだよな」
「そうなの?」
「持ってみ」
菱和が見せて寄越したのは、本革製の漆黒のブーツ
ストラップとインステップストラップが施されたスタンダードなエンジニアブーツだった
手渡されると、思いの外重みを感じた
「ぅお、結構ずっしりくるね‥‥足疲れない?」
「慣れ、だな。最初は堅てぇけど、革だから履いてりゃ馴染んでくるし、作りがしっかりしてるから長く履けんだ」
今まで革靴に縁のなかったユイは菱和の話に興味を抱き、頻りに頷いた
ゴツいブーツのコーナーを抜けると、カラフルなスニーカーが並ぶコーナーに出た
革の匂いから、ゴムの臭いへと移り変わる
「───あ、これ」
ふとユイの目に留まったのは、ハイカットのスニーカーだった
柄は、黒とピンクの市松模様だ
ユイの私服や私物は派手な色味や原色のものが多く、男気に入ったものにピンク色が使われていてもさほど気にはしていない様子
今度はユイの好みに興味を惹かれ、菱和はこくん、と首を傾げた
「ふぅん‥‥やっぱそういうのが好きなんだ」
「何だかんだ見て回るけど、結局いっつも“CONVERSE”か“VAN'S”になっちゃうんだよねー。‥‥あ、でもこれも良いなぁ」
ユイがもう一つ気になったのは、ユニオンジャック柄のハイカットスニーカー
こちらは、サイドジップが施されている
「履いてみれば?」
菱和に促され、ユイはその辺にあった椅子に腰掛けた
まずは、最初に気になった市松模様のスニーカーを試着する
軽く歩いてみて、感触を確かめた
「ど、かな」
「こっちも履いてみ」
次に、ユニオンジャックのスニーカーを試着した
先程同様、数歩歩き、履き心地を確かめる
「‥‥どっちが良いと思う?」
「‥俺はこっちのが好き、かな。今日の服に合ってる」
菱和が指差したのは、ユニオンジャック柄のスニーカーだった
「じゃ、これにする!俺もこっちの方が気に入っちゃった!あ、靴紐も見て良い?」
「わざわざ靴紐変えんのか」
「うん、俺の“ポリシー”!結び方も色々あってさ、スニーカーって結構奥深いんだよねぇ」
そう云って、ユイはいそいその靴紐のコーナーへ向かった
菱和はその後をついていき、ユイの横に並んだ
「‥‥‥ねぇ、どれが良いかなぁ。沢山あり過ぎて迷う‥‥」
原色からネオンカラーまで、カラフルな靴紐が並ぶ
唸りながら悩むユイの横で、菱和も靴紐を眺める
ユイが抱えるスニーカーをちらりとを見遣り、徐に靴紐を一つ手に取った
「‥‥‥‥、これとか」
「‥合う!」
「そ?」
菱和が選んだものは、青に黒いラインが入った靴紐だった
ユニオンジャックといえば、赤×青
ユイのイメージに、ぴったりと合致したようだった
お気に入りの靴と紐を携え、早速会計へと進む
サイズを伝え、店員は店の奥から新品の箱を取り出してきた
「箱はどうなさいますか?」
「処分してください。袋だけ貰えますか?」
「かしこまりました」
会計を済ませると、ユイは早速靴を履き替えることにした
椅子に腰掛けるとスニーカーの爪先を自分の方に向けて膝に乗せ、既存の靴紐を外し、購入した青の靴紐を開封する
「ちょっと待っててね」
ユイは鼻唄混じりで青い靴紐を通していった
「‥‥変わった通し方してんな。どうなんの?それ」
「んふふ。見てて!」
縫い物をするように器用に靴紐を通していくユイの姿を、菱和は興味深そうに見入った
一筆書きのように星の形が出来上がっていき、スニーカーの紐は瞬く間に星結びに仕上がった
「‥完成!」
「へぇ‥‥面白いな」
「でしょ!良かったー、ちゃんと全部覚えてた!」
両足とも星結びにすると、スニーカーを履いて紐を軽く整える
立ち上がり、菱和に感想を求めた
「ど、かな」
「似合ってるよ。お前っぽい」
「‥、えへへ‥‥」
「‥良かったな」
菱和は柔らかく笑み、はにかむユイの頭をぽんぽん、と叩いた
「さーて‥‥次どこ行くか」
「なんか小腹空いちゃった。おやつタイムとかどう?」
「じゃあ、どっか店捜すか。‥‥あ。あと、ちょっと一服さしてくんねぇ?」
「それなら、煙草喫えるお店行こ!」
「いいよ。どっかその辺に灰皿あんだろ」
菱和はユイが履いてきた靴が入った袋を提げ、颯爽と出口へ向かう
然り気無く荷物を持ってくれたことに、心が鳴る
菱和の気遣いに感謝しつつ、ユイは靴屋を後にした
135 たこ焼き
クローゼットを漁った割には、結局いつもと何ら変わらない服装になってしまった
ユイは前日の夜に準備しておいた衣類を携え、着替えを始めた
トップスは袖の色が違うラグランのロンTの上に、モノクロのユニオンジャックがプリントされた白いTシャツを合わせた
Tシャツから覗くラグランの袖は、右が青と黒、左が緑と黒のボーダーになっている
ボトムはウエストで選んだ少しダメージの入ったシンプルなジーンズで、やや丈が長く脚にゆとりがある
2回ほどロールアップすると、漸くちょうど良いくらいのサイズだった
上着には、臀部が隠れるほどだぼっとしている大きめの黒いパーカーを羽織った
これはわざとサイズオーバーしたものを選び、毎年寒い時期になると大活躍するお気に入りのパーカーの一つだった
今一度鏡で今日のコーディネートを確認すると、財布と携帯をボトムのポケットに突っ込んで自宅を出た
菱和と待ち合わせをした駅前までの道程
バスに揺られ、車窓から外の景色を眺めた
冬期休暇中ということもあり、ユイと同じような学生らしき少年少女がちらほら
制服だったり私服だったり、将又ジャージにウインドブレーカーだったり、その姿によって外出の目的が何となく掴める
中には、ユイ同様デートに出掛けている人間もいるのだろう
───俺、これからアズとデートなん、だ‥
街並みが移り変わってゆく
バスが駅へと近付いていくのに比例し、心拍数が上がっていく
時刻は11:05
待ち合わせの時間を僅かにオーバーしており、バスを降りたユイは足早に駅前へと向かった
駅構内へと続く階段の麓
その傍らに怠そうに佇む、長身の男の姿が目に入った
───え、あれアズだよ、ね?
それは確かに菱和だった、が、何か普段とは違った雰囲気がし、声を掛けるのを僅かに躊躇う
「───アズ!」
自分の名を呼ぶ声が聞こえると、菱和は徐に顔を上げた
睦月という極寒の時期に、デコルテがざっくり見える薄萌葱色のトップス
その下に黒のロンTを重ね着し、腰にはいつものようにウォレットチェーンを下げ、更に、差し色の赤いチェックのネルシャツが巻かれていた
ダメージ加工が入った濃いグレーのジーンズの裾は、草臥れた8ホールブーツの中にくしゃくしゃに押し込まれていた
菱和もまた、普段の私服と何ら変わらない出で立ちだったが、いつもと大きく違うところが一つだけ───
───アズ、帽子だ
声を掛けるのに躊躇った理由は、これだった
帽子を被る菱和は、今まで見たことがない
だらりとしたニット帽を被っていることによって鬱陶しい前髪が更に鬱陶しく下がり、きちんと前が見えているのか定かではない
「ごめ‥‥待った?」
「いや」
息せき切った様子のユイを柔らかく見ると、菱和はふ、と口角を上げた
「帽子被ってるの、珍しいね。初めて見た」
「‥‥変?」
「んーん、めっちゃ似合う!」
「‥そ。ありがと。‥‥さて、行くか」
徐に歩を進める菱和
いよいよ、菱和との初デートが始まる───ユイは緊張しつつ、その後をついて歩いた
「後で我妻んとこ行って良い?夕べお前と話したあと電話来てさ」
「‥うん、全然良い!店長に会うの、今年初だ!」
「そうだな。なんか、『会わせたい人がいる』っつってたんだよな」
「え、俺行って大丈夫なの‥?」
「お前も『一緒に連れて来い』ってさ。今日、何時までイケる?」
「何時まででもオッケー!」
「そっか。晩飯なんだけどさ、休み前に『実家来る』って話してたろ」
「ああ、うん。‥‥ひょっとして、アズの母さんのご飯!?」
「うん。どう?」
「やった!!嬉しい!超楽しみ!!」
「じゃあ、夕方までに何食いたいか考えといて」
「うん!何がいっかなぁ‥‥ふふ」
「──────‥‥ってさ、そこまでしか考えてなかった」
「え?」
「デートのプラン。‥‥初デートなのに、ごめんな」
───そんなこと
「‥‥‥、寧ろ、そこまで考えててくれてて、嬉しい、よ。俺、『何着てこうか』ってことばっかずっと悩んでたもん‥‥」
「そうなん?‥‥そのパーカー、めんこいな」
「う、うん。お気に入りなんだ」
菱和があれこれ考えていてくれたことを知り、コーディネートばかり気にし過ぎていた自分が恥ずかしくなったユイは、パーカーのポケットに手を突っ込んだ
結局、午前中はノープラン
人混みを掻き分けて街をぶらつき、目に留まった店に適当に入店し、一通り物色して店を出る
この繰り返し
それでも、大好きな人と一緒に過ごす時間に心が躍る
ユイは次第に緊張状態から自分らしさを取り戻し、無邪気に雑貨を手に取り菱和に話し掛ける
菱和は、そんなユイを穏やかに見ていた
12:00を少し過ぎた頃、ユイの案内で件のたこ焼き屋へ向かった
繁華街から少し外れたところにある古びたプレハブ小屋
その傍らに、赤い幟がはためいていた
「はい、いらっしゃい」
「こんにちは!」
ユイは入店し、店主に軽く挨拶をした
狭いプレハブ小屋には、香ばしい香りが立ち込めている
油の跳ねる音が、一気に食欲を唆った
二人並んで、メニュー表に食い入る
「おすすめは、何だっけ」
「これ!出汁!あと、チリソース!」
「んじゃ、それで」
「はいよ。毎度どうも」
菱和はボトムの後ろポケットから財布を取り出し、千円札を店主に手渡した
「あ、お金‥‥」
「要らねぇ」
「駄目だって!割り勘にしなきゃ‥」
「良いって。こんくらい素直に奢られろよ」
前にも似たようなことがあった
いつかの放課後、PANACHEでレモンティーの代金を払おうとしたリサのことを思い出し、菱和はくすっと笑った
疾うに財布を仕舞った菱和を見て申し訳なく思い、ユイは眉間に皺を寄せた
「‥‥んな顔してっと、美味いもんも美味くなくなるぞ」
「むぅー‥‥‥‥。‥‥じゃあ今度、なんか奢らして。絶対だよ」
「ん。わかった」
菱和は、膨れっ面のユイの頭をぐしゃぐしゃと撫でた
「これは、おまけね」
店主はたこ焼きの他に、ペットボトルに入ったホットの緑茶と駄菓子を寄越した
「おっちゃん、いつもありがと!」
「はいよ。狭いけど、ゆっくりしてってね」
プレハブ小屋には、イートインのスペースが設けられている
出来立てのたこ焼きとおまけを受け取ると、二人はそこに座った
パックに入った8個のたこ焼き
湯気が沸き立ち、チリソースとマヨネーズの甘酸っぱい香りが忽ち唾液を分泌させ、踊る鰹節が胃を刺激する
出汁は使い捨ての小さな容器に入っており、ユイは何もかかっていないたこ焼きの上に満遍なく垂らした
「これこれ!めっちゃ美味いから!ね、先食べてみて!」
目をキラキラさせているユイに促され、菱和は割り箸を携え、出汁が染みたたこ焼きを一口囓った
「───あっっつ‥」
「‥ふふっ‥‥どぉ?」
「‥‥‥美味ぇ。こういうの食ったの初めて」
「そっか、良かった!ふわふわでじゅわーってしてて、美味いよね!」
「うん。超美味ぇ。何個でもいけそ。‥‥“明石焼き”って、こんな感じなんかな」
「“あかしやき”?」
「関西のどっかじゃ、出汁に付けて食うんだってさ。食ったことねぇからわかんねぇけど、こういう感じなのかもしんないな」
「へぇー‥‥」
ユイの云う通り、出汁の染みたたこ焼きはふわふわしており、口内はあっという間に出汁の香りに包まれる
続いて、チリソース味のたこ焼きを食す
甘酸っぱく香辛料の刺激もあるスイートチリソースと、相性抜群のマヨネーズが程好く絡む
「チリソースも、合うな」
「でしょでしょー!?良かったぁ、アズの口に合って!」
「今度は、タコパだな」
「たこぱ?」
「実家でたまにやってたんだ。たこ以外にも、チーズとか北寄入れても美味いし。みんなで突いてさ、結構楽しいと思うよ」
拓真やリサやアタル、カナや上田
和やかな雰囲気の中たこ焼き器を囲み、立ち込める香ばしい香りに、美味なたこ焼きを舌鼓───
───そんなの絶対楽し過ぎる
「‥うん!!」
そんな日がいつか必ず来ることを願い、ユイは大きく口を開けてたこ焼きを頬張った
「‥‥マヨ付いてんぞ」
「‥!!」
指摘されるや否や、細く長い指がユイの口元に付いたマヨネーズを拭い去る
指先は真っ直ぐ菱和の口へ向かい、マヨネーズはその口内へと消えていった
こんなこところで“不意打ち”を食らうとは予想だにしていなかったユイは堪らず赤面し、案の定菱和のからかうような笑い声が聴こえた
134 INVITATION
アタルの自宅から帰宅したユイ
辰司が用意していた夕食を食べ、暫し父との談笑を楽しむと、入浴を済ませて自室へ戻った
部屋に入るや否や、ベッドへとダイブした
枕に顔を埋め、溜め息を吐く
「‥はー‥‥‥亜実ちゃんが、結婚かぁ‥‥」
亜実は、ユイにとって姉のような存在だった
拓真の姉である葉子もまた、同じような存在だ
拓真ともアタルとも、幼い頃から家族ぐるみで付き合いがあり、皆一緒に過ごしてきた
実兄の尊のみならず、アタルや亜実、葉子にも可愛がって貰った記憶がある
亜実や葉子も、家族のように大切な存在だ
幼い頃の思い出を幾つも反芻すると、亜実が嫁ぐという事実に、嬉しさも、幾許かの淋しさも感じつつ
心底幸せそうな亜実の顔を思い出し、ユイはふ、と笑んだ
ふと思い立ち、ベッドから起き上がる
携帯を手に取り、誰かに電話を掛け始めた
電話の相手は、菱和だ
『‥‥もしもし』
「あ、アズ。こんばんは」
『ふふふ‥こんばんは』
「‥な、何で笑うんだよ」
『別に』
「‥‥‥‥今、話せる?あの‥‥特に用事はないんだけ、ど‥‥はは」
『ふふ‥‥うん。良いよ』
電話の向こうで、くすくす笑う声が聞こえた
『スーツ、いつ見に行こうか』
「あ、うん。まだ大丈夫かな‥」
『式は5月っつってたよな。それまでに買えば良いと思う。でも、スーツの他にもYシャツとネクタイも買わなきゃなんねぇから、あんま迷うようなら早めの方が良いのかしんねぇけど』
「そー‥‥だね‥俺、優柔不断だからなぁ‥‥」
『まぁ、冠婚葬祭っていつあるかわかんねぇしな。学生のうちは制服あるけど、今のうちに一着くらい持ってても良いと思うよ。‥近いうち、どっか見に行っか』
「うん、宜しく!色々教えて!」
『うん。‥‥っつーか、まだ休みあるしどっか行かね?』
「うん!行こ!PANACHEもまだ行ってないし‥あ、たこ焼も!いつ行く?」
『ああ、いつでも良いよ』
「じゃあ、明日‥‥って、急過ぎるか」
『良いよ、全然。‥‥‥‥したら明日、デートすっか』
「‥‥でー、と‥?」
『うん。初デート、だな』
“デート”
その響きを聴いた途端に、顔が熱くなる
そういえば、まだデートと呼べる行為をしたことがない
第一、菱和とデートをする場面を全く想像できない
剰え、デートに“たこ焼き”という取り合わせ───
───色気もへったくれもないな‥‥
ユイは俯き、黙りこくってしまった
『‥‥ん、なした?』
「や、何でも、ない」
『そ。‥‥迎えに行く?それともどっかで待ち合わせする?デートらしく』
「う‥、‥‥‥‥じゃあ、待ち合わせした、い」
『何時が良い?』
「俺は、何時でも‥‥」
『‥‥んー‥‥‥じゃ、11:00に‥‥駅前集合で』
「わかっ、た」
『‥‥そういや、たこ焼って昼飯に出来そう?』
「う、うん。結構大きいから、一パック食えばお腹一杯になると思う」
『そっか。‥‥じゃあ明日、どこ行きたいか考えといて』
「えーと、うん‥‥‥」
『‥‥あれ。ひょっとして、今からもうキンチョーしてる?』
「や‥そ、なことな‥‥くはない‥‥かな」
『ふふ。そっか』
「あ、アズは、緊張しな、い‥?」
『‥俺?‥‥緊張っていうより、楽しみ。かな』
「そっ‥‥か‥。あんね、俺、ほんとそういうの経験なくて‥」
『何云ってやがる、俺だって初めてだよ』
「‥‥、そ‥」
『嘘じゃねぇって』
「は、はぃ‥‥てか、ほんと、なんかやらかしたらごめん。今のうちに謝っと、く」
『何だそりゃ。‥まぁ、お互い初めてなんだし、肩の力抜いてこ』
「ぅ‥‥うん‥‥‥‥」
『ダイジョブダイジョブ。へーきへーき』
「‥何でそんな余裕なの‥‥」
『さぁ。何でかな』
「‥‥‥、ドキドキしたり、しないの?」
『“ドキドキ”?‥‥してるよ』
「へ‥」
『‥‥‥さ、明日の予定も決まったことだし、早めに寝るべ』
「う、うん。じゃあ‥‥おやすみなさい」
『ん。おやすみ』
「───‥‥‥‥‥“デート”‥‥」
通話が終わると、強烈に印象に残ったワードが思わず口に出た
デートらしいことなど、今までしたことがない
自分が思いつく限りのデートの風景
食事をしたり
映画を観たり
手を繋ぎながら肩を寄せ合って街を歩き
水族館や遊園地などの、所謂“デートスポット”と呼ばれるような場所へ出掛け───
「───ぅわわわ‥」
大好きな人とのデートだ、きっと楽しいだろう
だが、一先ず照れが先行してしまう
現に、菱和と手を繋ぎながら何ともベタなデートをしている様子を想像した途端、ユイは赤面してベッドに突っ伏してしまった
徐に顔を上げ、溜め息を吐く
「‥‥‥こんなんで、大丈夫かなぁ‥‥っていうか、集合時間しか決めてない‥‥‥‥」
かといって、壮大なデートプランなど思い浮かびやしない
デートの相手は菱和
長身ですらりとした菱和と、“ちんちくりん”な自分
並んで歩いていても、周囲から“恋人同士”だとは到底思われないだろう
恐らく菱和は気にはしないだろうが、“ちんちくりん”と一緒に街を歩かせるのが申し訳なく思えてしまう
果たして『菱和が自分とのデートを楽しんでくれるかどうか』と、一抹の不安を抱く
取り敢えず───
───何着てこうかな‥‥
ユイは徐にクローゼットを開け、衣装ケースを漁り出した
***
『お晩ですーアズサちゃあん!あけおめー、ことよろー!』
「‥‥‥ああ」
『何でそんなテンション低いのさー?ことよろだよ、こ・と・よ・ろ!』
「るせぇな。酔ってんのかよ」
「うーん、そうねー。お屠蘇の残り飲んでるーあはははー。アズサちゃんが『ことよろ』って云うまで電話切らないからね」
「はいはい。ことよろ。ほんとしつけぇな。‥で、なんか用かよ」
『あのさぁ、明日うちの店来てくんない?会わせたい人がいるんだよねー』
「‥は?」
『どうせ暇でしょー?』
「暇じゃねぇよ。勝手に暇人認定すんな」
『え、どっか出掛けるの?』
「ユイと“デート”」
「あらま!そうなの!そっか、じゃあユイくんも一緒につれておいでよー!」
「‥‥‥、明日じゃねぇと駄目なのかよ」
『うん。明日じゃないと駄目ー。店は休みにしたから、いつでもおいでねー!』
携帯から規則的な電子音が流れる
「‥‥このボケナス」
我妻への憎まれ口を呟くと、菱和は携帯をソファへと放った
133 MARRIAGE
三箇日が過ぎ、少しずつ正月気分が抜け始めてきた
「冬休み中にPANACHEへ行こうか」「バンドの練習はいつにするか」
ユイは冬休みの残りの日にちを指折り数えては、休みを満喫出来るよう様々な予定を考え出した
そんな折、間もなく仕事始めを迎える尊が地方へと帰らなければならない日がやって来た
尊を空港へと送り届けるべく、辰司は車を出した
助手席には尊が、後部座席には共に見送りにと馳せ参じたアタルがユイと並んで座す
空港はUターンラッシュのピークを迎え、普段以上にごった返していた
軽く昼食を済ませると、尊の搭乗の時間まで観光客に紛れ銘菓や特産物の試食に興じ、巨大な窓のある展望デッキから飛び立つ飛行機を何度も見送った
一頻り観光客気分を味わい、ごたついている搭乗口から尊を見送ると、3人は駐車場へと戻った
帰路の途中、アタルは後部座席から身を乗り出して辰司に声を掛けた
「親父さん、帰りユイ借りてっても良いすか」
「うん?構わないよ」
辰司はにこにことし返事をした
急遽“借りられる”ことになったユイは、首を傾げる
「何?なんかあんの?」
「ああ。ちょっと大事な話あんだ。ひっしーも呼んである」
「え‥そうなの」
「おう。たーもバイト終わったら来るから」
辰司は嬉しそうにハンドルを握っていた
「その面子ってことは、バンドの話かい?」
「ふひひ。そうっす」
「じゃあ、真っ直ぐアタルくんち向かうね。父さんは晩ご飯作って待ってるから」
「うん、有難う!」
新年早々、バンドメンバーが集まる機会が度々訪れている
ユイは、わくわくしながら一ノ瀬宅到着を待ち侘びた
***
「ユイちゃん!明けましておめでとう!」
「亜実ちゃん!久し振りー!」
アタルの自宅には、アタルの父母と、姉の亜実がいた
「もー相変わらずめんこい!元気してた?」
「いらっしゃい。寒かったでしょ」
「ユイくん、ちょっと背伸びたかい」
一ノ瀬家全員が歓迎ムードの中、アタルだけはユイに憐れみの視線を向ける
「親父、やめとけって。何の慰めにもなってねぇ」
「『慰め』って何だよ!ちょっとくらい伸びてるかもしんないじゃん!」
「あんたが“おがり”過ぎなんだよ。何でこんな無駄に成長したかね。頭赤いし、マッチ棒みたい」
アタルの母の放ったその言葉で、ユイと亜実はゲラゲラ笑い出した
「マッチ、棒‥‥‥ぶはっ!!」
「やだ母さん、その表現適格!」
「息子の成長を『無駄』とか云ってんじゃねぇよ!!俺だって好きでこんな背伸びたんじゃねぇっつの!!」
アタルのがなり声を裂くように、チャイムが鳴った
「あ。たっくん来たんじゃない?」
亜実はいそいそと玄関に向かった
「ちわー」
来客は、案の定拓真だった
「たっくん!いらっしゃい‥───」
笑顔で出迎えた亜実は、拓真の後ろに突っ立っている長身の男にビビり、絶句した
呆然としている亜実の後ろから、ユイとアタルがひょこっと顔を覗かせる
「おー、一緒だったのか。ちょうど良かったな」
「拓真、おかえり!いらっしゃいアズ!」
「たまたまそこで会ったんだ。亜実ちゃん、たけにいの代わりにベース弾いてくれてる菱和くん。ひっしー、あっちゃんのお姉さんの亜実さん」
「‥こんにちは」
「───っそ!!!ヤバいマジイケメン!!!」
亜実は、軽く会釈する菱和をガン見した後唐突に叫び声を上げた
「‥ぶはっ!ははは!亜実ちゃん、ひっしー引いちゃってるよ!」
「おま‥何だよそれ。ボキャブラリー0じゃねぇか」
「亜実ちゃん、面白ーい!」
語彙力が崩壊した亜実の言葉に、ユイと拓真とアタルは爆笑
菱和はきょとんとし、全てを静観している
「は‥‥ご、ごめんなさい‥一ノ瀬 亜実です」
「‥ビビらしてすいません。初めまして、菱和です」
我に返り赤面した亜実は軽く頭を下げ、菱和も再度頭を下げた
***
一ノ瀬家に集ったHazeのメンバーは、アタルの部屋に招かれた
先程車内でアタルが云っていた通り、この面子で集まるということはバンド絡みの話題であるということ
「お待たせー」
亜実がマグを5つ盆に乗せ、アタルの部屋に入ってきた
「これ、なに?めっちゃいい匂い!」
「“オルヅォ”っていって、これはチョコレート味の麦茶なの。最近のお気に入りなんだー。牛乳出しだから、ホットチョコレートみたいな味するよ」
亜実は早速マグに口をつけた
“チョコ”と聞き、ユイもマグに手を伸ばし、オルヅォを口に含んだ
予め温められていたようで、ほんのりと香る香ばしさとチョコレートがじんわりと胃に落ちていく
「ほんとだ!チョコの味!甘い!」
「ね、美味しいでしょ?」
ユイと亜実が顔を見合わせオルヅォに舌鼓を打っていると、拓真も菱和にマグを手渡し、自らも携えた
「あっちゃん。今日はバンドの話なんだよね?」
「おう。やっぱ、こいつが居るから不自然か?」
「いや、うん、そうだね」
亜実が飲み物を持ってきてくれただけではなく、そのまま部屋に居座っていることに違和感を覚えた拓真は軽く頭を掻く
そう云われてみれば、と、ユイも首を傾げた
「まぁ、そうだよな。でも、今回の話のメインはこいつなんだ。おい、お前から話せよ」
アタルに促され、皆に注目された亜実は気恥ずかしそうにぽつりと話し出した
「‥‥あのね、実は‥‥‥‥私、今年結婚することになったの」
「え、マジで!!?」
ユイと拓真は身を乗り出した
「ねぇ、いつするの!?」
「5月には式をやろうか、って話してるんだけど」
「わー、すげぇ!亜実ちゃん、おめでとう!」
「‥おめでとうございます」
「やー、ほんとめでたいなー」
「ふふ、有難う!‥それでね、みんなに余興をお願いしたいなーと思って」
「よきょう?」
聞き慣れない言葉に、ユイはきょとんとした
「出し物的なやつ。バンドで何曲か演奏して欲しいな、って」
「ふえぇ、マジか!そんなオファーくるなんて思っても見なかった」
これで、ミーティングのメインが亜実だということに合点がいったメンバー
「この話、受けて良いか?」
「俺は良いよ」
「俺も!」
「問題ないっす」
「ほんと!?有難う!嬉しい!!」
ユイも拓真も菱和も頷き、亜実は嬉しさのあまり満面の笑みを零した
「でもさ、うちのバンド、ウェディングソング無いよ。作るの?」
「まさか。そんな時間ねぇよ。今演ってんのか、なんかカバーするかだな」
「そっか。何が良いかなぁ」
「どかーんと盛り上がるやつ宜しくね!みんなお酒入ってるから、きっと盛り上がると思う!」
「そーそー。しゃしゃって前出てくる奴絶対いるからよ、多少ぐだっても大丈夫」
アタルはニヤニヤしながら煙草に火を点け、灰皿を菱和の近くに置いた
菱和も、軽く頭を下げた後煙草に火を点け始めた
「うははー、楽しみだね!」
「てか、旦那さんはバンドとか大丈夫な人?俺らの曲結構うるさいからさ‥‥」
「全然平気!っていうかね、『余興やってもらえないか』って云い出したの、彼からなの。『弟がバンドやってる』って話したらノリノリでね。音源も聴いてるんだよ!だから、絶対喜ぶ!あーもう何だか待ちきれない!私、電話してくる!」
そう云って、亜実は浮き浮きと部屋から出ていった
「ふふ、亜実ちゃんほんと嬉しそうだね」
「まぁなぁ‥‥もう落ち着いても良い年ではあるしな」
「旦那さんて、どんな人?会ったことあるの?」
「すげぇ温厚な感じ」
「その人、“お義兄さん”になるんだよね?大丈夫なの?」
「俺がっていうより、向こうがだいじょぶかって感じすっけどな。やっぱ最初はビビられたよ」
「え、その髪で会ったの?」
「んなわけねぇだろ。向こうの家族と顔合わせだったし黒くしてったけど、次に会ったときにゃ元に戻してるからなまらビビってたっけ」
「ははは!やっぱりね!その顔でその髪だったら絶対ビビるよー!」
「うっせぇ、アホチビ」
「あーでも、親戚の前で演んの緊張するなぁ」
「そっか、拓真の親戚でもあるもんね」
「てか、スーツ買った方が良いかな?」
「はぁ?制服あんだろ」
「えー‥‥制服じゃ全然カッコつかないじゃん‥亜実ちゃんだってドレス着るんじゃん。俺もお洒落したい」
「‥‥お姉さんがメインだからな」
「や、そうだけどさ‥‥」
「っつーか、お前がお洒落したところで誰も見てねぇよ」
「うるさいなぁ、こんな機会滅多にないからお洒落したいんだよ!結婚式なんてそうそう行けるもんじゃないし!てか、みんなでお揃いにしよ!」
「ぷっ‥コミックバンドみたいになりそ」
「くっ‥はは!意外とアリかもしんねぇな!」
「でしょでしょ!?じゃあやっぱスーツ買わなきゃ!」
「つーか、お前の場合特注じゃね」
「何で?」
「チビ過ぎてサイズ無さそう」
「それは云えてるかも」
「もぉ、またそうやって!身長いじるのやめろよ!」
「‥‥ついてってやろうか、スーツ買うの」
「え‥良いの?」
「ん」
「そうだね。ひっしーに選んでもらったら?」
「うん‥‥じゃあそうする。ありがと、アズ」
「ん」
「裾上げ、“キッチリ”宜しくな」
「うぃす」
「何でそこだけ強調すんだよ!!」
「だから、チビ過ぎんだって。お前は」
「そこへいったら、あっちゃんはスーツ映えるよなぁ。ひっしーも、制服よりスーツの方がキマりそうだね」
「‥大して変わんなくね?シャツとタイとブレザーだろ、制服と大差ねぇよ」
「お前は持ってんのか、スーツ」
「一応」
「そっか‥‥じゃあ、たーもスーツ用意すれば完璧じゃんか」
「え、コミックバンドでいくの?」
「良いんじゃね?楽しそうじゃん」
「統一感あるしな」
「じゃあ、みんなスーツで!」
亜実の結婚話からはやや遠ざかっているが、久々のミーティングは話題に事欠くことなく、いつまでもスーツやら曲目についての話題に花が咲いた
132 菱和家の元旦
「ただいま」
「お帰りなさい」
「梓!お帰り!」
「‥‥親父」
「久し振りだな!明けましておめでとう!」
玄関先まで出迎えて来た母(正確には伯母)の真吏子と父(正確には養父)の翼
母とは定期的に顔を合わせてるけど、父の姿を見るのはその言葉通り久々だった
どっかの大企業の重役とかで(詳しくは知らない)、日本全国はおろか海外まで一年中飛び回っている父
忙しくしてはいるものの、“正月には必ず帰ってきて家族と過ごすこと”だけはどの年も欠かしたことがない
これは、父の信条らしい
ソファに座ると、親父は「待ってました」と云わんばかりの顔で、嬉々としてぽち袋を手渡してきた
これも、毎年恒例の風景───
「梓!ほら、お年玉!」
「もうそんなもん貰って喜ぶ年じゃねぇよ。普段から小遣いだって貰ってるし」
「何云ってるんだ、お年玉と小遣いは別だろ?まだまだ子供扱いさせてくれよ。正月気分も味わいたいし!」
そう云って親父はニヤニヤしてる
子供扱いって‥‥あと半年もすりゃハタチなんだけど‥
母さんは横でくすくす笑ってるだけで何も云わねぇし‥‥‥‥まぁ、一応息子らしく年に一回の正月気分とやらに貢献しとくか‥‥あって困るもんじゃねぇし、な
「‥‥‥あざす」
っつーか何だよこの袋に描いてあるやる気ねぇ顔したダセぇ猫は
用意したの母さんじゃねぇな、ぜってぇ
親父のセンスはマジで壊滅的だ
「お前、どこで年越ししたんだ?」
「‥ダチんとこ」
「ほぉ、友達と年越しか!俺も昔やったなぁ。朝まで起きてて、初日の出見に行ったりとかしてな!」
「‥‥俺もそれやってきた。だから今めちゃくちゃ眠みぃ」
「だらしないなぁ、俺は2日の昼までずーーーっと起きてたことあるぞ!」
「‥‥そんなに起きて何やってたの?」
「住んでた街の神社全部回ったり、とか」
「‥ふふ、くだんねぇ。‥‥でも、楽しそう」
「楽しかったぞー、前日から5円玉しこたま用意してな!あー懐かしい‥‥今からでも一緒に行くか?」
「行かねぇ。外寒みぃ。眠みぃ」
親父と俺は、“父と息子”っていうより“年の離れた友達”って感じ
親父は父親振りたいときもあるらしいけど(お年玉寄越してきたりとか)、この関係は俺が望んだこと
そして、親父もそれを受け入れた
父親のことを何一つ知らない俺は、「どう接していいかわかんねぇ」って正直に親父に伝えた
そしたら、
「別に俺を父親だと思わなくてもいい。君にとって都合のいいときだけの父親で全然いいし、書類上、戸籍上だけの父親でも全然構わない。関係云々の前に、君と家族になれるのがとても嬉しいんだ」
にこにこしながら、親父はそう云った
多分‥‥いや絶対に、“変人”なんだろう
でも、だから、この人たちの家族になることを選んだ
お陰で、十分過ぎるほど衣食住が満たされてる
クソ狭めぇボロアパートで極貧生活しかしてこなかった俺にとっては何もかもキャパオーバーするほどスケールがでか過ぎて、初めてこの家に来たときは正直ガチでドン引きした
でも超金持ちだってことを少しも鼻にかけないこの人たちは、何つーかさっぱりしてて、すげぇ居心地良かった
ただ、絵に描いたような家族ってのがいまいち慣れなくて、むず痒くなるときがあって
『家族団欒は、たまにで良い』
そう思った俺は「一人暮らしをしたい」と云った
折角恵まれた生活を与えてもらってるのに、なんてバカなことを‥‥そんな風に捉えられるだろうと思ってた
でも、この人たちは俺の考えや訴えを否定したりしなかった(但し、一人暮らしに関しては『定期的に帰ってくる』という条件付き)
その時だけじゃない
何時如何なる時も、俺の望みを叶えてくれた
今回、“家族で年越しする”っていう決まりを破ってしまうことも許してくれた
やっぱり、“変人”なんだろうな
母が、台所から声を掛けてきた
「梓、お腹空いてない?」
「ああ、大丈夫」
「じゃあ、甘酒でも飲む?」
そういや朝、神社で飲んできたな‥
「‥‥ん」
「真吏ちゃん、俺も!」
「はいはい。今淹れるね」
いつも思う
母さんは、親父のどこが、何が良くて一緒になったのかって
余計なお世話かもしんねぇけど、ほんとそう思う
マグに入った甘酒を、三者三様にして口に含む
あったけぇ、甘酒‥‥美味い
胃がじんわりしてきたところで、母が話を振ってきた
「最近、料理してるの?」
「ん。夕べと今朝も、ダチんとこで蕎麦と雑煮作ってきた」
「お前、渋いなぁ‥‥そんなもんまで作っちまうようになったのか」
「別に大したもんじゃねぇよ。母さんの見様見真似だし」
「やっぱそういうとこは真吏ちゃん譲り、なのかな。はは。将来は料理人か?」
「やだぁ。私の立場なくなっちゃう」
「そんなことないよー。妻の手料理はまた別物でしょー」
「‥ふふ、嬉しい!」
俺が云うのもなんだけど、この夫婦は年がら年中仲が良い
何で息子を前にしても相変わらずこんなラブラブ(死語)なんだろうな‥‥もう一生やっててくれ(云われなくてもそうするだろうけど)
「ほんと、すっかりハマったわね」
「うん。楽しいから。趣味の範囲でしかねぇけど、食ってくれる奴もいるし」
「そう。ふふ‥‥じゃあ、調理師免許とか取ってみたら?」
「調理師‥‥?‥‥‥でも、まだ一年ガッコあるし‥‥」
「おお!真面目ーー!ちゃあんと学校行ってるんだな、偉い偉い!」
「フツーだろ、ガクセイなんだから」
「とか云って、一年のときはサボりまくってたでしょ。っていうか殆ど行ってなかったでしょ」
「‥さーせん」
「『免許取りたてだったからテストだけやりに行ってあとは運転しまくってた』だっけ?あの話聞いたときほんと笑ったわ、ははは!」
「もー、笑い事じゃないってば!ただでさえ2年遅れてるのに、留年なんてしたらたまったもんじゃないと思ってヒヤヒヤしたんだから!」
親父はバカ笑いしてるけど、母さんには高校入学する前から散々心配迷惑苦労掛けまくった
この母親は、14歳の時点で九九すらままならねぇポンコツ以下の俺の学力をたった2年で中学卒業レベルまで底上げした
普段は物腰柔らかな佇まいしてっけど、内に秘めてる根性とか底力とか執念は並大抵のもんじゃねぇ
衣食住は勿論ガッコまで通わせて‥‥“普通の生活”を送らしてもらってることには、ものすげぇ感謝してる(伝わってるかどうかはわかんねぇけど)
っつーか留年なんてするかよ、してたまっか
「‥‥もうこれ以上ダブんねぇから」
「約束よ!?」
「はい約束します。‥‥‥っつうか仮に調理師の免許取ったとこで、それで食ってくかどうかまだ決めらんねぇ」
「はー‥‥うん、そうね。でも、経験積んどくのはアリなんじゃない?」
「経験、って‥‥」
「どっかの料理屋さんでバイトする、とか。実務経験積めば、中卒以上の学歴で試験受けられるみたいよ。趣味と実益兼ねられて一石二鳥じゃない?」
「‥‥実務経験て、どんくらいやりゃ良いの?」
「2年、だったかな」
「ふぅん‥‥‥‥」
確かに料理は好きだけど‥‥今が充実し過ぎてる所為か、そんなこと考えもしなかった
バンドに支障のない程度に‥‥‥‥皆にも、話しとかなきゃなんねぇか
「───親父。母さん」
「‥うん?」
「ちょっと早えぇけど、誕生日プレゼント強請って良い?」
「おう、何だ?」
「‥‥バイトする許可を、ください」
軽く頭を下げても何の反応もねぇから顔上げてみたら、親父も母さんもぽかんとしてた
「‥‥‥‥え、それが今年のプレゼント?そんなんで良いのか?」
「うん」
「───‥ふふっ」
「っははは!何を云い出すのかと思えば‥‥勿論、バイトは好きにやって構わないぞ。っていうか、ほんとにそれで良いのか?」
「うん」
ぶっちゃけると、去年の誕生日プレゼント(?)は『一人暮らしをする許可』、一昨年は『車の免許取得費用・約30万円』だった
「‥‥わかった。じゃあそうしよう。お前がその気なら、馴染みの店に口利きしとくぞ」
「‥‥‥‥」
何だそれ
正直めっちゃ助かる
コミュ障にとって最大の難関『面接』を受けないで済む
‥‥でも、それはなんか違うよな、やっぱ
「‥‥‥‥や、いい。自分の足で捜す。どうしても決まらんかったときは、頼むかもしんねぇけど」
「‥そっか!まぁ、自分が良いと思った店で働くのがいちばんだよな」
「‥んで、幾ら入れたら良い?」
「‥‥、何が?」
「バイト代。うちに、幾ら入れりゃ良い?」
母はきょとん、としたあと、溜め息を吐いた
「‥もう。そんなこと考えなくても良いわよ。自分で稼いだお金は、自分で好きに使いなさい」
「‥‥いや、でもさ、アパート代だって光熱費だって」
「「要ーらーなーい!!その気持ちだけでじゅーぶーん!!」」
‥‥綺麗にハモりやがった‥‥‥‥
「‥‥‥わかりました。有難うございます」
まぁ‥‥バイト代なんてたかが知れてるか
親父の携帯が鳴った
親父はそそくさと席を外した
その隙間を縫うかのように、母は口を開く
「ほんと、見た目からは想像できないくらい行動力あるよね、あなたは」
「そう、かな‥‥」
「そうよ。料理も一人暮らしも車の免許も、楽器もバンドも。バイトも、たった今『する』って決めたでしょ」
そうか‥‥そういうこと、なのか
自分の行動力とか全然意識したことなかった
そういや、いつだったか佐伯にも『真面目』って云われたっけ‥‥未だに何の自覚もねぇけど
「───一年のときとはまるで別人みたい。全然サボってないし」
「ん?」
「学校。楽しい?」
「‥うん、まぁまぁ」
「そう。‥‥一緒に年越しするようなお友達が出来て、ほんとに良かったわね」
まるで自分のことのように、嬉しそうにそう話す母
親っつーのは、こういうものなのかな‥‥今年はも少し帰ってくる回数増やそうか
友達、か‥‥‥‥‥あ、
「‥‥そういや、母さんの飯食いてぇって奴いてさ。冬休み中に連れてきて良い?」
「あら、そうなの?構わないけど‥‥もしかして、一緒に年越ししたお友達?」
「ん、そう」
「‥‥‥女の子?」
この顔は‥‥‥‥さっきとは違った意味合いで、嬉しそうな顔の母‥‥
「‥いや。男」
「あ‥、そう。‥何作ったら良い?」
「何でも良い、と思う。何でも美味そうに食う奴だから」
「ふふっ、それは作り甲斐があるわね」
期待を裏切っちまって申し訳ねぇけど、母さんならあいつを歓迎してくれる筈だ
「‥‥目ぇしぱしぱする‥少し寝てくるわ」
「そうしてらっしゃい。晩ご飯の時間になったら起こすからね」
「ん」
甘酒の入ったマグを携えて、自室に向かう
床には塵一つ落ちていなくて、ベッドには真っさらな布団が敷かれてあった
ここでしか喫わない煙草のヤニ臭さも無く、灰皿も綺麗になってた
俺が一人暮らしを始めてからも、『いつ帰って来ても良いように』と、母は定期的に部屋を掃除している
甘えさせてもらってんなぁ‥‥‥‥
机にマグを置いてベッドにダイブすると、柔軟剤の甘い香りがした
ついさっきまで、この腕の中にいたのに───もう顔を見たくなる
「───‥‥‥‥会いてぇな‥‥」
離したくない
離れたくない
手を繋いでたい
温さを感じたい
柔らかい髪に触れたい
紅潮した頬を撫でたい
抱き締めてたい
独り占めしたい
いつまでも腕の中に捕らえておきたい
ずっと、ずっと
どんだけあいつのこと好きなんだよ俺は
そういうこと想うなんて、やっぱ相当“毒され”てんな‥‥‥
っつーかあいつ「性感帯かよ」ってくれぇ首筋弱過ぎだろ
あの反応、初めて見た
もうちょいやってりゃ、また違う顔が見られたんだろうな‥‥ああほら、やっぱ顔見たくなっちまう‥
「‥‥‥‥‥」
眠てぇ‥‥瞼が重い‥‥‥寝るか‥‥───
131 「Tack.」
リサの気遣いに後押しされ、ユイは自室に向かった
ドアを開けると、リサの云う通り菱和がいた
「‥アズ」
菱和は椅子に座って机に頬杖をつき、転た寝をしていた
メッシュ混じりの長い前髪が、さらりと流れている
───夕べからずっと寝てないし、疲れてるんだろうなぁ‥‥
夜食や年越し用の蕎麦を拵え、元旦になってからも眠ることはなく、早朝から雑煮を作ってくれていた
現在の時刻は間もなく正午頃───限界を迎えていてもおかしくはない
至れり尽くせり状態であったことに、申し訳なさと感謝の想いが込み上げてくる
静かに寝息が聴こえる
寝顔を見ていると、何だかよくわからないが胸の辺りがそわそわし始める
今は、二人きり───そう意識した途端、心臓が鳴る
連泊していたときに抱いたものと同様の感情に支配されたユイは、そっと菱和に近付いた
その唇目掛け、菱和との距離を詰めていく
「──────‥‥まーたお前はそうやって。人が寝てるときに」
目の前から低く嗄れた声が聴こえた
眠っているであろうと思われた菱和の目がぱっちりと開き、ユイはたじろいだ
「───ぅあ!!ご、ごめ‥!」
慌てて身を離そうとしたが間に合わず
逆に菱和から一気に距離を取られ、唇を奪われた
新年初のキスも、不意打ちだった
ユイは項を捕らえられ身動きがとれず、されるがまま立ち尽くした
何度か口付けを交わすと、菱和はユイの顔を覗き込んだ
「‥‥いつしようかと思ってた。ずっと」
機会を窺っていたらしい菱和は意地悪そうに口角を上げた
ユイは赤面し、目を瞬かせる
「あんま人いると迂闊にこういうこと出来ねぇから、二人になれてちょっと嬉しい」
「‥ん‥‥‥‥‥正直云うと、‥‥俺も、したかっ、た‥んだ‥‥」
目を泳がせつつ、心境を吐露したユイ
徐に伸びてきた大きな掌が、紅潮した頬を包んだ
「‥何それ。めんこい」
いじらしくて堪らなくなった菱和はふ、と笑み、再びユイに口付けした
今までのもどかしさを晴らすべく、ユイも夢中で菱和の唇の感触を確かめる
一頻り堪能すると、菱和はユイを膝の上に跨がらせた
不意にぐらつくユイの身体を支えるようにその腰に抱き付き、胸の辺りに顔を埋め、長い溜め息を吐いた
二人の重みで、椅子がぎ、と軋む
いつもよりも、菱和の頭が自分よりも低い位置にある
見慣れない景色ではあるものの、感触や温もりは変わらない
菱和の首に絡み付くように腕を回し、ユイは身を預けた
「‥‥なに、してたの。ここで」
「ちょっと部屋見てた。あんまじっくり見てなかったなーと思って」
「う‥‥もっとちゃんと片付けとけば良かっ‥た」
「ふふ‥‥気にしてねぇよ。‥‥‥‥は‥‥眠みぃ‥‥‥」
「ベッド、使いなよ」
「いや。今横んなったらガチで寝ちまう。‥‥っつうか、今すげぇあったけぇからこのままでも寝れそ」
「それじゃ休まらないじゃん‥‥。てか、全然寝てないし疲れてるでしょ。ほんと、ベッドで寝てよ」
「‥‥一緒に寝てくれる?」
「‥‥‥‥、‥う、うん‥良い、けど‥‥」
「‥‥よくよく考えてみりゃ、今ここに居んのって散々お前の寝顔見てきた人たちばっかだな。俺以外は」
「そ、そうだ‥ね」
「‥‥‥風呂も普通に入ってんだよな」
「そう、だね」
「何だよそれ‥‥すげぇ羨ましい」
「な、んで?」
「だって、お前の寝顔見たり一緒に風呂入ったりするようになったのつい最近だし。やっぱ家族と幼馴染みにゃ太刀打ち出来ねぇな。‥どうしても超えられない壁」
「な、何云ってんだよ‥家族とか幼馴染みとは“好き”の種類が全然違うんだから仕様がないでしょっ」
「‥‥‥‥‥、どう違うんだよ?」
「や、だから‥‥‥‥“寝顔とか裸とか見られるのが恥ずかしい的”な‥好き、だよ」
「‥‥ちょっと何云ってるかわかんねぇ」
「も‥だから、ドキドキしちゃうんだってば!!」
「‥‥自分で云っといてなに照れてんだよ」
「照れるよ!!悪い!?」
「‥‥別に」
「‥笑うなよ!」
「だって‥‥『照れるよ』って、威張って云うから‥‥ふふ‥」
「だっ‥!だから、悪い!?」
「別に。‥めんこい」
「何だよもう‥‥!」
もう、これで何度目だろう
今年も、こんなやり取りを繰り広げてしまうのだろうか
先行きが不安でならないユイに対し、菱和は愉しげにくすくす笑っている
照れまくり狼狽える姿は、やはり“めんこい”───
「‥ユイ。好き」
不意に伝えられた想いに完全に面食らい、ユイは少し間の抜けた顔になる
その頬にキスを落とすと、「もっとしたい」という衝動に駆られる
悪戯にわざとらしく唇を鳴らしながら、菱和はユイの首筋や耳にもキスを落としていった
「‥ぅ‥?‥ちょ‥‥っ」
「‥‥‥うん?」
「ア、ズ‥待っ‥‥」
「‥‥何?」
こんなキスは、知らない
“擽ったい”という感覚は認識できるものの、単にそれだけではない
情欲に塗れた甘美な声と吐息に呑まれそうになる───刺激的で官能的な感覚と音に戸惑い、ユイは身をよじらせた
「‥や‥も‥‥やぁだ、ってば‥っ」
明確に拒否の声を上げると、その刺激はピタリと止んだ
「‥‥‥‥悪い。‥‥あんま可愛くて、つい」
「‥ふうぅ‥‥‥アズの意地悪」
「そんな反応されりゃ、意地悪したくもなるよ」
「む‥‥俺を困らせてそんな楽しいの‥」
「‥好きだからしたいんだ、沢山」
初心な反応が愛おしく、再三照れるユイを意地悪ながらも優しく見遣る菱和
漆黒の瞳に捕らえられると、早鐘が鳴り止まなくなる
菱和の愛情を独り占めしていることがこの上なく“幸せ”と感じる
「‥‥‥俺も好きだ、よ。アズ」
流れる黒髪を梳いてみると、菱和の瞳から意地悪さが消え失せた
ありったけの気持ちを込めて、ユイは菱和の頬にキスをした
「‥‥今年も宜しくお願いしま、す」
「‥こちらこそ。宜しくです」
二人は額を合わせ、暫し二人きりの時間に浸った
130 頌春
AM5:30
辰司が眠りこけ、他の皆がユイの部屋で未だトランプを続ける中
菱和は一人階下に降り、キッチンで雑煮の下拵えを進める
鍋に湯を張り沸かせる傍ら、大根、人参、牛蒡といった根菜を千切り、鶏胸肉を削ぎ切りにし、彩りにと用意した三つ葉も刻む
餅はトースターで軽く焼き色を付けて置いておく
持参した白出汁を鍋に注ぎ、散らした干し椎茸が戻ってから味を見る
───‥‥こんなもんかな
ほんの少し調整を加え、あとは材料を煮込むだけの状態となった
下拵えを済ませた菱和は、換気扇をつけて煙草を喫い始めた
AM6:00
リサが洗顔をしに降りてきた
キッチンから漂う出汁の香りに唆られ、思わず鍋の蓋を開ける
「‥‥良い匂い。お腹空いてきた」
「餅、多めに入れてやろうか」
「3つで良い。‥ほんとは、いっぱい食べたいけど‥‥正月太りしたくない」
「別に食や良いじゃん。お前なら、多少肥えても変わんねぇ気すっけどな」
「戻りにくくなるから、やなの」
「ふーん。案外気にするのな、そういうこと」
「‥女、ですから?」
「‥‥そ」
「‥‥‥‥‥‥でも‥‥今年もゴハン沢山食べさしてね」
菱和に背を向けたままそう呟くと、リサは洗面所へ向かった
怠そうにダイニングの椅子に腰掛けている菱和が、くす、と笑う
AM6:20
「お、なんか良い匂いする」
「ヤバい!腹減ってきたー!」
「‥かー‥‥眠みぃー‥‥」
「やっぱ、あっちゃんここにいる?」
ユイ、拓真、尊、アタルの4人が、トランプを切り上げて2階から降りてくる
ダイニングテーブルに座っている菱和が、リサの淹れた焙じ茶を堪能していた
「お、俺もお茶飲みたい!」
「あー、俺も貰おっかな」
「うん。今淹れるから座ってて」
「これ飲んだら、初日の出&初詣行くかぁ」
夜明けまであと数十分
極寒の寒さに備え、皆一同に温かい焙じ茶を啜る
「冗談抜きでさ、リサの淹れたお茶って美味いよな」
「ほんと。ただのお茶なのに、美味く感じる。‥‥なのに何で、カレシ出来ないんかねぇ‥‥」
「余計なお世話だよ。大体、お茶淹れるの上手いからって何の徳もないでしょ」
「俺はポイント高いと思うけどな!てか、リサは学校でもモテモテじゃんっ!」
「モテてないようるさいな」
「リサ、焦るこたねぇぞ。お前が“イイ女”だっての、俺らはわかってるかんな」
「‥‥別に焦ってるとかじゃないけど‥‥‥そういう気持ちにならないってだけで」
「じゃあ、そんじょそこらのヤツじゃ駄目だってことだな。っつうか、生半可な野郎じゃ俺が赦さねぇ」
「っていうか、何であっちゃんの許可が必要なんだよ?」
「あ?そりゃあ、悪い虫つかねぇように‥‥」
「それこそ余計なお世話なんじゃないの」
「‥そのうち『リサの父親です』とかって云いそう」
「おいおい、それ名案じゃんか!」
「初めて彼女の家に遊びに行って、こんな髪赤い人出てきたらドン引きだよね‥‥」
「‥‥ぜってぇ悪い虫付かなさそう」
「だろー!?ははっ!」
「ある意味“度胸試し”だよな」
「ああ、あっちゃんを見ても引かない人だったらOKってこと?」
「それはアリかもね!」
「見た目も中身もヤバいからなー、あっちゃんは」
「は?どこがだよ!?」
「いや、褒めてるから!」
「‥‥‥‥、もし、もし万が一彼氏が出来そうになったら、まずはあっちゃんに紹介するよ」
「───ぶはっ!ははは!」
「リサ、マジかよっ!」
「マジだよ。あっちゃん、お願い出来る?」
「おー、任せろ!」
一頻り笑ったところで、皆揃って支度を始める
何だかんだと云いつつ、アタルも出掛ける準備をし始めた
AM6:40
石川家を出発した一同は、朝焼けがよく見える高台を目指して歩き出す
凍てつく空気が頬を刺し、吐く息も凍りつきそうな寒さの中
6人でなるべく固まりながらその道程を歩いた
「うー‥‥さむ‥」
「ほんと、寒いなー」
「あっちゃん、やっぱ家にいたら良かったのに。てか、今からでも帰れば?」
「や、ここまで来たら帰るのも面倒臭せぇ。うぅー早く帰って飲み直してぇ」
「腹減ったぁ‥‥お雑煮つまみ食いしてくれば良かった‥‥」
「ああ、早く食いたい!めっちゃ良い匂いしてたもんね!」
「‥‥口に合うと良いけど」
「合う合う。絶対合う」
拓真は謙遜する菱和にくすくす笑った
高台には、既に近所から集った先客がいた
なるべく朝陽が見易い位置を陣取り、数十分後の日の出を待った
AM7:25
空が朱鷺色に染め上げられていく
待ち侘びていた瞬間が訪れ、その場にいる全員が一同に食い入り、歓声や拍手が沸いた
シャッターを切る機械音も、ちらほらと聴こえてくる
森羅万象を照らす日輪はゆっくりと地平線を焼いてゆく
燦然と煌めきを増し、凍てついた空気を仄かに和らげる
「───‥わ」
ユイは思わず、小さく声を上げた
毎年のように見ているのだが、やはり込み上げてくるものがある
この瞬間に日本中が赤く染まっているのだと想像すると、背筋に悪寒が走った
「晴れて良かったな」
菱和は、柄にもなく感動に浸っているユイにゆったりと体当たりした
「ぅ‥うん‥‥。‥‥綺麗だ、ね」
「綺麗だな。‥来て良かった」
そう云った菱和の横顔が太陽の光で赤く染まっている
きっと、皆もそうなってるはず───そう思い、ユイははにかんだ
AM8:05
初日の出を観覧した後、一同は近くの神社へ向かった
参拝客も疎らな神社には、既に多くの御神籤が木に括り付けられていた
境内の傍にテントが張られているのが目に入る
中には初老の男性が二人おり、参拝客に紙コップを手渡している
「‥‥なに、あれ」
「甘酒。町内の人が毎年やってくれてるの」
リサが菱和の問いに答えた
テントでは温かい甘酒が無料で振る舞われており、焚き火も起こされている
どちらも、冷え切った身体を暖めるオアシスのような存在だった
ユイたちも早々に参拝を済ませ、甘酒を受け取った
極寒の中味わう温かく円やかな甘さは、格別だった
「ああー‥‥生き返る‥‥」
「毎年毎年思うけどさ、“五臓六腑に沁みる”ってこういうことだよね」
「ほんと、あったかい」
アタルは焚き火の側に置かれた木材に腰掛け、煙草を咥える
「ひっしー、煙草は?」
「‥あ。置いてきた」
「じゃあ、ほれ」
「ありがと」
菱和はアタルから煙草を一本貰い、隣に腰掛ける
二人は煙を吹かしながら暖をとった
AM8:30
石川家に到着した一同
リビングには寛いでいる辰司がいた
「ただいまー!」
「うお、眼鏡が曇る‥‥」
「ういぃ‥‥天国だ‥あったけぇ‥‥‥」
「やぁやぁ、お帰り。お疲れ様、寒かったろう。お雑煮あっためといたから。すぐ食べられるよ」
「やった!早く食お!」
「てか、先食ってれば良かったのに」
「いやー、そりゃ父さんも皆と一緒に食べたいさ」
「待たしてすいませんでした」
「とんでもない!さ、食べよう食べよう!」
湯気が立つ椀を携え、全員揃って雑煮を食す
三つ葉の香りが風味を増しており、根菜には出汁が沁み、程よく溶けだした餅が口内で蕩ける
こちらも、五臓六腑に沁みる味だった
「ふは、あつっ‥」
「うーーーんめえぇ‥‥」
「美味しいね。ほっとする」
「ほんとな。はー、美味い」
「菱和くん、有難うね」
「いえ。口に合ったなら何よりです」
「『合う』って云ったでしょ。ふふ」
「ほんと美味い!お代わりしたい!」
「お餅、焼こうか」
「ああ、少し焼いといたよ。トースターに入ってるから。足りなかったらもっかい焼こう」
「ラッキー!父さん、気が利くぅ!」
「みんな腹空かしてるだろうと思ってね」
「っつうかよ、雑煮で食うのも良いけど普通に餅としても食いたくなってこねぇ?」
「それなら、あとで作るよ。きな粉?醤油?」
「やっぱきな粉だろ、そこは」
「だよね。でも磯辺焼きも捨てがたい」
「意外とチーズも合うのよね」
「じゃあ、色々やってみますね」
「俺もやるー!」
「私も手伝うよ」
石川家での団欒
大好きな家族と友達、そして恋人と美味な食事を共に出来ることがより一層食欲を増進させ、胃も心も満たされていく
こんな時がまた来れば良いな───そう思い、ユイは餅を口に含んだ
そのうちアタルと辰司はビールを飲み出し、ソファで眠ってしまった
「ほんっと、飲兵衛だな」
「ふふ。おじさん、さぞ嬉しいんだろね」
「まぁ、あんま普段飲まないからな」
そう云って、尊は二人に毛布を掛けてやる
「餅は昼にでも食おっか」
「そうだね。じゃあ片付けするか」
「良いよ。やっとく」
リサは率先して片付けを始めた
食器を流しへ運ぶとキッチンは思いの外綺麗で、切り餅ときな粉、醤油がスタンバイされている
「───あんた、いつの間に」
「‥‥‥‥ん‥‥ああ、すぐ食えるようにと思ってさ」
菱和は換気扇の下で、素知らぬ顔で煙草を吹かしている
「眠くないの?」
「‥‥少し」
「寝てくれば。ユイの部屋、空いてるよ」
「お前こそ寝れば。‥‥ひでぇツラしてんぞ」
「るさいな」
菱和をじと、と睨み付けると、リサは洗い物に取り掛かろうとした
「ああもう、んなことしなくて良いってば」
「俺らがやるから、休んでて!」
ユイと尊が腕を捲りながらキッチンへと来る
二人は並んで洗い物を始めた
拓真はダイニングの椅子に座り、二人の後ろ姿を眺めながら呟いた
「‥‥こーやって並んでると兄弟だな、やっぱ」
「‥ほんと」
リサはふ、と笑った
AM11:20
「───あれ、アズは」
「多分あんたの部屋にいるよ。さっき上あがってくの見た」
「そっ‥か」
「‥‥行かないの?」
「いや、うん‥‥」
「今のうちに行ってきなよ。こんだけ人いたら、なかなか二人きりになれないもんね」
「ぅ‥‥‥」
「‥‥大丈夫。暫く誰も上に上げないでおくから」
「‥‥ありがと、リサ」
129 BROTHERHOOD-Ⅱ
「次いつ帰ってくんだよ?」
「早くてGWかな。ユイのこともあるし、ちょいちょい帰ってくるつもりではいる」
「ふーん。じゃ、時間あったらスタジオだな」
「え、やだよ」
「‥何でよ」
「だって俺、今全然ベース触ってないもん。腕鈍りまくってるなんてもんじゃない」
「関係ねぇべ」
「やだ。恥ずかしい」
「何年バンドにいたと思ってんだよ‥‥今更恥ずかしいも何もねぇだろうに?」
「行こう」「嫌だ」のやり取りを数回続ける尊とアタル
双方折れる気配はない
ふと会話が途切れ、その隙間を見計らっていたかのように菱和が口を開いた
「‥‥俺も聴いてみたいす。尊さんのベース」
「ほらなー!?やっぱスタジオ行くべよ!」
「やめてよー、菱和くんまで」
尊は思わず苦笑いした
アタルはニヤニヤし、メロイックサインを作って尊を煽った
「や、前にユイが云ってたんす。尊さんと俺の音は『同じ味がする』、って‥‥俺も尊さんが居た頃の音源聴きましたけど、どんだけ聴いても何がどう同じなのかさっぱりわかんなくて」
「‥‥‥‥ミルクティー‥‥?」
尊はきょとんとし、ユイが尊の“味”だと指摘したものの名前を口にすると、菱和はこくりと頷いた
弟の特異体質、“共感覚”
その感覚は、兄である尊ですら不可解なもの
況してやこんなエピソードを聞けるなど、思いもよらないことだった
「‥‥そんなこと云ってたんだ、あいつ‥‥‥」
「そんなら聴き比べるっきゃねぇべ!ひっしーも気になってんだし。な?」
「‥‥‥まぁ‥‥時間があったら、な」
自分と同じ味がする人間が存在する───未知の感覚の話はとても興味を惹かれる
それは尊も同じようだった
結果的に自分が折れてしまったことに納得したくないのか、尊は難しい顔をしながら頬の辺りを軽く掻いた
「───あ、みんなしてずりぃの!俺らにもなんか作ってよ!」
噂をすれば何とやら
なかなか帰ってこない3人に業を煮やしたユイが降りてきて、リビングのドアからひょっこりと顔を出した
アタルは目を細め、軽く舌打ちした
「ち‥‥見付かったか」
「兄ちゃんとアズも、トランプしようよ!」
「これ飲んだら行くよ」
「うん!早く飲んで上来てよ!ほらあっちゃん、はーやーく!」
「でけぇ声出すなよ、親父さん起きちまうだろ」
グラスの中身を飲み干してしまっていたアタルは真っ先にユイに捕まった
冷蔵庫を物色して何本かのペットボトルとグラスを3つ携え、渋々2階へと向かって行った
ダイニングテーブルに着席したままの尊と菱和は、先に連行されたアタルをほんの少し憂い、ゆっくりとモスコミュールを味わう
───あっちゃん、ジンジャーベースが好きなのかな‥‥ビールベース‥?
透き通った琥珀色のモスコミュールを眺め、菱和はそんなことを思った
「───キツくない?」
声を掛けられた菱和はグラスから目を離した
「ウォッカ。結構度数強いけど、大丈夫?」
「平気す」
「酒、強いんだね」
「‥‥‥そうなんすかね‥‥」
「ふふ、多分ね。全然顔変わんないもんね。菱和くん、今年二十歳になるんだよね?多分あいつ誕生日過ぎたら鬼のように飲ませてくると思うから、迷惑だったら遠慮なく云いなよ」
尊は申し訳なさそうに笑み、ゆっくりとモスコミュールを飲んだ
この一晩だけでも、アタルは存分に美酒を振る舞ってくれたと思う
年明け前に飲んだシャンディガフも、今飲んでいるモスコミュールも、アタルの配分は絶妙だった
自分が二十歳になった折、果たしてどんなものを振る舞ってくれるのだろうと淡い期待を抱き、少し口角を上げた
「‥‥、いえ、全然。楽しみす」
───‥‥‥‥っつーか俺、
良いか悪いか、どちらかと云えば───いや、確実に悪い
菱和がまだ未成年だという事実に、もう誰も突っ込もうとしない
───ま‥いっか、もう
ぐ、とグラスを傾けると、ジンジャーエールの炭酸が喉を通り抜け、ウォッカのクールな苦味とライムが後を引く
不良時代に悪友たちとふざけて飲んだ缶ビールとはひと味もふた味も違う“女殺し”のモスコミュールは、確実に脳を刺激してくる
だが、酔いが回っている感覚は無い
尊の云う通り、恐らく菱和はアルコールに耐性がある体質なのだろう
中身が半分ほどになったグラスの中の氷が、カラ、と音を立てた
「‥‥ユイ、だいぶ懐いてるみたいだね」
尊がふと、ユイについて触れる
「この前云ってたよね、飯御馳走になってるとかって?共感覚のことまで話してるくらいだから、よっぽど気を赦してんだなーと思ってさ」
のほほんと話す尊の言葉に、先刻外でアタルと話していたことが思い起こされる
アタルの話だと、自分は安心感を与えられているようだとのことだが───
「‥‥だと良いんすけど」
『どうかそれが真実であるように』と祈る
“それ以上のこと”を語る必要はないと思い、菱和はまた琥珀色のグラスを見詰めた
「───まぁ、そりゃそうか。“大好きな人”だもんな」
尊が紡いだ言葉に、菱和の動きがピタリと止まった
『何となくだけど、尊はお前らのこと気付いてんじゃねぇかな』
『あいつの云う“大好きな人”って、1000%お前のことだろ』
──────マジかよ
アタルが云っていた“1000%”はガチだったのだと思い知らされる
尊もまた、菱和が弟と恋仲であることを確かめたかったのだろうか───
「‥‥ね」
訝しげもなくにこりと笑い掛け、同意を促す
菱和の心臓が、どく、と鳴った
「‥‥、‥‥‥‥───」
沈黙は、肯定していることになるだろうか
否定する気は更々ないが、やはり実の兄に真実を語るのは些か勇気が要る
しかし、尊が事情を把握している以上、有耶無耶にするのも可笑しな話だ
何も語らぬつもりでいたが、菱和はグラスを置き、重い口を開いた
「───気にならないすか」
「‥ん?」
「‥‥こんな“形”してる奴が弟と仲良くしてて、‥迷惑じゃないすか」
「全然。寧ろ、感謝してる。‥‥あいつが辛いときも傍に居てくれて、ほんとに有難う」
尊もグラスを置き、菱和に向き直って徐に頭を下げた
支えるべきであろう時に、自分は何も出来なかった
その代わり、ユイは拓真やリサ、菱和の存在に救われていた
3人はそれが当然のことと思い、自分達の意志でユイの傍に居ただけだ
見た目など、関係ない
形振り構わず弟を想いやってくれる人間が身近に沢山いるということへの、多大な感謝
家族として、兄として当然の想いだ
尊の想いが、じわりと胸に沁みる
「───感謝しなきゃなんねぇのは俺の方です」
「‥‥、え‥」
尊は『寝耳に水』という顔をし、目を瞬いた
「‥‥俺、今までまともに友達とか居なくて。今は、ユイもそうだけど、佐伯とかリサとも一緒に居るようになって、他にもダチ増えたし、バンドも楽しいし‥‥‥‥‥あいつがバンドに誘ってくんなきゃ、今頃どうしょもねぇ人生しか歩んでなかった筈です」
下らなかっただけの世界が、変わった
自分の居場所を見付けた
“そこ”に存在していても良いのだと、“それ”を手離したくないと思った瞬間から、何もかもが色めき出した
その色を付けたのは、ユイだ
『お前は、俺の“恩人”』
いつか、ユイにもそう伝えたことがあった
本人はピンとこなかったようだが、菱和の想いは今も変わらずにいた
「‥‥全部、全部あいつのお陰なんです。今の俺が在るのは」
静かに吐き出されたその心は、ぽたりと落ちた雫が水面に広がっていくように尊の胸に響いた
───この恵体でも、抱えきれないものが沢山あったのかな
無論、身体と精神の大きさは比例しない
だが、単純に、尊はそう感じた
誰にでも本人にしか解り得ない苦悩や葛藤があり、それらと上手く付き合えていたり手離す術を見付けられたならば御の字だが、誰しもがそう器用に生きられるわけではない
生きづらさを抱えている人間は、そこら中に溢れ返っている
菱和もご多分に漏れず、つい最近まで人生そのものに悲観していた
自分でも『どうしようもない』と思うほどの道を辿ってきたというのか
『まともに友達が居なかった』というのは自らの選択だったのか、将又そうせざるを得ない事情があったのか
初対面の時から、菱和に対して“やや大人びている”という印象を抱いていた
どんな人生を歩んできたのかはわからないが、“そうならざるを得なかった”のかも知れない
その軌跡によって、今の菱和が形作られている
人一倍騒がしいユイを相手にしても、アタルの茶化しにも余裕の構え
気難しい面があるリサとも、上手くやれているようだ
無愛想で無表情で無口と聞いてはいたが、全くそんなことはない
一癖も二癖もある連中と付き合える柔軟さを持ち合わせ
友人への気遣いや礼儀を弁え
砕けてはいるが年上の人間へ敬語を使い
見た目とは裏腹の素直さと謙虚さを持ち合わせ
メッシュ、ピアス、煙草といった不良の印象が掻き消えるほど真面目で実直な人間が、弟の“大好きな人”───
───ほんと、“イイ奴”だな。それに引き換え、あいつは‥‥‥
果報を伝えてきた弟の朗な声を思い出した
「‥‥‥基本アホだし、五月蝿くて落ち着きなくて思ったことすぐ口に出すKYだしアホだし天然だし、面倒かけると思うけど‥‥ユイ共々、これからも宜しくお願いします」
まだまだ幼稚で未熟な弟の存在が他人に影響を与えていたとは、況してや菱和に『あいつのお陰』と云わしめてしまうほどの影響を与えているなど露知らず
性格も体格もアンバランスではあるが、本人たちが幸せであるならばその程度のことは大したことではないと思える
細やかながら二人が益々睦むことを願い、尊は今一度深く頭を下げた
───“アホ”って、2回も云った
この世の誰よりもユイのことを熟知しているであろう兄の、辛辣な言葉
だが、その言葉尻には愛情すら感じられる
『誰だって、家族の幸せを望むだろ。‥‥尊も、ユイが幸せなら相手が誰だろうと文句ねぇよ、きっと』
───ほんと敵わねぇな、あっちゃんには‥‥
伊達に20年近く親友でいるわけではない
その絆をまざまざと見せ付けられた
兄弟、親友、恋人───どんな形であれ、互いに想いやる心は気高く感じられる
鬱陶しいだけだった人との繋がり
今は、ただただ貴いものだ
奇妙で奇特な廻り合わせ
自分もこの全ての縁を大切にしたいと、菱和は強く望む
「‥‥こちらこそ、宜しくお願いします」
菱和が顔を上げたところで尊がグラスを手に取り、軽く傾ける
菱和もグラスを持ち、小さく乾杯をした
カチ、と小粋な音が鳴る
尊がふ、と笑みを浮かべると、菱和はほんの少し会釈した
二人は再び、ゆっくりとモスコミュールを味わった
128 BROTHERHOOD-Ⅰ
2人が室内に入ると、ちょうど尊が冷蔵庫を開けようとしているところだった
リビングのドアが開く音に振り返った尊は、目を丸くする
「どこ行ったのかと思えば‥‥まさか外で喫ってたの?」
「ああ、気分転換に。クソ寒かったー」
アタルと菱和は寒さで赤くなった指先を擦り、ヒーターに近寄る
「当たり前だろ‥‥菱和くんまで連行して‥‥‥風邪でも引かせたら大変だろ」
「こいつタフだし、へーきだよ」
「お前が云うなっての、折角来てくれてるのに!もう外で喫うなよ。菱和くんも、ここで喫って良いからね」
頬や鼻を赤く染めてへらへら笑うアタルに呆れた視線を寄越し、尊は台所の換気扇を指差した
アタルは差し出された灰皿に吸い殻を落とし、生返事をする
「へいへい。‥つぅか尊、なんか作っちゃっか?」
「‥‥じゃあ、モスコ」
「おう!ひっしー、お前もちょっと待ってろ!」
「うん」
暫し暖をとった後、アタルは台所に向かった
冷蔵庫からウォッカの瓶とジンジャーエール、ライムジュースを取り出すと、グラスにウォッカとライムジュースを1:1の割合で注ぎ、そこにジンジャーエールを適量加える
モスコミュールで満たされたグラスが3つ、ダイニングテーブルに置かれた
「ほい」
「どーも」
「‥お前も!」
「‥‥頂きます」
3人は軽く乾杯をし、グラスに口を付けた
ウォッカのクールな苦みにジンジャーエールの炭酸と仄かな甘味、そして爽やかなライムの香り
引き締まった風味のモスコミュールが、3人の喉を通っていく
「───“climb-out”って、3年前だったっけ」
モスコミュールに舌鼓を打っていると、尊が唐突に呟いた
「‥ベース、弾いてたよね?」
菱和を見て、にこりと笑む
“climb-out”
それは3年前、菱和が我妻に“無茶振り”をさせられたライヴの名前
思いもよらぬ発言に呆気に取られつつも、菱和はこくりと頷いた
「‥‥はい」
「やーっぱそうだよね。あー良かった。これでほんとにすっきりした」
「あ?何だそれ?」
アタルは首を傾げ、2人を交互に見遣る
「ほら、俺がバンド抜けるってときにユイと拓真から菱和くんの話聞いてさ、集合写真見してもらったじゃん。『どっかで見たことあるなー』って、ずーっと思ってて。『ああ、あんときベース弾いてたカレだ』って、この前やっと思い出したの」
尊の脱退に伴い、昨年春に行われたバンドのミーティング
その時に見た写真の菱和に抱いた“見覚えがある”という印象
菱和の口から明確に答えが返ってきたことでその記憶が間違いでなかったと確信した尊は、満足げにモスコミュールを口にした
3年前の自分を知る数少ない人物が目の前にいる
その奇妙な偶然に、呆然とする菱和
「‥‥‥‥、そうだったんすか」
「ふふ。あんときから、あんま変わってないね。長身で髪も長くしてて」
「ふーん‥‥そんときからこんなブアイソだったんか、こいつ?」
「こらこら。失礼だろ。‥あ、でもメッシュは入ってなかったような」
「‥‥あんときはまだ入れてなかったす」
「やっぱり?」
「よく見てんなぁ。っつぅかよく覚えてんな」
「目立ってたから。見た目も十分インパクト強かったけど、とにかくあの“音”が───」
“climb-out”が行われた当時にベース歴2年余りの菱和が“無茶振り”させられていたことを、尊は知らない
それを差し引いても、菱和の姿と音は尊の記憶に鮮烈に刻まれるほどの衝撃だった
煌めくステージの上に不釣り合いな無表情と、我武者羅で太っといベースライン───
「───今でも覚えてるよ。ほんと、衝撃的だった」
我妻の“無茶振り”に付き合わされた菱和には、観客に意識を回す余裕は皆無だった
更に、半ば自棄糞になりながら弾いていたそれは、他人と音を合わせることの快感を未だ知らぬ音
今よりも断然“青かった”当時の自分を、よもや尊に見られていたとは───
少し気恥ずかしくなった菱和は、軽く頭を掻いた
「‥‥恐縮です」
「ふふふ。‥我妻さんね、あの日色んな人に菱和くんのこと“愛弟子”とかって自慢してたよ」
尊の言葉に思考が停止し、したり顔の我妻が脳裏を過る
───あんにゃろう‥‥知らぬ間にそんなこと触れ回ってやがったのか
「‥‥‥‥あいつはただのアホです」
のらりくらりと喋る我妻の様子が容易に脳内再生され、菱和はボソリと憎まれ口を呟いた
尊とアタルは思わず噴き出す
「‥ぶっ‥‥云うねぇ、菱和くん」
「ははっ!“アホ”呼ばわりかよ!‥‥っつぅか、我妻さんと付き合い長いんか?」
「んー‥‥‥もうかれこれ5年くらいなる、かな」
「ベースは我妻さんに教わったんだ?」
「‥、まぁ‥‥」
「あの人、元プロだろ?直々に教われるなんて、すんげぇ贅沢なことじゃんか。超絶羨ましいぜ」
「‥‥あいつがプロだったって、知ってたんすね」
「“RIOT”でしょ?知る人ぞ知る伝説のバンドだよね。いつだったかその話したら、『黙ってて』って云われて。だから、ユイと拓真には話してないんだ」
silvitの常連でも我妻がプロのベーシストであったことを知らない人間の方が圧倒的に多く、事実、ユイは甚く驚いていた
一方、アタルと尊は知っている様子だ
触りだけならば、菱和は我妻がバンドを辞めた理由を知っている
だが、特別無口なタイプ故他言はしないだろうと踏んでの判断だろうか、口止めまではされていなかった
解散理由の触りをユイに打ち明けたことに特に罪悪感を抱きはしなかったが、我妻が話したがらない理由もユイが知らなかったことにも納得し、菱和は軽く頷く
「‥‥なぁ、我妻さんのベースって、どんな感じなん?教わってたんなら、ちょっとくらい聴いたことあんだろ?」
「“どんな”‥‥‥‥、あいつ、解散したあとは二度と楽器弾かないつもりだったらしいんす。だから俺も滅多に聴いたことないんすけど、やっぱ‥プロと素人は目に見えて違うな、と思います。なんつーか、オーラが半端ねぇっていうか‥‥‥昔の音源と比べても全く遜色ねぇし、全然ブランク感じさせねぇのはやっぱすげぇな‥って」
尋ねられ、記憶を辿るも、菱和でさえ我妻のベースを聴く機会は少なかった
それでも、自分しか知らない僅かな情報を伝える
尊とアタルは、神妙に頷く
「‥‥でもあいつ、基本いっつものらくらしてるし、大したこと教わってないんで‥‥正直“教わった”うちに入るかどうかも怪しいす」
そう云って、軽くモスコミュールを煽る
菱和と我妻
2人がどういった経緯で出会ったのかは知らないが、尊には唯一断言出来ることがあった
「───ほんとにお気に入りなんだね、我妻さん。菱和くんのこと」
我妻が普段からのらりくらりしている我妻のキャラクター
そうではない、“半端ないオーラを放つ姿”を、菱和の前でなら見せているよう
剰え、『二度と楽器を弾くつもりはない』と云いつつ自分の技術を教授したのは菱和を気に入っているからこその行為なのではないかと、尊は率直にそう思った
尊の言葉が腑に落ちない菱和は、少し首を傾げた
「‥あいつが無駄に絡んでくるだけです」
「愛されてるんだねぇ。正に“愛弟子”」
「‥‥あいつが勝手にそう云ってるだけす。‥あの日も、あいつが弾くっつーから行ったのに無理矢理楽器押し付けられて、仕方なく演っただけで」
「素直じゃねぇなぁ‥‥。愛弟子にサイコーのステージ用意してたんじゃねぇの?」
「ただの思い付きです、ぜってぇ」
「それでも、菱和くんなら弾いてくれると思ったんじゃない?そう思うってのもわかってて菱和くんに弾いて欲しかったんでしょ、きっと」
尊とアタルは2人の関係性を貴く感じ、我妻の菱和への想いを馳せた
“climb-out”の日
端から弾くつもりがなかった“少し年の離れたお節介な楽器屋のジジイ”は面白半分にベースを託し、“やたら無愛想で尖った目付きのクソ生意気なガキ”は嫌がりながらも無茶振りに付き合った
尊とアタルには、2人が互いに信頼を置いていなければ成立しないやり取りだったのではないかと思えた
不良同然だった当時の菱和を受け入れ、楽器に触れる機会を与え、如何なる時も対等に接してきた我妻
silvitに出入りするようになってから現在までその態度は変わらず、やさぐれた心の澱が徐々に薄れていくのを、我妻も、菱和自身も感じていた
だが、我妻が勝手に“愛弟子”と呼んでいるだけで、自分達の間に師弟愛など存在しない
ベースを勧められたことに対して感謝の気持ちこそあるものの、それ以上でもそれ以下でもない
菱和にとっては、そんな認識だった
図らずも構築された関係性に、今更感謝の念を抱くことや慕うことを恥じらっているだけなのかも知れない───
───死ぬほど嚔でもしてやがれ、クソジジイ
尊とアタルにわからない程度、菱和は口角を上げた
「菱和くん、ベース歴何年?」
「5年です」
「じゃあ、“climb-out”の時で2年か。2年であれだけ様になってたら、我妻さんも満足だったんじゃないかなぁ」
「ふーん‥‥そんなすげかったんか。お前、そん時どんくらい練習してたんだ?」
「‥‥左手の指全部、水膨れ出来ました」
「うぇ、全部て‥‥でも俺もベース弾き始めの頃はよく水膨れ作ってたなぁ‥‥ギターの弦と全っっ然違うもんね」
「‥指“出来る”までは痛いすよね」
「だよねー。‥‥っていうかさ、イイ音出すよなぁ。前に音源聴かしてもらったけどさ、“RED SILK”とかもう、ゾクゾクしちゃった」
「‥‥恐縮です」
アタルが2杯目のモスコミュールを作り始める
3人は酒を酌み交わしながら、再び楽器やバンドの話に興じる
「‥‥尊さんは元々、ギター弾いてたんすよね」
「ああ、うん。そう。で、あのレスポール、ユイにやったんだ。バンドやろうかーって話になったとき『他の楽器はやらない』の一点張りで、余ってたパートがベースだったから俺がやることになってさ。‥‥序でに云うと、アタルも元々はギターじゃなくてドラムやる予定だったんだよ」
「そうそう。俺が叩いてんの見て拓真が『タイコやりてぇ』って云い出してさ」
アタルは余っていたレモンの輪切りを噛みながら、拓真がいる階上を指差した
「‥あっちゃんが、ドラム‥‥」
ツンツンの赤いウルフヘアを振り乱しながら、何なら上半身は裸でドラムをしばき倒す姿が、容易に想像出来た
「今考えればいちばん良い布陣だよな、案外バランス取れてて」
「結果的にはなー。チビは根っからのギター小僧だし、たーも器用だからすぐ色々叩けるようになってよ。で、今はお前がベースだし、な」
アタルはレモンを噛んだままニカッと笑った
尊がユイにレスポールを託し、ベースを始めたこと
拓真がアタルに影響を受けてドラムを始めたこと
ユイとアタルのツインギターが成立したこと
我妻が菱和にベースを勧めたこと
尊がバンドを脱退し、菱和が新たなベーシストとして加入したこと
このバンドが結成されたこと、このバンドに居られること
その全てが、必然的だったのだろうか
果たして誰にも知る由もないが、その必然性に誰もが感謝していることに変わりなかった
Haze結成の一端を垣間見、菱和は自分がバンドでベースを弾いていられることを改めて感慨深く思った
127 アズとあっちゃん
「だーーーーーもうやってられっかっっ!!!」
ユイのドヤ顔、拓真と尊の失笑に居た堪れなくなり、アタルは勢いよくトランプを床に投げつけた
「あーマジ腹痛てぇ‥‥あっちゃん、ほんと弱過ぎ」
「うっせぇ!折角俺が出そうとしてんのにこいつが邪魔してくんだろ!」
「いや、そうしないとユイも勝てないしな」
「大富豪て、そういうルールでしょ。てかトランプ全般そういうもんでしょ」
「わかってるよ!!でも今日はもうやめだ!ひっしー、一服しに行くぞ!」
「ちょっと、憂さ晴らしにアズを付き合わすの?」
「煙草でも喫わなきゃやってらんねぇんだよっ!お前、また今度やっかんな!覚えてろよっ!!ひっしー、行くぞ」
「うん」
ちょうどニコチンを欲していた菱和としては、願ったり叶ったりな誘いだった
尊は首を傾げ、訝しげに声を掛ける
「菱和くん、無理しなくて良いんだからね?」
「いえ、俺も喫いたいと思ってたんで」
アタルが立ち上がって部屋を出ていくと、菱和は尊に軽く会釈をしてからそのあとをついていった
***
「ちょっと外出ても良いか?」
「うん」
上着と煙草を携えたアタルは、菱和を玄関へと促す
菱和も自分の煙草を持ち、靴を履き始めた
「おお、寒っ‥」
戸を開けると、風が頬に突き刺さってくる
元旦の深夜は凍て付いていた
空は驚くほど澄んでおり、暖かく賑やかな室内とは正反対の静寂に包まれている
腕を擦りながら玄関先まで出ると、アタルはジッポを取り出す
手を添えてラッキーストライクに火を点け、一息吹かした
ジッポを手渡された菱和も、JPSに火を灯す
「付き合わせて悪かったな」
「いや、全然」
二人が吐いた煙と言葉が、静寂に消え失せる
アタルは軽く頭を掻き、ボソリと呟いた
「‥‥‥‥何つーか、‥‥ありがとな」
「‥‥、何が?」
「チビ助のこと。‥‥たーから聞いた。過呼吸のことも、お前んちに暫く泊めてたってことも。色々世話掛けたな」
尊からならば理解に苦しむことはないが、アタルからの謝辞は予想外だった
菱和は目を瞬かせ、その真意を探る
物心ついた頃から、アタルは弟が二人いるような感覚を抱いて過ごしてきた
幼馴染みであり親友でもある尊、その弟であるユイ
ユイと幼馴染みであり、アタルの従兄弟である拓真
4人はいつも一緒におり、沢山の時間を共有してきた
バンドを組むことになったのも、極自然な流れだった
ユイの周りにはいつも
兄である尊が、幼馴染みの拓真とリサが、そしてアタルがいた
その誰もが皆一様に、ユイを想っている
それは今までもこれからも不変な、ただ一つの事実
───あいつ、ほんと幸せ者だな
ユイとアタルの関係とユイを取り巻く人物の関係性を一つずつ辿っていくと、アタルの想いがじわりと心に滲んでいく
少し照れ臭そうに感謝を述べるアタルの横顔を見て菱和は少し口角を上げ、煙草を吹かす
「んーん。好きでやったことだから」
「そっか‥‥‥‥ほんとに好き、なのな。あいつのこと」
「うん。好きだね」
ユイへの想いをきっぱりと口にする菱和の実直な想いに心底安堵し、アタルは高らかに笑い声をあげた
「っふはは!云うねぇ!お前ほんと面白ぇな!!お前のそういうとこ、俺結構好きよ」
「‥俺も好きすよ、あっちゃんのこと」
「あ?‥云われなくても知ってるっつーの!」
無口で無愛想な菱和が時折“ぶっ込んで”くる所もお気にのようで、菱和という人間を知れば知るほどそのキャラクターがツボにハマっていく
反面、菱和はアタルのギターの技術や作曲のセンスに一目も二目も置いており、豪快で清々しい性格にも好感を抱いている
他の面々に比べると共に過ごした時間は少ない二人だが、何時しか妙な連帯感が構築されていた
それは互いに感じているところで、奇妙ではあるもののそれを受け入れることには何の抵抗も無いようだった
アタルが一頻り笑った後、菱和がぽつりと話し出した
「‥‥‥どうしたら良いすかね」
「ん?」
「ずっと迷ってたんすよね。ユイと俺のこと、尊さんに話して良いもんかどうか。‥あっちゃんと佐伯には話して良かったけど、尊さんはちょっと違うっていうか‥‥やっぱ“お兄さん”ってなると‥‥‥‥」
そこまで云ったところで、今度は菱和が頭を掻く
その気持ちもわからんでもない
ダチに話すのとは訳が違う
況してや、ユイと菱和は一般的な恋愛関係ではない
自分達の関係を打ち明ける前に外食に招かれたり年越しを共に過ごしたり
順番は逆になってしまったが、打ち明けるならば尊が確実に石川家に居る今がチャンスだ
話したところで何がどう変わるかは知る由も無いが、菱和は菱和なりに色々思案していたようだった
───こいつ、蕎麦湯がきながらそんなこと考えてたんか
アタルはふ、と笑みを零した
尊と自分の関係を知った上で殊勝に打ち明ける菱和に対し、真摯に返事を返す
「‥‥別に無理して話すこともねぇんじゃねぇの。俺らに話すのとは全然訳が違うんだから。俺から尊に話すって手もあっけど、それじゃなんか、やだろ」
「‥‥んー、‥‥‥そうすね」
菱和は頭を掻きながら煙を吐いた
気を揉むのは十分わかる
何処を見るわけでもなくぼーっと煙草を咥える菱和を見つめ、アタルは口角を上げた
「───何となくだけど、尊はお前らのこと気付いてんじゃねぇかな」
「‥‥‥‥マジ、すか?‥‥なんか、そんな雰囲気ありました?」
「結構前に尊と電話したとき云ってたんだけどよ。あのチビ、『名前は出さなかったけど“大好きな人が居る”』って、すっげぇ嬉しそうに喋ってたみてぇ。あいつの云う“大好きな人”って、1000%お前のことだろ」
“1000%”という奇想天外な数値に圧倒されつつ、菱和は面食らった
「‥‥‥‥それってほんとに“1000パー”俺のことすかね」
「ああ。“俺”が云うんだから間違いねぇぞ」
アタルは親指で自分を差し、したり顔をする
“尊の親友であるアタル”からの言葉は、ユイの云う“大好きな人”が菱和であるという信憑性をより高める
『兄ちゃん、聞いて。俺ね、今、すっげぇ大好きな人がいるんだ。でね、ちょっと前にわかったんだけど、その人も俺のこと好きでいてくれてたんだよ。なんか、めちゃめちゃ嬉しくてさー‥‥』
図らずも、ユイも菱和との関係を尊に打ち明けたいと思っており、そして既に伝えていたようだ
だが、“名前を出さなかった”ということを考えると、やはり『自分達の関係は受け入れられ難い』という思いがあったのだろう
それでも、大好きな兄に自分の存在を伝えてくれていたことは“嬉しい”の一言に尽きる
「んで、この前飯食いに行ったんだって?そんときはさ、別れ際のお前ら見て、なんか知んねぇけど『安心した』っつってたよ」
「安、心‥‥」
『尊が自分をどう捉えているか』
菱和にはそれがわからなかったが、少なくとも“弟が気を赦している相手である”ということは火を見るよりも明らかだったようだ
そうでもなければ、前回も今回も、わざわざ家族団欒の場に長身で無愛想な人間を招きはしないだろう
アタルの見解では『恐らく尊はユイと自分の関係に気付いている』とのことだが、尊本人の口からその事実を聞くまでは定かではない
だが、こんな見た目の自分であっても“安心感”を与えられていたのだとしたら、それでもう十分だと菱和は思った
───そっか
深く吸い込んだ煙草の煙をゆっくりと吐き、穏やかに笑んだ
アタルは短くなった煙草を地面に落とし踏み付けると、新しい一本に火を点けた
「‥‥石川家の“カテーのジジョー”的な話、聞いたことあるか?」
「ああ、うん。ユイが過呼吸になったときに聞いた」
「そっか。なら話しても大丈夫だな。俺もそこそこ知ってんだけどな、っていうかほんの少し関わってんだけどよ」
「‥‥そうなんすか」
「おー。‥‥ある日突然尊がユイ連れて、血相変えてうちに来てよ‥‥‥‥」
アタルは当時のことをゆっくりと語った
13年前
自宅で拓真と遊んでいたアタルは、夕方の来訪者を出迎えた
尊は息せき切った様子で玄関に佇んでおり、その傍らには、尊に手を握られて目を泳がせているユイがいた
「よぉー尊、“たっち”も。どうしたんだよ?」
「悪い。ちょっとこいつ預かってて欲しい」
「ん、それは良いけど‥‥あ、飯食ってく───?」
いつもの調子で接していたアタルは、改めて尊の顔を見てゾクリとした
どちらかというと冷静沈着な尊の眼差しから冷静さがほぼ欠落しており、憤怒、悲哀、憎悪───どす黒い感情が滲出していた
そんな尊を見たのは初めてのことで、その幼馴染みの表情は恐らく一生涯脳裏に焼き付いて離れないだろうと思える程のインパクトだった
「あ、ただしくんだ!」
とても『遊びに来た』とは云い難い雰囲気を感じ取ったアタルが怪訝な顔をしていると、そんなことは知る由もない拓真がリビングからドタバタと現れる
拓真は歓迎ムードだったが、ユイは不安げに尊を見上げてばかりいた
「‥兄ちゃ‥‥」
「お前はここに居な。アタルと拓真に遊んでもらえ」
「や‥‥兄ちゃん‥やだ」
尊はなかなか手を離さないユイの頭をぽん、と叩き、優しく笑った
「あとでちゃんと迎えに来るから。‥アタル、頼む」
「え、おい‥‥」
半ば無理矢理にユイを託すと、“弟を想う兄の顔”から再びどす黒い感情を剥き出しにし、尊はアタルの自宅を去った
『“なにか”あったのだ』
『放っておけない』
直感的にそう思ったアタルは、閉まりかけていた戸を思い切り蹴飛ばし開け放った
尊に託されたユイと、ドアを蹴飛ばした音に驚いた母の怒声などお構いなしに、アタルは尊を捜し近所を走り回った
辺りは夕暮れ、陽は沈みかけ足元も暗くなり、街灯が疎らに点き始めている
ふと目についた公園に尊が居るのを見つけ、一目散に駆け寄る
公園に足を踏み入れ尊に声を掛けようとしたところで、アタルはその動きを止めた
───あれは‥‥尊の叔母さん‥?
公園には、尊の他に尊の叔母の姿があった
尊は、先程見せたどす黒い感情の全てを叔母に向けて立っていた
対する叔母は、何やら青ざめた表情だった
「だから違うのよ、唯くんの“あれ”は‥」
「何が違うんだよ?あいつは何も喋らなかったけど、あんたの名前出した途端顔色変えたんだ。絶対あんただろ」
「だから、違うの。誤解よ‥‥あの子が、いけないのよ」
「あいつが悪いから、躾けたって云うのか?躾であんな身体になるのか?それともあれが“普通”なのか?だったら、世界中の子供の身体に痣が出来てるだろうな」
「なん、違‥‥」
「あんた、大人のくせに“躾”と“虐待”の違いもわかんないの───?」
二人でなにか話している
間に割って入ることを何となく躊躇し、アタルは公園の入り口で様子を窺った
内容は聞き取れないが、如何にもただならぬ状況であるということだけははっきりと認識出来た
「───もう二度と家に来るな。俺にも家族にも、近寄るな」
程なくして尊が一歩身を引き、叔母を残したまま公園を去ろうとした
叔母は激しく狼狽え、尊を引き止めようとしている
『行くならここだ』と、アタルは尊に駆け寄った
「! アタル‥‥たっちは?」
「悪り、お前になんかあったんだと思って‥‥置いてきちった」
バツが悪そうな顔をするアタル
尊は軽く溜め息を吐き、呆れ顔で云った
「‥‥そっか。やっぱこんな時間に連れてったのが悪かったな。俺の方こそごめん、有難う。もう帰るから」
先程の表情がまるで嘘のように、尊は“少年の顔”に戻っていた
見慣れた尊の顔を見て、アタルは安堵の表情を浮かべる
「尊くん待って、話を聞いて‥」
狼狽えたままの叔母が尊の腕を掴み、歩みを制止する
途端、尊はその腕を思い切り振り解き、また“あの”顔になる
そして、目の前に居る幼馴染みから一生聴く機会がないと思えるほど冷徹な声と言葉が、アタルの耳に谺した
「──────くたばれ。クソババァ」
アタルの安堵は忽ち消え失せ、尊の憤りを肌で感じた
そのうちアタルの母がユイと拓真を連れて公園に現れ、尊とアタルは事情を説明し、ユイへの虐待の実態が次第に明るみになっていった
「‥‥‥‥勿論オバサンにゃムカつきMAXだったろうけどよ、あいつがいちばん怒ってんのは自分自身だったんだよ。一つ屋根の下で一緒に暮らしててユイが酷てぇ目に遭ってたのに何も気付かないでいた‥って。『未だに後悔してる』って、たまに漏らすんだ。‥‥尊がどんだけユイのこと想ってるかは、俺がいちばん理解しているつもりだ」
尊は、親友にどす黒い自分をさらけ出すことも厭わずユイを護った
自らの範疇内でユイが虐げられていることに愕然とし、その事に気付かなかった自分の愚かさを卑下した
ただでさえ、母親が居ないことでユイは淋しい思いをしていた
勿論自分も同じ思いなのだが、『母が命を賭して護った大事な弟』だと、誰に云われずとも『自分は“兄”だから』と、直向きにユイを思いやって過ごしていた
そしてそれは、アタルを始めとした周りの目から見ても明らかだった
『もっと早く気付いてれば───』
ユイが過呼吸になった折、尊は幾度となく云い放ったその言葉をまた口にした
相手がアタルだからこそ安心して吐ける、弱音
「‥‥尊はさ、すげぇ“強か”なんだよ。あいつだって相当傷付いたと思う。でも、俺に話すのはいっつも“後悔”ばっか。てめぇのことなんかよりもまず、ユイのこと優先してんだよ。‥まぁでも、それが“血が濃いもの同士の絆”的な、さ。あいつら見てたら、『男兄弟って良いなぁ』とか思うんだよな」
そんな態度はおくびにも出さない
だが、それは確実に在る
無償の、愛
ユイと尊
石川家の“兄弟の絆”を聴き、菱和はゆっくりと頷いた
「‥‥‥‥うん、それは何となくわかる」
「‥‥尊とよく似てるよ、お前は。表面上はクールだけど、頭ん中じゃチビのことで細々と悩んだりしてるとことか、な」
くす、と笑い、アタルは煙草を咥えた
『アズって、兄ちゃんに似てるかも。‥‥よくわかんないけど、似てる‥気がする‥‥』
何時かユイに云われた言葉が、菱和の頭に蘇る
「‥‥‥‥、それ、前にも云われた」
「あ?」
「前にユイに云われた。尊さんと俺が『似てる』って」
「ははっ!そっか!ちゃらんぽらんなくせに意外と理解ってんじゃん、あいつも」
アタルはしたり顔でニヤニヤとした
露程も感じていなかったことをアタルにも指摘され、再び面食らう菱和
その肩を軽く叩き、アタルは穏やかに呟いた
「誰だって、家族の幸せを望むだろ。‥‥尊も、ユイが幸せなら相手が誰だろうと文句ねぇよ、きっと」
それは、『その相手が自分でも良いのだ』と思わせてくれる台詞だった
菱和にとって、石川兄弟と深く長い付き合いのあるアタルからの言葉は心強いものだった
ユイへの想いも些細な悩みも真摯に受け止めてくれた“リーダー”に、菱和は心から感服した
ユイを幸せにしてやりたいなんて、そんな烏滸がましいことは思わねぇ
でも、ユイが幸せに感じられるのなら
自分の存在が、少しでもユイの為になるなら
俺はずっとユイの傍にいる───
そんなことを思いながら、菱和は煙草の煙をぼんやりと見つめた
「‥‥‥‥あっちゃん」
「あん?」
「ありがとね。‥‥やっぱあっちゃんのこと好きだわ」
「ぶっ‥はは!!だぁかぁら、知ってるっつーの!‥‥と、そろそろ中入るか‥‥凍っちまいそーだ‥‥‥続きは中で、酒でも呑みながら話そうぜ」
「うん。なんか作ってくれる?」
「おお。お前結構イケる口だから安心したよ」
アタルはケラケラと笑いながら先程踏み付けた煙草を拾い、菱和を石川家へと促した
126 Inte ensam.
日付が変わってから
父さんは寝ちゃったけど、俺たちは朝までずっと起きてた
いつだったか、まだ兄ちゃんが家にいた頃
拓真とあっちゃんが俺んちに遊びに来て、夜中までトランプをやったことがあった
あっちゃんは「そのときのリベンジ」とか云って、“三枚大富豪”を挑んできた
『手持ちのカードが三枚しかない』ってこと以外は普通の大富豪と変わらないんだけど、これが結構白熱する
例えば、俺からカードを出すことが出来るとして、俺の手札が8、8、2で、あっちゃんがジョーカーを持っていなかった場合、500%の確率であっちゃんに勝てる
‥‥500は云い過ぎか
とにかく、あっちゃんに一枚もカードを出させることなく勝てる
まず俺が8を出して、その場を流して2を出す
2より強いカードはジョーカーしかないから、最後に8を出して終わり
場合によっては6とか9とかすごい中途半端なカードでも勝てたりするから、ほんとに白熱する
手札の中でたまたま最強のカードが一桁だったりしたら、もう緊迫感が半端ない
何回目かの勝負の時に、俺は11を出した
11は特殊なカードで、その場が流れるまではカードの強弱が逆転する『イレブンバック』というルールが適応される
3が最弱で2が最強だったのが、2が最弱になって3が最強になるんだ
俺はドヤ顔で4を出すあっちゃんに対して、にんまりと笑いながら3を出した
最後は8を出して、その場を流して終わり
こんな低レベルな勝負でも本気で悔しがるあっちゃんを見て、兄ちゃんも拓真も涙目になって笑ってた
結局、あっちゃんは連チャンで俺に負けまくってすっかりいじけて、アズを連れて煙草を喫いに行っちゃった
運が無いんだな、きっと
でも新年早々こんなことに運使っちゃって、俺は今年の後半どうなってるんだろ‥‥少し不安‥‥‥‥
あっちゃんとアズが煙草を喫いに行ってる間、兄ちゃんと拓真とリサの4人で普通の大富豪をやった
二人がなかなか帰ってこないから、3回くらいやった
知ってるルールを全部入れちゃうとワケわかんなくなっちゃうから、
・11バックあり
・2・ジョーカー上がり禁止
・マーク縛り無し
・スペ3返しあり
・都落ち無し
これくらいのルールでやった
成績は‥‥‥‥
俺は、あっちゃんには結構勝てるけど、兄ちゃんと拓真とリサにはあんまり勝てない
多分、カードを出す順番が悪いんだろうなぁ‥‥
何も考えないでポンポン出すからだめなんだろうな
でも、楽しい
皆と笑い合えることが
皆が一緒に居てくれることが
嬉しい
過呼吸になって失神したことで、家族だけじゃなくて友達にも沢山心配掛けちゃったけど
今までもこれからも、皆にはきっと沢山心配も迷惑も掛けちゃうと思うけど
『弱くても良いんだ』って教えてくれた
『俺は俺のままで良いんだ』って云ってくれた
だから、『もっと強くなる』って決めた
初詣に行ったら、“これからもずっと皆と一緒に居られますように”ってお願いしよう
‥‥‥‥毎年のようにあんま変わらないお願い事なんだけど、今は、ほんとに強く、そう願いたいんだ
125 晦日②
「台所、借りますね」
シャンディ・ガフを飲み干した菱和は辰司や尊に声を掛け、キッチンに立った
冷蔵庫を漁り、蕎麦を作る段取りをする
「お、待ってましたー。ってか、もうそんな時間か」
尊がリビングの掛け時計に目をやる
時刻は23:30頃
日付を越え、新年が始まるまであと僅か
つけっぱなしのテレビには、カウントダウンの瞬間を待ち侘びる参詣客で埋め尽くされた神社の様子が映っていた
頬杖をついて、拓真が皆に問う
「俺らはどうする、初詣?」
「行くかぁ?わざわざ面倒臭せぇなぁ‥‥」
アタルは新しいビールの缶を開けながら至極面倒臭そうな顔をした
「あっちゃんここにいれば?俺は行ってきたいなやっぱ。毎年行ってるし」
「俺もー!リサも兄ちゃんも行くしょ?」
「まぁ、起きられれば」
「私も」
「ねー、アズも行く?」
「‥‥みんなが行くなら」
キッチンにいる菱和は、ユイの問いに振り向き返事をした
「やった!‥でもさ、どうせ行くなら初日の出も見に行きたいな!」
「おいチビ、お前起きてられんのか?てか起きられんのか?」
「起きてられるよ!起きれるよ!あっちゃんこそ、そんな呑んだら寝過ごしちゃうんじゃないの!」
酒が進んでいるアタルは3缶目のビールを開ける
ユイの一言に、ふん、と鼻で笑った
「俺は親父さんと昼までのーんびり寝てっから良いんだよ」
「‥みんなで行きたいのに!ケチ!」
「まぁまぁ。じゃあ、アタルくんは俺と留守番ってことで」
「ですね!明日も昼間から呑みましょーや!」
意気投合する、アタルと辰司
尊がじとりと睨み付ける
「おいおい、呑兵衛共。程々にしろよな」
「だって、アタルくんと一緒だとついつい進んじゃうんだよー。ねー?」
「ねー!」
アタルと辰司が上機嫌で肩を組むのを、尊は呆れ顔で見つめていた
***
「出来ました」
菱和がダイニングにいる尊、アタル、辰司の前にそれぞれ丼を置いていく
「お、美味そー」
「良い匂いだねぇ」
湯気が立つ出来立ての蕎麦は、鴨南蛮のようだ
濃いめの汁に浸った蕎麦の上に、鴨肉と長葱が乗っている
シンプルながら、その見た目と匂いは「深夜に食しても申し分無い」と皆が感じた
「お好みで、天かすもどうぞ」
小鉢にたっぷりと盛られた天かすと七味唐辛子はセルフサービスにし、菱和はダイニングの空いている席に自分の丼を置いて座った
「わーい!俺入れるー!」
「俺もー」
「ユイ、私のも入れて」
「ほーい!」
「たー、七味くれ」
「はいはーい」
「あ。アタルくん、俺にもちょうだい」
「おいっすー」
各々が好みで天かすと七味を散らし、ユイ、拓真、リサは自分達の分をリビングのテーブルに運んでいった
「んじゃ、頂きまーす!」
「まーす」
蕎麦を啜る音が、一斉に響き渡る
菱和は箸を持ったまま、全員が蕎麦を口にするのを静観した
次第に、溜め息と共に感想が聴こえてくる
「‥‥あぁー‥‥‥‥美味しいね」
「‥ほんと、めっちゃ美味ぇ」
鴨の出汁と油分が溶け込んだ汁が、胃にじんわりと染みていく
蕎麦は更科で、するりと喉を通っていく
菱和の料理を初めて口にする尊と辰司は感嘆の表情を浮かべた
「『五臓六腑に染みる』って、このことを云うんだろうなぁ‥‥」
「ね!アズの料理、美味いっしょ!」
「うん。店で食うより美味いかもしんない」
「あー‥俺もう一杯食いてぇ」
「私もお代わりしたい」
蕎麦一杯で『お代わりをしたい』とまで云われるとは思ってもみなかった菱和は、「口に合ったようで何よりだ」と安堵した
「‥‥お粗末様です」
***
「あ。ねぇ、あと5分!」
皆が蕎麦を平らげた頃、ユイがテレビに注目した
つけっぱなしのテレビの時計表示は23:55
間もなく、新年が明けようとしている
ユイは、毎年のことながら年が明けるその瞬間を今か今かと待ち侘び、テレビに映っているタレントらと共にカウントダウンをする
他の皆も何となくそわそわする気持ちは同じだが、ユイは毎年人一倍ハイテンションでそのときを迎える
アタルはテレビに食い入るユイを呆れ顔で見た
「年が明けたからって、特別何も変わんねぇだろ」
「そんなことないよ!やっぱなんかちょっと違うじゃん!」
「まぁ、毎年毎年のことだけど、この瞬間はちょっとわくわくしちゃうよな」
「だよね!」
顔を見合わせるユイと拓真を尻目に、アタルは頭を掻いて溜め息を吐いた
「そんなもんかねー‥‥」
「あーあ、あっちゃんてば。もう純粋な気持ちで新年を迎えられなくなったんだね‥‥年とったね」
「るせぇバーカ。まだまだ気持ちは若けぇつもりだよ」
「“つもり”でしょー!?来年で幾つになるっけー?」
「24だよ。なんか文句あっか」
「別にー。10代と20代の越えられない壁を実感してるだけ」
「んだよそれ。んなこといやぁひっしーだって年越しゃ二十歳になんだろうがよ」
「あ、そっか。そうだったね。でもアズはハタチになっても高校生だし!」
「俺だってまだ学生だっつの!」
「ふーん、でもいつまで学生でいるつもりー?来年はちゃんと卒業出来るのかなー?」
「───てめえぇ、調子こきやがってこの野郎!!!」
「ふはは、怒ったー!」
ユイとアタルはふざけて部屋をどたばた走り回る
そのうちユイはアタルに捕まり、羽交い締めにされた
そしてその間に日付は越え、新年がスタートしてしまっていた
日付が変わる瞬間を待ち侘びていた筈が、すっかりその時を逃してしまったユイ
果たしてどんな顔をするのかと思いを馳せながら、拓真たちはじゃれ合うユイとアタルを静観していた
ふと視線を感じ、ユイは顔を上げた
「‥‥え、何?」
拓真がニヤニヤしながらテレビを指差した
時計の表示は、0:03と表示されていた
「──────あ、」
ぽかんと口を開け、テレビを見つめるユイ
ただただ呆気に取られたような、間抜けな顔をしている
大方「こんな感じになるんだろうな」と思っていた拓真と尊は、必死で笑いを堪えている
リサと菱和は素知らぬ顔をし、テレビを一瞥した
「‥‥‥‥‥‥」
「‥‥‥‥‥‥‥‥‥」
「‥‥‥‥あけおめ」
皆が沈黙する中、辰司がにこりと笑ってそう呟いた
ユイと拓真、アタルは噴き出した
「っことよろー!!」
「はははっ!今年も宜しくでーす!」
一同が、新年を慶び笑い合う
新しい年が明けてもきっとこの状況はずっと変わらずにいるだろう
昨年を思い起こせば良いことも悪いことも含めて様々な出来事があったが、新たな気持ちで前に進んでいこうと、各々がそう思っていた
日の出まであと6時間余り
辰司は一足先に就寝することにしたが、他の面々は早朝から初日の出を見に行く予定でおり、その後すぐに初詣を控えているのにも関わらず、どこからかトランプを持ってきて興じる様子
そしてアタルは冷蔵庫からビールを取り出し、尊と菱和に手渡している
石川家の夜は「まだ始まったばかり」のような雰囲気に包まれていた
124 晦日①
「来たよー」
「お邪魔します」
「おーいらっしゃい。あがってあがって」
晦日の夕方
自室でギターを弾いていたユイは、来客の声に気付いた
一旦ギターを置き、階段をかけ降りると、尊が玄関で来客を迎え入れていた
「‥拓真!リサも‥‥どうしたの?」
「よー。今年は石川家で年越ししようと思ってさ。あっちゃんもあとで来るよ」
「菱和くん、年越し蕎麦と雑煮作ってくれるって」
尊が振り返り、笑む
食材らしきものがぎっしり入っているサミット袋を提げた拓真とリサの後ろには、同じく袋を提げた菱和がいた
「‥‥今晩は」
「アズ‥」
目を丸くするユイを尻目に尊はリビングへ向かい、拓真たちも颯爽と靴を脱いで上がり込む
階段で3人を見送ると、菱和がユイに話しかけながら玄関をあがる
「‥‥うちに泊まってる間、佐伯から電話きたろ。あんときに、『“ここ”で年越し出来ないか』って云われたんだ」
「そう、だったん‥だ」
「お前が俺んち来た日に、尊さんとあっちゃんに相談してたらしいよ」
「知らなかっ、た」
「サプライズ的なやつじゃね」
そう云って、少し口角を上げる
「実家で年越さなくて良い、の?」
「ちゃんと話して来たから」
「そっ‥か」
「‥‥蕎麦と雑煮、食える?」
「うん、好き」
「そ。じゃ、夜まで待ってて」
菱和はユイの頭をぽん、と叩き、リビングに入っていった
ユイは未だきょとんとしていたが、菱和の香水の香りを感じると、家族とだけでなく幼馴染みや菱和と晦日という日を過ごせるのだと次第に実感し、嬉しそうにリビングに向かった
数十分後
ボストンバッグを背負ったアタルが石川家に来た
呼び鈴を押さずあがり込み、人一倍テンションを上げてリビングに入ってくる
「よー、遅くなった!」
「あっちゃん、いらっしゃい」
「案外元気そうだなチビ!‥‥ほい、お前の」
アタルはユイの頭をぐしゃぐしゃと撫で回すと、バッグからスウェットを取り出し、菱和に手渡す
「俺のがいちばんサイズ合うだろーと思ってよ。寝るときに着な」
「ありがと。借ります」
菱和は軽く会釈して、スウェットを受け取った
皆がリビングに会し、テレビを観ながら談笑をする
“合宿”宛らの雰囲気が漂い、ユイはわくわくした
『石川家で年越しをする』と提案をしたのは、拓真だった
年末年始は確実に父と兄がいるが、普段のユイは自宅で一人で過ごすことが多い
今までも食事や家事の面で何かと心配することは多々あったが、数日前に過呼吸になったことでその心配は増すばかりだった
ユイが少しでも気を紛らわすことが出来ればと思い、拓真は前もって尊とアタルに相談をしていたようだった
尊もアタルも快くその提案を受け入れ、菱和もその話を聞き入れた
当日まで黙っていたのは、菱和も云っていた通り『ユイをびっくりさせよう』と思ったからだ
和やかなときが流れる石川家のリビング
ユイは家族や友達の気遣いと優しさに顔を綻ばせ、皆の顔を一通り見回しながら笑んだ
***
21:00頃
年越し蕎麦に備えて夕食もそこそこに済ませ、皆まったりと過ごしている
「おーやーじーさんっ。なんか酒作りますかっ」
アタルがユイの父・辰司に話し掛ける
ダイニングのテーブルで柿ピーをつまみながらのんびりと酒を呑んでいた辰司は、上機嫌になった
「ふふ、じゃあお願いしようかな。アタルくんのカクテル飲むの久し振りだなぁ」
「ビールベースで作って良いすか?」
「うん、オススメのやつで」
「りょーかいっす!」
アタルは前もって冷蔵庫で冷やしておいたジンジャーエールを取り出した
同じく冷蔵庫で冷やされたビールと共に半量ずつグラスに注ぐと、あっという間にシャンディ・ガフの出来上がり
尊と自分の分、そしてもう一つ、同じように作っていく
「どぞ、シャンディ・ガフっす!」
「おおー、頂きます」
「お代わりあったら云って下さいね!尊ー、酒入ったぞー!」
「おー、今行く」
「ひっしー、お前もこっち来い!」
アタルに呼ばれた菱和と尊は、ダイニングに移動する
「ん、シャンディ?」
「美味しいよー、どっちの味も楽しめて良いねぇこれ」
辰司はにこにこしながらシャンディ・ガフを飲んでいる
酒が入りすっかりご機嫌の父を一瞥し、尊は軽く溜め息を吐いた
「‥で、何で菱和くんもこっち呼んだわけ?」
「あ?んなもんコレ呑ます為に決まってんだろ」
そう云って、アタルは菱和の目の前にシャンディ・ガフの入ったグラスを置く
菱和は何度か目を瞬かせた
「‥‥俺まだ未成年すけど」
「っかー‥‥‥‥んとにお前は‥‥真面目かっ!!19もハタチも大して変わんねぇっつの!今日くらい付き合えって!親父さんは出来上がってるから何も心配いらねぇし、お前の分はビールの量少なくしといたから。ほら、呑め」
「‥‥‥‥」
『まだ未成年』とは云いつつも、実は菱和は何度かアルコールを飲んだことがある───しかしそれは不良時代の話だ
久しく口にしていないアルコールに少し躊躇ったが、菱和はぐ、とシャンディ・ガフを飲み下した
アタルの云う通りビールの風味は抑えられていたが、混ざり合ったビールとジンジャーエールの喉越しが心地好く感じた
「いい呑みっぷりだねぇ。はい、かんぱーい」
辰司は自分のグラスを掲げ、菱和に乾杯を促した
菱和はノリノリの辰司に少し吹き出しそうになりつつ、グラスを合わせる
カチ、と小粋に鳴る音に、尊は目を細めた
「‥‥菱和くん、だいじょぶ?」
「‥‥イケそうです」
菱和はこくんと頷き、二口目を飲む
「‥‥‥まぁ、今日くらいはいっか」
「そーそー!オオミソカなんだからよ!っつーかお前、実は酒呑んだことあるだろ?」
「‥‥、何回か」
「だよなぁ!やっぱそーこなくっちゃな!」
「何がだよ、全く」
思いきりドヤ顔をするアタルを見て、尊は呆れた顔をした
続いてアタルは冷蔵庫に仕舞っておいたレモンを取り出し、輪切りにする
グラスを3つ用意し、先程使ったジンジャーエールを注ぐと、グレナデンシロップを大さじ2杯分ずつ加える
軽くステアすると、グレナデンシロップの赤い色がジンジャーエールに溶けていく
仕上げに輪切りのレモンを浮かべ、ノンアルコールのカクテルが出来上がった
「ほい、お前らの」
アタルはシャーリー・テンプルの入ったグラスをリビングに持って行き、ユイと拓真とリサにそれぞれ手渡す
「あ、これ!めっちゃ好きなやつ!」
「やった。頂きまーす」
ユイと拓真は直ぐ様口をつけるが、リサはまじまじとグラスを見つめていた
「すごい綺麗な色‥‥何入ってるの?」
「ジンジャーエールと、グレナデンシロップっつって、ザクロのシロップ。“シャーリー・テンプル”っていうカクテルで、よくこいつらに作ってやってんだ。ま、一口飲んでみ」
「うん‥」
アタルに促され、リサはグラスに口をつけた
ジンジャーエールの炭酸に溶け込んだグレナデンシロップは、ドレンチェリーのような濃く甘い風味を残しつつも、全体のバランスを保っている
シンプルな刺激のジンジャーエールに、鮮やかな彩りととろりとした甘みのグレナデンシロップ
その配分は、絶妙だった
「どうよ、リサ?」
「‥‥‥‥、‥‥美味しい。飲みやすいし綺麗だし、結構好きな味」
「‥だべ!美味ぇべ?俺もコレ大っ好きなんだよ、酒は入ってねぇけど」
アタルは満足げにニヤニヤと笑った
アタルが振る舞ったカクテルにのんびり舌鼓を打つ一同
晦日も残り数時間
いつもより賑やかな石川家の夜が、まったりと更けていった
123 lång telefonsamtal
“家族会議”が終わり、自室でぼーっとしていたユイは、ふと時計に目をやる
時刻は間もなく日付を越えるというところ
───まだ起きてるかな
思い立ち、携帯を手に取る
操作をして画面に映し出されたのは、菱和の名前
少し躊躇った後、ユイは通話ボタンを押す
3コール目で、低く嗄れた声が聴こえた
『‥‥‥‥はい』
「あ、アズ‥‥まだ起きてた?」
『うん。‥‥早速かけてきたな』
「へへ‥‥ごめ‥‥‥」
『や、なんも』
「今、電話大丈夫‥?」
『ん。‥‥あ、今日は、‥‥っつーより今日“も”、ありがとな。一緒にいてくれて』
それはこちらの台詞───
ユイはそう思った
心が砕けそうになっていた自分の傍を片時も離れず、尽くしてくれた
沢山、愛情をくれた
何度お礼を云っても足りないくらいだ
それなのに、逆に菱和から感謝される
自分は何も返せていないのに───申し訳なく思うユイの耳に、菱和の声が届く
『‥‥今日の飯、マジで美味かった。また今度、お気に入りの店連れてって』
「‥うん。アズと行きたいとこ、沢山あるんだ。‥‥あ、冬休み中にたこ焼き屋さん連れてったげる」
『‥‥たこ焼き?』
「丸山商店街の端っこにある小っちゃいプレハブみたいなお店なんだけど、大きくてふわふわでめっちゃ美味いんだー‥‥おっちゃんが一人でやってるんだけど、いっつも多めに入れてくれたりお菓子とかジュースとかおまけしてくれんの。ソースも色々種類あってさ。おすすめは出汁がかかってるやつ。ふやふやになって味が染みて、ほんと美味いんだよ」
『へぇ‥‥それ超美味そう』
「うん、絶対食べてもらいたい!」
『‥‥じゃ、近いうち連れてって』
「うん!へへへ‥」
ユイは長年慣れ親しんだ味を菱和と共有出来たことが嬉しかった
菱和が自分の好きなものを気に入ってくれ、共有出来るものがどんどんと増えていく
恐らく、菱和にもそういうものが存在するだろう
同じようにそれも共有していければと、ユイは思った
顔を綻ばせていると、煙草の煙を吹かしているのであろう息遣いが聴こえた
嗄れた声が、ユイに問う
『‥‥‥‥、‥‥なんかあった?』
「う‥?なんか、って‥‥」
───なん、で‥わかっちゃうの‥‥
ユイはギクリとした
少し前までこの部屋で家族会議が行われ、〆に号泣した
気持ちは落ち着いているものの、腫れぼったい目が瞬きをする度にぼんやりと霞む
『‥‥別に電話寄越すのに特別用事なんかなくても良いんだけどさ。‥‥‥‥声聴けるだけでも嬉しいしな』
電話越しで煙草を吹かしながらそう話す菱和の声
ひどく穏やかなトーンで『嬉しい』と云われたユイは一気に顔が熱くなり、心拍数が上がった
声だけのやり取りは、顔が見えない分一緒にいるときとはまた違った緊張感があり、ユイの脳内は菱和の一言で埋め尽くされていく
『‥‥‥、‥どした?』
「‥‥も、変なこと云うから‥」
『あ?俺なんかまずいこと云った?』
「‥‥自覚、ないの‥‥‥‥」
『‥‥‥‥、“声が聴けるだけで嬉しい”って?』
「ん‥‥そんな何回も云わないで」
『ふふ‥‥でもほんとのことだからしゃーないべ』
「そー‥‥ですか‥‥‥‥」
電話口で菱和がくすくす笑うのが聴こえる
今まで菱和に云われた言葉で何度も赤面してきたユイは、あまり感情を表に出さないタイプの菱和が『実は割りと思ったことを口に出す方』なのだと思った
『‥‥‥‥なんかあったか?』
軽く咳払いをし、ユイは話し出した
「ん‥‥‥。‥‥あんね、父さんと兄ちゃんに、『カウンセリング受けてみないか』、って云われたんだ」
『カウンセリング‥‥?』
「うん‥‥‥‥」
ユイは家族会議が行われたことを打ち明けた
家族が自分のことを考えてくれていたことに感極まって涙してしまったことも、全て話した
菱和はユイの話を黙って聞いていた
話し終えたところで、また煙を吹かすような息遣いが聴こえる
『そっか‥‥‥‥。‥‥お前は、どうする気でいるの?』
「‥‥、やるだけやってみようかなって思ってる、けど‥‥」
『‥‥けど?』
「ん‥‥不安というか緊張というか‥‥‥‥大丈夫かなぁ、って‥‥ちゃんと自分の話出来るかなぁ、とか‥‥」
『その辺は気にする必要ねぇよ。相手もプロだからな、ちゃんとお前の気持ちに配慮して話してくれるだろうし、お前が話しやすいようにちゃんと環境整えてくれるよ。‥‥カウンセラーとの相性もあるだろうから、“合わねぇ”と思ったら変えてもらえば良いし。‥‥俺もお前の話は聞くから、いつでも云いな』
「‥‥、うん、そっか‥‥‥‥。‥‥でも、カウンセラーの人は仕事でそういうことするでしょ。なん、で、アズは‥そこまでしてくれるの‥‥」
『‥“なんで”?‥‥お前が辛いとか苦しいとか感じてること自体めちゃくちゃ嫌なんだよ俺は』
「‥、だから、何でそこまで想ってくれるの‥‥?」
『‥‥“そんくらい好き”ってことだよ。お前が苦痛に感じてることは、全部取り除いてやりたい』
当然菱和の気持ちは嬉しいのだが、“相手にどこまで寄り掛かって良いものなのか”という判断が、ユイにはまだ難しいようだ
「‥‥‥、俺、ね、距離の取り方っていうのかな‥‥そういうの、まだよくわかんなくて‥‥‥‥拓真とかリサとは違った距離感‥でしょ、アズとは‥‥」
『‥‥‥‥、少なくとも、佐伯たちとは違う距離感で見てくれてんのな』
「うん‥‥そ‥だね‥‥やっぱり、違うよ、ね」
『‥‥。‥‥そんならさ、あんま理屈で考えんな。“何でかな”と思うことがあったら、“それくらい好きなんだな”って思えば良い。実際、単純にそれだけのことだから。‥‥距離の取り方なんかも、お前のペースでゆっくり落としてけば良いんじゃねぇの』
「‥‥、俺がそういうこと理解できるまで、待ってくれる‥‥?」
電話口から、ふ、と笑む声が聴こえる
『なんぼでも付き合ってやるよ。‥‥でもさ、云っとくけど、俺もお前の云う“距離感”とか探り探りだからな』
「そう、なの?」
『だって、まともに恋愛すんのお前が初めてだもん』
「‥‥ほんとに?」
『ほんと。っつーか、こんなことで嘘吐いたり変に見栄張る必要なくねぇ?』
「いや、だって‥‥慣れてるから‥‥‥‥」
『慣れてねぇっつの。ほんと疑り深いよな、お前って』
「だっ、て‥‥わか、ないんだも‥」
『そ。‥‥ま、その辺もゆっくり慣れてきゃ良いんじゃねぇの。‥‥‥‥俺は結構、楽しんでるよ』
「楽、しい‥‥?」
『‥‥お前の色んな顔とか反応見れんのが、楽しい。まだ見せてない顔も、沢山あんだろ。これから先もそういうのが沢山見れるんだなって思うと、結構楽しみだよ』
───そういう考え方もあるんだ‥‥
ユイは菱和の言葉に感心すると同時に、楽しむ余裕がある菱和が少し羨ましくなった
「‥‥俺も、アズの色んな顔見たい。もっと、アズのこと沢山知りたい。‥‥‥‥これからも、宜しくお願いしま、す‥‥」
『ふふ‥こちらこそ。‥‥‥‥あ、そだ。さっき部屋漁ってたら我妻のCDもう一枚出てきたんだけど、聴く?』
「‥あ‥‥うん!聴きたい!」
『今かけるから、ちょっと待ってな』
その後、菱和がかけた我妻のCDを電話越しで聴き、ユイはああでもないこうでもないと感想を云った
初めての長電話は明け方まで続き、終わった頃には空が白み始めていた
122 家族会議
拓真とリサを自宅に送り届け、石川家に到着する
自室に入り、ベッドに腰掛けて一息吐いていると、ドアをノックする音が聴こえた
「──────ユイ。ちょっと良いかい?」
辰司の声がする
ユイはドアを開け、父を出迎える
「何?」
「家族会議」
辰司の後ろから、尊が顔を覗かせた
「家族‥‥会義?」
ユイは少し首を傾げ、二人を部屋へと入れた
再びベッドに腰掛けると、尊と辰司はユイの正面に座り込む
辰司はユイの顔を見上げ、穏やかに話を切り出した
「───‥‥カウンセリング、受けてみないか」
唐突な話題に、ユイはきょと、とする
「‥カウンセリング‥‥?」
「‥‥‥‥お前、明らかに心に負担掛かってるだろ。今回のことでさ、親父と話し合ったんだ」
この度ユイが過呼吸になったことで学校から連絡を受け、二人は即日今後のユイのことについて既に話し合っていた
辰司は優しい表情をし、ユイを見上げる
「‥‥もし今後も同じようなことが起こったら、とか‥‥不安じゃないか?」
ユイは口を結び、俯いた
尊は地方で就職しており、辰司は出張が多く家を空けることが多い
今回はまたまた拓真たちがいてくれ事なきを得たが、もし今後誰もいない中過呼吸や失神という事態に陥ったら───
その不安感は、菱和の自宅に泊まっていた間もなかなか拭えなかった
「‥‥‥‥うん‥‥めっちゃ不安」
「そういう不安とか今後のことも含めて、色々頭ん中で整理したり、自分の力で何とか出来る手段をカウンセリングで得られれば‥と思ってさ。親父や俺の力じゃどうにもならないもっと深い部分に、お前自身の力でも適応出来るように‥‥カウンセリングはその手助けになるんじゃないか、って」
不安そうな顔をしている弟を優しく見つめ、尊はカウンセリングの必要性についてユイに説く
「“カウンセリング”って聞いたら『結構深刻なのか』とか『自分は病気なのか』と思うかもしれないけど、あくまで手段の一つであって、重く受け止める必要は全然ない。‥‥“生きづらさ”を解消する一手段として、『利用する』ってだけ。勿論、俺らもお前のこと全力でサポートするし」
ユイの人懐っこさや天真爛漫さは、幼い頃の出来事があったからこそなのではないかと尊は思っていた
多大な信頼を寄せる相手から二度と虐げられることのないよう、人一倍人懐っこく天真爛漫な人格が形成されたのではないか、と
それはユイが今までの人生経験の中で学び培ってきたものなので、悪いことではない
しかし、天真爛漫な笑顔の裏の大きな心の傷は、未だ癒えてはいなかった
こんな形で思い出させてしまったことを尊も辰司も悔やんでいるが、自分達の力だけではユイの心の傷は治せない
ユイ本人が受け入れるしかない現実が、何をどうやっても存在する
「‥嫌なら、また何か別の方法を探そう。‥‥ちょっとよく考えてみて」
大切な家族の一員を思いやっての提案
まずは、どんな手段でも良いからユイの力になれるものを足掛かりにし、自分たちに出来ることは精一杯やろうと決心する
ユイは家族に多大な心配を掛けてしまったことを嘆いていたが、そこは“家族なのだから”と、素直に二人の提案を聞き入れた
「‥‥‥‥うん、わかった。考えてみる」
ユイがゆっくりと頷いたのを見て、尊と辰司は胸を撫で下ろす
「っていうかさー、俺があのときもっと早く気付いてればこんなことになってなかったかもしんないなー‥‥って、未だに思うわ」
「尊‥‥それ云うなら俺だろう。お前も子供だったんだ、それにお前だって傷付いただろ。俺は父親なのに、ほんとに何にも気付かなくて‥‥情けないったらない‥‥‥‥」
「親父はしゃあねぇじゃん、生活リズムまるで違ったんだしさ。俺なんか毎日ずっと一緒に居たのに全然気付かなかったんだよ?‥マジでアホ過ぎて嫌んなる」
「何云ってるんだ。寧ろお前が誰よりも早く気付いたから、あの環境から抜け出せたんだ。お前がユイの為に啖呵切ったこと、今でも武勇伝だと思ってる。‥‥お前は良い兄貴だし、良い息子だよ。俺の自慢だ」
「やめろよそゆこと云うの。恥ずかしいから」
ユイは二人のやり取りを聞き、きょとんとしていた
兄と父が当時のことを未だに悔やみ、真剣に自分のことを考えてくれているということを、ゆっくりと実感した
「‥‥‥‥」
二人はふと、ユイの顔を見る
辰司は改めてユイに向き直った
「ユイ。お前も俺の自慢の息子だ。お前が笑顔でいてくれることが、父さんは何よりも嬉しい。‥‥辛いときに傍にいてやれなくて、ほんとにすまなかった」
「‥‥俺も、帰ってくんの遅くなってごめん」
辰司はユイに謝罪し、尊も頭を下げた
ユイはふ、と笑顔になり、二人に云った
「───大丈夫。‥‥『淋しくない』って云ったら嘘になるけど、拓真もリサもあっちゃんもアズも、みんな一緒に居てくれた。だから、大丈夫だよ」
いつものユイの笑顔
嘘偽りのない、心の底からの笑顔と言葉
ユイはきゅ、と拳を握る
「俺、もっと強くなりたい。ちょっと“あんなこと”思い出したくらいで過呼吸んなったりしないくらい、強くなりたい」
「それは違うよ。心が強い弱いってのとはまた別の話だから‥‥」
「わかってる。みんなが教えてくれた。でもね、強くなりたいんだ、ほんとに。弱い自分も自分だってちゃんと認められるように、強くなりたい」
「‥‥‥‥、なんかお前、暫く見ないうちにちょっと大人んなったな」
「みんなのお陰。みんなが、傍に居てくれたから」
ユイは再三、周囲への感謝の気持ちを述べる
辰司は溜め息を吐き、自分ですら付け入る隙のない友情や絆にほんの少しだけ嫉妬した
「はー‥‥拓真くんにもリサちゃんにもアタルくんにも、頭上がんないなぁ」
「良い友達持ったな、ほんとに。‥‥あと、菱和くんも」
「ああ、背の高い彼ね。随分仲良さそうだったなぁ。父さんは、あんまりみんなでワイワイするのは苦手なタイプかと思ってたけど」
「‥‥‥‥多分、今でも苦手だと思う‥‥」
「あ、そうなの?やっぱり苦手なんだ」
「俺さぁ、なーんか見たことある顔だなぁと思ったら3年くらい前に一回観てんだよな、菱和くん」
「え‥ほんとに?」
「うん。我妻さんの友達が主催したイベントでさ。夜遅かったからお前は連れてかなかったんだよ。アタルもバイトだったから俺一人で観に行ったんだわ」
ユイはピンときた
3年前、我妻の無茶振りに付き合わされたという菱和の話を思い出した
「‥‥あ、それ多分アズが云ってたやつだ。店長に無理矢理ステージ上がるように云われて演った、って‥」
「へぇ‥‥‥‥のわりには、めっちゃ上手かったけどな」
「‥ほんと!」
「我妻さんが『ベース教え込んだ』って自慢気に話してたけど、流石“我妻さんの愛弟子”って感じだった。今のプレイはわかんないけど、あれは相当な腕だったよ」
「菱和くん、か。今までにないタイプのお友達だな。穏やかで大人な子だね」
「うん!アズってね、昔はちょっとワルだったみたいだけど、今はもう喧嘩とかしてなくて、ベース上手いし料理も上手いし、超優しいんだ!」
「俺もアタルからちょいちょい聞いてるけど、“真面目で良い奴”って話だよ」
「そうかそうか‥‥‥‥そういえば今思い出したけど、“菱和”ってあけぼのに豪邸構えてる資産家さんと同じ名前だなぁ」
「ああ。それ、アズの実家だよ」
「え‥‥そうなの?“あの”菱和さんのご子息とお付き合いある、ってこと?」
「うん。あけぼのの実家も一回見たけど、マジで超でっかいよね!びっくりした!」
「‥‥ほぉ‥‥‥‥」
自分の知らぬ間にユイがそんなところまで人脈を広げていたことに驚き、辰司は息子のコミュ力の高さに感心せざるを得なかった
「‥‥‥‥ま、今後も家族仲良くやっていこう。至らぬ点も多々ありますが、宜しくお願いします」
「なに改まってんだよ」
「いやいや、大事なことでしょう。‥‥尊、ユイ。父さんはいっつも見守ってるからな。お前たち二人は、俺の大切な家族だ」
「親父、くさいからもうやめて」
尊は恥ずかしげもなく語る父の言葉に自分が恥ずかしくなり、手で顔を覆った
「‥俺も大好きだよ!父さんも、兄ちゃ、も‥‥‥‥ っ、‥‥ふあぁ‥‥‥‥」
笑顔で気持ちを伝えたユイの顔は次第に歪み、目からぼろぼろと涙が落ちる
感極まってしまったユイの頭を、尊が優しく撫でる
「なに泣いてんだよ、お前は」
「だっ、て、‥‥」
家族の愛情を、ひしひしと感じる
孤独を感じたことは、今まで沢山あった
だが、この絆は揺るぎはしない
ユイと尊の母親───辰司にとっては最愛の妻を亡くしたことは、ただただ無念でならない
ユイがその最愛の人と血を分けた妹から虐げられていたことは、更に追い討ちをかけたと云わざるを得ない
その出来事があってから、尊は叔母にも自分自身にも憤り、辰司は妻の親戚と絶縁することを決めた
その決断が正しかったのかどうかは誰にもわからないが、今こうして家族三人で過ごせていられることは何物にも代えがたい幸せである
ユイも尊も辰司も、その想いは皆同じだった
今後も家族が仲良く過ごしていけることを、願わずにはいられない
ユイは心から安堵して泣き、尊も辰司も号泣するユイを見守り続けた
121 チーズメンチカツ
ユイの父が帰宅したところで各々は車に乗り込み、いざ“きなり”を目指す
“きなり”のチーズメンチは、ユイが幼い頃から慣れ親しんだ味だった
家族の誕生日や入学式、卒業式などの折、お祝いを兼ねて父によく連れて行ってもらっていた
揚げ物中心のメニューでボリュームがあり、毎度毎度胃も心も大満足になれるお気に入りの店の一つだった
家族だけでなく、大好きな幼馴染みに加え菱和も一緒にとなると、いつも以上にテンションが上がる
注文をし暫し待っていると、各々が頼んだ定食がところ狭しと並び出す
カラリと揚がった香ばしい衣が、食欲を唆る
「‥美味そ!」
「おー良い匂いだなぁ」
「食べよ食べよ。遠慮しないでたーくさん食べてねー」
「頂きます」
「頂きまーす!」
各々が揚げ物を次々と口にする
さく、と衣が音を立て、噛んだ瞬間にじゅわ、と肉汁が溢れ出る
ユイは咀嚼しながら横に座る菱和に味の感想を求めた
「‥アズ、どぉ?」
「‥‥超美味ぇ。何個でも食えそう」
「‥でしょ!?良かったぁ!」
ユイはにこにこしながらご飯を頬張った
同じく、頬張りながら拓真がリクエストをする
「今度さ、作ってよ。チーズメンチ」
「ああ、良いよ。こんな上手く作れるかどうかわかんねぇけど」
「え、菱和くん料理するんだ?」
意外な一面を耳にし、尊が目を丸くする
「一応、それなりに」
「全っ然“それなり”じゃないから!俺らね、スタジオ帰りによく晩飯ご馳走になってんだ!アズってばもうほんっっと料理上手いんだよ!」
「ほんとなー。今まで食ったものぜーーーんぶ美味かった」
「お前ら、バンドに入って貰っただけじゃ飽きたらずそんなことまでしてたのか‥‥‥‥なんか、悪いね‥‥」
「‥いえ、全然」
菱和は少し口角を上げて、謝罪する尊に軽く会釈した
「あ。菱和くん、お家はどの辺?帰り送ってくよ」
「いえ、ここからそのまま帰ります」
「え‥‥でももう時間も遅いし‥‥」
「俺だけ方向違うし、送ってもらったら余計帰り遅くなるだろうから‥‥大丈夫です」
リサはちらりと菱和を見て、ぽつりと尋ねる
「‥遠慮してる‥‥?」
「‥‥‥‥別に」
リサがつ、と菱和を見つめる中、当の本人は黙々と咀嚼をする
辰司はにこりとし、菱和に云った
「どうせだから乗ってって。ついでだし、何も気にしなくて良いから」
辰司の言葉に、ユイも拓真も尊もふ、と笑顔を見せる
菱和は一同を見回した後、辰司の厚意にゆっくりと頷いた
「‥‥‥‥じゃあ、お願いします」
***
全員が食事を終え、口直しの温かいお茶を口にする
一同が暫し胃を落ち着かせる中、菱和は席を外そうとし、ゆっくりと立ち上がる
「アズ、煙草?」
「ん」
「じゃ、俺もトイレ行ってこよー」
拓真も立ち上がり、用を足しに席を外す
「煙草喫うんだ、菱和くんって?うちで喫ってっても良かったのにな」
外へと向かう菱和の後ろ姿を見て、尊がぽつりと呟いた
「‥‥あいつなりに遠慮してんじゃない」
「遠慮、ねぇ‥‥っていうかもう遠慮するような仲でもないんだろ?リサが普通にしてるくらいだし」
「‥‥どういう意味だよそれ」
「ん?その仏頂面が少ーし柔らかくなる程度には仲良しなんじゃないかってこと。初めてなのにめっちゃ馴染んでるし、相当仲良いんでしょ」
「‥‥知らない」
「ほんと照れ屋さんだな、リサは」
「うっさいよ、もう」
尊にからかわれたリサは、そっぽを向いた
リサと尊のやりとりを見て聞いて、ユイはくすくす笑った
「新しいお友達が増えて良かったなぁ、みんな」
のんびりと茶を啜る辰司の目が細くなった
そろそろ会計にと、皆が席を立つ
尊は一足先に外に出て、入り口に置かれた灰皿の前で煙草を吹かす菱和を見つけた
「お、いたいた。今会計してるから、もうちょい待ってて」
「‥‥はい」
菱和は軽く会釈し、返事をした
尊が横に並び、問い掛ける
「‥‥バンド、楽しい?」
「‥はい、とっても」
「‥‥やたら騒がしいのが約2名くらいいるけど、手焼いてるでしょ?」
ユイとアタルの顔が思い浮かんだ菱和は口角を上げ、穏やかな顔をした
「全然。‥‥このバンドでベース弾けて、ほんと良かったと思ってます」
「‥‥そっかぁ‥‥」
尊はユイやアタルから時々連絡を受けては、やれバンドがどうのライヴがどうのという話を再三聞いていた
ユイやアタルの話を聞く限り、自分が抜けた穴は菱和が十二分に埋めており、ただバンドでベースを弾いているだけではなく友人としても良い付き合いをしてくれているということがとても喜ばしく、改めて安堵の表情を浮かべる
「‥‥‥‥そういえば、ずっと気になってたんですけど」
「ん?」
「‥‥ユイって、何で“ユイ”って呼ばれてんですか。本名は“タダシ”ですよね」
「ああ。‥‥あんね、俺が小学校のとき、たまたま辞書かなんかで“唯一”っていう文字見たのね。んで、『お前の名前“ユイ”って読むんだ』って話して、そっから“ユイ”になったの。俺が“ユイ”って呼び続けてたらいつの間にか親父もそれが移っちゃったみたいで」
「‥‥‥‥なるほど。‥‥謎が解けました」
「ふふ。昔は“たっち”とかって呼んでたんだけど、“ユイ”の方が呼びやすいんだよね」
「そうですね、呼びやすいですね」
「でしょ?そんなわけで、今じゃ家族ですら誰も“タダシ”って呼ばないのね。‥ひどい話でしょ」
ユイが“ユイ”と呼ばれる所以
その理由を作ったのは、兄である尊だった
長年“ユイ”で慣れ親しんでしまった今、本名で呼ばれないことは本人ですら気にはしていない
何となく“家族の愛情”を感じ、菱和は少し口角を上げた
***
「‥‥そこのコンビニで降ろしてください」
「良いのかい?」
「はい」
菱和は自宅の最寄りのコンビニで降ろしてもらうことにした
車を出るや否や、運転手である辰司に向かってぺこりと頭を下げる
「有難うございました。‥‥すげぇ美味かったです、ご馳走様でした」
「いえいえ。また皆でなんか食べに行こう」
いずれまた来るであろうその機会を待ち侘びることとし、菱和は頷いた
車窓を開け、一同はそれぞれ菱和に声をかける
「風邪、引かないようにね」
「ひっしー、またね!」
「来てくれてどうも有難う」
「また今度ゆっくり遊びにおいでね」
ユイは少し身を乗り出し、人一倍別れを惜しんだ
「‥‥アズ、またね」
「‥‥‥‥なんかあったら、連絡しな。朝早くでも夜中でも、いつでも」
「うん。‥‥ほんとに、ありがとね」
「なんも。‥‥じゃ、また」
菱和は穏やかに笑み、自宅方面へと歩いていった
菱和の後ろ姿を見送ると、辰司は車を発進させた
「じゃ、帰りますよー」
「ほーい」
「はー、なんか雪降りそうだなぁ」
「明日辺り、降るかもって」
「マジ?」
「まぁ、もう暮れだもんなぁ」
いよいよ雪が降りだしそうな年の暮れ
初めてキスをしたこと
美味しい食事を作ってくれたこと
菱和の愛情を独り占めしていたこと
ずっと傍にいてくれたこと───
ユイは世話になっていた3日間余りの出来事を反芻しては照れ臭くなり、口元が綻んだ
年明けも菱和と一緒に過ごせるときを待ち侘び、ふ、と空を見上げた
120 石川家
ユイは2階に、拓真とリサと菱和はリビングにおり、それぞれユイの兄と父の帰りを待ち侘びている
リビングにいる3人が談笑していると、ガチャリと鍵の開く音が聴こえた
「お、帰ってきたんじゃない?」
「私、見てくる」
リサは玄関に向かい、石川家に帰宅した人物を出迎えた
ユイの兄・尊が、白い息を吐きながら入ってくる
「たけにい、お帰り」
「おーリサ、ただいまー。久し振りー。ごめんなー、遅くなって」
出迎えてくれたリサににこりと笑い掛け、尊はドアを閉め施錠した
寒い外気と室内の温度差に、あっという間に尊の眼鏡が曇る
「寒かったでしょ。お茶飲む?」
「おおー、相変わらず気が利くイイ女だなほんと。カレシ出来た?」
「出来てたらここに来てない」
「‥‥何だそれ、哀しい話だな」
「るさいよ、もう」
リサはじとりと睨み付けた
靴を脱ぐのに尊が視線を下に落とすと、見慣れないブーツが目に入る
「‥‥あれ、この靴誰の?アタル?」
「‥‥‥‥菱和の」
「お、噂の菱和くんか。来てくれたんだ?」
「うん。一緒に待ってた」
「そっかぁ‥‥も少し早く帰ってこれりゃ良かったなぁ。雪でバス遅れてさぁ、やんなるわほんと。‥ただいまー」
リサと話しながら、尊が居間のドアを開け放つ
「たけにい!お帰りー!」
拓真がにこやかに、軽く手を振った
───‥‥似てる
『顔は似てるってよく云われるんだよ。兄ちゃん眼鏡かけてるんだけど、俺も眼鏡掛けたら兄ちゃんそっくりみたい』
菱和は2、3度瞬きをした
初めて見る尊の顔は、果たして“眼鏡を掛けているユイ”そのものだった
「たけにい、菱和くん。‥ひっしー、ユイの兄ちゃん、タケルさん」
拓真が菱和と尊をそれぞれ紹介すると菱和はすっと立ち上がり、軽く会釈した
「‥‥お邪魔してます」
「っうお!!!でかっ!!」
立ち上がった菱和は悠然と尊を見下ろす背の高さ
尊は長身の菱和を見てたじろぎ、思わず声をあげる
「ちょっと、たけにい。お客さんになんて態度とってんの」
「あ‥‥すいません、初めまして‥‥ユイの兄の尊です。ユイが大変お世話になっております」
「‥‥菱和です、初めまして」
尊は初対面にも関わらず無礼な態度をとってしまったことを詫び、深々とお辞儀をし改めて挨拶をした
菱和もぺこ、と頭を下げた
尊は上着を脱いでソファの背もたれに掛け、拓真たちと一緒に座った
曇りで湿った眼鏡をティッシュで軽く拭いて掛け直すと、まじまじと菱和を見つめた
「写真も見たし“でかい”とは聞いてたけど、実物はなおでかく感じるなぁ。菱和くん、身長幾つ?」
「‥‥182です」
「うぉー‥‥でけぇー‥」
「あっちゃんと同じくらいあるもんね」
「今のバンドの平均身長半端ないな‥‥」
「ユイの所為でそんなこともないけど」
「ああ、そうか。‥‥てか、ユイは?」
「2階にいるよ。『たけにいの布団出す』って」
「あ、そぉ。別に自分でやるから良いのにな」
「ふふ、『見られちゃマズいもんでもあったらどーすんの』って云ったんだけどさー」
「そういう類いのもんはここ出る前に全部処分したっての。ばぁか」
二人の会話を聞いて、菱和はふ、と口角を上げる
「親父が帰ってくるまで、これ食って待ってよ」
尊は鞄から“土産”の一つを取り出したが、後ろからリサに取り上げられた
「ユイ呼んでくる。‥お茶入ってるからね」
ちょっとした“猥談”はダイニングにいたリサにもばっちりと聴こえていた
リサにとっては見慣れた風景、聞き慣れた会話であり、『いつものこと』だと思い別段気にする様子を見せず、クールな面持ちのままダイニングのテーブルに土産を置くと颯爽と2階へ上がっていった
「あー‥‥またやっちまった。女の子の前であんな話しちまって、はしたないな」
「そだね、自重しよ‥‥。ひっしーも、お茶飲も」
「うん」
リサが女であることを把握してはいるものの、ついいつものノリで下ネタを喋ってしまったことを拓真と尊は深く反省した
3人はダイニングへと移り、ユイとリサが降りてくるのを待った
***
リサに呼ばれたユイは尊が帰宅したことを聞き、足早に階段を駆け降りてきた
「───兄ちゃん!」
「ユイ。ただいま」
「お帰りっ!」
ダイニングの椅子に座る尊に、無邪気に後ろから抱き付いた
「おいおい、お茶溢すからやめろっての」
「これ、たけにいのお土産。お茶に合うわぁ」
「お、美味そ!」
尊が用意した“土産”は、柔らかい求肥のようなもので餡を包んだ和菓子だった
リサが淹れた焙じ茶との相性は抜群だった
ユイは行儀悪く、尊に抱き付いたまま菓子をとって口にする
「さぁーて‥‥もうそろ親父も帰ってくっかなぁ‥何食おうか」
「俺、“きなり”行きたい!」
「お、チーズメンチ?良いねぇ、さんせーい」
「リサは“きなり”で良い?」
「私は何でも」
「‥菱和くんは?」
突然話を降られた菱和は、面食らった顔をした
一同が菱和を見守る中、拓真が尋ねる
「ひっしー、揚げ物平気?海老フライとか豚カツとか。“きなり”はさ、チーズメンチがめちゃくちゃ美味いんだよ」
「‥‥そんなに美味いのか、その店」
「うん!絶品!ふふっ。アズもね、きっと気に入るよ!」
「‥‥そっか」
尊は菱和の横顔を見て、ユイや拓真と打ち解けている様子であることに心なしか安堵した
「ただいまぁ」
程なくして、父親が帰宅した
皆、一斉にリビングのドアを見やる
「あ、父さん!」
「お帰りー」
「お邪魔してまーす」
「お帰り、おじさん」
歓迎ムードに沸く中、菱和は尊のとき同様に立ち上がって軽く会釈した
「‥‥今晩は」
「うおぉ!ははっ、でかいなぁ!!」
見慣れない長身の姿を目にし、父親は感嘆する
一同は口々に父親の態度や言葉に様々な感想を云った
「‥たけにいと同じ反応」
「ちょっと、親父さん。初対面でしょ」
「親父、お客さんだっつの」
「たけにい。人のこと云えないっしょ」
「‥‥さーせん」
「ははっ!父さん、アズだよ!初めまして!」
「や、ごめんごめん‥‥新しいお友達?尊と唯の父です、どうも今晩は」
ユイの父・辰司は、軽く頭を掻いて気さくに挨拶をした
───血は争えねぇってやつか
菱和はそんな風に思い、軽く口角を上げて会釈した
「‥‥初めまして、菱和といいます」
119 石川家
「‥‥俺ね、何となーく、“More Than Words”の意味がわかったかも」
「‥‥‥ん‥?」
「『言葉よりももっと』って意味でしょ?‥‥夕べ、その‥‥‥キス‥したときに、何となく実感した」
「‥そうなん‥‥?」
「‥‥、『好き』、って、云わなくても、伝えられるって、わかったから‥」
「‥‥‥俺が寝てるタイミングで?」
「や、それは‥‥ほんと、ごめん」
「んーん。最初『何事か』と思ったけど、すげぇ嬉しかったよ。‥‥‥でも、どっちもおんなじくらい欲しいかな」
「ぅ‥‥え?」
「‥‥だいぶ前にヌーノのインタビュー記事読んだんだけど、“More Than Words”には結構深い意味があってさ。『“好き”とか“愛してる”とかいう類いの言葉を軽々しく使うから、その“魔法の言葉”さえありゃどんな状況でも修復出来ると誰もが思ってる。でも時には、それ以上のことをして気持ちを表さなきゃいけない。“言葉以外のやり方”も存在する』‥ってさ。‥‥でも“そういう言葉を望んでないってわけじゃない”とも歌ってる」
「その歌詞‥どこ?」
「最初んとこ。‥“It's not that I want you not to say.But if you only knew”。‥‥記事読んだ当時はヌーノが何云ってやがんのかさっぱりわかんなかったけど、今なら俺も少しだけわかる気がするよ。‥欲張りかもしんねぇけど、言葉も、それに代わるものも、両方欲しいな」
「ど、努力しま‥す」
「ふふ‥‥別に無理しなくて良いよ」
「無理じゃない、よ!アズのこと、好きだもん‥」
「‥‥‥好き?」
「‥、‥‥うん」
「‥‥俺も、好きだよ。ユイ」
「‥‥、ふ‥‥‥」
「‥‥これからも、沢山するから覚悟しとけよ」
「ん‥‥‥」
「‥顔、真っ赤」
「だ、って‥!」
「ふふ‥‥‥」
2人は寝起きに“More Than Words”の歌詞の意味を振り返り、“言葉以上に伝えられるもの”を存分に共有し合った
***
ユイは15:00頃まで菱和の自宅で過ごし、帰る身支度を始めた
昨日拓真とメールでやり取りしたことをふと思い出し、『菱和も誘ってみる』と云っていたのをすっかり忘れていた
身支度を整える傍ら、菱和に打診した
「あのさぁ、アズ」
「ん?」
「今日の夜ね、ゴハン食べに行くの、アズも一緒に行かない?」
突然の誘いに、菱和はきょとんとした
「‥‥‥‥、俺が行って邪魔じゃねぇ?」
「何で‥?アズさえ良ければ、一緒に行きたいんだけど」
「‥‥。‥‥‥‥じゃ、お言葉に甘えて。どっちにしろお前を家まで送るつもりだったし、俺も支度するわ」
「‥うん!」
元々ユイを自宅まで送り届けるつもりでいた菱和は、財布と携帯をポケットに突っ込めば支度は済んでしまった
流石にユイの自宅で煙草を喫うわけにはいかないと思い、出掛ける前の一服をする
「忘れ物ねぇ?」
「うん、ない!」
「‥‥ま、あったとしてもすぐ会えるんだろうけどな」
「‥ふふ。そうだね」
時刻は15:30前
二人は揃って玄関に向かう
「そだ、これやる」
「ん?」
靴を履いたところで、菱和はキーケースに付けてある自宅の鍵を外し、ユイに手渡す
鍵を受け取ったユイは、目を丸くして菱和を見上げた
「‥‥貰っちゃって、良いの?」
「鍵あれば、いつでも来れるだろ。俺がいなくても、好きに出入りして良いから」
菱和の部屋の鍵を貰った───自分の生活空間に躊躇いもなく迎え入れてくれる
ユイは、貰った鍵をぎゅ、と握り締めた
「‥有難う」
「ん。‥‥行くか」
「あ、アズ。ほんとに、ほんとーーーに、お世話になりました」
ユイは深々とお辞儀をした
菱和はふ、と口角を上げると、そっとユイを抱き寄せ、額に軽くキスする
「またいつでもいらしてください」
キスする度に、ユイは目を丸くして頬を赤らめる
勿論今も、ご多分に漏れない
少しの間は、したくても出来なくなる───そう思うと益々離れがたくなり、この部屋から出したくなくなってしまう
菱和は名残惜しそうにユイの頭をぽんぽん、と叩き、優しく笑いかけた
***
16:00を少し過ぎた頃
2人は石川家に到着した
鍵はかかっておらず、既に拓真とリサが待機しているようだった
玄関を開けると案の定、拓真のスニーカーとリサのパンプスがあった
「ただいま!」
「おー、お帰りー!」
「お帰り。寒かったでしょ。‥‥菱和は?」
「いるよ!」
ブーツを履いている菱和は、少し間を置いてリビングに入ってくる
「よう」
「ひっしー!いらっしゃーい!」
「案外早かったね。適当に座ってて、今なんか飲むもの持ってくるから」
「お気遣いなく」
「ひっしーも行くっしょ?飯食いに」
「ああ。家族と幼馴染み団欒のとこ水差しちゃ悪りぃけど」
「そんなこと、なーんも気にしないで良いのに!」
「たけにいにも、ちゃんと伝えてあるから」
「‥‥そっか」
菱和はソファに座り、自分が“イレギュラー”であることはもう気にしないことにした
***
「あ。俺、兄ちゃんの布団出してくる。押し入れにしまったまんまなんだよね」
「あんま勝手に他んとこいじくんなよ」
「へ?何で?」
「もしかしたら見られたくないもの隠してあるかもしんないじゃん」
「どこに?」
「‥‥‥‥“ベッドの下”、とか?」
「そーそー!」
菱和の一言にけらけら笑い出す拓真
ユイには何故拓真が笑っているのか皆目検討もつかない様子で、軽く首を傾げる
───ベッドの下?何隠すんだよ?点数悪かったテスト?‥‥俺ならまだわかるけど、っていうかそんなんしたことないけど、兄ちゃんに限ってそんなことあり得ないし
「‥‥別にいじくんないよ、そんなとこ。‥変なの」
ユイはきょとんとしたまま階段を上がっていった
見送った拓真と菱和は、思わず苦笑いした
「‥‥‥‥あいつ、マジで鈍いのな」
「ほんとねー。ピュア過ぎてたまにどこまで話して良いかわかんなくなる。‥‥でも願わくば、ユイには永遠にピュアでいてもらいたい」
「それは、無理じゃね」
「いや、わかってんだけどさ。やっぱいずれはそういう知識も身に付くよなぁ、哀しいけど」
「‥‥‥‥‥‥、“いずれは”、な」
その言葉に含みを感じた拓真
ユイに“無駄な知識”を植え付けるのは自分でもリサでもアタルでも尊でもなく、今自分の横で意地悪そうにほくそ笑んでいる菱和かもしれない
そんなことを想像すると、少しだけ背筋がゾクリとした
「‥‥‥やーめーてー、ひっしーいぃ‥‥お願いぃ‥‥」
「安心しな、“今んとこ”はあいつに余計な知恵つける気ねぇから」
「“今んとこ”じゃなくてぇ、俺の願いは“永遠に”なのぉ‥‥頼むよぉ‥‥‥‥」
「さて、どうなるかな‥」
『全ては自分次第』だと云わんばかりに含みを持った笑いを浮かべている菱和は、縋るように懇願する拓真の肩をぽん、と軽く叩いた
118 “More Than Words”
ユイが菱和の自宅で過ごすのも残り約一日
帰宅する時間が刻一刻と迫り、時計に目をやっては『帰りたくない』という気持ちが募っていく
『明日、16:00くらいに行くから。のんびり帰ってきなヽ(・∀・)ノ』
「おけ、わかった(・ω・)ノシ」
『 あと、ひっしーも明日の晩飯誘っとけば♪』
「うん、聞いてみる★」
電話を切った後、ユイは拓真とメールでそんなやり取りをしていた
それからは昨日までと何ら変わらず
昼までだらだらと過ごし
昼食を終えたら軽く家事をして
菱和の手の絆創膏を替え
夕餉の時間まで好きな音楽を聴いたり楽器を触ったり
そして、この日も二人揃って入浴をした
風呂上がり
キッチンで冷たい麦茶を飲み身体の水分を補っていると、リビングの掛け時計が目に入る
時刻は21:35頃
明日の今頃には兄と父が帰ってきている
会えるのを、ずっと待ち望んでいた
嬉しい筈の兄と父の帰り
だがユイの心には淋しさが募っており、壁に寄りかかってぼーっと時計を見つめていた
キッチンの換気扇の下で煙草を喫っていた菱和は、ユイの様子に気付き声を掛ける
「‥‥どした?ユイ」
「ん?んー‥‥‥‥なんか、明日のこの時間はもうここにいないんだなぁとか思って‥‥。‥‥‥帰りたくない、なぁ‥って‥‥」
ユイは正直に心境を伝え、はにかんだ
菱和には、感謝してもし足りないほど尽くしてもらった
なにか少しでも返せればと思い自分にできることをやったものの、十分ではないと感じる
何よりも、すっかり菱和から離れがたくなっており、会えない時間を考えては憂いた
「‥‥‥‥正直云ってい?」
「ん、何?」
菱和は煙草の火を消し、ゆっくりとユイに近付く
壁際に佇むユイの頬に触れ、顔を寄せた
「‥俺も帰したくねぇ」
耳元でボソリと呟かれ、ユイの心臓が鳴る
す、と身体を離すと、菱和はユイの頬を親指で擦りながら優しく云った
「‥‥でもさ、明日お前んちで佐伯たち待ってんだろ。皆で飯食いに行くんだよな。約束は守んねぇと。‥年明けたら、また泊まりに来れば良いよ」
ふ、と笑む菱和
ユイは少し不安げに顔を上げ、菱和の服をきゅ、と掴んだ
「また、来ても、良い‥‥?」
「なぁに野暮ったいこと聞いてんだよ」
菱和はユイの額にデコピンをした
「って!何すんだよもぉ‥‥」
「‥お前が来たいと思ったときに、いつでもおいで」
「‥‥、‥‥うん‥‥」
ユイは額を擦り、気恥ずかしそうに頷いた
菱和はユイに笑い掛けると、新しい煙草に火を点けた
***
菱和はベッドに寝っ転がり、俯せになってだらだらし始めた
軽く欠伸をし、怠そうに枕に顔を埋める
ユイはベッドの脇に腰掛け、菱和の顔を覗き込んだ
「‥‥眠いの?」
「ん‥‥今日は俺の方が先に寝そ‥‥」
「そっか‥‥‥‥じゃあ、今日は楽器弾くのやめるね」
「良いよ別に。‥‥なんか子守唄になりそうなの弾いて」
「子守唄‥‥?んー‥‥‥‥あ、じゃあ“More Than Words”とか如何でしょうか」
「‥EXTREME?」
「うん。小さいとき、寝る前に兄ちゃんに弾いてもらったことあるんだ」
「ふぅん‥‥。確かに入眠にはぴったりかもな。‥じゃあ宜しく、ヌーノ」
「あんなイケメンじゃないし恐れ多いよ!‥大好きだけど」
「ふふ‥‥‥‥イケメンだよな、ほんと」
「ね!‥チューニング下げるからちょっと待ってて」
「ん‥‥」
ユイは隣の部屋からギターとアンプを携えて戻ってきた
“More Than Words”に限らず、EXTREMEの楽曲は全て『半音下げチューニング』になっている
菱和はチューニングをするユイをぼーっと見つめていた
軽く爪弾いてから、ユイはイントロを弾き始めた
指板を滑る指の音と、節々にボディーを叩く音が心地好く響く
ユイは上機嫌で歌い始めた
俺が聞きたいのは「愛してる」って言葉じゃないって云ってるのさ
望んでない訳じゃないけど
でも、『感じるままを表現することが如何に簡単なことか』っていうことを君がわかってくれさえすれば、とは思ってる
その愛が本物だと証明するには、言葉以上のもの以外にないんだ
そしたら、わざわざ「愛してる」なんて云う必要もなくなるんだろうな
だって、云わなくてもわかるからさ
この心が二つに引き裂かれたら、君はどうする?
君に教えたい言葉以上のものっていうのは、俺への愛が本物だと感じられるものだ
君の「愛してる」を奪ったら、君は何て云う?
もしそうなったら、ただ「愛してる」って云えば良かったものも、変えられなくなるね‥‥‥‥
こうして君と話して、わかってもらおうとしてる
君はただ目を閉じて、手を差し伸べてくれさえすれば良い
そして触れてきつく抱き締めて、絶対に離さないでくれ
俺が何処へも行かないように
俺が欲しいのは、言葉以上のもの以外にないんだ
そうしたら、「愛してる」なんてなんて云う必要もなくなるんだろうな
だって、云わなくてもわかるからさ
言葉なんかよりも───
この曲に関しても、ユイは和訳を知らない
“More Than Words”という言葉の意味は理解しているが、この歌詞が何を伝えたいのかまではわからない
ただ、“言葉よりも態度で気持ちを表して欲しい”という想いは、今のユイならば多少は理解できるかもしれない──────
最後のピッキングを終え、ユイは顔を上げた
「‥‥‥‥あ‥‥」
気付けば、菱和が肘を枕にして眠っている
静かに、深く、寝息が聴こえてきた
───寝ちゃった‥‥やっぱ気疲れさせちゃってたかな
ユイはギターを置き、そっと菱和に近付いた
「‥‥アズ」
声を掛けるも、反応がない
やはり眠ってしまったようだ
静寂の中に、菱和の寝息が聴こえてくる
自分がいつもそうしてもらっているように、ユイは菱和の髪を撫でた
さらりと流れる黒髪から、閉じられた瞳と通った鼻筋が見えた
顔のパーツを一つ一つ目で追っていくと、やがて唇へと辿り着く───
ふと、ユイは菱和に“キスしてみたい”という衝動に駆られた
途端、心臓が速く脈打つ
あ、どうしよう
なんか、止められそうにない‥や
アズ寝てるから良いかな‥‥アズも俺が寝てる間に『しちゃいそうになった』って云ってたもんな‥‥‥‥
っていやいや、違う違う!
それでもアズは俺が起きてるときにしてくれた‥!
‥‥ああ!でももうなんか無理!よくわかんないけど無理!
アズ、ごめん───
ユイは、菱和の唇にそっとキスをした
キスと云えるかどうかも微妙なほど、軽く触れただけだった
すぐに顔を離し、急激に照れ臭くなり赤面する
何故こんなことをしたくなったのか、自分でも何がなんだかわからなかった
ただ、無性に、菱和に“キスがしたくなった”
───アズが俺に“したくなる”気持ちって、こんな感じなのかな‥‥
「‥、‥‥‥」
初めて自分から菱和にキスをしたユイ
衝動を押さえられなかったことを反省し、眠っている間にしてしまったことに『ちょっと卑怯だったかも』と思いつつも、菱和の寝顔を見つめて少しはにかんだ
「───‥足んねぇ」
菱和が眠りに就いていると思っていたユイは、突然聴こえた低い声に驚き弾けるようにビクついた
「‥!‥‥起きてた、の‥あ───」
菱和は目を開けると徐に手を伸ばし、ユイの頭をぐっと引き寄せ、謝罪の言葉を述べようとしたユイの口をその言葉ごと塞いだ
「‥ん‥、‥ふ‥‥っ‥‥‥‥」
大きな掌が、頬と頭を捕らえて離さない
細長い指が、ふわふわの髪に絡みつく
乱暴な、強めのキスだった
ユイはすっかり面食らってしまう
されるがままなのをいいことに、菱和は角度を変えて何度もユイにキスをする
ただ触れるだけでなく、時折あむ、と口に含み、軽く吸う
ちゅ、と鳴る唇
菱和の深い息遣いを、感じる
ユイは、ただただ困惑した
唇が離れるほんの僅かな瞬間に息を吐こうとするも、濃厚な口付けは不意討ちの連続
おまけに顔をがっちりとホールドされ、一切身動きがとれない
「んん、ん‥‥───」
息苦しさを覚え、声にならない声が漏れる
菱和はユイを解放し、顔を離すや否や軽く頭突きをして低い声でボソリと呟く
「‥‥こんなことなら俺も、お前が寝てるときにすれば良かった」
菱和が執拗にキスを繰り返したのは、半ば“当て付け”のようなものだった
「‥‥ん‥‥す、みません‥でした」
ユイは目を丸くしたまま、色んな意味で謝罪をした
菱和は“当て付け”たようにしすっかりユイを困惑させてしまったが、いじらしさにふ、と笑みを零す
「‥‥‥‥ありがと。‥‥悪い、ほんと先寝る」
そう云って、ユイの頭を軽く撫で、また枕に顔を埋めた
「‥うん‥‥おやすみ‥‥」
───‥びっくりしたー‥‥‥
自分のキスも十分不意討ちだったかもしれない
だが、菱和のキスはそれ以上だった
『“習うより慣れろ”って云うだろ』
何時かの菱和の言葉が頭に響き、ユイは口を結び何度も目を瞬いた
鼓動はバクバクし続けており、治まる気配がしない
───でも、全然嫌じゃなかった
沢山のキスをくれた菱和
「好き」と言葉にしなくとも、愛情表現が出来る
“そういう関係”になれたということを、改めて実感する
「───‥あ」
笑い合えること
傍にいること
寝食を共にすること
抱き締め合うこと
手を繋ぐこと
キスをすること
その全ての行為に、愛情を感じる
言葉じゃなくても、言葉なんかよりも、伝えられる想い───
ユイは、先程奏でた曲“More Than Words”の意味がストンと心に落ちていくのを感じた
───そっか、
慈愛の心を抱いているのは、自分だけではない
胸の辺りが、じんわりとする───
「‥‥‥ありがとね、アズ」
ユイは菱和に布団を掛け、ギターを片付け始めた
117 Varje gång jag ser ditt sovande ansikte‥‥
朝は嫌いだった
“今日一日、また生きなければならない”と思っていたから
沈んだ気持ちを起こすのに、多大なエネルギーを要する
朝が来る度、自分を支配していたのは“死んでいなかった”という後悔
毎朝こんな気持ちになるくらいなら、いっそ永遠に何も考えられず終わっていた方がマシだった
でも今は違う
目を開ければ、ふわふわの髪の毛が見える
童顔の寝顔はより子供っぽく見えて、可愛らしく思える
自分をしっかりと捉えている華奢な手
とるに足らない重さ
手離したくない温もり
目覚めの瞬間に愛おしい人が隣にいることが、こんなにも嬉しいとは思わなかった
寝顔を見る度に、朝を迎える度にこんな気持ちになれるのなら、生きていることもバカには出来ない
不思議と
だが、確実に
───何でか知んねぇけど、この顔見てたら“何でも出来る気”になんだよな‥‥
ぼんやりとユイの寝顔を見つめながら、菱和は柔らかく笑んだ
ふとユイが目を覚まし、菱和に笑い掛ける
「‥‥‥‥はよ、アズ」
「おはよ」
寝起きの瞼にそっとキスされると、ユイは気恥ずかしさに顔を埋める
「‥‥、今、何時かな」
「知らねぇ」
アンニュイな朝
だらだらとベッドに横たわり、じゃれ合ってみたり優しさや温もりを感じたり
二人にとってはいつもの情景となった朝の一時が、今日も訪れる
腹の虫が騒ぎ始めた頃に、二人は漸くベッドから起き上がった
菱和は煙草を一本喫い、ユイはカラカラの喉に麦茶を流し込んでその横顔を見つめる
怠そうに煙を喫っては吐き出すその仕草を見ることが、ユイにとっては至福の瞬間だった
───アズは俺の寝顔が可愛いとか云うけど、俺はこの顔が好きなんだよな‥‥なんて
煙草を喫っている菱和は、寝起き同様酷く無防備だ
ぼーっと煙草を吹かすその後ろから“膝かっくん”でもすれば、奇声を上げて慌てふためく姿が見られるかもしれない
行動に移そうとは思わないが、そんなことを想像して、ユイはほくそ笑んだ
「‥‥‥‥そういやさ、」
「‥‥‥‥‥‥あ、何?」
やはりぼーっとしていた菱和は、多少のタイムラグを置いてユイの声に返事をすふ
「アズってさ、結構喫う方だよね、タバコ」
「ああ、うん。あっちゃんよりは少ねぇかもしんねぇけど」
「あっちゃんは俺から見ても喫い過ぎだよ‥‥。ガッコにいる間はさ、我慢してんの?」
「‥‥一人でいたときは、屋上で喫ってたよ。‥お前らが出入りするようになって、学校に持ってくこと自体やめた」
「! そうなんだ‥‥何で?」
「万が一先公に喫ってるとこ見られて、お前らも疑われたり停学んなったら嫌じゃん」
「‥‥‥そ、っか‥」
「‥‥朝飯、何食おっか」
「‥パン、ある?」
「角食とバターロールならあるけど。どっちが良い?」
「じゃあ、ロールパン食べたい。‥‥あと、トマトのスープ」
「‥‥トマトのスープ?」
「うん。‥‥初めてここに泊まったとき、作ってくれたでしょ。今思い出した、あれ超美味かったなーって。‥また食べたい」
「ああ、ミネストローネか‥‥今作るから、待ってて」
「お願いします」
***
菱和がミネストローネを作っている間、ユイは寝室の布団を整えることにした
ベッドから布団を下ろし、シーツと枕を直していると、机に置きっぱなしの菱和の携帯が鳴った
特別見るつもりはなかったものの、表示されている電話の主の名前が目に入る
ユイは携帯を持ち、キッチンで調理している菱和の下に行った
「アズ、電話。拓真から」
「‥‥佐伯?」
菱和は調理をやめ手を洗い、タオルで軽く拭いてから携帯を受け取った
新しい煙草に火を点けつつ、通話ボタンを押す
『もしもし、ひっしー?おはよー』
「はよ。どした?」
『ユイ、どう?』
「‥元気だよ。よく寝てるし飯も食えてる」
『そっかぁ。大したことなさそうなら良かったよ。やっぱ“そこ”にいるのがでかいんかねー』
「どうだろな。だと嬉しいけど、俺も」
『ふふ。‥‥あのさぁ、ちょっと相談なんだけどね』
「ん、何?」
『たけにいとかあっちゃんと色々話したんだけど、年末年始‥‥‥‥───』
二人の会話が気になりつつも、ユイは布団を整える
掛け布団を広げたところで、菱和が寝室に入ってきた
「ユイ」
ユイが布団を整えていたことに若干驚き、菱和は半ば呆れたような顔をした
自分を呼ぶ声に振り返ったユイはきょと、とする
「‥‥‥佐伯がお前と話したいって」
菱和はユイに携帯を差し出すと、ユイの頭をくしゃくしゃと撫でて寝室から出ていった
ユイはベッドの脇に座り込み、拓真との会話を始めた
「拓真、おはよ!」
『お、ユイ。元気そうだな』
「うん!元気だよ!」
『良かった良かった。心配するだけ無駄だったかな』
「そんなことないよ。‥‥どうも有難う」
『いいえー。‥明日さぁ、親父さんとたけにい帰ってくるまでリサと一緒にお前んち居るから。たけにいがお土産くれるっていうからさー。親父さんも、晩飯食いにどっか連れてってくれるって』
「‥ほんと!うん、わかった!兄ちゃん、何買ってくんだろう」
『何だろなー、美味い銘菓だと良いな』
「ふふ、ゴハンも楽しみだね!」
『だな。‥‥んじゃ、明日な』
「うん!どうもありがとね!」
拓真なりの気遣いか、それとも本当に“尊からお土産を貰う為”だけなのか
どちらの場合であっても、誰かと一緒にいられること、独りでいる時間が少なければ少ないほど、ユイの心は安堵した
***
「別にあんなことしなくて良いのに」
「ん?」
「布団。一人でごそごそ何してんのかと思えば‥‥‥‥あんなもん夜寝る前にぱっと出来んだろ」
「あれくらいはやって当然でしょ。ただでさえ色々迷惑かけてんのに‥‥バチ当たっちゃうよ」
「‥‥どんだけ心狭めぇんだよ、お前の信じてる神様は」
千切ったパンを齧り、菱和はくすくす笑った
「ここにいる間は、何でもいいから俺が出来ること、やらして」
ユイは唇を尖らせ、少し俯く
菱和にとっては、自分の好意でユイを自宅に置いているのだから申し訳なく思うことも特別気を遣う必要もないことだった
反面、ユイは、菱和の好意は“一宿一飯の恩義”どころでは済まされないと感じており、布団を整えた程度で返せるものでもないが、自分に出来ることをやりたいと切に思っていた
───ただ近くにいてくれりゃ、それで十分なんだけどな
それでも、ユイの気持ちは有り難く、菱和はユイの頭をぽんぽん、と叩いた
「‥そ。じゃあ、何かかんかお願いしますわ」
「うん‥‥‥何でもいいからさ、ほんとに」
「‥‥‥‥‥‥、したっけさ、『脱げ』っつったら全裸になってくれる?」
「‥そういうのは違うだろ!!」
「今“何でもいい”っつったろ」
「家事とかの話だよっ!」
「‥‥冗談だって。‥冷めるから早く食いな」
───も、冗談か本気かわかんないときあんだよな、アズって‥‥
からかわれて顔を赤くするユイを尻目に、菱和は意地悪そうにくすくす笑いながら悠々とコーヒーを啜った