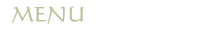NEW ENTRY
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/02)
(11/09)
[PR]
1-3“ALLT③
「いやーオニーサンめっちゃ凄かった!マジ吃驚した!」
「最初すげぇ面白い顔して追い掛けてきたから笑っちゃったよね、焦ったけど」
「マッスルカーニバルの人かと思ったよ、良いもの見せてもらったぁ」
「っていうかお前らも凄いな!あんなやり方されたら店もGメンも真っ青だよ!」
チャリとダッシュ
自分達の勝利を確信しての逃亡劇の末に敢えなく取っ捕まった男子高校生たちと、肩を並べて和気藹々と話す伊芙生
剰え、万引きの手段をベタ褒めしている
どうやら、精神年齢が合うらしい
男子高校生たちに力の限り怒号をぶつけた直後、たまたま近くを通りかかった主婦のママチャリを借りて猛スピードで追い掛けた伊芙生
その先には30段ほどの石段があり、男子高校生たちは自転車に乗ったまま恐る恐る階段を下り始めた
なにビビってやがんだ、全然怖くないぜ───
伊芙生は少し助走をとって階段の一番上からママチャリごと思い切りぶっ飛び、男子高校生たちが一番下に辿り着く前に見事着地を決めて立ちはだかった
男子高校生たちは伊芙生の先回り(?)の刹那、驚嘆と恐怖に戦き次々と衝突して倒れた
借り物のママチャリは着地の衝撃で派手に歪んでしまったが、無惨な姿へと変わり果てたママチャリに引き換え奇跡的に無傷の伊芙生が間髪入れず連行しようとした矢先、男子高校生たちは伊芙生のアクロバティック且つアグレッシブな行動に堪く感動し、そのまま流れるように皆でNäckrosorへと訪れた
「───で、どうやって万引きしてたんじゃ?」
「ん、まず二人で店員に話し掛けて、その隙に一人がトイレ行ってタグ剥がして‥‥って感じ」
「あとは、皆で一人を囲って周りから見えなくする、とかね」
尋ねられた男子高校生たちは、嬉々としてその手口を披露した
「ほぉ‥‥自分等で死角を作り出すんじゃな、なるほど」
「トイレに持ってかれたんじゃ、店側もたまんねぇな」
ボックス席で食後の珈琲を啜る憂樹と蓉典も、万引きの手口に思わず感心し頷いた
無論、感心している場合ではないのだが───
「───こらこら君たち、さっきのサラリーマンと女子高生と同じようにその子たちを諭す為にここへ連れてきたんじゃないのかい?」
Näckrosor店内で唯一の常識人である迦一が、思わずツッコミを入れた
「あ、いやほら、こいつらと同じ目線で物事考えなくちゃいけんし‥‥な?」
「ああ、まぁ‥そういうことっす」
迦一は目を泳がせて言い訳する憂樹と蓉典の言葉に呆れ、それ以上感知しないことにした
「──てかさ、あんな芸当見ちゃったら万引きなんかどーーーでも良くなっちゃった。スカッとしたよ」
「ほんとほんと!実際、万引きよか楽しかった!」
「オニーサン、またなんか凄い技見せて!」
自分たちが犯した罪を何処へ棚上げするやら、男子高校生たちは目を輝かせて伊芙生へ期待の眼差しを向ける
「いやー、さっきのアレはたまたまだし‥‥今度同じことやって怪我しない保証はないから‥‥‥‥」
「そうなの?じゃあ、あれってマグレ?」
「うん。“ああいうこと”するのは初めてじゃないけど無傷でいられるのはマグレだよ、いっつも」
「そうなのかー。‥でもでも、今までマグレだったんなら次も大丈夫じゃね?」
「随分軽く云ってくれるなー‥‥‥迂闊に大怪我出来ないんだよ、ぼくわ」
「何それ??」
「ふふん。俺はな、ウルトラレアブラッドなんだ。 俺の血は希少中の希少種で、高値で取引されてんだぜ」
「っぎゃはは!何だよそれ!!!」
「オニーサン、実はさっき頭打ったんじゃないの?」
「いや、マジだから!これ、ガチのマジ!」
ニヒルにキメたつもりが“厨二病”とでも捉えられたのか、伊芙生は男子高校生たちに散々嘲笑われた
「‥おい、コソ泥共。今のはほんとの話だぞ」
蓉典はのそりと立ち上がってカウンターまで足を運び、伊芙生をフォローしつつその頭をぐりぐり撫で回した
「え、そうなの‥‥?」
「だから、ガチのマジだって云ったろー?」
伊芙生はドヤ顔をし、至極誇らしげにした
「そう、なのか‥‥‥‥なんか、すいません」
「は?何で謝んの?」
「だって、アレでもし大怪我してたらめっちゃやばかったじゃん」
「うん‥‥チャリ同士ガチでぶつかったら死ぬらしいしな」
「たかが俺ら捕まえるのに死なれでもしたらすげぇ後味悪かった‥‥あー、なんかバカらしくなってきたな」
「ああ、ほんと。‥‥‥‥オニーサン、ごめんなさい」
「さっき追い掛けてきたとき、大爆笑しちゃってすいませんでした」
急にしおらしくなった男子高校生たちを見て、憂樹はくすりと笑った
「漸く自分達の立ち位置がわかってきたんか。‥‥まぁ、万引きとぼっくんが怪我するかどうかはまた別の話じゃけん。でも、“そういう結末が待ってるかもしれん”っちゅー危機感は持ってて損はないかもしれへんな」
「‥‥はい。すみませんでした」
「ん。でも、二度目はないからな。‥‥‥‥あんだけ激チャリしたから腹減ったろ。迦一さん、カツサンドある?」
「ああ、今出すね」
迦一は冷蔵庫からボリューミーなカツサンドを取り出し、伊芙生と男子高校生たちの前に置いた
序でに、キンキンに冷えたレモンスカッシュをお供に出す
「これ食ってから帰んな、超美味いから。俺の奢りだ」
伊芙生はカツサンドに一口かぶりつくと、にこりと笑った
***
「よー、良くやったなお前ら。お疲れ」
伊芙生たちがカツサンドとレモンスカッシュを堪能し御満悦の男子高校生たちを見送ると、ちょうど、店の奥から菩希と提午が顔を出した
「ういーす」
「お疲れさん」
「迦一さん、珈琲貰える?」
「はいはい、只今」
菩希と提午が伊芙生と並んでカウンターに座すと、迦一は珈琲を淹れ始めた
店内に、香ばしい珈琲の香りが漂う
今回は、『万引き犯を捕まえて欲しい』と店の人間に懇願されての依頼───万引き犯を現行犯で引っ捕らえてNäckrosorへ連行するまでが、“実働部隊”に課せられた仕事だった
憂樹たち三人は口々に「そんなことは警察に任せておけば良い事案だ」とぶーたれたが、店主はわざわざALLTに依頼を寄越した
その理由は、『明らかにGメンらしき人間が店舗にいるよりも犯人の警戒心が解かれると思ったから』だ
少なくとも憂樹、蓉典、伊芙生の三人は、Gメンや警察官のように万引き犯を取り締まる立場の風貌ではない───憂樹はパッと見チンピラ、蓉典はガラの悪いあんちゃん、そして伊芙生は一回り近く年下の男子高校生にコケにされるほど間抜けな見て呉れだ
無論、店主は警察にも相談には行っているが、『防犯カメラのチェックを』『見回りの強化を』とお決まりの台詞を吐くだけだった
“来るもの拒まず”、“どんな依頼でも受ける”のが、『何でも屋』の信条───
「───で、チャリぶっ壊したって?」
菩希の眉と口の端が、くっと釣り上がった
伊芙生の目が、泳ぐ
「あああーあれは、えーと、不可抗力というか何というか‥‥」
「までも、結果オーライなんじゃねぇの?」
「むー、ぼっくん凄いのぉ。ほんまに怪我無いんか?」
「平気す」
「チャリの修理代金は給料から天引きな」
「‥‥ふぁい」
憂樹と蓉典のフォローも空しく
提午は慰めのつもりで、落胆する伊芙生の肩をぽんぽん、と叩いた
残りの報告をBGMに
迦一はゆったりと笑み、明日の営業に向けての仕込みを始めた
PR
1-2“ALLT”②
「っ離せよ!この変態ジジィ!!」
「うっせぇ、ブス。とっとと歩け」
「このやろ‥『痴漢だ』って叫ぶぞ!!」
「お好きにどうぞ。どうせ冤罪だし」
「みなさーん、この人痴漢でぇーす!!」
「みなさーん、このジョシコーセー万引き常習犯でぇーす。この鞄の中身は百均でパクった戦利品しか入ってませぇーん」
「っ、てめぇっ!!」
「ベンキョードーグは一体どこにあるんでしょおかぁー?」
「全部学校だよっ!!」
「教科書学校に置き去りにしたまんま、真っ昼間から万引きしてるジョシコーセーはここでぇーす!お巡りさぁーん!」
「うるせぇっ!!黙れ!!」
「お前が先に叫び出したんだろうが、このブス」
痴漢呼ばわりされたことなど意に介さず
蓉典は取っ捕まえたやんちゃな女子高生を引き摺るように、騒然とする街並みをずんずん歩いていく
女子高生は何とか逃れられないものかと必死に抵抗を試みるが、その手首を蓉典にがっちりと掴まれている
「俺に捕まっただけ有難いと思いな。店の人間に捕まってたら問答無用で警察行きだぞ。親とか学校に連絡されたくないだろ?」
「‥‥、‥‥‥っ」
女子高生は悔しそうに顔を歪めた
どうやら、『警察沙汰になりたくない』『親に連絡されたくない』は図星のようだ
「‥‥別に弱味握ってどうこうしようなんてこれっぽっちも思ってねぇから。ガキのくまちゃんパンツなんざクソも興味ねぇし」
「んなもん穿いてねぇよエロオヤジ!!」
「あっそ。とにかく、穏便にコト済ましたいなら大人しくついてきな。悪いようにはしねぇから」
蓉典はぱっと手を離し、女子高生を宥め賺した
今なら逃げられる、否、追い付かれてまた捕まってしまうかもしれない
『悪いようにはしない』という言葉だって、とてもじゃないが信じられない
だが、何の根拠も無いのに『その言葉を信用しても良いのではないか』という気になるほど、見上げた蓉典の顔はひどく穏やかだった
剰え、折角捕まえた“獲物”に逃げられる可能性が十分あるにも拘らず、いとも容易く拘束を解いたこの男───一体、何を考えてるんだろう?
女子高生の心に、寸分の迷いが生じた
「‥‥‥、どこ連れてく気だよ」
「珈琲が死ぬほど美味い喫茶店」
「‥‥は?」
「世界一美味いんだ。しかも、タダで飲める。ラッキーだと思わねぇ?」
「‥‥‥‥、私、珈琲飲めない」
「そうか。そりゃ勿体無いな‥‥じゃあ、何が好きだ?」
「‥‥‥、‥‥そこ、ココアある?」
「ああ、あるよ。奢ってやる」
蓉典はにこ、と笑むと、颯爽と歩き出した
この女子高生は逃げない、大人しく自分の後をついてくる───勿論何の根拠もないが、その思惑通り、女子高生は辿々しく蓉典の後をついて歩いた
***
店先に置かれたボードに、チョークで『今日のおすすめ』が書かれている
傍らには、錻の如雨露に入った橙、黄、桃色のガザニア
外で喫煙が出来るよう、灰皿とベンチも置いてある
窓硝子越しに店内をちらりと見ると、客は数えるほどしか居ないよう
「とうちゃーく。さ、どーぞ」
蓉典はNäckrosorのドアを開け、女子高生を中へ通した
歩く度に床が軋む木目調の店内
香ばしい珈琲の香り
ショーケースに並んだケーキ
BGMのジャズ
洒落た家具
レトロな雰囲気
女子高生は、不思議と心が落ち着いていくのを感じた
「うわぁああぁん‥‥ごめんなさいぃぃ‥‥」
突然、店の窓際のボックス席から号泣する男の声が聴こえてきた
「わかりゃ良いんじゃ、わかりゃ。もう二度とすんなよ。たかが万引き、されど万引き。今度見付けたら、絶対警察に連れてくけん。家族に迷惑掛けるようなことはしちゃいけん。な?」
「は、はぃ‥‥すいません、でした」
ボックス席には、嗚咽を漏らすスーツ姿の男と、それを宥める憂樹がいた
異様な光景に、女子高生は肩を竦ませて目を瞬いた
「‥‥‥‥お前も、ああなるのかな?」
『“あれ”が数分後の自分の未来の姿かもしれない』と予見した蓉典の言葉に、女子高生は弾かれたように反応を示す
「今泣いてるあの男もお前と同じ、万引きの常習犯だ。家庭に居場所がなくて、ストレス発散に繰り返しやってたらしい」
「‥‥私にも説教かまそうってハラかよ」
「そんなつもりはねぇよ。取り敢えず座んな。あったかいもんでも飲んで、オジサンとのーんびり喋ろうぜ」
蓉典はカウンターの一番端の席に座り、煙草に火を点けて吹かし始めた
今ならまだ逃げられる───心が揺れたが、何故か足が動かない
仕方なく、女子高生は蓉典の隣に座った
「お帰り、蓉典くん」
「ただいま。この娘にココアください」
「はい、ちょっと待っててね」
甘曽は蓉典に灰皿を手渡すと、冷蔵庫から牛乳を取り出し、ココアを作る準備を始めた
***
「いっつも行ってんのか、あの百均」
「‥‥うん」
「今の百均てすげぇよなぁ。生活雑貨、食料品、化粧品、工具‥‥何でも置いてある。見て回るだけでもワクワクするよな」
「‥‥、別に」
「‥お前、学校行ってないのか」
「私が学校に行こうがどうしようが、あんたに関係ないだろ」
「ああ、無い。無いけど、“学校サボって昼間から街彷徨いて万引きしてる女子高生の心理状況”は気になるんだよな。‥目の前に“その”女子高生が居るわけだし」
「‥‥なにあんた。説教するつもりはないんじゃなかったの?」
「ないよ。‥何でお前が万引きするのか、ってのが知りたいだけだよ」
「そんなもん知ってどうするわけ?」
「後学の為に役立てる。今後同じような女をナンパするときに使えるだろ?」
「は‥やっぱただのエロオヤジかよ」
「違げぇ。俺は“ムッツリ”だから」
「‥‥ぶはっ!何が!どこが!!」
「はぁ?ふざけんな、よく見ろよこの顔」
「“ガッツリ”じゃんかその顔は!どの面下げて“ムッツリ”って?笑っちゃう‥っはは!あははは!」
「‥‥‥‥‥ふーん‥‥笑うと結構可愛いじゃねぇか。“ブス”とか云って悪かったな」
「‥!!な、‥‥そんなお世辞云ったって、何も出ないんだから‥!」
「おまけにツンデレかよ。お前のカレシになる男、苦労しそうだなぁ」
「っ余計なお世話だよ!」
「ふふ‥‥。‥‥‥‥なぁ、コソコソ盗み働くよか、今みたいに下らねぇことで笑ってた方がよっぽど楽しいと思わねぇ?さっきも云ったけど、どんな理由があっても、万引きは問答無用で警察行きだ。今までは上手くやってたかもしんねぇけど、次“やる”時に誰にも見付かんねぇ保証はどこにもねぇじゃん。暇潰しかゲーム感覚かなんか知らねぇけど、バレた時のこともっとよく考えろ。‥‥今よりも“笑う時間”減っちまうぞ」
「‥‥‥、結局説教してんじゃんか‥‥」
「説教じゃねぇ。オジサンからの、有難ーーーいお言葉。もし暇潰しとかゲーム感覚でそんなことするくらいなら、一緒にゲーセン行って本物のゲームやろうぜ。俺、こう見えてプライズ獲るの得意なんだ。プリクラだって一緒に写りまくってやるよ」
「‥‥‥、プライズは良いけど、プリは、無理‥‥グラサンかけた変なオヤジとのツーショットとかマジあり得ないし」
「あ?何だよそれ。‥‥まぁ良いや。遊び終わったら、ここでまたココア飲も。‥あ、今度ココアだけじゃなくて軽食とかケーキ食ってみろよ。ここのものは、マジで何でも美味いぞ」
「‥‥‥‥‥‥。‥‥ゲーセン、付き合ってくれんの‥‥?」
「ああ。時間あるときはいつでも付き合ってやっから、またここに来な」
「‥‥‥‥ほんとに、来るよ。良いの?」
「うん。待ってるよ。‥俺、蓉典。お前の名前は?」
「‥‥‥、‥今度会ったときに教える」
「はぁ!?お前、俺だけ名乗るとかズルくねぇ?」
「ズルくない。タダで女子高生と遊べるんだから、感謝しなよ」
「は‥‥あっそ‥‥‥」
「‥‥‥‥。‥‥これ、預かっといて」
「‥‥、預かっとくだけで良いのか?一緒に謝りに行くか?」
「‥‥‥‥うん‥‥」
「うん。‥‥今日は良いから、決心ついたらここに顔出せよ」
「‥‥ココア、美味しかった。‥御馳走様」
「ああ。帰り、気を付けてな」
***
「あー、ええなぁ女子高生‥‥俺もしょぼくれたリーマンより女子高生が良かった」
女子高生を見送った後、憂樹が蓉典の隣に座った
「はは。今度女子高生の案件当たったら、ばくって(交換して)やるよ」
「ほんまか?約束じゃぞ?」
「ああ。約束」
───‥‥‥‥やっぱ美味いな、ここの珈琲は
蓉典は煙草の煙を燻らせ、ゆったりと笑った
「‥そういや、ぼっくんまだ帰ってきてへんよな?女子高生よりも活きの良い男子高校生‥‥しかも三人じゃけん、苦戦しとるんじゃないか?」
「いつものことじゃん。そのうち帰ってくるさ」
「まぁ、そうやな‥‥なんか、腹減ってきたなぁ。迦一さん、今オムレツ作れる?」
「あ、俺もナポリタン食いたい」
「ああ。ちょっと待ってて、すぐ作るから」
蓉典と憂樹は談笑しつつ、暫し伊芙生の帰りを待った
***
「───んのやろおぉ、待ちやがれこのクソガキ共っっ!!!!!」
蓉典と憂樹がNäckrosorでオムレツとナポリタンに舌鼓を打っている頃───閑静な住宅街に、激チャリする三人組の男子高校生をダッシュで追い掛ける伊芙生の怒号が響き渡った
1-1“ALLT”①
剥き出しの天井、打ちっぱなしコンクリの壁、吸い殻だらけの罅割れた床───
アングラな雰囲気が立ち込める一室
中央に置かれた円卓を取り囲むように座す、五人の男
「───よーし。お前ら、散れ」
信濃 菩希(しなの ほまれ)の号令と共に、身支度を整えた三人の男が各々席を立ち上がる
警視庁公安部総務課長・那入 義釈(ないり よしとき)
彼は、自らの権限と責任の下、非公式の“何でも屋”「ALLT」を組織した
ALLTには、現在5名の精鋭が所属している
菩希は、長らく海外で活動していた元軍人
男でありながら濃い目のドギツいメイクを施しており、その目で見詰められれば忽ち恐怖感を憶えそうなほど妖艶で蠱惑的な雰囲気を醸し出している
しなやかで強靭な肉体以外に在隊時の面影は全くなく、メイクは“現在”の彼のトレードマークになっている
菩希の横でPCとにらめっこをしている戸根 提午(とね だいご)は、自他共に認める凄腕の元ハッカー
その腕を活かし、主に情報捜査を担当している
ハッカー時代に多大な恩義がある菩希には忠誠を誓っており、その証拠とも云うべきか、提午は菩希にだけは敬語を使って喋っている
リーダーである菩希と常時PCに張り付いている提午はあまり本部から動くことはないが、出張る時には二人は“バディ”となる
残りの三人はスリーマンセルで、ALLTに寄せられた“依頼”を遂行する実働部隊
指令を受け、命令を下す菩希と提午を“脳”とするならば、彼等は謂わば“手足”だ
その人となりは、元ジャンキー、特殊な性癖の持ち主、真の意味で“怖いもの知らず”───どいつもこいつも“曲者”だ
菩希は、その曲者たちに声を掛けた
「おい、予備のグラサン忘れんなよ」
「わかってるって。蓉典(ようすけ)、自分でもちゃんと予備持ってけよ」
「はいはい」
「‥‥さーて、行きますか」
北上 憂樹(きたかみ ゆうき)、天塩 蓉典(てしお ようすけ)、最上 伊芙生(もがみ いぶき)の三人は、アングラなALLT本部の扉を開け放った
鉄製の無機質な扉の向こうには約10メートル程のホールが扉同様無機質に続いており、その先には木目調のドアが聳え立っている
オートロックの扉がかちん、と閉まる音を確認すると、憂樹は木目調のドアまで進み、古ぼけた鍵を使って解錠した
ドアを開けると、焙煎したての香ばしい珈琲豆の香りが漂うカントリー調の純喫茶「Näckrosor」へと出た
三人は足並みを揃え、「Näckrosor」の店主・甘曽 迦一(あまそ かいち)へ声を掛ける
「行ってきまーす」
「ああ、行ってらっしゃい。気を付けてね」
甘曽は、三人に気さくに返事をした
喫茶店の裏のスペースであるALLT本部は、甘曽の“好意”によって格安で貸し出されている
そこ“まで”は、ALLTの人間には周知されている
“何故、甘曽はわざわざ低家賃でスペースを貸し出しているのか?”
“そもそも、何故純喫茶の裏に“何でも屋”の本部が置かれているのか?”
Näckrosorを後にする三人は、口には出さずともその二つの事柄を常々不思議に思っていた
そして、それらを尋ねたところで、疑問が解けること以外に何も意味を成さないことも熟知している
実働部隊は、手足のように云われた通りに動けば良いだけ───
憂樹、蓉典、伊芙生は、事前に提午から受け取った写真や地図を携え、街中へ散って行った
何故那入がNäckrosorを本部に選んだのか
それは“甘曽と那入が旧知の仲である”ということ以外に特別な理由はない
菩希以外の四人は那入の顔さえも知らず───ALLTが創られた経緯でさえ、リーダーである菩希以外は誰も知らなくても良い事だった
0-3 自己紹介
翌日
云われた通り、昨日と同じくらいの時間にNäckrosorを訪れた
お客さんが2、3人居るだけで、菩希さんたちの姿はなかった
取り敢えず、カウンターにいる甘曽さんに声を掛けることにした
「こんにちは。昨日はどうも有難うございました」
「おお、伊芙生くん。こちらこそ、時間をくれて有難うね」
「いえ。‥あの、菩希さんたちは‥‥」
甘曽さんはにこりと頷くと、俺に鍵をくれた
「‥トイレの奥の、“Staff Only”って書いてる部屋に行ってみてくれ。彼等はそこにいるから、チャイムを鳴らして。後で珈琲を持って行くね」
そう云えば、トイレの横っちょにそんな表示がされてるドアがあったっけ‥‥
鍵を受け取って甘曽さんに会釈してから、その部屋に向かった
解錠した木製のドアの先には、カントリー調の純喫茶とは正反対の、無機質で頑丈そうな鉄製の扉があった
横には小難しそうな機械が設置されている
多分、パスワードを入力しないとこの先へは行けないんだ
パスワードなんて知らない、どうすれば良いんだろう───あ、そうだチャイムだ‥機械の上に、ベルのマークが書かれたチャイムがある
そっと押すと、ガチャガチャと何回か音がした後ドアが開いて、提午さんがひょこっと顔を出した
「やぁ。待ってたよ。どうぞ」
招き入れてくれて、俺は足を踏み入れた
室内には丸いテーブルが一つと、テーブルを取り囲むようにして四つのキャスター付きの椅子
テーブルの上には、PCが3台
一番奥に、プチシューを摘まみながらテーブルに足を投げ出して座る菩希さんがいた
その横に、煙草を吹かす蓉典さんが足を組んで座っている
提午さんは俺を室内へ通すと、備え付けられたPCの前にさっと座った
「よう。時間通り来たな」
「こんにちは。あの、宜しくお願いします」
「ま、適当に掛けな」
促された俺は、空いてる椅子に座った
まさか、喫茶店の裏にこんな部屋があるなんて───
そこは、ちょっと異質というか、部屋と呼ぶには随分杜撰な空間だった
天井は配管が剥き出し、裸電球が2、3個、だらしなくぶら下がっていた
打ちっぱなしの壁には夥しい数の資料が雑然とテープで貼られていて、所々油性マジックとスプレーで落書きされていた
上にはばかでかいモニター、何も映し出されていない
壁際に置かれたキャビネットにはファイルが所狭しと並んでて、そこにも油性マジックでよくわかんない文字とか絵が殴り書きされてた
配線がのたうち回ってる床はヒビとかシミだらけで、煙草の吸い殻とか空き缶がそこら辺に転がってる
あとは、プリンターとかゴミ箱とか、漫画とかDVDが雑然と並んだメタルラック
小さい冷蔵庫と、ふかふかのソファも置いてあった
「悪いことなんて一つもしてません」とはお世辞にも云い難い、陰鬱でアングラな雰囲気が漂う部屋
この一室だけ世界から切り取られたかのような、そして“そこ”に平然と存在していられる人間もまた異様なんじゃないか、と思えた
でも、俺の好奇心は急上昇してた
“こんなとこ”で“何でも屋”をやってるこの人たちは、一体何者なんだろう───目の前の全てに、心が滾った
「ふふっ。まだどんなことやらされるかもわかんねぇのに、そんな目ぇキラキラさせてんの?」
「将来有望かもだねぇ」
菩希さんと蓉典さんは、感心したように俺を見て笑った
提午さんも、軽く口の端を上げた
「‥改めて自己紹介するよ。信濃 菩希(しなの ほまれ)。ここでは上下関係を付けないって決めてんだけど、取り仕切る人間は必要‥‥ってことで、一応ここのリーダー的な立場にいる」
菩希さんは、“何でも屋”のリーダー
提午さんは菩希さんを“さん”付けで呼んでるし、それは何となく“そうなんじゃないか”と思ってた
でも見た目は菩希さんよりも蓉典さんの方が年上っぽい‥‥いや、もしかしたらそれも見た目だけなのかもしんない
続いて、提午さんが自己紹介してくれた
「利根 提午(とね だいご)です。基本的にPCいじって、みんなのサポートをしてます」
そう、基本提午さんはNäckrosorでもPCをカチャカチャしてる
だから、
「‥俺、提午さんのこと、ずっと“意識高い系”だと思ってました」
その印象を口にすると、菩希さんは突然噴き出して大笑いした
「ふっははは!こいつが“意識高い系”だって!?有り得ねぇわ!!」
「だって、喫茶店でPC弄るって、“意識高い系”の代名詞みたいなもんじゃないですか?」
「確かにそんなイメージあるけどよ、それやるなら普通、純喫茶よりも小洒落たカフェでやらねぇか?Näckrosorで“意識高く”されても、ただ滑稽にしか見えねぇし!あっはははは!」
「そんなに笑わなくてもよくないですか‥‥?まぁ、意識高くないのはほんとの話ですけど‥‥」
提午さんがしょぼくれた顔で、腹を抱えてる菩希さんを見遣った
「えっと、なんか、すいません」
「ううん、全然。‥さっき菩希さんが云ったけど、ここじゃ年上だから偉いとかそういう上下関係は取っ払ってるんだ。だから、敬語は要らないからね。俺も菩希さんにだけ個人的に敬語使ってるだけだから」
「‥‥わかりまし、た」
今までNäckrosorでずっと敬語で喋ってたんだもん、いきなり敬語を取っ払うのなんて無理だよ‥‥
ま、その辺は追々‥‥‥‥
「おい」
「ん」
一頻り笑った菩希さんが目配せすると、蓉典さんはテーブルから少し距離をとってサングラスをかけ直した
菩希さんはどこぞからナイフを取り出した───今度のは昨日の果物ナイフとは違う、殺傷能力の高いサバイバルナイフだ
昨日のようにペン回しの要領でくるんと一回転させると、菩希さんは頭の上でスナップを利かせてナイフを放った
その動きは全く無駄がなく、やっぱり瞬速だった
ナイフは俺の頬を横切って、壁にぶち当たった
また数ミリでも動いてれば、俺の頬はナイフで裂かれて流血してただろう
ナイフが床に転がる音が聴こえて、瞬時にそっちを見る
普通の人なら、ここらで冷や汗でもかくのかもしれないな
ああそっか、多分俺が「恐怖を感じない」って云ったことの信憑性を再度確かめる為にこんなことをしたんだろう、と思った
ってか、菩希さんてマジで何者なんだろう‥‥何の躊躇いもなく他人にひょいひょい刃物向けられるなんて、「もし怪我させちゃったらどうしよう」とか思わないのかな、それとも
よほど自分の“腕”に自信がある、とか───?
「‥大した面構えだな。‥‥昨日も今も、身の危険を感じなかったのか?」
ぼんやりとナイフを眺めてると、蓉典さんが尋ねてきた
「‥‥そーですね、はい」
「普通、刃物出された時点でビビらねぇか?」
「ビビらない、ですね」
俺の答えにくす、と笑うと、蓉典さんは席を立って、ナイフを拾い上げた
そして、菩希さんに返すと、再び席に座った
「‥‥‥況してや、大してよくわかりもしねぇ人間に『何でも屋やらねぇか』って誘われたり“こんなトコ”に連れてこられたら、『どんなヤベぇことさせられるんだろう』って身構えそうなもんだけどな。‥‥天塩 蓉典(てしお ようすけ)。このお方から仰せつかった任務を遂行する奴隷です」
蓉典さんは菩希さんを一瞥して、皮肉っぽくそう云った
「こらこら、語弊のある云い方すんなよな。お前がM気質だから顎で遣ってやってるんだろ」
「Mとちゃいまんがな」
「いーや、お前はMだね。その顔は生粋のM顔」
「違うって。‥‥いや、MはMで良いんだけど、“マゾ”じゃなくて“ムッツリ”のMね」
「どっちも大した変わんねぇじゃんか!」
菩希さんと蓉典さんがSだMだとやり取りしていると、電子音とロックが外れる音が聴こえた
ドアの向こうから、珈琲カップが5つ載った盆を携えた憂樹さんが入ってきた
ここに来る前に甘曽さんに持たされたのかな?
「悪い悪い、遅くなった」
「このクソボケ。こいつより遅れるとかどういう神経してやがんだ。大体時間決めてんのにいっつもどこで油売ってんだてめぇは。LSDブチ込むぞコラ」
ちっとも悪びれた素振りを見せない憂樹さんに向かって、菩希さんは矢継ぎ早に罵声を浴びせた
それでも、憂樹さんの顔には反省の色が見えない
多分、普段からこう、ルーズな人なんだろうな
「勘弁してシナ。ほら、美味しい珈琲持ってきたけん」
菩希さんのご機嫌を取るように、憂樹さんは珈琲を手渡した
「ったく‥‥‥‥憂樹、御挨拶して」
「おお。ぼっくん、俺は北上 憂樹(きたかみ ゆうき)さんじゃけん、宜しくな!」
そう云って、憂樹さんは俺にも珈琲をくれた
っていうか、名前だけなら既に知ってるんだけど‥‥
「はい、宜しくお願いします」
皆で珈琲を啜りながら、暫し談笑に更ける
これからどんなことをするのか、俺の気持ちは逸る一方だった
「っていうか、ほんとにビビってねぇの?とんでもねぇことさせられるかもしんねぇんだぞ?少なくとも俺は、ここに連れてこられた時結構ビビってたんだけど‥‥」
「そりゃ俺もじゃけん。まぁ、ぼっくんの顔見りゃ嘘吐いてるようにも見えんけどな。ぼっくん、ほんとに怖くないんじゃもんな?」
「別に。何とも思いません。‥‥‥‥ワクワクは、してますけど」
本心を吐露したら、俺以外の全員が軽く噴き出した
「ははっ!蓉典よか肝据わっとるんじゃん!」
「いや、ビビんねぇ方がおかしいから。‥‥ああ、悪い。別にお前がおかしいとかそういう意味じゃ‥‥‥いや、おかしいか‥?」
「自分が“おかしい”ってのは自覚してますんで。全然気にしてません」
「なーに云ってやがる。ここにいんのは全員キチガイだから安心しな」
菩希さんの一言で、また俺以外の全員が噴き出した
「まぁ、よっぽどのことがない限り危険な仕事は請け負わないから。‥‥あ、でもそれじゃ駄目なのか。危なくないと、モチベーション下がっちゃう?」
「どうですかね‥‥わかんないですけど‥‥‥」
正直、俺のこの感覚は自分でも未知数だ
まだそれに出会ってないってだけで、もしかしたら今後恐怖を憶えるような瞬間があるかもしれない
危険は、楽しい
楽しみが減るのは残念なことだけど、万が一死んじまったりしたらそれこそ楽しみどころの話じゃなくなるしな、うん
「で、今日は何すんの?」
「提午、依頼見てみ」
「ちょい待ち」
「新人もいるし、超簡単なのにするからな」
「うぃー」
提午さんはPCを操作して、メールフォルダを開いた
その中から、“今日の仕事”を餞別するらしい
さて、俺の“何でも屋”稼業、初仕事
愈々、始まります
0-2 喫茶「Näckrosor」
俺が危険を顧みない「ヤバい奴」だと感付いた人間は、俺の周りから挙って居なくなった
別に独りは嫌いじゃないからそれで良かったんだ、お陰でお気に入りの喫茶店「Näckrosor」を見付けられたから
暇さえあればそこで珈琲を飲んで過ごして、すぐにマスターの甘曽(あまそ)さんと仲良くなった
基本ぼっちの俺は気付けばNäckrosorの常連になってて、他の常連客とも仲良くなった
ある日、甘曽さんはNäckrosorが出来た経緯を話してくれた
数年前に脱サラしてNäckrosorを開き、サラリーマン時代からNäckrosorが軌道に乗るまでの間に幾つもの困難があったと聞かせてくれた
「この美味しい珈琲の味は、甘曽さんの血と汗と涙の結晶だ!」なんて堪く感動した俺は、自分が「恐怖を感じない人間である」こと、「特殊な血液型である」ことを甘曽さんに打ち明けたんだ
身の上話をしたところで、甘曽さんは顔色を変えた
あ、もしかしてドン引きされたかな
甘曽さんは今まで周りにいた奴等とは違う、この人なら俺を受け入れてくれると思ってたんだけど
折角見付けたお気に入りの居場所が無くなっちまうのは嫌だな───
そう思った矢先、
「‥‥伊芙生(いぶき)くん。君、特に決まった仕事はしてないって云ってたよね?」
「え、ええ、はい‥‥フリーターです」
「‥‥んむ‥‥‥‥。‥‥君さえ良かったら、“仕事”を紹介したいんだが。面接の話を取り付けようと思うんだけど、時間あるかい?」
「面接‥‥今からですか?」
「ああ。どうかな?」
特に断る理由もなく、俺はその“仕事”の話を聞くことにした
甘曽さんはにこりと笑って、どこかへ電話をかけ始めた
そして、店の看板を“close”にして、「奢りだ」とホットサンドを振る舞ってくれた
30分後くらいに、閉店してる筈のNäckrosorに来客があった
ひょっとして、さっき甘曽さんが電話をしてた人?面接をしてくれる人かな‥‥?
そう思って振り返ると、そこにはNäckrosorの常連客がいた
しかも、一人だけじゃなく、4人───
***
「迦一(かいち)さん。“新人候補”って、ソイツのこと?」
「ああ。急に呼び出して悪かったね」
「いえ、ちょうど終わったとこなんでグッドタイミングでしたよ」
俺を“ソイツ”と云った人、信濃 菩希(しなの ほまれ)さんは、甘曽さんに軽く会釈してさっと俺の横に座った
甘曽さん──下の名前は“迦一”(かいち)さん──は、常連客4人分の珈琲を淹れ始めた
「何じゃ、“ぼっくん”じゃったんか」
「うぃーす」
「こんにちは、伊芙生くん」
「あ、どうも、こんにちは」
妙な訛りで俺を“ぼっくん”(=迷子の男の子に「ボク、」と声を掛けるようなニュアンス)呼ばわりしたのは、憂樹(ゆうき)さん
軽いノリで挨拶してきたのは蓉典(ようすけ)さん、いつもグラサンかけてる人
紳士に挨拶してくれたのは提午(だいご)さんで、いつもノートPCを開いてカチャカチャしてるけど今日は持ってきてないみたい
三人は、カウンターで珈琲を受け取ると窓際のボックス席に行った
「待たせたな」
「あの、じゃあ、面接は」
「ああ。俺がやる。宜しくな」
菩希さんは俺を見遣ると、ニッと口の端を上げた
紫がかった金髪のベリーショートに、くっきりと引かれたアイラインに囲まれた瞳、燦然と艶めくゴールドの瞼、ワインレッドのルージュが映えるニヒルな口元───まるでパリコレに出演してるモデルみたいな出で立ちだけど、歴とした男だ
そう云えば菩希さんの仕事の話は聞いたことなかったな
一体何をしてるんだろう?
「───で、迦一さん。こいつが“向いてそう”ってのは?」
「ああ。さっき、とても興味深い話を聞いてね」
甘曽さんが寄越したシュガーポットの蓋を開けて、菩希さんはスプーンに山盛りの砂糖をのっさりと珈琲に入れていく
甘党らしい、けど、いつも「これは入れ過ぎなんじゃないか」ってくらい砂糖をぶち込む
もうこれ珈琲の味わかんないじゃないか‥‥?完全に素材の味を殺してます
「ふーん‥‥‥‥。‥‥お前、そんなに面白い奴なの?」
にこりと笑った菩希さんは、女性に負けないくらいガチで綺麗だ
てか俺、そんなに面白いこと云ったっけ??
「俺が当ててやろうか」
「何」
「そうじゃなぁ‥‥“逆立ちしたままコーラ一気飲みできる”、とか?」
「うわ、何の役にも立たねぇじゃんそれ」
「ぜーったい噴き出すやつだね」
「あ?ダメか?じゃけ、“ケツで歩ける”」
「無理無理、没」
「それもダメか‥‥この前ギネスに載ったらしいんじゃけど。ほんじゃら、“鼻からラーメン食える”とか‥‥‥‥」
ボックス席では、俺の「面白いところ」について盛り上がってる
てか、あの三人は何でここにいるの??
「‥‥ひょっとして、“恐怖を感じない”ってこと、ですか?」
甘曽さんの様子を窺うと、「その通り」と云わんばかりに頷いた
「何だそれ、詳しく聞かせろよ」
「詳しくってか、そのまんまです。‥‥恐怖ってものを、一切感じないんです」
「‥‥‥‥何じゃそりゃ‥‥っつーかさっきの、全然見当違いじゃったな‥‥」
ボックス席から、気の抜けた憂樹さんの声がした
提午さんと蓉典さんは、興味深そうに黙ってこっちを見ている
「───‥試してみようか」
そう云って菩希さんは席を立ち上がり、甘曽さんが洗い物をしてるキッチンに向かった
徐に果物ナイフを取り出してくるんと一回転させると、カウンター越しに俺の顔目掛けて真っ直ぐ突き出してきた
その動きは、コンマ何秒かという神がかり的な瞬速だった
「ちょ、菩希さん───!!」
俺に危険が及ぶと感じたのか、提午さんは慌てて席を立って菩希さんに声を掛けた
「‥は、‥‥驚いたな。マジかお前」
ナイフの先は、俺の左目の数ミリ目前にあった
少しでも動いてたら眼球に傷が付いてたかもしれないという寸止め───そう考えると恐ろしい、と思うのが普通の感覚だと思うけど、俺は特に何とも思わなかった
例え突然ナイフを突き付けられても、全然怖くないから
てか、刃物の取り扱いが確実に素人じゃないですね
菩希さん、アナタ、何者ですか??
「‥今、シナは眼球狙ったんだぞ。結構マジで」
蓉典さんが、掛けているサングラスを少しずらしてそう呟いた
「え‥そうだったんですか?」
「“そうだったんですか”って‥‥‥瞬き一つしなかったな」
「まぁ、フツーの感覚ならガードするなり何なりするだろうな。それに今の、“反応が遅れた”って感じでもなかった」
「“恐怖を感じない”ってのは、ほんとの話みたいじゃな?」
きょとん顔の俺を他所に、ボックス席は騒然とした
その後すぐに、身動ぎ一つしなかった俺に感心し始めた
「まだよくわかんねぇけど‥‥取り敢えず、なんか一つやってみっか?」
「‥‥って、それは‥‥」
「一応、採用。俺は“ここの常連客”としてのお前しか知らないけど、今はそれで十分だ。それに、やるかやらないかはお前の自由だから、あとは仕事の内容見て決めな」
確かにその通りだ
俺だって、この人たちのことはここの常連客であること以外はあまり知らない
知らないけど、何故か俺も“それで十分だ”と思えた
「‥えと、宜しくお願いします」
「ああ、宜しく。早速だけど、明日から動けるか?」
菩希さんは甘曽さんに「勝手に触ってすいませんでした」と謝罪して、ナイフを洗って仕舞った
甘曽さんは特に何も気にしていない様子で、にこにこしながらお手製のプリンアラモードとホイップクリームの袋を菩希さんに手渡した
菩希さんは容赦なくプリンアラモードにホイップをこんもり絞り出した
だから、そんなに盛ったら元々の味がわかんなくなっちゃうじゃん‥‥‥
採用、てことは、取り敢えず新しい仕事が決まったわけだけど、俺には最大の疑問があった
「‥‥あの、それは良いんですけど‥‥一つお尋ねしても良いですか」
「何?」
「菩希さんは、何のお仕事されてるんですか?」
菩希さんも、ボックス席の三人も、俺の疑問を聞いてニヤニヤしていた
プリンアラモードに盛られたホイップを指に一掬いして口に含むと、菩希さんは軽く舌舐りして云った
「───“俺ら”は、“何でも屋”だよ」
***
「明日、今日と同じ時間にNäckrosorに居てくれ。仕事の内容は明日話す」
そう云って、菩希さんはホイップてんこ盛りのプリンアラモードを食べ始めた
ああ、見てるこっちが胸焼けしそう‥‥
特に用事がなくなった俺は、甘曽さんと少し世間話をしてから帰宅した
帰宅してから色々考えた
菩希さん“たち”がやってる「何でも屋」って、どんなことをするんだろうか?
文字通り「何でもする」ってことなら、もしかしたら何かしらヤバいこともやってるのかもしれない
例えば、
小麦粉みたいな粉末が入ったアタッシュケースと、黒いスーツを来たおっかないオジサンたちが持ってきた黄色いお菓子がぎっしり詰まったケースを夜中に埠頭で交換したり、とか
例えば、
トランクの中にガムテープでぐるぐる巻きに拘束された瀕死の人間みたいなものが入ってるにも拘わらず、ロールスロイスを海に沈める、とか
例えば、
大きな頭陀袋に入った“何か”を、野犬が掘り返さないように樹海まで行って深く深く穴を掘って埋める、とか
とにかく、「何でも」というととっても犯罪臭いことをやるんじゃないかと思わずにはいられなかった
までも、そんなんでも俺は全然怖くないんだけど‥‥
帰り際、菩希さんは「バックレても構わないから」と笑っていた
別に俺、定職に就いてる訳じゃないし、これはコンスタントに収入を得られる良い機会かもしれない
それに、危険なことヤバいことは、俺が常に欲してるものだ
一体、どんなことが待ち構えているのか───
そんなことを考えながら、その日は眠りに就いた
0-1 「Feel no fear.」
俺は、生まれつき恐怖を感じない
何でか知らないけど、俺には“怖さ”を感じる器官が機能していないんだ
だから、何処へでも無鉄砲に突っ込んじまう
そして、その瞬間が楽しくて仕方ない
小さいときからそうだった
橋の欄干とか線路の上を歩いてみたり、電柱に登って電線を伝ってみたり
高いところなんて「大好き」っていうレベルじゃない、寧ろ愛してる
バイクの免許を取って、夜中の港で沢山チキンレースをやった
暴走族の喧嘩やヤクザのドンパチにも、どさくさに紛れて参加した
そんだけ自ら危険な目に遭っても、特に何とも思わない
全然怖くないんだ
とにかく、生か死かのギリギリ、スリリングな状況が大好きなんだ
正直、自分でも“異常だ”と思う
だけど、一つだけ重大な弱点がある
俺は100万人に一人という割合の特殊な血液型
Rh-よりも遥かに珍しいらしく、そういう血は“稀血”(まれけつ)と呼ばれている
稀血でいちばん有名なのは「ボンベイ型」ってやつかな、テレビドラマにも出てきたことがある
稀血はどっかの機関に長期冷凍保存しておくらしく、万が一の時の備えとして輸血バンクに登録してある
「迂闊に輸血が必要なほど大量出血するような大怪我が出来ない。輸血が必要になったからとて、すぐに自分に適合する血液が届く訳じゃない」
それが、俺の最大の弱点だ
幸いなことに、今まで輸血が必要なくらいの大怪我はしたことがない
恐ろしいくらい運が良いんだろう
何にせよ、俺は、生きるか死ぬかという危険な状況下に身を置くことを、止められないんだ