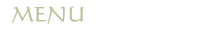NEW ENTRY
[PR]
64 密談③
アタルは自宅で大学での課題を進めていた
課題が終わると遅めの夕飯を済ませ、だらだらとバイト先へ向かった
バイト先であるバー“JAM”に着いた頃、時刻は22時半を少し過ぎていた
スタッフルームに入り、ロッカーを開け、店の制服である真っ新な白いシャツと黒いスラックスに着替える
「はよーっす」
店に出るなり、店長がアタルに手招きした
「あ、アタルくん。お友達来てるよ」
「へ?トモダチ?」
「端のボックス入ってもらってるから」
「‥‥ほーい」
アタルが一番端のボックスを覗き込むと、ソファに座り怠そうに煙草を吹かす長身の男───菱和が居た
見た目は成人男性に見えなくもないが、年齢を偽ってまで酒を呑みに来たとは考えにくい
何か他に理由があるのではないかと思ったアタルは、いつものように気さくに話し掛けた
「‥‥よう。練習どうだったよ?」
菱和は顔を上げ、軽く会釈した
「‥‥‥‥お疲れ様です。ぼちぼちっすね」
「そっか。何飲む?」
「烏龍茶貰ったから、大丈夫す」
「そうか?ビールでも注いで来るか?」
「‥‥俺まだ未成年すよ」
「そうだっけ、はは」
アタルは菱和の向かいに座り、煙草に火をつけた
「っつうか、よく俺のバイト先知ってたな。云ってたっけ?」
「ユイと佐伯に聞きました」
「そっか。なんかあったか?」
「ちょっと、話あって」
「ん、何だよ?」
菱和は煙草を灰皿に押し付け、神妙な面持ちでアタルに話す
「───‥‥‥‥暫く、バンド休まして欲しいんす」
神妙な面持ちながら、眼光には何やら強い意思を感じる
想像していたよりも深刻そうな話であると考え、アタルは煙草を灰皿に置き、菱和の顔を覗き込むようにして尋ねた
「‥‥‥嫌んなったか?」
「んーん、全然。寧ろ、すげぇ楽しいす。楽器やってて良かったって、ほんと思う。‥‥でも、このままバンドに居たら、“また”何か起きちまうってこともないとは限らない。‥‥だから、そうならない為にはどうすれば良いか、少し考える時間欲しいんす」
自分がバンドに居ることでリサが拐われた“あの日”のようなことが、最悪それ以上のことがまた起こり得るかもしれない
どちらにしても、歓迎できる出来事ではないことに変わりはない
菱和は駒井から電話があったことでより一層それを危惧し、その可能性をアタルに打ち明けた
アタルは火をつけたばかりの煙草を一旦消した
「なんかあったんか?」
「‥‥‥‥今はまだ」
「‥‥‥、だったら、そんなん今考えることもねぇんじゃねぇの?」
「‥‥今すぐにでも、俺が居ることで生じる不利益をどうにかしたいんす」
「不利益、ねぇ‥‥‥‥。‥‥理由如何によっては、お前がバンド抜ける可能性もあるってことか?」
「‥‥なくはない、と思います。とにかく、迷惑かけたくないんす。俺の中の問題なんで、俺一人で考えさせて下さい。‥‥こんな話してすいません。まずはリーダーにちゃんと話さなきゃと思って‥‥すいません」
菱和は頭を下げた
わざわざバイト先まで出向いて自分にこんな話をするということは、第三者が介入することは恐らく無理だ
菱和が真面目な性格であることは十分理解しているが、頑固な一面があることも知っている
“あの日”もそうだった
周りの制止も聞かず、菱和は一人で廃ビルへ向かった
“あの日”の全てのことに、菱和は責任を感じていた
それはアタルも重々理解している
そして、今も──────
幾ら自分達が力を貸すと云ったところで何が何でも菱和は一人で解決しようとする
アタルはそう感じた
「‥‥そっか‥‥‥‥わかった。‥‥でも一つ聞かしてくれ。お前のほんとの気持ちはどうなん?お前自身は、“抜けたい”とか思ってんの?」
「出来ることなら、抜けたくないす。‥‥こんなバンド、きっともう二度と出会えない」
菱和は俯き、そう呟いた
決して誰でも良いわけではない
このバンドは、絶対にこのメンバーでなければいけない
バンドとは、そのどれもが奇跡としか云いようがない確率でメンバーが集まり出来ている
そう想えるバンドに出会え、メンバーにも恵まれ、そこに居られることがこの上なく嬉しい
絶対に失くしたくない、とても大切なもの
自分にとって、バンドはとても重要な位置を占めている
「ははっ、だろうな。どのパートも粒揃いだからな、俺含めて」
アタルはドヤ顔をし、ニヤけながら煙草を咥えた
菱和は頷き、くす、と笑った
「‥‥‥‥俺ん中では、すげぇ大事なもんです。バンド自体も、メンバーも。‥‥バンドが無くなったり続けられなくなったりすることと自分の気持ち、そんなん比べるまでもなく前者の方がずっとずっと大事す」
バンドや自分たちに対して抱いている感情を素直に吐露する菱和
アタルは嬉しく思った
菱和を、手離したくはない
今のバンドにとって、菱和は不可欠である
真っ直ぐで真面目な菱和の性格やプレイは、バンドの冷静さや調和を保ち、しっかりと支えてくれる大切な存在だ
そして、バンドのリーダーである自分に筋を通そうと訪ねてきたことに対し、やはり『真面目な奴』だと思えてならない
少し呆れた顔をしながら、煙草を吹かす
「‥‥‥‥お前って、案外不器用なのな。料理はめちゃくちゃ上手ぇのに」
「そうすね‥‥不器用すね。‥‥色々考えたけど、これが今自分に出来る精一杯でした」
「そっか。‥‥‥‥でもよ、これだけは云っとく。あいつらも俺も、おめぇの云う問題に巻き込まれたりすることくらい何とも思っちゃいねぇぞ。例えそれがバンド存続の危機に直面するようなことだったとしても。‥‥特に、あのチビは」
アタルは煙草を咥えたままニヤリとした
アタルにも菱和にも、“あのチビ”の顔が浮かぶ
──────ユイ
菱和は、ふっ、と口角を上げた
「‥‥‥‥確かに、あいつは特にそうかもしんないすね」
「だろ?あいつ、本気で空気読まねぇときあっかんな。‥‥ま、俺でなんか力になれることあったらいつでも云ってこい。あいつらには、折見て話しとくよ」
「‥‥お願いします。すいません、迷惑かけて」
「気にすんな。おめぇがとことん納得するまで考えりゃ良いさ」
「‥‥はい」
「お前、まだ時間ある?折角来たんだし、ゆっくりしてけよ」
「はい」
「‥‥‥‥あとよ、マジでいい加減敬語止めろよな。前にも云ったろ?」
「わかりました」
「‥‥、二日酔いどころか五日酔いになるくれぇ呑ますぞてめぇ」
「勘弁してください。っつうか、そんなことしたら捕まりますよ」
「‥バレなきゃ良いんだよ!」
アタルは菱和をジロリと睨み付け、煙草を灰皿に押し付けた
決してアタルをおちょくるつもりはないのだが、まだ暫くアタルには敬語を使い続けようと思い、菱和は少し笑った
63 護りたいもの
ユイたちが帰宅した後
部屋はしんと静まり返り、無機質な空間になる
油ものが多かった今夜の食事
ユイと拓真は下らない話をしながら2人で食器を洗い、片付けた
綺麗に並んだ食器をちらりと見て、菱和は換気扇の下でだらだらと煙草を喫い始めた
───ほんと、何なんだろうなあいつら
ついさっきまでキッチンに並んで食器を洗っていた2人の姿を思い出し、菱和はほんの少しだけ笑んだ
リビングのテーブルに置きっぱなしの携帯が音を立てて震える
菱和は煙草を持ったままリビングへ向かい、携帯を手に取った
見慣れない番号からの着信だったが、菱和は何の躊躇いもなく通話ボタンを押した
「‥‥‥はい」
『‥‥‥‥‥‥‥‥』
電話の主は、何も喋らない
かけてきた奴が無言とは、どういうつもりなのか
若干苛ついた口調で、菱和は返答を促す
「‥‥もしもし」
『‥あ、あの‥‥‥‥菱和?』
「‥‥誰」
『俺。‥‥駒井だけど』
BURSTにいた頃は互いに番号を登録していたが、脱退に際して必要ないと思った菱和はとっくに電話帳から古賀や駒井の番号を消去していた
駒井は未だ、菱和の番号を登録したままなのだろう
特に不信がることもなく、菱和はぶっきら棒に言葉を返した
「‥‥‥‥なんか用か」
『あ、ああ。あの、前に話した件なんだけど‥‥』
「‥‥‥‥古賀のこと?」
『ああ。‥‥今まで何もなかったか?』
「別に何も」
『そっか‥‥それなら良いんだ。あいつ、元BLACKERの奴等集めて、お前のこと捜してるみてぇで』
「‥‥‥‥ふーん」
『‥‥‥高野がさ‥‥昨日ヤられたんだ‥‥‥‥大したことはなかったんだけど‥‥。とにかく、お前も気を付けてた方が良いかもと思って‥‥』
駒井の声は、少し震えているように感じた
嘗て共にバンドをやっていた
ただそれだけの関係だった筈なのに
『バンドはバンド』と区別していた菱和と、結果的に古賀にひれ伏す形になっていた高野と駒井
高野が何者かに襲われたとなれば、自分にもその危険があるということ
いつ来るかわからない古賀やBLACKERの残党の恐怖に怯えるのもわからなくはない
逆恨みされる筋合いなど皆無なのだが、古賀は口で云ってどうにかなる相手ではない
それは、菱和も駒井も重々理解している
───マジでどうしようもねぇな
菱和は煙草を喫い、溜め息を吐くように煙を吐き出した
「‥‥‥‥わかった、どうも」
『あ、菱和』
「‥‥何」
『お前のことだから大丈夫だと思うけど、マジ気ぃ付けて‥‥あいつら、何するかわかんねぇからさ‥‥‥‥もしかしたら、また‥‥』
「‥‥ん。んじゃ」
駒井はまだ何か云いたげな様子だったが、菱和は通話終了ボタンを押した
そのまま携帯をソファに放り、少し短くなってしまった煙草を喫いにキッチンへ戻った
先ほどまでの騒がしく賑やかな雰囲気の余韻が、一気にぶち壊されていく
雰囲気だけならまだしも、自分を取り巻く全てのものが侵食されていくような気がする
駒井が云いたかったことは、恐らく自分以外の人間が傷付けられる可能性のことだろうと菱和は思った
現に、自分と話していたというだけの理由でリサは拐われたのだから
そんなことは、駒井の口から聞かずともわかっていることだった
高野と駒井から話を聞いた段階で、既にその可能性も頭の中に入っていた
そんな話、今更改めて聞きたくはなかった
菱和は、苛ついて髪を掻き上げた
確かに自分一人ならどうとでもなる
不本意ながら喧嘩することも厭わねえ
また骨折ったりしたら結局バンドに迷惑かけることになっちまうけど‥‥
それよりも、あいつらに危害を加えられることだけは絶対にあっちゃならねぇ
仮に、今すぐ古賀たちをぶっ潰しに行ったとしても、また報復とか下らねぇこと考えるかも知れねぇ
どうすれば良い?
どうすればあいつらを危険な目に遭わせずに済む?
どうすれば───
ぐるぐると思考が巡る中、菱和は一つの結論に辿り着いた
──────俺が今後一切あいつらと関わらなければ良いのか
その結論とは、『まずは自分がユイたちから離れること』だった
屋上に集い囲む昼食
下らない話を交えてのバンド
どうにかなってしまいそうなほどの高揚感を味わえるライヴ
先ほどまでのような和やかで楽しい雰囲気
愛おしいと想っている、ユイの笑顔───
その全てを自ら手離すのは、名残惜しくて仕様がない
本当は、自分の意志に反している
だが、背に腹は変えられない
苦渋の決断だが、致し方ない
あいつらの身に危険が及ばないなら、てめぇの意志なんざどうだって良い───
「──────‥‥‥‥“寿町”‥‥」
菱和はちらりと時計を見た
時刻は22時を回ったところ
直ぐ様煙草の火を消し、ジャケットを羽織った
ソファに放ったままの携帯と、煙草をポケットに押し込んで自宅を出た
覚悟を決めた菱和の行き先は、一つしかなかった
62 青椒肉絲、油淋鶏
菱和が高野と駒井に会いに行ってから二日後
学校に行き、屋上で昼食を摂り、放課後はスタジオへ
この日は学校の課題があるとのことで、アタルは不参加だった
スタジオでの練習が終わると、菱和の自宅へと向かう
普段と変わらない時間を過ごすユイ、拓真、そして菱和
ユイと拓真は心配を掛けまいと、リサとカナが高野と駒井につけられていたことを未だ菱和に黙っている
菱和は既にその事を知っており、一人秘密裏に動こうとしている
『自分の思惑はまだバレていない』と、互いに思っていた
自宅へ向かう道すがら、菱和は2人に献立を問う
「今日は何食う?」
「んーとね‥‥‥‥じゃあ、中華が良い!」
「中華、ね‥‥‥何が良い?」
「青椒肉絲と、油淋鶏!」
「佐伯もそれで良い?」
「うん。‥‥‥‥あ、じゃあ炒飯もお願いして良い?なんか手伝うから」
「‥‥わかった」
───こいつら、熟、食欲あるな
そう思い、菱和は少し口角を上げた
足りない食材を買い足し、2人は菱和の自宅を訪れた
ユイと拓真はあーでもないこーでもないと会話を続けながら室内へ上がる
2人が来ることで、必要最低限の家具しか置かれていない殺風景な室内が一気に賑やかになる
最早BGMとなりつつある2人の雑談を背に、菱和はすぐに調理に取り掛かる
「‥‥あ、俺野菜切るよ。ちょっと手洗わして」
拓真はキッチンへ行き、手を洗う
菱和はその好意に甘えることにし、拓真が下拵えを終えるまで煙草を喫って待っていることにした
ユイも、拓真が包丁を握る姿をにこにこしながらカウンター越しに見守る
野菜に包丁を入れていく拓真を見て、菱和は煙を吐きながら云った
「手際良いな」
「まぁねー。ひっしーほどじゃないけど、俺もたまに料理やるんだー」
そう云いながら、拓真は上機嫌で次々と野菜を切っていく
「‥‥へぇ。じゃあ、機会があったらなんか作って」
「いやー‥‥それは無理っしょ」
「何で?」
「そりゃ、ひっしーにゃ敵わんからさー。完全に見劣りしちゃうもん」
「そんなことないじゃん。いつだったか拓真が作ったコロッケ、美味かったよ!」
謙遜しつつもさくさくと下拵えを進める拓真に向かい、ユイが身を乗り出して話し出した
「ふーん‥‥コロッケ、ね‥」
低く呟いた菱和の声に、拓真の手がぴたりと止まった
ちらりと横を見ると、菱和が煙草を咥えたまま目を細めている
「おまっ‥‥余計なこと云うなよ‥‥!てかコロッケなんてだいぶ前の話だし!」
「何だよー?良いじゃん!また今度作ってよ!」
「たっくん、俺もコロッケ食いたい」
「うぅー‥‥‥‥勘弁してよー、菱和さぁん‥‥」
心底意地悪そうな顔をした菱和に“たっくん”と呼ばれた拓真は苦笑い
ユイはにこにこしながら2人を眺めていた
***
拓真が材料を切り終えたところで、続きは菱和にバトンタッチ
ユイと拓真はリビングで相変わらず談笑をしている
中華特有の香辛料と胡麻油の香り、強火で炒められる食材の音に、ユイも拓真も次第にそわそわし出す
細切りのピーマン、筍、牛肉に、オイスターソースが絡んだ青椒肉絲
香ばしく揚がった鶏肉に葱がふんだんに盛られてある、甘酸っぱい香りの油淋鶏
炒飯には青椒肉絲と油淋鶏の調理で余った細かな野菜が入っており、彩り豊かである
テーブルに並んだ中華の数々は、益々ユイと拓真の食欲を唆らせる
2人仲良く手を合わせ、菱和の料理に舌鼓を打った
「濃くないか?」
「ぜーんぜん。美味い、美味いです」
「ほんと、美味い!油淋鶏サイコー!あー、あっちゃん勿体ねぇー!こんな日に来れないなんて!」
「うんうん。まぁ、今日は大変残念でした、ってことで」
ユイと拓真は次々と食事を頬張る
2人の食欲に満足し、麦茶を注ぐ菱和は2人にひょんな疑問を尋ねた
「‥‥そういや、あっちゃんてどこで働いてんの?」
「寿町にある“JAM”っていう店だよ」
「寿町‥‥‥‥」
「なに、気になるの?」
「いや、どんなとこなんかなーと思って」
「めっちゃお洒落だよ!カウンターの後ろにボトルが沢山並んでてさ、キラキラしてんの!俺あの店大好き!」
ユイは青椒肉絲を口一杯に頬張った
「へぇ‥‥行ったことあんのか」
「うん、ちょこっと遊びにね。まだお酒飲めないから、ほんとに行っただけ。ひっしーは、来年なったら呑みに行けるね」
「そっか。アズ来年ハタチになるのか。‥‥なんかオトナって感じ!」
「ほんと。ハタチって聞くと、いきなり大人になったような感じするよなー」
咀嚼しながらうんうん、と頷く2人
「‥‥お前らもあと3年したら二十歳じゃん」
「3年て、意外と長いよ!ね?」
炒飯用の蓮華を咥えながら、ユイは拓真に云った
拓真は麦茶を飲み干して一息ついた
「んー、そうなぁ。‥‥‥‥二十歳の自分って、何やってんだろなー。いまいち想像出来ねぇや」
「二十歳になっても、バンドはやってたいなぁ」
「そうだな。それは俺も思う。何を於いても、バンドは続けてたいな」
「アズは?」
箸を進めつつ、ユイと拓真は菱和を見つめた
「‥‥‥‥、俺も続けられてたら良いなと思う」
穏やかにそう云い、菱和は麦茶に口をつける
菱和の言葉に安堵の気持ちを覚え、ユイははにかみながら云った
「バンドとアズの飯は外せないな、ずっと!」
「二十歳になったらお前も料理くらい覚えろよ」
「無理無理!俺不器用だし!」
「‥‥最初から諦めんなよ」
「だって、料理って難しくない?あの料理にはこの材料でー、この調味料使ってー、って。俺、頭使うの苦手だしさー」
「いやいや、同じことだよ。‥‥例えばさ、」
拓真は箸を置いた
「今こうやって飯食ってるけど、何が目的?」
「‥‥腹減ってたから?」
「うん。空腹を満たす為、だよな?じゃあさ、ギターは何の為に弾いてる?」
「そりゃあ、‥‥もっと上手くなりたいから、かな」
「うん。つまりさ、『空腹を満たす為』に、『料理をする』。『上達する』に、『ギターを弾く』。ほら、おんなじっしょ?」
「‥‥‥‥うん」
「だから、ギターに費やしてる情熱をちょこっと料理に向ければ出来るようになるんじゃないの?実際、ギター上手い人って料理にハマる人多いみたいよ」
「ふーん‥‥‥‥」
料理もギターも、“結果”ではなく“過程”を楽しめば何倍も面白い
そして、“過程”を重んじれば“結果”は自然についてくるものだ
拓真の話はとても分かりやすく、ユイも菱和も感心し納得した
「───‥‥でもさぁ、やっぱ俺は料理出来なくても良いや」
「え、何でそうなんの?」
拓真は拍子抜けした
「もし俺が料理にハマっちゃったら、アズの料理食う機会減るかもしんないじゃん!それなら、もっとギター弾けるようになった方がずーっと良い!こんな美味いもん食えなくなるなんて、絶対やだ!」
ユイはにこっと笑いながらそう云い、油淋鶏を美味しそうに食べた
「‥‥ああ、そりゃごもっともだわ。俺もこんな美味い飯食えなくなるのは嫌だな」
ユイには料理を覚えるつもりなど更々無いということがわかり、若干呆れつつも、拓真はユイの言葉に同意した
今まで、他人に食べさせることを前提に料理を作ったことの無い菱和は、自分の腕など所詮人並みだと思っていた
だが、実際に他人に食べさせてみて初めて、人並みよりは少しくらい上なのかも知れないと感じた
事実、菱和の料理を口にしたユイも拓真もアタルも絶賛しており、世辞で『美味い』と連呼しているようにも思えない
それならば、
───もっと精進しなきゃなんねぇかな
「‥‥‥‥そうかい」
食事を進めるユイと拓真を見ながら、菱和は少し口角を上げた
61 密談②
時刻は間もなく日付を越える
菱和は3人の余韻が残る自宅を後にし、車を走らせた
行き先は隣街にある、乗降客の少ない無人駅
二度と足を踏み入れることはないと思っていた街に、再び赴くことになろうとは───
憂いながら、行き交う車も殆ど無い深夜の道を通る
目的地周辺で車を停め、溜め息を吐いた
ここは嘗て、よく通っていた街───前に在籍していたバンド、“BURST”の拠点であった街だ
街の外れにはBURSTとして最後にライヴを行った会場も、リサが拐われ監禁された廃ビルもある
あの夜のことを思い出せば鬱になってしまいそうなほど忌まわしい地となってしまったこの街は、BURSTのメンバーであった古賀、高野、駒井の地元でもある
足の無い高野と駒井の移動手段は、主にバスと電車だった
最寄りの駅で張ってれば、必ず現れる──────
BURSTとして共に活動していた頃、帰宅は決まって深夜過ぎだった
2人が未だ以前のような生活を続けていて、運が良ければ会える筈だ
菱和は無人の駅構内で2人が現れるのを待つことにした
隅にあるベンチに腰掛け、煙草に火をつける
足を投げ出し怠そうにし、学校でユイたちの話を聞いてからずっと同じことを考えていた
高野と駒井は、基本的にはいつも古賀に従っていた
古賀の何を恐れていたのかはわからないが、3人の上下関係ははっきりしていた
どちらかといえば喧嘩が得意だったり好きだったような印象もなく、リサが拐われた一件も古賀の命令でやったとしか思えない
今回、リサとカナをつけ回したことも、古賀の命令なんだろうか
だとしたら初めから古賀の所に行けば話は早いのだが、リサの話だと古賀の姿は無かったと聞く
もしかしたら、別の理由があるのかも知れない
理由もなく人を殴ったりはしない、したくない
だからまずは、2人がそんなことをした理由を知りたい
ただ、理由によっては、再び完膚なきまでに叩きのめす───
老朽化し、寂れた無人駅
最終列車が通過する音が聴こえた
「‥‥‥‥でさ、この前の箱で仲良くなった奴が‥‥」
「ああ、あの人な。ちょっと頼んでみっかー‥‥」
男の話し声がする
声の主は、ギターを背負った高野と、スネアが入ったバッグを提げた駒井だった
高野がいち早く菱和の姿に気付き、立ち止まって驚愕する
「──────‥‥‥‥菱、和‥‥!」
「え?‥‥あ───」
駒井も菱和に気付き、立ち止まる
───今日が無理なら何日か通うつもりだったけど、運が良かったな
「──────‥‥ツラ貸せ」
菱和は立ち上がって煙草の火を消すと、無表情で2人に一瞥くれ、ついてくるよう顎で促した
高野と駒井は困惑気味だったが、歩き出す菱和の後をついて行った
駅構内を出て、脇にある駐輪場まで歩く
菱和は2人に向き直り、低い声で云った
「───この前のライヴの帰り、俺のダチつけ回したんだってな」
高野と駒井は、ギクリとする
菱和は、更に低い声で語気を強めて云い放った
「‥‥‥‥どういうつもりか知んねぇけど、場合によっちゃお前らのこと今この場でどうにかしねぇとなんねぇんだよな」
限り無く無表情な菱和の顔にたじろぐ高野と駒井は、慌てて弁解した
「い、いや‥‥ちょっと話あって‥‥‥‥」
「あの女たちにじゃなくて‥‥‥‥‥‥寧ろ、菱和に」
「──────は?」
菱和は予想外の2人の発言に面食らい、眉を顰めた
「‥‥‥‥だったら初めから直接俺んとこ来いよ、回りくどくて面倒臭せぇ。‥‥何だよ、話って」
苛ついた口調で話す菱和に畏縮する2人
『この場でどうにか』とは云いつつも現時点では菱和には手を出す気は無く、2人も菱和がそういう人間ではないことはわかっているのだが、“あんなこと”をした自分達へならば今にも殴りかかってきそうだと若干おどおどしている
「‥‥古賀の野郎がさ、お前のことまだ相当恨んでるから、『気を付けろ』って伝えて欲しかったんだ」
「ほんと、それだけ伝えて貰おうと思って‥‥」
2人の行動は古賀の命令によるものではなく、自分達の意思だったらしい
菱和は若干呆れ顔でまた軽く溜め息を吐いた
「‥‥‥‥誤解されるようなことすんなよな」
「いや、それは悪かった。でも‥‥“あんなこと”しちまった手前、面と向かっても云えなくてさ」
「警戒されても仕方ないってわかってたけど‥‥とにかく、古賀のことお前に伝えたかっただけだから」
2人は未だ菱和を若干畏れつつも真に菱和の身を案じ、真剣な眼差しを向ける
「‥‥ふーん‥‥‥‥‥」
「‥‥‥‥でもびっくりした。まさかこんなとこで待ち構えてるなんて」
「‥‥あいつら不安がってたし、ほんとならもう誰だかわかんなくなるくれぇ伸してやるつもりだった。でも無駄な喧嘩したくねぇし、どっちにしても話くらい聞かねぇとと思っただけだ」
古賀絡みの話であったことに落胆しつつ、意図的にリサやカナを傷付けようとしていたわけではなかったことに安堵し、菱和は煙草に火をつけた
怠そうに煙を吐く菱和
その態度と相反する菱和の心理と、言葉
思い返せば、菱和は見た目に反し『真面目で実直な男』だった
高野も駒井も、菱和の第一印象は『何を考えているのかわからない怖い奴』だった
しかし、いざ話をしてみるとすぐに畏怖の対象ではなくなった
サポートとしての立場ではあったものの、練習やライヴには欠かさず参加し、用が済めば直ぐに帰宅
ただ単に興味がなかっただけかもしれないが、打ち上げやファンの女子高生たちとの乱痴気騒ぎに混ざったことなども皆無
“BLACKER”が他のチームと喧嘩をするときに駆り出されたりすることもあったのだが、菱和は一度足りとて加勢に行ったことはない
菱和の腕ならば、高野と駒井を“伸す”のに時間はかからないだろう
だが敢えてそうせず、自分達の行動の意図を知りたいと深夜にわざわざ隣街まで赴いた
菱和にこんな行動力があるとは、高野も駒井も予想外だった
そして、今菱和の身近にいる人間は、一刻も早く危険因子から遠ざけたいと願うほど大切な存在なのだろうと思えて止まない
駒井は、その思いを素直に言葉にした
「───‥‥ほんとに大事なんだな、あの女とかバンドのダチのこと」
駒井の一言を聞き、菱和の脳裏にユイやリサの顔が浮かぶ
───もう、
「‥‥‥‥‥‥、ただ大事とか、そういう次元じゃねぇ」
聴こえるか聴こえないかわからないほど低く呟いた菱和の言葉に、高野と駒井は怪訝な顔をする
「え?」
「‥‥何でもね」
菱和がそれ以上言葉を発することはなく、高野は軽く息を吐いた
「‥‥ま、こっちも古賀のこと伝えられたしちょうど良かった。ここまで車で来たのか?」
「ああ。‥‥つか、俺にそんな話するってことは、もう古賀とは切れてんの?」
「切れてるも何も、俺ら元々ただバンドやりたかっただけだし‥‥‥‥古賀が“BLACKER”とつるみ出してから、ワケわかんなくなっちまって‥‥情けねぇ話だけど、いつの間にかあいつの言いなりになってた」
「“BLACKER”も今回のことで解散したっぽい。古賀は頭の人にも高橋って人にもボコられたんだけど、俺らは手ぇ出されなかった。そういうのもあって、実は俺らも古賀に恨まれてんだ‥‥正直、いつ何かされるかってビクビクしてるよ」
高野と駒井は顔を見合わせて苦笑いした
気に入らないというだけで無関係の友人に手を掛けようとした古賀のことを思えば、2人が怯えるのも多少は理解出来た
───だからって、こいつらには何の義理もねぇけど
菱和は少し気を張らなくてはならないと思い、俯いて煙草の煙を吐いた
「‥‥‥‥お前の今いるバンド、すげぇ良いな」
高野がそう云ったのを聞き、菱和は顔を上げた
「観に行ったんだ。今回のも、先月のマンスリーも。菱和には、あのバンドが合ってる」
駒井も高野の話に同調する
「‥‥‥‥そりゃどうも」
菱和はふい、と目を逸らし、少しだけ口角を上げた
伸び伸びと楽しそうにベースを弾く菱和の姿は、2人の脳裏に鮮明に焼き付いていた
Hazeというバンドこそ、菱和が本領を発揮出来る場所であると実感し、加入直後にも関わらず見事に溶け込む菱和の才能にただただ感心するばかりだった
元より、菱和はHazeへの加入を強く望んでいたが、再三行われたBURST脱退の話し合いは平行線を辿るばかりだった
そして“、あんなこと”が起こった
高野も駒井も、なんて下らないことをしたのだろうと悔い、菱和がHazeとしてベースを弾く姿を見て『加入出来て良かった』と心から思った
「‥‥‥あんときは、マジですまなかった」
「ほんと云うと、俺らずっと後悔してたんだ。まさか古賀があすこまでやるなんて思ってなくてさ。古賀を止めることも出来なくて‥‥ごめん」
唐突に、2人は“あの日のこと”を詫び、頭を下げた
───古賀に比べりゃ、こいつらはまだまだまともだな
謝罪する2人の姿を見て、菱和は後先考えず伸さずに済んで良かったと思う
「‥‥‥‥別に。‥‥っつうか、俺もお前ら殴ってるし」
「‥はは。そういやそうだっけ。めっちゃ痛かったわ」
「ほんと。あんな重いの食らったの初めてだったな」
菱和は2人を殴ったことを微塵も後悔しておらず、謝罪する気も更々無かった
例え古賀に脅され命令されてやったことであったとしても、菱和にとっては大切な友人を傷付けられるところだった
それは、何よりも赦しがたいことだ
犯した罪は消えない
それを本人たちが悔いているのならばそれで良いと思い、それ以上喋ろうとはしなかった
古賀と決別した2人はHazeに加入した菱和の噂を聞き、ライヴを観に行った
そこには、BURSTに居た頃とはまるで別人のような菱和の姿があった
見違えるほどステージ映えし、自分達とでは決して見せることの無かった菱和のベースのプレイに目を奪われ、驚愕した
菱和の真の姿を目の当たりにした2人は、自分達の技術が菱和の腕には到底及ばないことを痛感した
そんなことは端からわかっていたのだが、それでも、共に活動してくれていたことには感謝していた
菱和が“活きる”場所
それは自分達のところではなかった
凄腕のベーシストとバンドをやっていたという事実と誇り
惜しい人材を失った後悔
多大な羨ましさと、期待
“あの”一件以来、高野と駒井の頭の中は、そんなことばかりで溢れ返っていた
「陰ながら、応援してっから」
「またライヴ観に行くよ。楽しみにしてる」
2人は、菱和にそう云い残して去っていった
リサとカナは、もう高野と駒井につけ回されることはない
それだけでも今日は良かったとしよう
‥‥‥‥でも、まだ一つ、問題が残ってる
それをどうするかは、また考えることにする
取り敢えず、今は
───‥‥‥‥‥‥‥眠みぃ
菱和は車を取りに、駐車場へと向かった
60 Neapolitan
その日、ユイと拓真は念の為カナを自宅近くまで送り、リサと一緒に帰宅した
リサが自宅に入るのを確認すると2人も足早に帰宅し、支度を済ませてバスでスタジオへ向かった
バスに揺られながら、2人はリサの件を話し合った
「しかし、もう2ヶ月くらい前の話なのに向こうもよくリサのこと覚えてたな」
「リサの顔、結構目立つもんね」
「まぁな‥‥‥‥取り敢えず、折り見てあっちゃんに相談してみよ」
「うん、そうだね。こんなときこそリーダーに相談!」
「こんなときしか相談することもないんだけどな‥‥‥‥。あ、あとお前、絶っっっ対顔に出すなよ。ひっしーに知られたら元も子もない」
───アズ
「‥‥わかってる。俺だってアズに心配かけたくない」
自分達とバンドをやる為に形振り構わず行動を取った菱和のことを考えるユイの眼差しは、いつになく真剣なものだった
急いでいたものの、いつもの集合時間より若干遅れており、2人は駆け足でsilvitに向かう
息急ききって、ユイは勢いよくドアを開けた
「こんにちはー!」
「やぁ、いらっしゃい。アズサちゃんとアタルくんなら、仲良く煙草喫ってるよー」
我妻は2人に気付き、にこりと笑って裏口を指差した
いそいそと裏口に回ると、菱和とアタルが怠そうに煙草を喫っていた
「やっと来やがったか!遅せぇんだよお前ら!」
「ごめーん、つい話が盛り上がっちゃって‥‥」
「どうせまた下らねぇ話でもしてたんだろ?ったく‥‥これで5本めだぞ!?」
へらへらと笑うユイの顔を見て、アタルは苛ついて煙草を吹かす
拓真は、アタルと並んで煙草を喫う菱和に尋ねた
「ひっしーはそれ何本目?」
「‥‥2本目」
「あっちゃんが喫い過ぎなんだよ。まだ少し時間あるのに‥‥ほんとせっかちなんだから」
「うっせぇ。とっとと始めんぞ」
「いって。‥‥はいはい」
アタルは拓真の頭を軽く叩いてから、灰皿に煙草を押し付けてスタジオに向かった
拓真も頭を掻きながらそのあとに続く
菱和は未だ、怠そうに煙草を吹かしている
「あっちゃん、早く弾きたくて待ちきれないみたい」
「‥‥そりゃお前もだろ」
「あ、バレた?」
「いつものことっしょ」
「‥まぁね!行こっ、アズ!」
にこりと笑い掛けるユイ
菱和は最後の一口を喫うと、穏やかに頷いてユイと共にスタジオに行った
ライヴのあとにリサとカナが高野と駒井に後をつけられていたことを知ったのは、ほんの一時間前のこと
余計な心配を掛けまいと、わざわざ自分のいないところでそんな話をしていたユイたち
拓真に釘を刺された通り、ユイは菱和に“隠し事”をしていることを悟られまいと、普段と変わらず接するよう努めた
菱和が“その話”を聞いていたことを、ユイたちは知らない
悟られないよう努めるのは、菱和も同じだった
ただ、菱和はユイよりも遥かに感情が表に出難い
菱和は、『こういうとき、無表情というのは至極便利なものだ』と思った
***
練習が終わると、4人はいつものように菱和の自宅へと向かう
「あっちゃん、今日もアズんち行けるね!」
「今日は反省会だからな。しこたま食ってやらぁ。今日は何なん?」
「ナポリタン。俺、前もってリクエストしといたんだー」
「ほー。期待してんぜ、シェフ」
「‥‥その期待に添えれば良いけど」
「またまた。謙遜しなくても、十分美味ぇから」
アタルは軽く顎を掻く菱和の肩をぽん、と叩く
それを見て、ユイと拓真はくすくす笑った
菱和は拓真がリクエストしたナポリタンを恙無く作り終えた
細く切られた玉葱とピーマン、ウインナーと共にケチャップで和えられたパスタが盛り付けられた皿を目の前にし、皆思い思いに粉チーズを振り掛ける
「‥‥美味ぁ!初めてなのに、なんか懐かしい味する!」
「『古き良き洋食屋の味』って感じだな」
「うん、美味いなーやっぱり。リクエストして正解だった」
「‥‥ひっしー、タバスコねぇか?粉チーズもも少し欲しいな」
「ん、あるよ。持ってくる」
「あっちゃん、タバスコなんてかけたら味変わっちゃうじゃん!このままでも十分美味いのに!」
「うるせぇ。ケチャップ口に付いてんだよこのチビ助」
「え、どこどこ?」
「がっつき過ぎ。ひっしー、お代わりある?」
「ん。目一杯食ってって」
「拓真だってがっついてんじゃん!俺もお代わりいるー!」
「おいガキ共、俺の分も残しとけよ!」
「‥‥ほんとに沢山作ったから、ゆっくり食えば」
清々しいほどの、3人の食欲
自分の料理の腕前など、高が知れてると思っていた
ユイたちが本当に自分の腕に満足してくれているのか、ただ単に空腹だからなのかはわからない
だが、どちらにしても、喜ばれていることに変わりはない
この騒がしい夕餉の雰囲気が、心地好かった
食事を終えた4人は、先日のライヴの反省会をした
曲の出来にそれなりに満足だったこともあり、話題はユイがピックを客席に放ったことへとシフトしていった
「‥‥あれはねぇよなマジで。お前、もっと落ち着いて弾けよ」
「でも、なんかみんな喜んでくれたじゃん!」
「完璧“棚ぼた”だったけどね。ピック一つであんなに盛り上がるなんて思ってなかったわ」
「でしょ!?なら、結果オーライじゃん!」
「女の人も沢山あっちゃんのピックに群がってたしねー。あっちゃんも満更でもなかったんじゃないのー?」
拓真が意地悪そうな顔をしてそう云うと、アタルは負けじと意地悪そうに云った
「‥‥お前、今度スティック投げろよ」
「‥やだよ!俺のなんて、しかもあんなボロボロのスティックなんて誰も欲しがらないよ」
全力で拒否する拓真の横で、ユイも意地の悪そうな顔をした
「新品買って忍ばせとけば良いじゃん!で、終わったらそれ投げれば‥‥」
「いーやーだ。誰も取ってくれなかったら切ないし、怪我したら大変っしょ。てか、新品投げるなんて勿体なさ過ぎる」
「まぁ、スティックはちょっと危ねぇな。っつぅか、それよりもまずひっしーのピックだべ」
「え?でもひっしーピック必要ないじゃん。指弾きなんだし」
「だから、それこそ投げる為だけに用意しとけば良いんじゃねってこと」
アタルはニヤニヤしながら菱和の顔を見てそう云った
途端、ユイが目をキラキラさせた
「え、それなら俺も欲しい!」
「‥‥何でだよ。アホかお前」
「だって、アズのピックなんて絶対レアじゃん!」
「そんなら普通に買ってもらえば良いだろ」
「それじゃ何の意味もないっしょ!使ったばっかのほやほやのやつをキャッチするのが良いんでしょ!」
「っつうかお前がベース用のピックなんて持ってても仕様がねぇだろ。大体、ひっしーがピック投げるとき何処に居る気だよ?」
「‥そりゃ客席でしょ?ピック争奪戦に混ざりたい!」
「ギター持ったままステージ降りて、ひっしーがピック投げるの待ってんの?」
「え?」
「‥‥まず、演奏が終わったらギターを抱えたまま急いでぎゅうぎゅうの客席に降りて、良いポジション取ろうと思って客掻き分けてもみくちゃになっているうちにシールド外れて、スピーカーから変な音聴こえて、そのうちギターごと上に担がれて胴上げ状態になってわっしょいわっしょい‥‥‥‥‥‥‥‥」
3人は、拓真の話を順番通りに思い浮かべてみる
「‥‥‥で、結局ピック受け取り損なうんでしょ?そこまでやってユイクオリティだよね」
「全然クオリティ高くねぇし!」
拓真とアタルは、腹を抱えてゲラゲラ笑う
ユイはムキになって身を乗り出した
「ちゃんと受け取るし!‥‥じゃあ、演奏終わったらすぐ手渡しで貰う!」
「‥‥それもなんか変じゃない?ってか、それなら結局最初から買って貰った方が早いじゃん」
「演奏終わって『はい、ピックどーぞ』ってか?何のこっちゃわけわかんねぇし!」
「お、面白過ぎる‥‥!っははははは!」
想像すればするほどよくわからない状況になっていく
拓真とアタルは涙目になって笑った
「───もう、何でも良いじゃん!俺もアズのピック欲しいよおぉ!!」
「‥‥‥まだ投げるって決まった訳じゃねぇし、もしそんときが来たらやるよ」
菱和はユイを宥めるようにして云った
そこへ、アタルがボソリと呟く
「‥‥手渡しで?」
菱和もこの状況を楽しんでいるようで、アタルの問いに至極真面目な顔をしてこくりと頷いた
拓真とアタルはまた弾けるように笑い出す
「もおぉ、アズまで面白がるなよ!!」
菱和も、意地悪そうに少し口角を上げる
3人に小ばかにされ、ユイは顔を赤くした
一頻り笑い話を終え、3人は菱和の自宅を後にした
快晴の夜空は澄み切っており、星が疎らに瞬く
吐いた息は、ほんの少し白くなる
「寒くなってきたなー」
「ほんとだね」
「風邪引くなよお前ら。特にお前。‥‥あ、心配ねぇか。バカだから」
「バカじゃないし!勉強できないだけ!それにねぇ、あれは『バカは風邪引いてるかどうかもわからない』っていう意味なんだよ!」
「どっちにしてもあてはまんじゃんよ」
「‥違うし!あっちゃんのバカ!!」
「‥‥、俺はバカじゃねぇよな?」
「うーん、どっちもどっちだねぇ‥‥」
「あ!?てめっ!このチビと一緒にすんな!」
「こっちの台詞だし!あっちゃんと一緒にすんなよ!」
「うひょ、怖えぇー!」
3人はふざけながら、帰宅の途に着く
***
騒がしかった室内が、一気に静まり返る
菱和は余韻に浸りながら煙草を喫った
立ち上る煙をぼんやりと眺めながら、放課後教室でユイたちが話していたことを思い出した
───‥‥‥‥あいつら今何やってんだろ
ふと思い立ち、菱和は軽く身支度を整え、自宅から出て行った
59 密談①
週末のライヴが終わり、月曜の朝
朝は嫌いじゃない
学校に行けば、友達にも会えるし
でも今朝は、起きた瞬間から気が重い
───何ていうか、最低な朝だ
リサはライヴの帰りに後をつけられたことをユイたちに話すつもりでいたが、胸がざわざわして落ち着かない
学校へと向かう足取りも、自然と重くなる
教室に入ると、ユイと拓真は既に登校していた
違うクラスの上田もユイたちに混ざり、ゲラゲラ笑いながらライヴの話をしていた
リサは真っ直ぐユイたちの元へと向かった
「おはよ」
「あ、リサ。はよー」
「‥‥‥‥ちょっと話あるんだけど」
「おう、何?」
リサは上田を一瞥した
出来ることなら、ユイと拓真にだけ打ち明けたい話───
「‥‥俺、教室戻るわ。そろそろ予鈴鳴るし。また昼休みな」
上田はリサの表情を見て『恐らく自分には聞かれたくない話題なんだろう』と察した
にこりと笑み、ふらふらと教室から出ていった
リサは申し訳ない気持ちになったが、空気を読んでくれた上田に感謝した
上田を見送ると、拓真は怪訝な顔をした
「結構大事な話?」
「うん、‥‥あのね‥‥‥‥──────」
話し出そうとしたとき、菱和が教室に入ってきた
リサはぐっと口を噤み、言葉を飲み込んだ
「‥‥、あとでにする」
「え、どしたの?」
「‥またあとで」
「‥‥‥‥?ん、うん。‥‥わかった」
さっと自分の席へ向かうリサの後ろ姿を見て、ユイも拓真も首を傾げる
ふと、菱和が着席したのが目に入る
拓真は、『菱和絡みの話なのかもしれない』と、何となく察しがついた
昼休み
いつものように屋上に集うユイたち
昼食後、男共がライヴのことやら小テストのことやら下らない話に花を咲かせる傍ら、リサは柵に寄りかかりぼーっとしている
カナはリサの横に並び、話し掛けた
「‥‥‥‥もう話したの?昨日のこと」
「‥‥まだ。放課後話すよ」
「そっか‥‥‥ねぇ、私も一緒に居て良い?」
「うん」
リサは輪になって話し込んでいるユイたちをちらりと見た
その輪の中には、勿論菱和も居る
その見た目と雰囲気で随分損をしてきたんだろうなと、リサは思う
勿論本人の所為ではないのだが、初めから拒絶されるくらいならば寧ろ自分から他人と接触するのを避けようとしてしまう
事実、絵に描いたような一匹狼の菱和はユイたちと関わるまではそうして過ごしてきた
リサにも身に覚えがあった
日本人以外の血が混ざっているリサの顔付きはどちらかというとキツめだ
その大きな瞳で見つめると、怒りの感情を抱いていないにも関わらず『こいつは今とても機嫌が悪い』『怒らせてはならない相手』だと思われ、他人の態度に多少は傷付いた経験がある
自分にも他人が近寄り難い雰囲気があるのを自覚している為、リサはわざと他人を遠ざける行動を取ってしまう菱和の気持ちがよく理解出来た
だが、ユイと仲良くなってからの菱和は明らかに表情が変わった
冷たい無表情の中にも柔らかく穏やかな心が時折現れ、ふとした拍子に滲み出る
菱和と自分は、よく似ている──────
初めは、大嫌いだった
大事な幼馴染みが間違った方向へと誘われて行くような気がしていた
多少は嫉妬の気持ちもあっただろう
でも、今は違う
漸く菱和の“人間性”とやらがわかり、自分はそれを受け入れられている
だから、出来ることならこの日常がいつまでも続いて欲しいと願っていた
それなのに
──────ぶち壊してくれんな、バカ野郎
リサは心底、“あの”男たちを地獄に突き落としてやりたいと思った
***
リサはまだ話が出来ていないまま放課後になってしまったことを少し悔いた
今週は視聴覚室の掃除当番だったのだ
予め、ユイと拓真に待っていて貰えるようカナに頼んでおいている
毎日使うわけではない視聴覚室は、綺麗な方だった
何故綺麗なのに掃除をしなければならないのか
少しくらいサボっても良いだろうに
そう思い苛立ちながらさっさと掃除を済ませ、待たせているユイたちに申し訳なさを抱きつつも急いで教室に戻った
教室で、ユイは自分の机に、カナはユイの椅子に座り、拓真は2人の傍らに突っ立って3人で話をしている
菱和の姿がなく、リサはほっと胸を撫で下ろした
「お、来た来た」
「ごめん、なかなかタイミングなくて。あんたら今日バンド練習でしょ?なるべく早く終わらせるから‥‥」
「タイミング?」
ユイは首を傾げた
「‥‥‥‥ひっしーには聞かれたくない話なんでしょ?」
「え?」
拓真の一言に、ユイは驚いた
リサも、目を丸くする
「今日はもう献立リクエストしといたから。『買い物すんのに早めに帰る』って」
「何リクエストしたの?」
「ナポリタン。簡単に作れるもんにしといた。好きっしょ?」
「わぉ!好き好き!」
ユイの顔が綻ぶ
「これで、安心して話せるっしょ」
拓真はにっこりと笑った
他人の感情に敏感なタイプの拓真は、リサの心情を汲み取ると同時に菱和にも不快な思いをさせないよう機転を利かせてくれていた
拓真に多大な感謝をし、リサは心置きなく話し出した
「‥あのね、昨日の帰り、変な奴らに後つけられたの」
「──────え!!!」
ユイと拓真の顔付きが瞬時に変わる
「何ともなかったの!?」
「うん、平気。大声で叫んで走って逃げたから。‥‥‥‥でもね」
カナは軽く笑って答えたが、続きの言葉を云いづらそうにする
同じく云いづらそうにしていたリサは、ここからが本題だと思い、意を決して話し出す
「‥‥‥‥この前、私のこと拐った奴等だったの」
ユイと拓真の顔が曇った
リサを拐った人物
大切な友人を傷付けた人間
ユイも拓真も、その顔をはっきりと覚えている
「それって‥‥」
「菱和が前にいたバンドの奴。主犯格の奴は居なかったけど、残りの2人だった。ちらっと見ただけだけど、間違いないと思う」
目を見開いたユイは、そのまま動かなくなる
拓真は大きな溜め息を吐いた
「‥マジかよ‥‥、しつこい奴等だなぁ‥‥‥‥ほんとに何もされてない?」
「うん、大丈夫だよ。‥‥でも、菱和くんには黙っておいた方が良いんじゃないかな‥‥って」
カナは不安そうに、リサの顔をちらりと見た
リサが拐われた一件は、カナも知っている
しかし、カナがその事を知ったのはあれから数日後のことだった
例えその場に居たとしても何も出来なかったかもしれないが、下手をすればリサが一生残る傷を負うことになったであろうことを考えると、一足先に帰宅したことを後悔し、殊更リサのことを心配していた
そして昨晩、リサを拐った人物と先日後をつけていた人物が恐らく同一人物であると打ち明けられた
リサもカナも、菱和の所為ではないことはとっくに承知の上
しかし───
「‥‥‥‥あいつのことだから、また喧嘩でもしそうでおっかなくて。もし今怪我したらライヴも出来なくなるでしょ。そうでなくても“あのとき”結構酷い怪我だったし。‥‥あんたたちにもあいつにも、もうあんな思いして欲しくない」
拓真は、何故リサがこの話を菱和の耳に入れたがらなかったのか十分納得した
「うーん、そうなー‥‥ひっしーなら即ボコりに行きそうな予感」
「でしょ?もう何の関係ないのに、余計な心配かけたくないし‥‥私たちほんとに何ともないから、今話したことはあいつには黙ってて」
「‥‥‥‥わかった」
リサの話を黙って聞いていたユイは、唇を噛み締めて頷いた
***
───何だ、あいつらまだ居たのか
唐突に今日の夕食をリクエストしてきた拓真
ざっと冷蔵庫の中身を思い出し、足りない食材の買い出しに行く為早々に帰宅しようとした菱和は、提出物の出し忘れに気付き、教室に戻って来た
教室に入ろうとしたところ、リサの重苦しい声が聞こえた
「‥‥‥‥この前、私のこと拐った奴等だったの」
菱和は気配を殺し、教室の外で4人の話を黙って聞いていた
58 暗転
一足先にライヴ会場を後にしたリサとカナ
残りのバンドを観る為にライヴ終了まで会場にいるユイたち、そして打ち上げに混ざるつもりで共に残っているケイと別れ、街灯の少ない夜道を歩く
「あーあ、私もピック欲しかったなぁ‥‥」
「そんなの、云えば幾らでもくれると思うけど」
「もう、違うんだってば!投げてくれたやつをキャッチしたいの!」
「あ、そう‥‥‥」
カナは、大ファンと云っても過言でないほどHazeの曲や雰囲気を気に入っている
確かに、一言頼めばピックの一つくらいユイもアタルも喜んでカナに渡すだろう
しかし、客席に投げられたものを手に取るチャンスは滅多になく、特別なことだ
憧れている、大好きなバンド
そのメンバーが使っている私物であれば、どんなものでも欲しいと思えるもの
その辺の感覚がいまいち理解できないリサは、いつまでもユイやアタルのピックを手にした観客のことを羨んでいるカナに呆れた顔をした
2人の後ろから、ひたひたと足音が聞こえる
リサはいち早くそれに気付き、カナの話を聞きつつも後方に注意を向けた
最寄りの駅までの道をわざと遠回りしてみると、やはり足音は自分達の後をついてくるようだった
数ブロック歩いたところで、リサは『自分達はつけられている』と確信した
カナもそれに気付いたようで、不安そうにリサに腕を絡ませる
「‥‥‥‥‥ねぇ、うちら後つけられてない?」
「私もそう思ってた。ちょっと急ご」
ライヴ会場へ引き返そうにも、距離的には駅へ向かった方が近い
歩くペースを少し早めるも、後ろの足音もそれについてくる
女子2人で歩くにはとても心細く感じてしまう、人気のない夜道
カナはどこの誰なのかもわからない何者かに後をつけられる不安から、苛立ちを募らせる
「もう何なの、どこまでついてくる気なの!っていうか誰よ!?」
「落ち着いて。大丈夫、もう少ししたら大きい通りに出るから‥‥」
リサが宥めようとしたとき、カナは立ち止まって絶叫した
「──────っきゃあぁぁぁーーー!!!!!」
「何っ‥‥!?」
「こういうときは、大声で叫ぶの!きゃあぁぁーーー!!!助けてえぇーっっ!!!」
無我夢中で叫ぶカナの声に、リサはただ驚くばかり
咄嗟にリサの腕を掴み、カナは走り出した
「行くよっ、リサっ!!!」
「あっ、ちょっ‥‥!」
リサも、引き摺られるように走り出す
──────!!‥‥‥‥‥‥
ちらりと振り返ると、見覚えのある男の姿が目に入った
カナの声に驚いたのか、狼狽えたまま追い掛けて来ることはなかった
安堵するも、訳がわからなくなる
何で、今更──────
思い出したくもない出来事が、リサの頭の中を埋め尽くした
57 “GOLD RUSH”
マンスリーライヴ当日
ざわめくライヴハウス内
出番まで時間を潰すことにしたHazeのメンバーに、ライヴを観に来たリサとカナも輪に入り、人混みに紛れて過ごす
「ユーイユイ、こんばんはっ」
突然、誰かに後ろから抱き付かれた
驚いた拍子に振り返ると、唇にピアスを付け、頭は白に近い金髪の、ズタボロのガーゼシャツを纏った男がニコニコしていた
「ケイさん!びっくりしたぁ!」
「んっふー。友達のバンドも出るから、観に来たんだー」
朗な笑顔に、一同もつられて笑みそうになる
ケイの装飾品が増えていることに気付いたアタルは、こくんと首を傾げる
「お前、ピアス増えたの?」
「うん、初口ピ。似合う?」
ケイは唇のピアスを指差し、にこっと笑った
「今回は、残念だったな」
「ほんとねー。スケジュール合えば、俺らも出たかったんだけどなー」
「メンバーが社会人だと、都合つけるの難しいよね」
「うん。俺も来年専学卒業だし、いちばん暇なのはいっちーになるわ。あ、でもいっちーも来年は受験生か?」
ケイの話を聞いて、ユイは素朴な疑問を抱いた
「上田、大学行くのかな?」
「知らん。それよりもまず、あいつが行ける大学なんてあんのかね」
拓真は冷たく云い放った
カナが拓真の話に同調する
「それ云えてるー!樹、アホだもんね」
「お前ら‥‥あいつのアホさは俺もよく知ってるけど、この場に居ないからって寄って集って悪口云うなよ」
「何云ってんの、あっちゃんだって今上田の悪口云ったじゃん!」
ユイがアタルに反論した
ケイは更に上田のアホさ加減を嘲笑う
「いっちーがアホなのは周知の事実だから、仕様がないね」
拓真やカナはケイの言葉に同意し、くすくす笑った
***
のんびりと談笑していたHazeメンバーは、ライヴの開始とともに控え室に向かった
Hazeの出番は6バンド中4番目だった
リサとカナはケイの友人が所属するバンドを一緒に観た
「あのヴォーカルの人、上手いですね。たまに『何でヴォーカルやってんの』ってくらい下手な人いるけど、あの人はほんとに上手」
「‥学校で会ったら云っとくよ。あいつ絶対喜ぶわ」
カナの言葉に、ケイはニコニコと笑う
「ケイさんって、V系とか好きなんですか?ケイさんみたいなファッションの人って、V系好きな人多いみたいだし‥‥」
「ううん。俺はパンクとかメタルが好き。でもいちばん好きなのはMarilyn Mansonかな。知ってる?」
カナはケイが挙げた人物を知らず、首を捻り、うーん、と唸る
「‥‥なんか、『白い人』‥ですよね」
リサは少しは知っている様子で、その人物の印象を云った
リサが抱くマンソンの印象はかなり漠然としていて、ケイは思わず笑った
「『白い人』‥‥‥‥ふふっ、そうそう。かなりイカれてて、見てたらスカッとすんだよね」
「ユイくんたちはその人の曲聴く?CD持ってるかな?」
「聴いたことくらいはあると思うけど、多分持ってないんじゃないかな。ユイの好みとは少し違うから」
「なになに、Manson聴きたい?CDなら腐るほど持ってるから、良かったら貸すよ」
「ほんとですかー!?じゃあ、お願いします!」
「うん、いっちーに渡しとくね」
満面の笑みを浮かべるケイ
激しく裂けているガーゼシャツとサルエルパンツ、そしてラバーソール
一見女の子に見えなくもない童顔に加えて華奢な身体つきのケイがダイナミックなドラムを叩くことなど、見た目からはとても想像がつかないとリサは思った
***
あれこれ話しながら他のバンドを観ているうちに、Hazeの出番が来た
リサは今日も、握手をすることを忘れてはいなかった
いつも、いつも
『楽しめますように』
『無事終わりますように』
互いに想いを込めて、交わされる手
3人が握手する姿を見ていたカナは、いつか感じた羨ましさを思い出していた
アタルが弾くイントロがゆっくりと流れ、それが途切れるとキラキラとしたカッティングが響く
弾いているのは、ユイだ
「‥‥『GOLD RUSH』だ」
リサがそう呟いた
「ん?今の曲?」
「うん。あっちゃんが新しいギター欲しくて、でも高くて買えなくて、『金欲しい』って思いながら作ったんだって」
「ふふ、なんかあっちゃんらしいね」
「‥‥ほんとですよね」
リサが話すGOLD RUSHのエピソードを聞いて、ケイは微笑ましく思った
ユイの自宅に遊びに行けば、いつもギターの音が聴こえてくる
リサは何度も、ユイが練習するGOLD RUSHのフレーズを耳にしていた
新しい玩具を与えられてはしゃぐ子供のように、ユイはギターを掻き鳴らす
自宅でもライヴハウスでも、それは同じことだった
───今日も、大丈夫みたいね
リサは、笑顔でギターを弾くユイの姿を見て、そう思った
***
色とりどりのライトが、ステージ上の4人を次々と照らし、曲に彩りを添える
厭らしいがなり声と艶やかなギター
時折跳ねる賑やかなもう一つのギター
重く低く唸るベース
鳩尾に響くドラム
音を重ねるにつれて、新たな反応が生まれる
全てがぴたりと嵌まると、オーディエンスは息を飲み、一層沸き立つ
貪欲な観客たちは紡ぎ出される音を餓鬼のように貪り、息吐く暇さえ与えない
頭も、指先も、次第に感覚を失くしてゆく
演奏している方も、正気を保つのが精一杯だ
“GOLD RUSH”の他に3曲ほど演奏したHaze
全ての曲において、4人は互いに煽り煽られ、快楽の頂点まで上り詰める
「──────あっ!!!」
最後の曲の終盤、ピックスクラッチをした拍子に手が滑ったユイは、そのままピックを客席に放ってしまった
まだ間延びした機械音やシンバルの音が響く中、観客は我先にとピックに群がり、手にしたものは歓喜の声を上げた
ミュージシャンがライヴで客席にピックを投げることがあるが、まだまだ自分はそんなことが出来るレベルではないと思っていたユイは、事故とはいえ予想外の客席の反応に驚いた
「‥‥‥‥ほんと、アホなんだからよ」
最後の最後に失態を犯したユイに、拓真とアタルは呆れ顔
菱和も、無表情にユイを見つめていた
ユイは苦笑いして軽く頭を掻いた
「アタル様ーーー!!!」
「アタル様も投げてー!!」
自分の名前を叫ばれ、アタルはギクリとした
アタルのファンらしき女性客から、期待の眼差しが向けられている
アタルは困ったように客席を一瞥すると、ピックを放り投げた
女性客は押し合い圧し合いし、一斉に群がる
「女って怖えぇー‥‥」
拓真は苦笑いをして立ち上がり、袖に下がろうとした
「おーい、スティックも投げろー!!!」
遠くから、男性客の声が聞こえる
拓真ははっとして客席を見た
「ふふ、投げろって云われてるよ?」
「‥‥‥こんなボロ、わざわざ投げなくても良いだろ」
拓真は軽く一礼してそそくさと袖に引っ込み、ユイも客席に頭を下げてそれに続いた
「アンコール!アンコール!」
「行かないでー、アタル様ー!!」
「おぉーい、ベースは投げないのかー!?」
まだまだ興奮冷めやらないオーディエンス
黄色い声が行き交う客席に少し一瞥くれると、アタルは菱和の元へと歩み寄る
肩を抱くと、まだ何か期待している観客に向かって舌を出した
「もう投げれるもんはありません!俺らがダイブするしかなくなっちまうからー」
残念ながら、菱和はピックを使って演奏をしない
他に投げられるものといえば、自分達の楽器か自分達自身しかない
そのどちらも、出来る筈がない
オーディエンスはそれをわかっていながらも、大歓迎と云わんばかりに腕を上げる
「それでも良いぞー!」
「アタル様、来てー!!」
「冗談!‥また観に来てねー!有難うございましたー!」
アタルは菱和の肩を抱いたまま、客席に一礼した
菱和もそれに倣い、深々と頭を下げる
客席からは笑い声と拍手がいつまでも鳴り止まない
後ろ髪引かれる思いでそれを堪能し、2人は連れだって袖へ下がった
「お前もピック用意した方が良いかもな」
「‥‥まだそんなレベルじゃないと思うんだけど‥‥‥‥」
「なぁに云ってんだか‥‥ま、客席に投げるだけなら要らねぇか?指弾きだしな、お前」
控え室に向かって歩きながら、アタルはニヤニヤ笑った
56 Hug
スタジオでの練習を重ね、あっという間にマンスリーライヴを翌日に控えた
リハーサルも無事に終え、あとは当日に向けての心構えをするのみとなった
アタルの提案でスタジオ練習は早めに切り上げ、遅くならないうちに解散することになった
そして今夜は菱和の自宅へ行くのを止め、全員真っ直ぐ帰宅することにした
「俺、買い物あるから先帰ってて」
菱和は駅方面ではなく、週末の夜に浮き足立つ繁華街へと向かおうとしていた
アタルは軽く手を上げてにこっと笑う
「おう、わかった。明日、宜しくな」
「うん。気ぃ付けて」
「お前もな」
菱和が振り返ったのを見て、ユイたちは揃って駅方面へと歩き出そうとした
と、突然、ユイが立ち止まって叫び出した
「──────あ!俺も買い物あったんだ!すっかり忘れてた!」
ユイの声は、まだあまり距離の離れていなかった菱和の耳にも届いていた
ちらりと振り返り、ユイを見る
「アズー、俺も一緒に行って良いー!?」
ユイが菱和に向かって手を振ると、菱和は踵を返して来た
拓真とアタルは呆れ返っていた
「ギターに熱中すると他のことはほぼ疎かになるもんなー」
「ほんとアホ。弾きすぎて食事もとらなくなる変態だもんな」
「うるさいな!変態じゃないってば!早く帰んなよ!」
「ほいほい。補導されんなよ」
「ひっしーと一緒なら大丈夫じゃない?じゃ、また明日ー」
拓真とアタルは駅方面へと歩き出した
ユイと菱和はそれを見送り、繁華街へと向かった
「アズは何買うの?」
「日用品。お前は?」
「電池。ストックもう無くてさ。昨日テレビ付けたらリモコンの電池なくなってやんの。あれ、壊れたかな?と思って焦っちゃった!」
「お前らしいエピソード‥‥‥じゃあ、コンビニより安く買える店まで行くか」
目的地も決まり、2人は並んで歩いた
***
買い物が済んだ2人は駅方面へと向かった
「‥‥ねぇ、まだ時間ある?」
ユイは歩きながら、云いずらそうに菱和に尋ねる
ちらりと見たユイの顔は初ライヴの前日と同様、名残惜しそうな表情をしていた
「‥‥‥‥少し話すか?」
「‥‥大丈夫?」
「ん。‥‥‥‥まだ帰りたくねぇんだろ?」
「うん‥‥‥でも、折角あっちゃんが早く帰れるようにしたのになんか悪いなっ、てのもあって‥‥」
「‥‥云ったろ、『お前の気が済むまで付き合う』って。何も遠慮すんなよ」
そう云って、菱和は煙草に火をつける
「‥アリガト!」
ユイはにっこり笑った
前回と同様、駅前に点在する広場で談笑することにした2人
ベンチは殆ど埋まっていた
座り込んで話すほどの時間をとらないつもりで、2人はベンチが設置されていない、あまり人気の無いところまで移動した
「はー、“GOLD RUSH”マジ楽しみ!」
「‥‥前から思ってたけど、あっちゃんてセンス良いよな。この前の新曲も良かったし、あっちゃんの曲は独創的で結構好き」
「センスの塊だよね、あの人は!そこにそれ入れちゃう!?って時もあるけどちゃんとハマってるし、ほんと独特だよねー。歌も上手いしさ。俺、頭上がんない。ただのギターバカじゃないんだよねー」
「‥‥お前もただのギターバカじゃねぇじゃん」
「‥‥‥‥そう?」
「佐伯もあっちゃんも云ってるよ、お前は努力家だって。お前のギター聴いてたら、ほんとそうなんだろうなって思う。‥‥でも努力だけじゃどうにもならないこともあんじゃん。それはもう才能で補うしかないわけでさ、一点集中出来るとことか努力出来る才能を持ってるってことっしょ、お前は」
ユイのギターの技術に対する拓真やアタルからの評価、そして自らの印象を実直に話す菱和
ユイ自身は自分が楽しいと思えることをやり、その為に努力しているだけなのだが、メンバーからその努力を認められているとわかり、顔が綻んだ
「‥‥‥‥そんな風に思われてたんだ、俺。‥なんか嬉しい!」
「‥‥たまに跳ねてっけどな」
「あー‥‥‥よく云われる。気を付けてるつもりなんだけどさー。テンション上がり過ぎたら何も考えらんなくなっちゃうんだよね」
「『今キてんのかな』とか『すげぇ好きなフレーズなんだろな』とかすぐわかるから、聴いてて楽しいけどな」
「楽しんでくれてるんだ?」
「うん。楽しいよ」
「‥そっか!」
少し冷えるようになってきた夜
空も空気も澄んでいるように感じられる
ひんやりとした風が木々をざわめかせ、秋の訪れを伝え来る
風に吹かれ、ざわざわと鳴る樹の葉
それに掻き消されてしまいそうになるくらいの低い声で、菱和はぽつりと本音を呟いた
「───‥‥‥‥ずっとお前とバンド出来たら良いな」
菱和の声は、ユイの耳に届いていた
たまに呟く菱和の本音は、ユイにとっては嬉しい言葉ばかりだった
今の言葉も、御多分に漏れない
「俺もそう思ってるよ。今、すげぇ良い状態だし。やっぱり、あの時声掛けてて良かった!仲良くなれた上に一緒にバンドも出来るなんて、俺ってツイてる!アズが居てくれて、ほんとに良かった!」
笑い掛けるユイの笑顔を見ても、菱和は心がざわつくことが無くなった
寧ろ、安らぐような気がしていた
その微妙な変化が現れたのは、ユイのことを“好き”だと自覚した頃からだった
菱和は俯き、薄く笑った
「‥‥‥‥お前には、マジで感謝しなきゃな」
「え?何で?」
感謝される覚えが全く無く、ユイは目を丸くする
菱和は空を見上げ、話し出した
「──────学校に行かなくなったのは、中学入ってからだった」
菱和の感謝と学校の話がいまいち噛み合わず、ユイは少し首を傾げた
「学校なんて、全然楽しくなかった。色々あってグレて、毎日喧嘩ばっかしてて、終いにゃ大怪我して。余計、学校に行こうなんて思わなかった」
怪我の話をしたところで、いつか見た菱和の身体の傷痕がユイの頭を過った
たった一度見ただけだが、鮮明に脳裏に焼き付いている菱和の胸の傷痕
ユイは背筋がゾクリとした
菱和は続けて話す
「親があんまり云うもんだから編入してみたは良いけど、去年一年はやっぱりつまんねぇ場所としか思えなかった。俺がこんな成りだから仕様がねぇのかもしんねぇけど、クラスの奴等はみんなビビって目も合わせようとしねぇ。‥‥‥でもお前は、一緒にバンドやりてぇとか仲良くなりてぇとか云ってわざわざ俺に話し掛けてきた。お前のお陰で、俺は全然退屈じゃなくなった。ダチも増えた。お前が話し掛けてきたのが、全部のきっかけだった」
そう云い、穏やかな表情でユイの顔を見た
「だからお前は、俺の“恩人”」
珍しく過去の話をする菱和
菱和の話を黙って聞いていたユイは『恩人』と云われ、面食らった
「‥‥大袈裟だよ、恩人なんて!」
「大袈裟じゃねぇよ。少なくとも俺は、そう思ってる」
菱和は真っ直ぐユイを見つめている
ユイはきょとんとしていたが、軽くはにかんだ
「恩人、かぁ。なんか照れるなぁ、へへ」
見ている方までつられて笑顔になってしまいそうになる、心が綻ぶようなユイの笑顔
今まで沢山の表情を見てきたが、菱和にとってユイの笑顔はいつも“可愛い”と感じられた
菱和はユイに近付き、徐に手を伸ばした
ユイの頭を、自分の肩に引き寄せる
大きな掌の感触がユイの後頭部に伝わると、菱和の肩にとん、と額が当たり、香水の香りが鼻を擽った
───え‥な、何これ
突然のことに驚き、ユイは身動きが取れなかった
急激に心拍数が上がり、菱和にこの行動の意図を尋ねるのが精一杯だった
「‥‥‥‥ど、したの?」
「‥ん?‥‥感謝の気持ち」
顔が見えない分、本当にそうなのかどうかがわからない
ユイの緊張がどんどん高まっていく
「‥そ、そう‥‥なの?」
「ん。‥‥‥‥有難う、ユイ」
菱和は顔を寄せ、ゆっくりとユイの頭を撫でた
「‥‥‥う、うん‥こっちこそ、有難う。仲良くしてくれて」
ユイの頭を優しく撫でる菱和
何だかよくわからない状況だと思いつつ、ユイは軽く身を預ける
ユイから礼を云われ、菱和はくす、と笑った
ユイの頭をぽんぽんと軽く叩き、身を離した
「‥‥明日も、宜しくな」
そして、柔らかく笑む
何度か見てきたその表情は、決まっていつも不意打ちだ
緊張が上乗せされていくユイ
だが、菱和の貴重な表情を見られたことにみるみる嬉しくなり、すぐに笑顔になる
「‥うん!楽しもうね!」
***
帰宅の途についたユイ
いつもより、心臓が早く動いていることに気付く
思わず立ち止まり、胸に手を当ててみた
──────‥‥‥‥あれ‥?
明日のライヴは楽しみだ
楽しみであることに変わりはないのだが
ライヴを待ち侘びるワクワクやドキドキとはまた違った感覚
菱和に抱き寄せられたこと
頭を撫でられたこと
『恩人だ』と礼を云われたこと
まさか早鐘の原因がその所為であるとは、露程にも思わなかった
55 揚げ出し豆腐
Hazeは次のマンスリーライヴに向けて練習を始めることになった
ユイは学校の休憩時間、着席したまま前の授業の教科書やノートを片付けもせず、拓真とアタルのバイトのシフトを手帳のカレンダーにメモしながらにらめっこしている
「‥‥うーんと‥‥‥‥」
「何書いてんの」
考え事をしながら唸り声をあげるユイの真後ろから、菱和が声を掛けた
ユイが真上に顔を上げると、自分を覗き込んでいる菱和の顔が見えた
長身な菱和は、着席して尚背の低いユイを見下ろす
「あ、アズ。あんねぇ、練習の日程考えてたんだ。あとでまとめてアズにも報告するから!」
「ふぅーん‥‥マメだな」
「あ、そうだ。アズの日程も聞いとかなきゃと思ってたんだ。駄目な日ある?」
「俺はないよ、いつでも大丈夫」
「そっか。じゃあ、取り敢えずこんなもんかなぁ‥‥‥‥よし、出来たっ!今月はこんな感じ!」
ユイは得意気に出来上がったスケジュールを菱和に見せた
「‥‥‥‥、漢字間違ってる」
「え!どこ!?どれ!?」
「19日。機材調整の“機”」
ドヤ顔だったユイは慌てふためき、間違った漢字をペンでくじゃぐしゃと消した
***
スタジオに集まったHazeのメンバーは各々定位置につき、談笑しながら練習を進める
「何演るか決めたの?」
「そろそろストックの曲やっても良いかなぁと思ってたんだよな」
「良いねー。練習し甲斐があって」
拓真は軽く腕を伸ばしてストレッチした
ユイはストックの曲を思い浮かべてみる
「今までライヴで演ってないのって‥‥“GOLD RUSH”とか?」
「そうなぁ。ひっしーも居るし、時間的に“DIG IN”も出来そうかと思ってたんだけど。どうよ?」
アタルが菱和に尋ねる
「うん。貰ったCDは一通り弾いたし、大丈夫」
「じゃあそれでいこ!」
特に意見がぶつかることもなく、加入して間もない菱和を然り気無く気遣うことも怠らず、すんなりと事が決まっていく
少なくとも、菱和はHazeに加入してからメンバー同士が良い争いや喧嘩をしているところを見たことがない
アタルのリーダーシップ故のものなのか、仲の良い幼馴染みで構成されているバンドだからなのか、平和主義者ばかり集まっているのか
いずれにしても、決断力の早さや清々しいほどの仲の良さはHazeの強みであると思った
「そんじゃ‥‥何からやる?」
「“GOLD RUSH”やりたいー!」
「‥‥お前、ほんと好きな」
「大好き!早くやろ!」
アタルが呆れ返るほどお気にの曲を演奏出来るとあって、ユイは張り切ってギターを構えた
“GOLD RUSH”は、随所に散りばめられたカッティングが印象的な曲になっている
カッティングの好きなユイの為に作ったといっても過言ではなく、また疾走感のあるものに仕上がっている
アタルが『一攫千金当てたい』という願望を詞に充てた為、拓真が『GOLD RUSH』と名付けた
対する『DIG IN』は、シンプルだがヘヴィな印象の曲
『DIG IN』には『突っ込む』という意味があり、リズム隊の勢いがキーになっている
比較的初期の頃に作られた曲で、アタルの“若さ”が滲み出ている
ユイも拓真もアタルの作る曲には外れがないと思っており、菱和もまた、技術的な面、バンドや曲の雰囲気をとても気に入っていた
人間的にもギターの音色に関しても、ムードメーカーでマスコット的存在のユイ
常にメンバーを気遣い、屋台骨としてしっかりとバンドを支える拓真
ガラは悪いがバンドのことを強く想う、絶対的リーダーのアタル
比較的キャラの濃い個々のメンバーの個性も、勿論好きだった
迎え入れてくれたことや腕を認めてくれたことに恥じぬよう、自分にやれることを精一杯やろうと心に決め、Hazeというバンドに改めて感謝した
***
練習が終わると、全員が揃って菱和の自宅へと向かう
「今日はあっちゃんもアズんち行けるんだよね?」
「ああ。今日の献立は?」
「何食いたい?」
「和食も、作れるか?」
「どんなの?」
「‥‥揚げ出し豆腐」
アタルは少し恥ずかしそうにそう云った
菱和にとっては、意外なリクエストだった
アタルが和食を好きだとは知らず、少し目を丸くする
「良いねー!揚げ出し豆腐!」
「あっちゃん、渋いチョイスだね」
ユイと拓真は、アタルの意見に賛成のようだった
「なんか急に食いたくなって。ひっしー、大丈夫か?」
「うん。じゃあ、豆腐だけ買ってくわ」
「いえーい!みんなで買い出し行こ!」
4人は、最寄のスーパーへと向かった
***
自宅に着くと、菱和は早速調理に取り掛かる
3人はリビングでのんびりしていたが、ふと立ち上がったアタルがギターを取り出した
「ちょうど新曲作りてぇと思っててよ。思い付いたフレーズくっ付けてみたから、ちょっと聴いてみてくれっか?」
「お!聴く聴く!」
「ひっしー、アンプ借りるぞー」
「うん」
調理中の菱和は、キッチンから返事を寄越した
アタルはギターアンプをリビングに運び込み、シールドを繋いでギターをセットした
軽くチューニングを合わせるとソファに座り、ギターを弾き始めた
弾きながら、メロディーラインを鼻唄で歌う
ゆっくりと、優しい印象のイントロ
Aメロ、Bメロも柔らかい雰囲気だったが、サビに入ると急激に哀愁漂うものに変化した
切ないアルペジオが室内に響き、ユイも拓真も菱和もアタルのギターに聴き入った
ワンコーラス弾き、アタルはギターのスイッチを切った
「‥‥‥‥こんな感じかな」
「めっちゃカッコいいじゃん!」
「うん、すげぇ好き!切ない感じだけど、良いね!」
「今まであんま無かったんじゃない?こういうの」
「ん。ライヴ映えはしねぇと思うけど、上手くアレンジ出来れば良いんじゃねぇかなと」
「うん、やろうよ!続き作って!」
「ひっしー、どうよ今の?」
「俺も気に入った。すげぇ色気あって、良いね」
「おっしゃ。じゃあこれベースに曲作るわ」
揚げ出し豆腐が出来るまで、アタルはユイと拓真にアドバイスを受けながらノートに記憶を走らせた
***
菱和は、揚げ出し豆腐の他にも簡単なサラダと味噌汁を作った
揚げ出し豆腐には、細く切られた人参や玉ねぎが入った飴色の餡がかけられている
味噌汁からは、香ばしい胡麻油の香りが漂う
「頂きまーす!」
「どうぞ」
3人は、まずはメインの揚げ出し豆腐を口に運んだ
「美味ぁ‥‥沁みるわぁ」
「餡が美味いね!豆腐とすげぇ合う!ね、味噌汁は何入ってんの?めっちゃ良い匂いすんだけど」
「もやし。胡麻油で炒めた」
「へぇー、初めての味。母さんに頼んで作ってもらおっかな」
「お前、女だったら良い嫁になったろうなぁ」
「‥‥そーかな」
菱和は軽く頭を掻いた
「男をゲットするには胃袋を掴めって云うじゃん?料理できる奴はポイント高けぇよ、やっぱ」
「女じゃなくても、充分モテるんじゃない?背ぇ高いし、顔も良いし、料理も楽器も上手いし」
拓真が云った言葉に、ユイもアタルも頷く
菱和は軽く溜め息を吐いた
「‥‥‥‥如何せん、性格がさ。難ありだから」
3人は、真面目な顔の菱和を一斉に見つめた
菱和は3人の視線に若干たじろいだ
突然、アタルが吹き出す
「ひゃははは!何云っちゃってんのお前!?」
「全然難ありじゃないじゃん!優しいし、真面目だし」
「謙遜してんでしょ、ひっしーったら」
ユイは揚げ出し豆腐を頬張り、拓真はくすくす笑っている
菱和は真面目に云ったつもりだが、3人には洒落だと捉えられたようだ
「つぅか、今まで女と付き合ったことあんのか?」
「無い。女って苦手」
「え、そうなの?」
3人は、菱和の答えに目を丸くした
「煩くて好きじゃねぇ。そういう女ばっかりじゃねぇってのはわかってるけど」
「告られたことは、あるっしょ?」
「‥‥何回かは」
「全部お断り?」
「ん。興味ねぇから」
「超絶優良物件なのに、勿体ねぇなぁ」
「‥‥んなことないっすよ」
菱和は少しだけ口角を上げた
4人は、談笑しながら食事を進めていった
菱和の女性遍歴を聞いたところで、ユイは何故かほっとした気持ちになっていた
54 手
菱和が加入してから初めてのライヴが終わり、ユイは安堵して帰宅した
ギターを下ろすとスタンドに立て掛け、ベッドに仰向けに寝転がり、長い溜め息を吐いた
天井を仰ぎ、今夜のライヴでの出来事を反芻した
天井に手を伸ばし、翳してみる
もう、手は震えていない
今まで経験したことのなかった手の震えは、菱和に握られると不思議と落ち着きを取り戻した
暖かく、大きな、優しい手だった
あの手が、指が、ずっと欲しかった
そして、その望みは叶った
学校に居ればペンを握り、字を書く
バンドではベースを弾き、練習が終われば自宅で料理をする
自分と自分の大切なものを、護ってくれたこともある
今日は、震える自分の手を握ってくれた
自分と同じように震えていたが、その手はとても大きく、心強かった
──────アズの手って、良いなぁ
ユイは菱和の手の感触を思い出し、ぎゅっと拳を握り締め、菱和の存在に只管感謝した
***
週明け、月曜日
昼休み、リサはお弁当を持って屋上に向かった
重いドアを開け放つと、柵に寄り掛かって怠そうに景色を眺めている菱和が居た
菱和はリサの姿を一瞥すると、また怠そうに景色を眺めた
リサは、菱和と同じように柵に寄り掛かった
「‥‥‥‥あいつらは?」
「みんなでコンビニ行った」
「ふーん‥‥お前は行かなかったの?」
「別に用事ないし」
「そっすか」
会話が途切れると、リサは菱和をじっと見つめた
リサの視線に気付くと、無愛想に口を開く
「‥‥何」
「‥‥‥‥別に」
リサはふいっと顔を逸らした
菱和は、何か云いたげな様子のリサを覗き込んだ
「‥‥ああ。俺、殴られるの?」
リサには菱和を殴る理由が見つからず、眉を顰めた
「───は!?何でそんなことしなきゃなんないの!」
「云ってたじゃん、『つまんなそうに弾いてたらぶん殴る』って」
菱和は意地悪そうにくつくつと笑い出した
その言葉に、リサはむすっとする
「‥‥そんなことする必要、ないじゃん」
「そうなの?」
「‥‥‥‥つまんなそうには、見えなかったから」
「‥‥そっか」
菱和の笑みは、意地悪なものから穏やかなものに変わっていた
リサは少し咳払いをした
「‥‥‥‥‥何ていうか‥‥昨日、ほんと凄かった。たけにい‥‥ユイのお兄ちゃんが居た頃の音も好きだったけど、あんたのベースも安心して聴けた。あんたもみんなも、‥‥凄く楽しそうだった」
「ん、すげぇ楽しかったよ」
「だから‥‥‥‥‥‥‥‥『だから』っていうのも変だけど‥‥‥‥ユイのこと、これからも宜しくね」
リサは菱和と目を合わせず、唇を尖らせてそう云った
素直ではない態度とは裏腹に放たれたリサの言葉
リサなりにユイを気遣い、大切な存在であるユイのことを『宜しく頼む』と云ってきた
つい数ヶ月前までは、こんな風に会話が成立することすら想像出来なかった
菱和はリサにも受け入れられているということを、素直に嬉しく感じた
「‥‥‥‥ん、わかった」
そしてまた、穏やかに笑った
ドアの方が騒がしくなる
ユイと拓真、カナ、そして上田が揃って屋上へと来た
「リサー、お待たせー!ポッキー買ってきたから、後で食べよ!」
カナがリサに手を振る
4人は昼食を持ってリサと菱和の元へと駆け寄った
「あー腹減った。早く飯食うべ」
「っていうか、2人ともまだ食ってなかったの?先食ってて良かったのに。もしか、待たせちゃってたんだったらごめん」
「いや、なんも。少し話してたからな」
「何話してたの?」
「‥心配性な保護者からの、大事なお話」
「保護者って云うな!!」
「保護者?」
「うっさい!!余計なこと喋るな!聞くな!」
「リサ、座ろ。お腹空いてんでしょ?早くご飯食べよ!」
きつく声を荒げるリサを宥めるようにし、カナはリサを座らせた
ユイは全員が昼食の準備を整えたところで手を合わせて号令をした
「んじゃま、頂きまーす!」
「ほーい」
「頂きやーす」
輪になって食べる昼食
いつの間にか、この光景が“いつものこと”となった
先日のライヴの話題を交えつつ、終始穏やかな時間が流れた
53 LIVE!!
無事出番を終えたHazeのメンバーは、SCAPEGOATの面々を残して袖へと下がった
そのまま控え室に戻り、全員が肩で息をしながら椅子にどかりと座り脱力した
「あー、疲れたー!!」
「マジ楽しかったー、やっぱジョイントやるとテンション違うわ!」
「ひっしー、どうだったよ?」
「‥‥‥‥すんげぇ楽しかった」
「‥そうか。まぁ、つまんなそうには見えなかったな」
「うん。なんか後半は自分でも変になってた」
「ははは!そうだったんだ!でもやっぱライヴはそうじゃなきゃね!」
「上出来だ。これからもあんな調子で頼むぜ」
「うん」
「さーてと‥‥‥‥あいつら観に行っか?」
「そだね。ユイ、どうする?」
普段なら一等先にライヴの感想を述べるユイが、控え室に戻ってきてからは一言も発していない
椅子に座り、ぼーっとしている
「‥‥ここにいる」
ユイの様子がいつもと少し違うように見えたが、拓真とアタルは敢えてそれを追及しようとしなかった
「‥そっか。ひっしーは?」
「‥‥俺もここにいるわ、少し休む」
「わかった。じゃ、俺らSCAPEGOAT観に行ってくるわ」
そう云って拓真はアタルと共に、控え室から出て行った
静まり返る控え室
菱和は立ち上がり、呆然としているユイに声を掛けた
「‥‥どした?」
「──────‥‥‥‥俺、めっちゃ手ぇ震えてる」
声を掛けられたユイは菱和の顔を見て、不安げに笑った
覗き込むと、ユイの指先が震えていた
「‥‥俺も、すげぇ楽しかった。でも‥‥今なんか、ちょっと変だ。いつもはこんなことないんだけど‥‥‥‥」
そう云って、ユイは目を丸くして自分の掌を見つめた
未だ興奮冷めやらぬ脳内や心臓
頭の先から指先、足の先まで、全てが快感で埋め尽され、溢れ出て止まらない脳内物質
強迫観念にも似たような感覚で弾き続けた指先
そして、快楽や昂揚感と同等かそれ以上に、不安や緊張もつきまとう中の演奏
張りつめていたものが一気に解け、その反動が今になって出てきているような気がしていた
ふと、掌が、大きな掌に包まれた
ユイは少しビクつき、顔を上げた
菱和はユイの前に跪き、ユイの手を握っている
ユイの顔を見上げた菱和の前髪が、揺れる
「‥‥大丈夫。俺もだから」
穏やかに笑みながら力を込めて握ってきた大きな手もまた、小刻みに震えているのが伝わってきた
不安や緊張の糸が切れたの、菱和も同じだった
リサとはまた違う想いで握られた手
ユイは不思議と、次第に落ち着きを取り戻していくのがわかった
手の震えが徐々に無くなっていく
菱和に手を握られているからだと、自分の手を包み込む大きな手を見てそれを自覚した
「──────‥‥アズ」
「ん?」
「もうちょい、このまんまでいてくれる?」
「‥‥‥‥ん」
菱和は、更に力を込めてユイの手を握った
ユイは薄く笑い、菱和の手を握り返した
52 LIVE!!③
リサはずっと、菱和の姿を観ていた
『つまんなそうに演奏したら、ぶん殴る』
菱和にそう云ったリサ
今日の菱和は、無表情とはいえつまらなさそうには見えなかった
『あいつが大事なもんは、俺にとっても大事』
嘗て菱和が放ったその言葉は、ユイを想う気持ちと同じくらいリサのことも想っているということに他ならない
自分を見る眼差しは、ユイを見るそれにどこか似ていると思っていた
時にはからかったり、悪態をついたり、意地悪なことを云ったり
自分が拐われたときは、身を呈して護ってくれた
隠れていた菱和の人間性がじわじわと滲み出てきては、第一印象とは程遠いものになっていく
足掻いたところでどうなるものでもないと、諦めかけていた筈のあらゆるもの
“普通”ということ、友達の存在、楽しみや快楽
そして、やっと手に入れた自分の居場所
少し躊躇いながらも、触れた瞬間、一気に愛おしくなる
手放すまいと必死にそれを抱く大きな手と、指
ポーカーフェイスは片時も崩さない
が、その裏の滾るような“熱”は伝わっていた
以前のライヴでは、“こんな音”じゃなかった筈だ
BURSTにいた頃の音とはまるで違う
勢いや正確さは変わらずだ
だが、自分が求めていた、求められている場所で自分の出し得る全てを解放するそのベース音は、気持ちの面でだいぶ変化のあったプレイに見事表れていた
求められているなら、存分にこの腕を奮おう
居場所をくれた優しさに、心からの慈愛を
自らを欲してくれた面々に、惜しみ無い感謝の意を込めて───
───これじゃあ、殴れないじゃん
リサは、菱和のベースに、全てを見守る“暖かさ”を感じた
***
“knife”の後にもう一曲演奏したHaze
オーディエンスの歓声は、彼等の演奏が終わったことを惜しむものになっている
「バンドの曲はこれで終わりです、聴いてくれて有難う!」
喉を酷使したアタルに代わって、ユイが頭を下げながらオーディエンスに礼を云う
菱和と拓真も、深々と頭を下げた
「そんじゃ、今からジョイントやりまーす!準備するから、ちょっと待っててねー」
アタルは袖に待機していたSCAPEGOATを呼んだ
SCAPEGOATのメンバーがステージに上がると、黄色い声援が飛ぶ
各々が準備を進める中、ハジが客に向かって話し始めた
「お邪魔しまーす、SCAPEGOATでーす!Hazeとのジョイントは2曲演ります!それ終わったら俺らの出番だから、最後まで逃げんなよー?」
客席から拍手が起こった
Hazeはアタルのインパクトとユイの可愛さとのギャップが好印象で、『どういう繋がりで一緒にバンドをやっているのか』と興味を引かれる客が多く、曲も評判が良かった
SCAPEGOATはルックスでも演奏面でも定評があり、メンバーの半分が社会人であることでファンの年齢層も幅広く、マンスリーライヴでも人気のバンドだった
HazeとSCAPEGOATが仲良しであることはマンスリーライヴの常連客にとっては周知のことで、ジョイントをやる度にどちらのバンドにもファンが増えていった
ジョイントの一曲目はケイがドラムを担当する
拓真はアタルとハジのいるマイクのところに行き、ハジを中心にして3人で並んだ
ステージの右にはユイと菱和が、左には上田とユウスケがそれぞれ並び、準備を整えた
「オッケーだよー」
ケイは全体を見回し、ハジに合図した
ハジはマイクを構え、一言呟いた
「──────一緒に遊ぼう?」
その声を合図に、上田がトルコ行進曲の冒頭部分を速弾きする
重いドラムのリズムと空弾きのギターが絡まり、ハジは叫ぶように歌い始めた
「DO YOU WANNA PLAY!!!?」
ユイの敬愛するバンド、EXTREMEの“PLAY WITH ME”
缶蹴り、かくれんぼ、モノポリー、刑ドロ、ジャングルジム、ロンドン橋、お医者さんごっこ、いないいないばぁ、ボール遊び、砂遊び‥‥
この曲の歌詞には様々な遊びが出て来て、ラップのように歌い上げる
そして何度も、繰り返す
“DO YOU WANNA PLAY WITH ME”
“君と遊びたいんだ、一緒に遊ぼうよ”
遊び心満載の曲の中盤は、かなり難易度の高いギタリスト泣かせの超絶速弾きが待ち構えている
ユイと上田とアタルは、話し合って小節毎に区切って決めた自分の担当のギターソロを順番に弾いていった
一人ずつ前へ出て、得意気に弾きこなしていく
アタルはともかく、ユイと上田のプレイには客席からどよめきが聴こえた
高校2年生という年齢を考えると、EXTREMEが好きでそれなりに聴ける演奏が出来るということはかなりの意外性があり、観客の度肝を抜いた
ドラムとベースは特段難しいことはなく、ケイはニコニコしながら叩き続け、菱和とユウスケは小節毎に交互に弾いたりオクターブで重ねて弾いたりした
「DOYOU,DOYOU
WANNA,WANNA
PLAY,PLAY WITH ME
PLAY WITH ME」
全員でハジの声に掛け合いをする
〆にユイと上田が速弾きのフレーズをユニゾンで弾き、一斉に締めた
息を吐く暇もなく流れるように曲は終わり、途端に大歓声が巻き上がる
特にミスもなく1曲目が無事成功したことと沸き上がるオーディエンスに全員が安堵し、全力で2曲目に臨む
***
「有難う御座いました!えーっと‥‥俺らは普段から結構仲良しで、今までも何度かジョイントさせて貰ってます。出会って何年くらいになるかな‥‥あっちゃん、覚えてる?」
ハジはMCを挟んだ
その間に、ケイが拓真と入れ替わる
ケイはハジの横に並び、拓真は椅子や太鼓の位置をセッティングし直した
「あー‥‥もう5年くらいなるかな」
ユウスケが横から話に混ざる
「出会った頃はまだ高校生だったよね」
「そうだ、お互い『ガラ悪いなぁ』とか思ってたんだよなぁ」
客席からくすくすと笑い声が聞こえた
「因みに、ココ3人同い年でーす」
ハジがアタルとユウスケ、そして自分を指差した
途端、客席からは「えー!?」だの「嘘ぉ!」だのとどよめきが聞こえる
「‥何今の!?タメに見えない?誰か老けてる?」
「お前じゃねぇの?」
「いや違うし!マジで同い年だから!」
また笑いが起きる
ユイや上田も笑っていた
「Hazeも俺らもメンバーの年齢バラバラなんだけど、楽しくやってます!今後も観る機会あったら宜しくね!あと一曲演ります、さっき演ったのと同じ、“EXTREME”っていうバンドの曲です。楽器隊が超かっけぇんで、注目してください!あんま俺ばっか観ないでねー!」
おちゃらけたハジのMCに、笑いと拍手が起こる
ハジが拓真を振り返りゴーサインを出すと拓真は軽く頷き、一度スティックをくるりと回してイントロ部分を叩き始めた
ドラムが築いたリズムにユウスケが一筋の重いベースラインを紡ぎ出し、アタルが奏でる妖しいアルペジオがその上に滑り乗る
そこへ、ハジが呟く
「You read the papers today?」
ユイと上田のグリッサンドを皮切りにリフが始まり、ラップのようなAメロが重なる
EXTREMEの楽曲の中でも特にファンク色の強い、“CUPID'S DEAD”
中盤にはこの曲の真髄とも呼べるギターとベースによるユニゾンがあり、未だギターキッズ達の心を捉えて離さない
歌詞はとある“悲劇的な喜劇”を歌ったもの
情熱故の犯罪
オムツをつけた身元不明の被害者は、片手に弓矢、もう一方には手紙を掴んでベッドに横たわっていた
手紙には一言、『キューピッドは死んだ』と書かれていた
何度も何度も、『“キューピッドは死んだ”と、新聞の見出しにはそう書いてある』と繰り返す
そして全員で、その特ダネを“号外”として伝え、合唱する
「EXTRA,EXTRA,EXTRA,EXTRA!!」
曲は中盤に入り、怒濤のユニゾンパートが始まる
楽器隊の4人が目配せする
ユイと菱和は互いを見やり、4小節を弾く
ユイはニコニコと、菱和はポーカーフェイスを崩さぬまま弾いていく
次の4小節は上田とユウスケが同じフレーズを弾く
そのあとは、ユイとユウスケが一緒に弾いたり、菱和と上田が一緒に弾いたりと組み合わせを変えて弾き続けた
ユニゾンの間、ハジとアタルとケイは手拍子をして楽器隊と観客を煽る
最後の大サビになってもユニゾンは続いており、ユイは上田と同じフレーズにハーモニクスを利かせて歪ませ、ユウスケは菱和より1オクターブ高く音を重ねて弾く
───“楽しい”どころの騒ぎじゃねぇ
幾度となくステージに上がってきたが、今日のこの日は今までとはまるで違った
味わったことのない高揚感
身体中の血が滾る
指は驚くほどよく動き、快感にも似た何かが脳内を駆け巡る
楽しむ余裕すら無くなるほどの快感が、菱和を支配していた
51 LIVE!!②
ザワザワとしているオールスタンディングの客席
前のバンドの熱が残る、暗転しているステージの上
スイッチやケーブルを踏まないように、定位置に付く
拓真がセットと椅子の調整をし、シンバルの音を鳴らす
ユイと菱和とアタルはそれぞれシールドとアンプを繋ぎ、軽く音を出してみる
エフェクターの準備は出来ている
チューニングもほぼ合っている
暗がりの中で、アタルが拓真に合図すると、カウントの音が響いた
ライトに照らされる4人
ギターのリフとユニゾンするベース
そして、それに重なるドラム
アタルがイントロに一発シャウトをかますと、客席は一気に高揚した
一曲目は、全編通してほぼギターとベースのユニゾンで構成されている“RED SILK”
ユイと菱和は互いに目配せし、拓真も全体を見ながらリズムを刻む
マイクを構えて歌うアタルの赤い髪と同じカラーのSGが、ライトに照らされて映える
アタルが歌う傍ら、ユイと拓真が「BULLSHIT!!」と掛け合いをする
サビに入ると、一層ヒートアップするアタルがオーディエンスに負けじとがなる
ユイはギターを弾きながらハモる
2回目のサビが終わると曲調は変わり、ベースがそのテンポをゆっくりと刻む
そこにドラムが加わり、ギターの重いリフが乗る
ユイはリフを弾きつつ、低い声で歌詞を呟いた
End of the world of the country is bright red
My heart was dyed red.
Throw off the clothes,touches the skin,murmured the name.
And,I will be conquered from the core.
Dive deep inside of you to follow a long history‥‥‥‥
歌詞の最後の部分に被せるように、アタルはワウペダルを踏みながら、ギターソロを奏でる
ユイの弾くリフに歪んだギターソロが重なる
ソロが終わるとアタルはまたシャウトをし、それを合図に全員がそのまま最後のサビへと雪崩れ込む
演奏が終わると、一瞬の静寂の後、オーディエンスの歓声と拍手が巻き起こった
4人は無事一曲目が終わったところでそれぞれ安堵し、軽く息を吐く
ユイと拓真とアタルは、久々のライヴでも今まで通り変わらない印象
菱和はというと、無表情なのは変わらなかった
だが、決してつまらなさそうということはなく、当の本人も至って楽しくベースを弾いていた
楽器を弾く人間からすると、その腕は目を見張るものだった
加入から一月ほどしか経っていないのだが、元々持ち合わせている才能も相まって上手くバンドに嵌まっている
ユイと拓真とアタルの音に、寸分の狂いもなく心地よく重なっていた菱和のベース
聴き慣れている尊のベースと比べても遜色は無いように思えた
客席から全てを観ていたリサはゾクリとし、軽く腕を擦った
***
───満員じゃん
ライトに照らされたステージからは、客席はよく見えるわけではない
だが、後ろの方まで人が居るのは目視できる
菱和は人の多さに感心し、軽く髪を掻き上げた
「どーも、“Haze”です。初めましての人は初めまして」
アタルがMCを挟む
観客は大歓声に沸いた
「きゃーっ、アタル様ー!!!」
アタルのファンと思われる女性の声が響いた
軽く会釈すると、アタルは続けて話した
「‥‥ベースが抜けて暫くマンスリー出てなかったけど、この度新しいベースが加入したんで紹介します。“ひっしー”です、はいみんな拍手ー」
アタルに掌を向けられ、菱和はぶっきら棒に会釈した
ユイはニコニコしながら拍手をし、拓真はハイハットを踏む
オーディエンスからも拍手が飛んだ
「あ、こいつ“コミュ障”だから何も喋らねぇんです、すいませーん」
アタルが意地悪そうにそう云うと、客席から笑いが起こった
アタルにほんの少しの悪意があるのを感じたが、コミュ障であることは事実なので、菱和は特に何とも思わなかった
「今日はひっしーが入ってから初めてのライヴなんですけど、このあとSCAPEGOATの奴等とジョイント演ります。俺らを観たことある人も初めて観たって人も、是非楽しんでって下さい」
アタルの言葉を聞いて、ユイは深々とお辞儀をした
「じゃあ、次は“knife”っていう曲演ります。聴いてください」
ライトの調子が変わり、拓真はカウントを始めた
曲が始まると、チカチカと光り出す
“knife”は、シンプルなミディアムテンポの曲
リフにはハーモニクスが入り、ナイフのような鋭さを強調させている
大好きなカッティングが随所に入っており、ユイはノリながら弾き続けた
ギターを弾きながら歌うアタル
Bメロとサビの部分にハモりを入れる拓真
それを支える、菱和のベース
シンプルな曲だからこそ、バンドのバランスの良さが際立つ
Words that casual remark are hit me like a “knife”.
I'll hold you like demons!!
食い入るようにマイクに向かって歌うアタルは、赤い髪の所為もあってか迫力がある
滑るようにギターソロを弾きこなし、再び歌い出す
終盤に入ると、ユイは頭を振り乱しギターを掻き鳴らした
全ての音が止む中、ユイだけは音を出し続ける
間延びしたハーモニクスが、会場に響き渡った
50 LIVE!!①
ライヴ当日
開場前にも関わらず、Sound Hallの前はごった返していた
マンスリーライヴの常連バンドの名前が看板に書かれており、HazeとSCAPEGOATの記載もある
最大で300ほどのキャパであるSound Hallは、ユイたちの住む地域では比較的大きい会場であり、マンスリーライヴは地方からも参加者が集まるほどの賑わいを見せている
夕方
ユイたちは最後のリハを行った後、控え室に集まった
控え室は2バンドで共有することになっている
ユイたちは3番目、SCAPEGOATは4番目なので、ハジたちと同じ控え室
6畳ほどの狭い室内は8人入ればぎゅうぎゅうで、すし詰め状態になっている
「菱和くん、初ライヴだねー。めっちゃ楽しみなんだけど!」
「つうかさ、新メンバー加入後すぐジョイントなんて、俺らついてねぇ?」
「役得だよね。あっちゃんたちと仲良しで良かったー」
「ははっ。俺らも久々だから、いつもとテンション違うよな」
「もう、今日は全部楽しみ過ぎる!」
「俺ら、袖で観てっから」
「うん!観てて!」
「てめぇ、演ってるときによそ見すんなよ」
「しないよ!」
「たっくん、俺も熱視線送るから!」
「要らん」
時刻は18時
間もなく、マンスリーライヴが始まる
ドアをノックする音が聞こえ、全員が一斉にドアの方を見た
「どうぞー、誰?」
ドアから一番近い位置にいたユウスケが扉を開けると、リサとカナの姿があった
「あ、リサちゃん?カナちゃんも」
「え、マジ!!?」
お気に入りの女の子の名前を耳にし、一番反応したのはハジだった
ユウスケに促され、リサとカナは会釈しながら控え室に入った
「こんばんはー!観に来ましたー!」
「よー、よく来たなぁ」
カナは笑顔で挨拶しているが、リサはいつもの仏頂面だった
菱和を除くHazeの面々には見慣れた光景だが、SCAPEGOATの面々は女子の登場にすっかり浮かれる
「わぁお、相変わらず可愛いねぇ二人とも」
「いらっしゃい。久し振りだね、元気だった?」
「はい!あの、これ差し入れです!」
「え、なになに?」
リサとカナは、持っていた紙袋をユイに渡した
ユイは袋を広げて、匂いを嗅いだ
「‥美味そーな匂い!何これ?」
「マフィン。出番まで、お腹空くんじゃないかと思って」
ライヴが夕方か夜に始まり、終了後に打ち上げを兼ねて食事に向かうことが多い為、メンバーたちはいつも食事を控えている
そのことを見越しての甘いお菓子の差し入れは、有難いことこの上なかった
「おお!助かる!」
「やべぇ、急激に腹減ってきた」
「どんなのが好きかわかんなかったから、適当に作ってきたんだけど‥‥」
「え!!手作り!!?」
ハジは『手作り』というワードに、弾けるように反応した
「はい、昼間のうちに二人で作ったんです。ね、リサ?」
ニコニコしているカナの横で、リサは黙って頷いた
「えっと、味はプレーンとチョコチップと紅茶とコーヒーなんだけど‥‥」
「じゃ、俺これー!」
カナがラインナップを告げたところで、ユイは袋から迷わずチョコチップのマフィンを一つ取り出した
「あっ、俺もチョコチップ!」
「俺プレーンが良いな」
「俺、コーヒー!」
「ほーい、どうぞー」
ユイは袋を広げて、メンバーの元へと駆け寄った
アタルと拓真はプレーン、ユイと上田はチョコチップ、菱和とケイは紅茶、ユウスケとハジはコーヒー味のマフィンを貰った
各々がマフィンを手に取り、頬張り始めた
甘い焼き菓子の香りが、室内に漂う
「‥美味っ!めっちゃ美味い!」
「コーヒー味って初めて食ったけど、結構イケるね」
「ほんとですか?良かったー!」
リサとカナは余っていた残りのマフィンを半分こし、皆と一緒に食す
カナはそっと菱和に近付き、声を掛けた
「菱和くん、どぉ?」
菱和は咀嚼しながら返事をした
「‥‥美味い。コーヒー飲みてぇ」
「良かったぁ!菱和くんて、甘いもの苦手かなーと思ってたんだけど‥‥」
「いや、結構好き」
「そうなの?また何か作ったら、食べてくれる?」
「ああ、喜んで」
カナは全員が手作りのお菓子を喜んでくれたことに胸を撫で下ろし、懸念していた菱和からも『甘いものは大丈夫』だと明確な答えを聞けて安堵した
「あー、ほんとコーヒー欲しくなるわこれ」
「ミルクティーでも良いな」
全員が舌鼓を打ちながら、マフィンを味わいつつ談笑する
ユイは菱和の食べているマフィンを見て、話し掛ける
「アズは、紅茶?」
「‥‥ん」
「‥はい!」
ユイは自分の持つ食べかけのチョコチップマフィンを少し千切り、菱和に差し出した
菱和は手に取り、口に運んだ
「‥‥美味いな」
「んっ!」
「‥‥俺のも食う?」
菱和も、ユイと同じくらいの量を千切ってユイに渡した
「‥うんまぁ!紅茶、美味い!」
「美味いよな」
マフィンを分け合うユイと菱和
「───あ、なんかデジャヴ」
「何が?」
「なんか、こんな感じどっかで見たような気がして‥‥‥‥」
「‥‥それ、この前の唐揚げじゃない?」
「ああ、それだ」
上田が導き出した答えに納得した拓真は、マフィンにかぶり付いた
「何?唐揚げって」
と、ケイが拓真に尋ねる
「この前、ユイが自分のべんとの唐揚げをひっしーにお裾分けしたことがあって。なんか、そん時に似てるなーって」
「へぇ。ゆっちゃんて、時々そうやって可愛いことするよね」
ユウスケは微笑みながらユイを見つめ、カナはユウスケの言葉に同意する
「そうなんですよね!やだもう、ユイくんったら!」
「え、普通じゃない?美味いもんは、分かち合いたいっしょ!」
ユイはニコニコしてマフィンを頬張った
マフィンを包んでいる紙製のカップを破きながら、アタルはユイに云った
「おいチビ、口にチョコチップ付いてんぞ」
「‥え、どこどこ?」
「そんなとこも、可愛いよね」
「違げぇよ。ガキなだけだ」
「子供扱いすんなよ!」
「うっせぇ、チビガキ」
ユイとアタルのやり取りに、周りはくすくす笑う
リサは、無言でユイにティッシュを手渡した
***
「あー美味かった。御馳走様でした!」
「御粗末様でしたー」
「マジ有難う!ほんと美味かったわ」
「いえいえ、また何か作ってきます!」
カナはすっかりSCAPEGOATのメンバーと打ち解けている
その様子を静観しているリサに、ユイはティッシュを返し、そのまま掌を差し出した
「リサ、有難う!」
リサはティッシュを受け取ると、当然のことのようにユイの手を握った
「‥‥頑張って」
「うん!観ててな!」
「あ、俺も」
「ユイのこと、宜しくね」
「任せとき!」
拓真も、リサと手を握り合う
強く念を込め、握られた手
そこには、確かな絆が感じられる
「あ、あっちゃんたち練習する?俺ら煙草喫ってくるわ」
「おう、わかりぃ」
SCAPEGOATのメンバーは、リサ、カナと一緒に控え室から出て行った
「相変わらずやってんのか」
「うん!久々だし、パワー貰わなきゃ!」
「なんかもう、験担ぎみたいなもんなんだよなぁ」
「ほんと、ね!」
ユイと拓真は顔を見合わせる
「‥‥こいつらさ、ライヴ前は絶対って云って良いくらい握手してんだよ。念送り合うみてぇに」
アタルは怪訝な顔をしている菱和に、3人の握手について説明した
「‥‥何してんのかなって思ったけど、そういうことだったんだ」
「いっつもやってんだ。あれやるとさ、上手くいくような気がするんだよね。リサから力分けて貰ってる、っていうか」
ニコニコとそう話すユイを見て、菱和は何度かゆっくりと頷いた
「お前ら、ほんと仲良しな」
アタルは柔らかく笑み、ギターを担いで爪弾き始めた
ユイも、弦を切らないように控えめにギターを弾き始める
菱和は速弾きをして指慣らしをし、拓真は椅子に座ってテーブルの縁をスティックで叩いた
時刻はあと数十分で19時になる
スタッフがユイたちの順番を告げに控え室へ来た
「Hazeさん、全員揃ってますか?そろそろスタンバイお願いします」
「うぃーす」
「じゃ、こっちの“いつものやつ”もやりますか」
「ひっしー、こっちゃ来い」
アタルは菱和に手招きした
菱和が来ると同時に、3人は互いの肩に腕を回した
「円陣。ステージ出る前必ずやるんだ!」
菱和もユイたちに倣い、ユイと拓真の肩に腕を回す
「ひっしー、お前このバンド入って楽しいか?」
「うん、すげぇ楽しい」
「‥‥よし。俺らは“バンド”だ。何より大事なのは、俺らと同じくらい客を楽しませること。お前が上手いのは知ってっけど、ぶっちゃけ演奏の上手い下手は二の次だ。お前がブアイソなのはわかってるし、『無理矢理笑え』とまでは云わねぇ。でも、楽しいなら心の底から楽しめ。これは今日だけじゃなくて、これから先もずっと同じこと。‥良いか?」
「‥‥うん、わかった」
菱和は静かに頷いた
「まぁ、ユイ一人だけで4人分のテンションだろうからお客さんには伝わるだろうけどねー」
「んふふー」
「よっしゃあ、久々のライヴだ。たーのーしーむーぞーおおお!!!」
「っしゃあっ!!!」
円陣を終え、各々は楽器を手に持ち、ステージへと向かう
「アレやると、全然気合いが違うんだ!初めてライヴやったときから、ずっとやってんの」
「‥‥握手も円陣も、良い習わしだな」
「でしょ?今度から、アズもリサからパワー貰いなよ!」
「‥‥‥‥あいつの手握ったら、取り敢えずぶん殴られそうなんだけど」
「へ?何で?」
「‥‥何でもね」
菱和は頭を掻きながら、ステージに向かった
49 続 前夜
喫茶店を後にした4人
ユイと菱和、上田とユウスケは方向が同じなので店の前で別れた
星が疎らな夜空の下、ユイと菱和は並んで歩いた
「はー‥‥明日かぁ。楽しみだなぁ。ね、アズも楽しみ?」
ユイは菱和の顔を覗き込んだ
菱和はいつものように生返事をする
「‥‥ん」
「‥‥‥‥んふふー」
覗き込んだまま、ユイはニヤニヤと笑った
「‥‥何だよ」
「別にー!あー、楽しみすぎて今日は寝れないかも!」
「寝不足でステージ上がったら最悪だぞ」
「ダイジョブ!どんだけ酷い顔してても多分照明でわかんないよ!」
「‥‥顔だけじゃなくてさ」
週末の街は普段よりも活気づいており、一杯ひっかけたサラリーマンや飲み屋を梯子する若者の姿がちらほら
ふと、ユイは立ち止まった
「‥‥‥‥あのさ、も少し、時間ある?」
「‥‥ん?」
「なんか、まだ帰りたくないっていうか‥‥‥‥もうちょっと喋りたいなー‥‥って」
このまま別れるのが名残惜しく、迷惑だと思いつつもそわそわしながら自分の思いを吐露する
菱和は携帯を取り出し、時計に目をやった
時刻は22:30を回っていた
「‥‥、良いよ、別に」
いつもより穏やかな声で、菱和は返事をした
駅前通りに点在する広場と、その中にある休憩用のベンチ
二人はそこを目指すことにし、再び歩き出した
広場にはスケボーやストリートダンスの練習をする若者や、デート中のカップルが所々に居た
適当に空いているベンチを見付け、並んで座った
「‥‥‥‥ごめんね。俺の我が儘に付き合わせて」
「別に。家帰っても一人だし、何もすることねぇし」
「あ、そっか!アズ一人暮らしだもんね」
菱和は煙草に火をつけ、怠そうに喫い始める
ユイは膝を抱え、ベンチの上で丸くなった
「‥‥‥‥俺ね、めっちゃ淋しがり屋なんだ。スタジオの後とかライヴの後とか、今日もだけど、楽しい時間のあとはすっげぇ空しくなっちゃって、家に帰りたくなくなるんだ」
「‥‥誰もいないのか?」
「うん。ここんとこずっと一人。父さんは俺が高校入ってから出張多くて、春までは兄ちゃんが居たけどもう地方行っちゃったし」
ユイが語る家族構成に、何処の家庭にも大抵はいる筈の人物が登場しない
尋ねても良いものかどうかほんの少し悩んだが、菱和は思い切ってユイに訊いてみた
「──────‥‥‥‥‥母親は?」
「‥うち、父子家庭なんだ」
ユイは軽く笑い、そう答えた
“母”というワードが出てこない時点で何となく想像はついていた
しかし、家庭の事情をそれ以上追求する必要性は感じず
菱和はほんの少し頷き、煙草の煙を吐いた
「‥‥アズは、一人で家にいて淋しくならない?」
「もう慣れた」
「そっかぁ‥‥。アズは、大人だね。俺なんかより、ずっと」
「んなことねぇと思うけど」
「ううん。俺、いつまで経ってもガキだなって思ってるもん」
「‥‥ガキなのと淋しがり屋なのはまた別の話だろ」
「そう、かな?」
「大人になっても、淋しがり屋の奴は沢山居るよ。楽しい時間の後に空しくなるのも別に普通のことなんじゃねぇの」
「アズも、そうなる?」
「‥‥今まであんま“楽しい”って思ったことねぇからいまいちわかんねぇけど、名残惜しいって気持ちは少しある」
「今日は、楽しかった?」
「うん。すげぇ楽しかったよ、“二次会”も含めて」
「‥そっか!良かった!」
ユイは、にこっと笑い掛けた
「──────多分、お前と居るから楽しいのかも」
菱和は、ぽつりと本音を呟いた
ユイは目を丸くし、何度か瞬きをして確認する
「‥‥‥‥、ほんとに?」
「うん」
「俺と居て、楽しい?」
「うん」
「俺、いっつもうるさくしてるのに?落ち着きないのに?」
「今更じゃん、そんなの」
「いや、そうだけどさ‥‥って、やっぱそう思ってた?」
「‥‥『いっつも元気だな』くらいにしか思ってねぇ」
「あ、そう‥‥‥」
うるさくて落ち着きがないところは、ユイは短所として自覚している
周りにいる友人はそれが長所でもあると捉え、菱和が口にした通り『いつも元気な奴』という印象で見ている
ユイは菱和も同じ印象を抱いているということが嬉しくもあり、切なくもあり、複雑な心境になった
膝を抱えたまま、ゆらゆらと軽く体を揺する
菱和は煙草を踏みつけ、火を消した
夜空を仰ぎ、ユイに一言云った
「‥‥お前は、そのまんまがいちばん良い」
ゆっくりとユイを見て、穏やかに笑む
───笑った
笑って欲しい
いつもニコニコじゃなくて良いから
もっと、アズの笑顔を見てみたい───
常々そう思っていた
その筈なのに
いざ見せられると
どうして良いかわからなくなる
不意打ちのような菱和の笑み
酷く穏やかな顔に、心臓が鳴るのがわかる
気付けば菱和はいつもの顔に戻っていた
ほんの僅かの間の、滅多に見られない菱和の笑顔
ユイの脳裏に焼き付いたそれは、未だ心臓を打ち付けている
当然ながら、菱和には自分が笑ったことでユイの心臓の鼓動を加速させているという自覚は無かった
「‥‥っていうかさ、“そのまんま”って、子供っぽいままで良いってこと?」
「‥‥‥‥‥‥」
「‥何で黙るのさ!」
「‥‥別に」
菱和は、少しだけ笑った
今度は、意地悪な顔をしていた
「さて。日付変わる前に、帰るか」
「‥‥うん、そだね」
ユイの顔を見ると、まだ名残惜しそうにしている
見兼ねた菱和は軽く溜め息を吐いて、膝を抱えたままのユイの前に立った
「‥‥‥‥もし一人で居てどうしょもなくなったら、連絡しな」
「‥え‥‥?」
「電話でもメールでも、会ってこうやって直に話すんでも良い。気が済むまで付き合うから。それでお前の気が紛れるなら、幾らでも相手になるよ」
見上げた菱和の顔
鬱陶しい前髪が風に揺れ、その眼差しが街灯の灯りにほんのりと照らされる
優しい、眼差し
何故、そこまでしてくれるんだろう
アズと居るのは、凄く好きだ
出来れば、もっと沢山時間を共有したい
だけど、そんなことをしたら迷惑なだけなんじゃないか
今だって俺の我が儘に付き合わせちゃってるのに
俺はアズに何も返せないかもしれないのに
アズは優しい、良い奴だ
「‥‥‥‥良いの?そんなこと云っちゃって。夜中にいきなり電話しちゃうよ?寝てても起きるまでかけ続けるよ?それでも良いの?」
「ああ」
「俺、話長いよ?アズが飽きて喋らなくなっても、ずっと喋ってるよ?」
「うん」
菱和は表情を変えず、ユイの言葉に返答した
本当に、真夜中の長電話にも嫌な顔一つせず付き合ってくれそうだ───そんな気がした
「覚悟、しといてね」
「‥‥上等だ。いつでも来やがれ」
菱和は、また柔らかく笑った
ユイがどんな顔で笑うかを、菱和はよく知っている
ユイもまた、菱和の笑った表情がどんなものなのかを知った
どんな表情であっても
いつも、そのままで居てくれることが、嬉しい
2人は、互いの存在が大きくなっていることを実感していた
48 前夜
ライヴ前日
リハーサルを行う為、ユイたちはライヴ会場である“Sound HALL”に向かった
ステージではSCAPEGOATがリハの最中で、ユイたちは隅っこでリハの様子を観ていることにした
ハジはユイたちに気付き、歌いながら軽く手を上げた
菱和は、このとき初めてSCAPEGOATのメンバーの音を聴いた
ハジはリハとはいえ本番宛らのような迫力があり、よく通る声だった
ヴォーカルとしての魅力が十分にあった
上田が使用しているギターは淡い色のストラトキャスターで、チャラい見た目に反し、どこか哀愁漂う音色だった
ユウスケのベースは、やたら不規則に動くベースラインだった
決して耳障りではなく、寧ろ心地よさを感じる
ケイは終始ニコニコしながらドラムを叩いている
女子に見られがちな小柄で可愛い見た目とは裏腹に、存在感のあるドラムだった
“楽しそう”という印象は、上田を始め、他のメンバーも変わらない
「ユイ、外出てなくて大丈夫?」
「うん、平気!駄目そうなら出るから」
「SCAPEGOATは何味なんだっけ?」
「ブルーハワイ」
「かき氷の?」
「うん。爽やかな感じ」
「‥‥まぁ、何ていうか、納得できる」
「っつうか、一人ひとりの音はまた違うんだよな?」
「違うよ。でもグッチャグチャに混ざってわけわかんなくて吐きそうになるから、何とか全体的に聴くようにしてる」
「訓練して出来るようになったんだよな」
「そうそう、慣れるまで結構大変だったんだよ!」
「‥‥便利なんだか不便なんだか」
「慣れれば楽しいけどね、色んな味して」
「‥‥‥‥変な奴」
「‥余計なお世話だし!」
ユイは唇を尖らせた
SCAPEGOATのリハが終わり、ハジたちがステージから降りてきた
「よー、お疲れー」
「お前、あんな飛ばして明日大丈夫なの?」
「ヘーキヘーキ!俺、無敵だから!あっちゃんたち、次っしょ?俺ら休憩がてら観てっから」
「ああ。じゃ、準備しますか」
「宜しくお願いしまーす」
ユイたちはハジたちと入れ替わり、ステージで準備を始めた
PAと返しの調整を行いながら、ライヴでやる楽曲を演奏し始めた
「ほんと良いね、菱和くんのベース」
「うん。まだ加入して間もないのに、ちゃんと馴染んでる」
壁に寄りかかってHazeの演奏を聴いているSCAPEGOATのメンバーは、率直な感想を述べる
それを聞いて、上田がぽつりと呟いた
「‥‥それって、ユイの所為かもな」
「ん?何で?」
「俺はクラス違うけど、ユイと拓真と菱和はガッコでずっと一緒にいるから、さ。拓真よりユイの方が一緒にいる時間断然長いし、良いのか悪いのか知らんけど何かしら影響受けちゃってんじゃないの、菱和も」
「なるほど。ゆっちゃんと菱和くんてアンバランスだと思ってたけど、意外と良い組み合わせかもしんないな」
ハジが頷いて納得する
「‥‥それ、背の高さのこと云ってる?」
「まぁ、こんなこと云っちゃ悪りぃけど、背はアンバランス過ぎるな」
「あーあ、リハ終わったらユイにチクろ」
「あっ、てめっ!」
上田とハジはふざけて小突き合いを始めた
***
「やぁ、精が出るねぇ」
ユイたちのリハが終わった頃、マンスリーライヴの主催者である照が現れた
40代くらいの風貌でありながら、髪を明るく染め眼鏡を掛けており、実年齢よりもずっと若く見える
ユイたちがバンドを組んだ辺りからの顔馴染みでもある照は、気さくに声をかけてくる
「あ、こんにちはテルさん!」
「すいません、今回も我が儘きいてくれてほんとに有難うございます」
「いやいや、他のバンドもジョイントとかやりたがってたからちょうど良かったよ。やっぱ、こっち側もどんどん新しいことやってかなきゃね」
「助かります、マジで」
「君たち見てるとさ、なんかこう、自分の若いときを思い出すなぁ。良いよねぇ、若さが滾ってて」
「テルさんも出れば良いじゃないすか、ドラム叩けるんだし」
「ははっ。今忙しくてね。またの機会にするよ。‥‥他のバンドも張り切ってるから、明日は宜しくね!」
「はい、お願いします!」
対バンを申し出るバンドは他にも居るのだが、最初にジョイントをやりたいと云い始めたのはアタルやユウスケだった
『どうせやるなら楽しいことをやりたい』というアタルたちの意見を、照は『面白そうだから』という理由であっさりと快諾した
それをきっかけに、照はマンスリーライヴにジョイントの形態を組み込むようにした
毎回ではないにしろ、それなりに人気のあるバンドが共演するとライヴ自体も成功するので、頼めば大抵は許可が降りる
HazeとSCAPEGOATは、ジョイント用の2曲を合わせることにした
話し合っただけで上手くいくほど簡単ではない楽曲を選んでしまったことを少しだけ後悔しながら、全員が曲に集中する
それぞれが目配せをしながら、難しそうな部分は入念にチェックしていく
リハが終わった頃、時間の許す限り調整を行う8人は汗だくになっていた
***
外へ出ると、既に陽は落ち真っ暗になっていた
風に晒された素肌がとても涼しく感じる
アタルや拓真、ハジ、ケイはこの後バイトを控えており、取り敢えずこの場で解散することになった
残った4人は、カフェでだらだらとすることにした
「ゆっちゃん、喫煙席でも大丈夫?」
「良いよ、全然気にしないから!」
「あ゙ー、マジ煙草喫いてぇ」
菱和とユウスケはブラック、ユイはキャラメルマキアート、上田はハニーラテを注文し、それぞれ注文したものをカウンターで受け取り、喫煙席へ向かう
人も疎らなカフェは、陽気なジャズが流れていた
「‥そっか、こん中で煙草喫わないのユイだけか」
上田は着席するなり、早速煙草を取り出す
「上田って何ていうやつ喫ってんだっけ?」
「マルメンライト」
「まるめん?」
「マールボロメンソールライト。知らない?」
「興味ないもん、煙草なんて」
「そっか、そうだよな‥‥」
「JPSか。渋いね。菱和くんにぴったり」
「‥‥‥‥、HiーLiteもかなり渋いすね」
「んー。やっぱこれじゃなきゃね、駄目なんだ」
「よくそんなキツいの喫えるよなー」
「キツいのが良いんじゃんよ。この脳天に突き刺さる感じ、堪んないねー」
「うへ、ユウスケって地味にMだよな」
「いや、ドSだし」
三者三様、お気に入りの煙草を味わう姿を軽く見回し、ユイはキャラメルマキアートを一口飲んだ
「たけちゃんって、煙草喫わないっけ?」
「うん。喫わないよ」
「そうだっけか。なんかあっちゃんと混ざっちゃってんな‥‥まぁ、喫わないに越したことないわな。全然良いことないし」
「そだね、気軽に喫える場所はどんどん減ってくしなー」
「良いことないのに、何で喫うの?」
ユイの素朴な疑問に、3人は押し黙る
「‥‥‥‥‥‥、何でかな、わかんない。いっちーは?」
「うーん‥‥‥‥わかんね。菱和は?」
「‥‥‥‥‥さぁ‥‥」
「‥‥まぁ、ビョーキだよね」
「ん、完全にニコ中だね」
上田とユウスケはニヤニヤしながら顔を見合わせた
菱和は黙ってコーヒーを啜る
「‥‥俺も煙草喫えたら、そういうのわかるのになー」
ユイは溜め息を吐いて、椅子にだらしなく座った
「そんなもんわかんなくたって良いよ」
「そうそう。わからない方がきっと幸せだから」
「んー‥‥でもさー、煙草も喫えないなんて子供臭いっていうかさー‥‥」
「全然そんな風に思ってないけど?」
「うん。ユイはまだ上る必要がない『大人の階段』なんじゃないの」
「別に二十歳になったからって皆が皆上る階段じゃないけどね。‥‥てか、いっちーも菱和くんもほんとはまだ喫っちゃ駄目な年だからね?」
「んなこたぁわーってるよ。俺の周りでバカスカ喫ってるユウスケたちが悪い!」
「人の所為にすんなっつの」
ユウスケは自分のことを棚上げする上田の頭を軽く叩いた
47 おひるごはん
「───あれ?何でおべんと2つあるの?まさか、2つ食べるの?」
「んなわけないでしょ、これはユイの」
お弁当が入った、赤と青の色違いの巾着
青い方はリサの母親がいつも買い弁のユイを気遣ってたまに持たせているもので、リサは事前にユイに『今日は昼食を持って来なくても良い』と伝えてあった
「はい、あんたの分」
「おっ、この巾着久し振り!ありがと!な、今日は2人も屋上で飯食わない?」
「え、私たちも行って良いの?」
「勿論!そん代わし、“しー”ね!」
ユイは人差し指を口の前に立てて、ニコッとした
開け放った屋上の扉から、風が吹く
乾いた涼しい風が、もうすぐ秋の訪れを伝える
屋上には拓真と菱和、そして上田がおり、既に昼食をとっていた
ユイはリサとカナを先に通し、扉を閉めた
「お、リサ。カナちゃんも」
「ユイくんが誘ってくれたの。うちらもお邪魔して良い?」
「どーぞどーぞ。華が無くてむさ苦しいと思ってたんだよねー。近藤サンと長原なら、いつでも大歓迎よん」
「樹、うざい。邪魔」
「え、何でそんな哀しいこと云うの‥‥」
カナは、腕を広げて歓迎する上田を軽くあしらう
上田はふざけて哀しそうな顔をした
普段意味もなく上田に絡まれている拓真は、ここぞとばかりにカナに加勢する
「カナちゃん、もっと云ってやって」
「はうぅ、たっくんまで俺のこと虐めるの‥‥?」
拓真は上田を無視し、ユイが持っている巾着に目をやった
「お、今日は“リサの母さんの日”か」
「えへへー、そうなんだ!ね、唐揚げ入ってる?」
「‥‥知らない」
「‥入ってんじゃーん!テンション上がるー!」
「ユイ好きだもんな、リサんちの唐揚げ」
「うん、めっちゃ好き!」
弁当箱を開けると、卵焼きやミニトマトに紛れ、ユイの大好きな唐揚げが入っていた
一つ摘まみ、にこにこしながら菱和の口元へ差し出した
「はいアズ、“あーん”!」
大好きなそれを自分よりも先に味わって欲しいと思い、ユイは何の躊躇いもなく最初の一口を差し出す
箸を使うことも憚られるほど待ちきれないのだろうと思っていた一同は目が点になった
菱和も目の前に唐揚げを差し出され硬直していたが、徐に首を傾けて唐揚げを口に咥えた
醤油と生姜、大蒜で漬け込んだ後、ブラックペッパーとハーブが混ざった衣を付けてカラリと揚がったスパイシーな鶏もも肉の唐揚げ
菱和は咀嚼し、親指で唇を軽く拭いながら感想を云った
「‥‥超美味ぇ」
「でしょでしょ!?リサの母さんの唐揚げは、世界一なんだー!」
ユイは菱和の顔を見て、漸く自分も唐揚げを口へ運んだ
「───なんかさ、今の“あーん”、『彼氏に手作りのおべんと食べさせてあげる彼女』みたいだった」
カナはユイと菱和をまじまじと見つめ、おかずを口にしながら云った
パックジュースのストローを噛み、上田が同意する
「ふふっ、確かに。男が男に“あーん”は初めて見たけど、そんなに違和感無かったな」
「ユイくんがやるから良いんだよね、きっと」
「‥‥だからって、行儀悪すぎ。せめて箸使えば」
「いやー、ついいつもの癖で」
ユイは全く反省の色を見せていない
「───ユイが女ならちょうど良かったのにな」
拓真がボソリと呟くと、
上田は噴き出した
「ぶっ‥‥はははは!ユイが女!?全然想像出来ねぇ!」
「いや、仮にカップルだとしたら、ひっしーよりユイが女の方がしっくりくるじゃん?今より少しくらい淑やかになるかもしんないし」
「いやー、幾らユイが女で可愛いカオで“あーん”とか云ってきても、絶対カノジョにしたいとか思えないな」
「ん、何でさ?」
ユイがもぐもぐしながら上田に尋ねる
「えー?なんか、常に元気良すぎて根負けしちゃいそうで。こっちが具合悪いときまでずっとこんなテンションなら、正直参っちゃうわ」
「あ、それは確かにうざいかもな」
拓真と上田は苦笑いしながら顔を見合わせた
「でもさ、それがユイくんの良いところじゃない?ね、リサ?」
「‥‥カナはユイのうざさ知らなさ過ぎ」
「え?全然うざくないけど?もしユイくんが女の子だったら、一緒に色んなとこ遊びに行きたかったなぁ‥」
「女じゃなくても、全然行くけど!カナ、“PANACHE”のクレープ好きなんでしょ?俺も好きなんだよね、今度一緒に行こ!」
「ほんとにー!?拓真くん、リサも、今度ユイくん借りてっても良い?」
「どーぞどーぞ!気の済むまでご自由に」
「てか、私たちに同意得なくて良いから」
「大人気だねー、ユイったら」
「そう?へへっ!」
談笑しながら昼食をとる5人に対し、菱和は黙々と食べ進めている
いつもの屋上が、いつも以上に賑やかになる
輪になって談笑するこの光景が、“いつものこと”となるのに、そう時間はかからない
屋上にいる全員が、そう感じていた
食事を終え、ユイと拓真は上田が持ってきたトランプに興じ、そこに菱和とリサとカナも加わる
リサは一早く上がり、初めて見る屋上からの景色をぼーっと眺めていた
「‥‥唐揚げ、すげぇ美味かった。お袋さんに礼云っといて」
2番目に上がった菱和は、リサの元へ向かい、声を掛けた
リサは菱和の顔をちらりと見てすぐに目を逸らし、生返事をした
「‥‥ん」
「‥‥、観に来るんだろ?ライヴ」
「うん、行く。‥‥‥‥またあんな顔して弾いてたら、ぶん殴るから」
「相当痛そうだな、そりゃ」
「結構本気で云ってんだけど?」
「‥‥そ。でも多分、殴られずに済みそうだわ」
菱和は、穏やかに笑った
たまに見せる意地の悪い顔ではなく、穏やかな柔らかい笑顔
───こいつでも、こんな顔するんだ
リサはまだわかりかねている部分もあるが、ずっと抱いていた菱和の良くない印象は、とうに消え失せていた
「なーんの話してんのっ!」
3番手で上がったユイは、2人に駆け寄った
菱和は振り返り、無表情の中にも意地の悪そうな表情を含んで云った
「‥‥俺をサンドバッグにしたいんだとさ」
「‥なっ!!そんなこと云ってないでしょ!?」
「何だよリサ、ストレス溜まってんの?」
「うるさい!!あんたも余計なこと云うな!!」
クールな瞳に隠された優しさ
口に出さずとも伝わる、友達を想いやる心
不器用な素直さ
リサと菱和は似ているところがあるが、煽り耐性が高い分、菱和の方が一枚上手だった
46 煙霧×生贄+洗礼
とある週末
SCAPEGOATとの合同ミーティングを兼ねた食事会を予定しており、Hazeの面々は会場であるレストランに入った
「ユウスケの名前で予約してんだっけ?」
「そうそう」
「ここね、ユウスケさんの知り合いがやってるお店なんだ。結構融通きくから、打ち上げとかによく使ってんの」
「ふーん‥‥」
「えーと、18時に予約してる“生野”です」
「“セイノ”様ですね。お待ちしてました、どうぞ」
店員に促され、“reserve”と書かれた札が置いてある席へと通される
SCAPEGOATのメンバーが来るまで、4人は暫し談笑をして待った
予定時刻を5分ほど過ぎた頃、SCAPEGOATのメンバーが到着した
「よー、遅れて悪い」
「こんばんはー」
脱退事件のときは特に気にしていなかった、というよりは気にしている余裕がなかったのだが、菱和はSCAPEGOATのメンバーの容姿に若干驚いた
ハジは袖が切りっぱなしのパーカーを着ており、肩から手首までトライバルの入れ墨が顕になっている
ユウスケはツートンカラーから黒に染め直し、その上から軽く青いスプレーをかけていて、穴が開いている全てのポストにゴツいピアスが付けられていた
ケイは、トップスは全体的に切り込みの入ったTシャツ、ボトムは太ももから足首まで派手に裂けたボロボロのダメージジーンズを穿いていた
シンプルなバンドTシャツに左膝だけがばっくりと開いたジーンズを穿いている上田が、どうしても普通に見えてしまう
以前、ユイが云っていた『上田が浮いてしまうほどガラの悪いメンバー』という印象が、この時初めて菱和にも伝わった
ハジたちは、菱和にも気さくに挨拶をした
「菱和くん、久し振り!元気だった?」
「‥‥‥‥はい」
菱和は軽く会釈をした
「大したことなくて、ほんとに良かったね」
「“Haze”加入、おめでとう!」
「有難う御座います。‥‥礼も詫びも出来なくて、すいませんでした」
顔を合わせるのは脱退事件の日以来
すっかり謝りそびれていた菱和は、深々と頭を下げた
ハジたちは面食らった顔をして、直ぐに噴き出し、笑った
「───ぷっ‥‥」
「っははは!そんなの全然気にすることないのにー!」
「そうだよ、俺らだってあんときなーんも出来なかったしなー」
「今後一切、堅苦しいのはナシ!ね?」
「菱和くん、これからも宜しくね」
菱和はまた軽く会釈した
ユイが横から耳打ちをする
「ね、みんなガラ悪いけど良い人たちでしょ!」
“良い人たち”なのは、脱退事件のときから既にわかっている
だが、見た目の印象よりも遥かに気さくで優しい人たちだと改めて感じ、菱和は納得してこくりと頷いた
「今日って、食べ放題飲み放題?」
「うん。がっつり食おうや」
「あー腹減ったー」
「酒は飲んで良いの?」
「アルコールは飲み放題に入ってないわ。飲みたいならまたの機会に」
「あっそぉ」
「何飲む?」
「面倒臭せぇから一杯目は全員コーラで良くねぇ?」
「じゃあ、二杯目から各自好きなの飲むってことで」
注文したコーラが席に届くと、全員グラスを持った
「じゃ、お疲れー!!かんぱーい!!」
少しずつ、食事も運ばれてきた
気軽につまめるポテトや唐揚げ、取り分けるタイプのサラダやピラフ、パスタが所狭しとテーブルに並ぶ
「んーと、一緒にやる曲ってEXTREMEだっけ?」
「そう、“CUPID'S DEAD”と“PLAY WITH ME”」
「ふわー‥‥どエラい選曲」
「どういう割り振りにしよっか?」
「当然、ヴォーカルはハジ。ギターは樹とユイに任せる。ドラムは交代で、やらない間はコーラス入って貰うって感じで考えてたんだけど‥‥」
「あっちゃんはどうすんの?」
「掛け合い多いし、歌う。適当にバッキングやるから。こんな感じでどうよ?」
「うん。良いんじゃない?」
「ベースは、小節毎に区切って弾けば良いかな」
「ギターもそうするべし?」
「そうだねー、どんな風にするか相談しなきゃね」
「今度、全員でスタジオ入るべ」
「うん、いつにしようか?」
食欲旺盛な男子が、8人
ボリュームのあるメニュー内容だったが食事はハイペースで進んでいき、締めのデザートもあっという間に平らげられた
「あー、食ったなー」
「んまかったー!ご馳走様でした!」
「さーて‥‥‥‥“アレ”、やりますか」
「あ、やっぱ今日もやっちゃう?」
「やるっきゃねぇべ!オネーサン、“裏デザート”一つお願い」
「かしこまりました!」
ハジはとあるメニューを追加注文した
数分後、店員が注文したものを席へ持ってきた
「お待たせしましたー」
店員が持ってきた皿には、一口サイズのシュークリームが乗っている
アタルはそれを指差し、ニヤニヤした
「この店の裏デザート、ロシアンシュー。このメンバーでここに来たら必ず頼んでんだ。8個の中に一つだけ“当たり”がある。残りは全部デスソース入り。ひっしー、どれでも好きなの選びな」
「え、アズ一人だけ?」
「まずは新入りから運試しだ」
普段であれば全員同時に食べているのだが、アタルは菱和にだけ先にシュークリームを選ばせた
菱和がこういった“ノリ”についていけるかどうか、或いはいつもの無表情が豹変する様を目撃したいだけのただの嫌がらせか
どちらにしても、これは菱和に対する“洗礼”だった
当たりの確率は8分の1
菱和はアタルに促され、特に選ぶ様子もなくシュークリームを一つ手に取った
全員が固唾を飲んで見守る中、菱和は何の躊躇いもなく口に放った
シュー生地はさくさくしていて軽い口当たりで、中にたっぷり詰め込まれたクリームにはバニラエッセンスと紅茶が混ざっている
くどくなく甘過ぎず、何個でも食べられそうだと思った菱和は、何度か咀嚼し味わった後シュークリームを嚥下した
そして、いつもと変わらず、無表情のままでいる
一同が、目を丸くした
「───‥‥‥‥あれ?」
「‥‥ひょっとして菱和くん、当たりだったの?」
「ん、美味いす。紅茶の味する」
途端、アタルはテーブルに突っ伏し激しく落胆する
「なーんだよおおぉぉぉ当たりかよおぉ!!つまんねぇえええ」
「‥‥‥‥、なんかごめん」
あまりの落胆振りに、菱和は取り敢えず謝罪した
「謝んなくて良いよ!てか当たりの確率低いのに、一発で当てるなんて!」
「っはははは!あっちゃんの目論見、見事に外れたね!」
「めっちゃ強運だねぇ、菱和くん」
「ほんと、すげぇな!」
「‥‥ご馳走様でした」
手を合わせ、挨拶をする菱和
落胆していたアタルは顔を上げ、意を決したように云った
「‥‥くそぉ‥‥‥‥じゃあ、俺らもいくかぁ」
「え、食うの?残り全部ハズレだよ?」
「そんなんわかってるよ」
「本気で云ってんの?」
「あたりめーだろ。いっつもそうしてんじゃんか」
「‥‥そだね、やっぱ残さないでちゃんと食わなきゃ」
「うぅー‥‥ですそーすぅ‥‥‥」
菱和以外の全員が、躊躇いつつもシュークリームを手に取る
「‥‥よーし、んじゃ『せーの』でいくぞ」
「うん」
「──────せーの!!!!!」
数秒後
菱和を除く他のメンバーはデスソース入りのシュークリームを口にし、悶絶した
45 Sår knivhuggen med en kniv
───‥‥‥‥良い匂い
目を覚ましたユイは、ぐりぐりと枕に顔を押し付けた
自分の寝具からは嗅ぎ慣れない匂いが鼻を擽る
すっきりとした香りにほんのりと甘さが混ざる、ユニセックスな印象の香水
そして、煙草の匂い───
ユイはゆっくりと目を開け、今自分が居る場所が自室ではないということに気付いた
気付くや否や勢いよく起き上がり、辺りを見回した
ベッドの横に置かれた小さな机
机の上には吸い殻が残る灰皿
部屋の片隅にはゴミ箱
床には数冊の音楽雑誌
正に、『寝る為だけの部屋』という印象だ
ユイはまだ少し眠気の残る頭と身体を何とか動かし、寝室を出た
リビングへ行くと、しんと静まり返っており、トマトの酸味のような匂いが漂っていた
昨晩良いだけ食べた筈の夕食が寝ている間にすっかり消化され、既に空っぽの胃を刺激する
テーブルには飲み掛けのコーヒーが入ったマグがあり、ソファには昨夜菱和が着ていたシャツがだらしなく置かれていた
キッチンの奥の方から扉の開く音が聴こえ、菱和が出てきた
菱和は濡れた髪をバスタオルで拭きながら脱衣所から出てくる
シャワーを浴びていたらしく、上は裸、下は少しウエストの大きいジーンズを穿いており、下着が少しだけ見えていた
「‥‥ん、起きた?」
まだ濡れている菱和の髪から、ぽたぽたと水滴が落ちる
細い腰に色白の肌、筋肉質な腕や身体
妙な色気が漂う
───“水も滴る何とやら”
そんなことを思ったが、まずは開口一番菱和に謝罪をした
「ご、めん!俺、夕べ寝ちゃったんだね‥‥泊めてくれて、有難う」
「‥‥よく眠れた?」
「うん、爆睡だった。てかアズ、どこで寝たの?」
「ん?‥‥そこ」
そう云って、菱和はソファを指差した
「‥‥‥‥ベッド占領しちゃって、すいませんでした」
「いえいえ」
菱和は少し口角を上げ、キッチンの換気扇を回して煙草に火を付けた
「‥‥ミネストローネ食える?」
「あ‥うん。食べれるけど‥‥」
「そ、んじゃ今あっためる。さっき佐伯から連絡来た。も少しで来るってさ。飯食って待ってな」
菱和はバスタオルを肩に掛け、煙草を喫い続けた
トマトの酸味のような匂いの正体は、菱和が起床してから作ったミネストローネだった
ついつい長居して寝てしまった自分をわざわざベッドに運んでくれた
家主である菱和をソファに寝かせてしまった
おまけに、自分より早く起床し朝食の用意までしてくれていた
昨晩から至れり尽くせり状態のユイは、唇を尖らせて申し訳なさそうにした
少し温くなったミネストローネの入った鍋を火にかけると、菱和は突っ立ったままのユイの側まで来る
「‥‥どした、座ってれば」
「う、うん」
促され、ソファに座ろうとしたユイは意識が別のところにあり、テーブルに足をぶつけてよろける
「───ぉわっっっ!!!」
「危ねっ‥───」
菱和は咄嗟に手を伸ばし、ユイの腕を掴んで引っ張った
菱和の力で容易く持ち上げられるほど軽いユイは簡単に引き寄せられ、あまりに拍子抜けした菱和はソファの縁に足をぶつける
2人は体勢を崩しそのままソファに倒れ込んだ
菱和はソファの肘掛けに頭を、ユイは菱和の胸板に顔を打った
菱和から、香水ではなく石鹸の香りがした
「───いってぇー‥‥‥」
「ご、めっ‥‥大丈夫‥!?」
ユイは鼻を擦りながら、慌てて菱和から身を離した
そして、肌蹴たバスタオルから覗く菱和の身体に絶句した
顕になった菱和の上半身
左の鎖骨の下辺りに、歪んだ傷痕があった
皮膚に残る生々しい傷痕に悪寒が走ったユイは、いつものように空気を読まず『その傷、どうしたの?』などとは云えなかった
視線の先に気付いた菱和は、無表情でユイを見つめた
菱和は傷を隠すつもりは全く無く、見られたなら見られたで別に構わないと端から思っていた
しかしユイは、見てはいけないものを見てしまったような、何か云いたげな、でも云ってはいけないような、そんな顔をしている
菱和は、ユイの機微を何となく感じ取った
「──────ユイ」
菱和が“ユイ”と口にしたのは、これが初めてだった
ユイは名前を呼ばれ、弾けるように反応する
「───は!‥あ、‥‥‥‥」
菱和はゆっくりと、ユイの顔に手を伸ばした
──────あ
多分、これは、今までとは違う
事故とはいえ、“見てしまった”
今回は流石に、菱和も怒っているかもしれない
この手は、一秒後には自分の頬を殴り付けているかもしれない
痛いのは嫌だ、殴られるのは嫌だ
しかし、それは最早仕方のないことだ
取り返しのつかないことをしてしまったと感じたユイは菱和に殴られるのを一瞬のうちに覚悟したが、菱和はその意に反してユイの額に軽くデコピンをした
「───ってぇっ!」
「‥‥‥‥そうやってぼーっとしてっから蹴躓くんだろ。‥‥怪我ねぇか?」
顔を上げると、菱和からは傷を見られたことを気にしている様子や怒っているようなオーラは微塵も感じられず、ただ呆れ返っているようにしか見えなかった
ユイは額を擦りながら、返事をした
「‥あ、うん‥‥平気‥‥‥‥」
ドアが開く音がした
それと同時に、拓真の声がする
「ユーイ、迎えに来たぞー‥‥───」
拓真の目に飛び込んできたのは、上半身裸の菱和に馬乗りになっているユイ
拓真から見ると、あまりにも不自然な状況だった
3人は、目が合いながらも硬直する
「───何してんの」
「え‥あ、いや、何も‥‥」
慌てふためくユイ
菱和は溜め息を吐いて、髪を掻き上げながら心底残念そうに呟いた
「‥‥‥‥あー‥‥俺もう嫁に行けねぇわ」
ユイは思わず菱和の顔を見た
まさかとは思いつつも、拓真は面白がってユイをからかい出した
「え!?もしかしてユイ、押し倒しちゃったの!?うわぁ、真っ昼間からそれヤバくね?」
「‥何!?俺何もしてないし!!アズも、“嫁”って何だよ!アズは男だろ!?」
「あー‥‥傷付いた。益々傷物にされた」
菱和はバスタオルで顔を覆った
「ははは!ユイ、やべぇことしちまったなー!どうやって責任とるんだー?」
「もおぉ、2人してからかうなよっ!!あのねー、‥‥‥‥」
ユイは漸く菱和から降り、慌てて拓真に弁解し始めた
44 Thinkin’ of …
菱和は室内の灯りを最小限にし、灰皿をリビングのテーブルに置いて、煙草に火をつけた
煙草を咥えたまま足を放り出し、ソファに寝っ転がる
寝室には、ベッドですやすやと眠るユイが居る
あわよくば、事に及ぶことが出来るかもしれないこの状況は、血気盛んな男子にとっては願ったり叶ったりだ
菱和も間違いなく血気盛んな青年なのだが、無防備なユイをどうにかしようという気は更々無かった
───草食男子かっての
寝室をちらりと見てから、ぼんやりと天井を仰いだ
煙草の煙がゆっくりと立ち上る
菱和は咥えていた煙草を手に取り、灰皿に灰を落とした
そしてまた、煙草を咥える
少し深く息を吸い、溜め息混じりに煙を吐いた
ユイが話し掛けてきたあの日以来、自分はすっかり“毒されて”しまった
死ぬほど退屈で嫌気がさしていた日常が、驚くほど新鮮なものになった
もしユイが話し掛けてこなければ、ずっとあのままだったかもしれない
鬱屈とした日々から抜け出す切っ掛けをくれた
自分の腕を欲してくれた
普通の日常を味わわせてくれた
惜しみ無く笑い掛けてくれた
俺は確かに退屈を手離して、ずっと望んでいたものを手に入れられた
俺はユイに、救われた
楽しいとか、嬉しいとか
そう感じるのは、気のせいでも錯覚でもなく、あいつがそばに居るから
でも、あいつが齎したものはそれだけじゃなかった
こんな気持ちを抱いたのは、生まれて初めてだ
最初は、この感情の正体が何なのか全然わからなかった
相手は男、同じ“もの”が付いている
普通ならこんな感情は有り得ない
でも、そんな事情を全て取り払い、一つの感情が凌駕する
ただの好意ではなく、もっと特別なもの
わざわざ隣に来ることも
騒がしい話し声も
屈託の無い笑顔も
ギターを奏でる指も
そこから紡ぎ出される音も
何の躊躇いもなく寄り添う旋律も
目配せしてくる視線も
美味そうに食う顔も
無防備な寝顔も
いつからか、“愛おしい”と思ってしまった
こんなことを本人に打ち明ければ、一体どんな反応を見せるのか
“からかってるだけ”とか“気が触れた”とか思われるかもしれない
云ったところで困らせるだけなら、無理矢理云う必要もない
そして、特別取り繕う気も無い
以前リサが云った言葉
『あんたがバイだろうがゲイだろうが』
いや、バイだのゲイだのというものとは違う
“男が好き”なんじゃなく、“好きになった相手がたまたまユイだった”というだけだ
別に、好きになったからってどうこうしようって気はない
“触れたい”と思ったことは行動に現れてしまったけど、それ以上のことをする気はない
少なくとも、理性が働いているうちは
ただ、ユイが、いつも在るがままで居てくれさえすれば
他には何も望まない───
壁に掛かっている時計に目をやる
時刻は深夜1時を回っていた
菱和は煙草を火消しに挿した
次第に微睡み、安らかに眠るユイのことを想いながら、ゆっくりと目を閉じた
43 “synesthesia”
明日は学校が休みだということもあり、ユイと拓真は菱和のアパートに長居している
音楽の話、学校の話、バンドの話
他愛もない会話が続く
「ヌーノってほんとヤバいよね!あれフルピッキングなんて絶対無理だから!」
「でも出来るようになったじゃん、それなりに」
「てかライヴビデオ観たらフルピッキングじゃなかったんだよね、それでも速過ぎて指死にそうになるけど!」
「うん、あれは死ねそうだわ。俺、あれ観てギターじゃなくてほんと良かったと思った」
「そう?てかドラムもヤバいじゃん」
「単純なことしかしてないし。あれについてくベースもなかなかヤバくない?」
「アズ、ピック使わないであれ弾いてるよね?」
「‥‥オルタネイトの方が多分良いんだろうけど、ピック嫌いなんだ」
「そういや前にも云ってたよね。何で?」
「ガリガリ煩ぇから」
「俺は指弾きのベースの方が好きだな」
「どっちかってと、俺も指弾きの方が好き!やっぱ音が柔らかいよね!」
「でも、あっちゃん音に拘る人だから、そのうち『ピック使え』って云ってくるかも」
「使わざるを得なくなったら、使うよ」
「無理なことは無理ってはっきり云って大丈夫だからね!」
「ん。そういうのはちゃんと云う」
「あっちゃんて、“苦い”くせに“甘い”から面倒臭いんだよね。ほんと、中身とそっくり!」
「チョコボンボン味だっけ。めっちゃイメージ通りなんだけど」
「ね!甘いのに苦いなんて意味不明だし!」
「大人っぽくて良いんじゃない?色気あるしなぁ、あっちゃんのギターって」
「そう、それだ!あっちゃんに“ボンボン”とか可愛過ぎるもん!」
菱和は2人の会話の端々にある一つのワードが気になった
音楽の話題に付随する、“味覚”
「──────“味”?」
「あ、そういやまだ云ってなかったっけ。俺特異体質で、音聴いたら“味”すんだよね!」
「‥‥‥‥‥‥‥‥いまいちよくわかんねぇんだけど」
「“共感覚”っていって、感覚的に音に風味を感じてるみたい。『聴覚と味覚を同時に感じる』、ってイメージかな」
拓真はユイの特異体質について首を傾げる菱和に説明をした
「‥‥キョウカンカク‥?」
「“シナスタジア”っていうんだって!ヌーノは芳香剤みたいな味で、ポール・ギルバートはカラフルなキャンディーの味!」
拓真は突っ込まずにはいられなくなる
「‥お前、芳香剤食ったことあんの?」
「無いよ!無いけど、なんか薔薇みたいな感じの味なの!」
「薔薇、食ったことあんの?」
「だから、無いってば!他に表現しようがないんだもん!てか、薔薇味のアイスとかあるじゃん!あんな感じ!」
「‥‥‥‥ふぅん‥‥変わってんな」
何となくイメージが出来た菱和が頬杖をついて頷くと、拓真は半ば呆れたような顔をする
「だろ?完全に色々拍車掛かってんだよ」
「“色々”って何だよ?」
「別にー。“変”って云われるの嬉しいだろ」
「嬉しいってか、わくわくする」
「ほーら、変わり者」
「変じゃないって!ちょっと変わってるだけ!」
「同じじゃん。どっちも“変”って漢字だろ」
「違うんだってば!あーもう、どうしたら伝わるかなぁ‥‥」
頭を掻くユイと、悪戯に笑う拓真
他愛もない夜が、まったりと更けてゆく
「もうこんな時間か。そろそろ帰ろー、ユイ───」
時計に目をやった拓真が立ち上がろうとすると、ユイはソファに突っ伏し、寝息を立てていた
「‥‥寝てるよ、おい」
「寝不足だっつってたもんな」
「ほんと、本能に忠実だな‥‥こいつさ、ライヴ前になるといーっつも引くくらい練習するんだよ。夜通しおんなじの弾きまくってんの。変態なんだよね」
「‥‥‥‥それ、あっちゃんも云ってた」
「あ、そう?ひっしーもそう思わない?」
「‥‥まぁ、よっぽど好きなんだなとは思うけど」
「ふふっ。云えてる。‥‥おいユイ、もう帰んないと‥‥」
「‥良いよ、起こさなくて。明日休みなんだし、このまま泊まらす」
拓真はユイの肩を揺すったが、菱和が制止する
「え‥‥そぉ?預けてっちゃっても大丈夫?」
「ん。構わねぇよ」
「ほんとに?じゃあ、明日迎えに来るわ。悪いけど、宜しく頼んます!」
「おう、気ぃ付けて」
拓真は早々に帰り支度をし、玄関へ向かった
菱和は玄関先で拓真を見送り、施錠した
時刻は間もなく日付を越えようとしている
夕餉の香りと会話の余韻が残る室内
ソファに突っ伏したままのユイから、静かに寝息が聴こえた
“好き”だと自覚した相手が、無防備に眠っている
ふわふわとした髪が柔らかそうに跳ね、童顔の無邪気な寝顔は単純に“可愛い”と感じられる
菱和はユイをベッドに運ぼうとし、担ぎ上げた
「‥‥軽っ」
すっかり眠りに入り脱力しているユイの身体は想像していたものよりもずっと軽く、思わず声に出てしまう
───華奢だな。この細っこい身体の一体どこにあの元気が詰まってんだか
そう思いつつ、菱和はユイを軽々と抱き、寝室のベッドへと運んだ
枕にゆっくりと頭を置くと、ユイが唸った
「‥んんー‥‥‥‥」
軽く口を開けて眠るユイ
音に味を感じる、蠱惑の口
菱和のベースの味も、この口内には広がっていた
菱和はそっと、ユイの唇を指でなぞった
───俺は、“何味”なんだろうな
何度か唇をなぞっていると、ユイは突然菱和の指を噛んだ
口に含み、甘噛をする
「‥って」
さほど痛みはなかったが、思わず声に出てしまう
軽く囓られた指をゆっくり抜くと、ユイはふにゃふにゃと寝言を云った
「‥‥も‥‥食えな、い‥‥‥‥───」
そして、また寝息を立てる
───夢ん中でまで食ってんのかよ
好意を寄せる相手の、無邪気な一面
菱和はくす、と笑い、ユイの身体にタオルケットを掛け、寝室から出て行った
42 Tandoori Chicken & Qeema Curry
週末を迎えた
何度か練習を重ね、“SCAPEGOAT”との対バンの話も双方が合意し、来るべき日に備えて練習を積む
オリジナル曲を3曲、SCAPEGOATとのジョイント用に2曲
ジョイント用の曲は『とにかく楽しめるように』をコンセプトに、難易度は高いがそれぞれのパートが際立つ楽曲を選んだ
「“CUPID'S DEAD”と“PLAY WITH ME”か、なかなか思い切ったな」
「でも、超楽しいじゃん!」
「まぁなー、どっちも最後の最後まで楽しめるよな」
「しかし、ユニゾンは俺より変態ギターの方がお誂え向きだな」
「変態じゃないから!2曲ともずっと弾きっぱなしだからちょっとでも触らないと指が鈍るの!」
「はいはい。っつうか俺歌わなきゃなんねぇし、ギターはお前と樹がメインでやれよ」
「うん、わかった」
「ベースはユウスケと相談して決めろ。お前らなら色付けることも出来るだろ」
「うん」
「ま、近いうちあいつらともミーティングするべ」
「ああ、それなら上田が『飯行こう』って云ってたよ」
「‥‥それもアリか。たー、樹にもあいつらに連絡しとけって云っとけな」
「うん、了解ー。じゃあ、“CUPID'S DEAD”から行くね」
乾いたスネアの音が響き、長く伸びたベースラインに妖しいアルペジオが滑り乗る
ギターとベースの粒が揃い出し、並走して『号外』を伝える
『天使は死んだ』と
飽きるほど弾いてきたフレーズに、意図も容易く重なるベース
兄である尊とも幾度となく弾き合った曲を、今度は菱和と共に奏でる
ユニゾンパートが埋め尽くす楽曲に、ユイはワクワクとゾクゾクが入り交じった変な感覚に陥った
“パープルヘイズ”が“回る”
それは麻薬よりも気持ち良いものかもしれないと、ユイは思った
***
スタジオを終え、店外に出る4人
ユイは伸びをして云った
「よっしゃー、アズんちでご飯だー!」
「めっちゃ腹減ったー。ひっしー、リクエストして良い?」
「ん、何食いたい?」
「鶏肉が食いたいっす。“ガッツリ”って感じの」
「“ガッツリ”ね。わかった」
「俺、これからバイトだから帰るわ」
3人で献立を考えて歩こうとする中、アタルは3人とは逆方向に向かおうとしていた
「‥‥ああそっか、そうだったね」
「え、何バイトとか入れちゃってんの?空気読みなよ」
「お前に云われたかねぇわこのチビ!!!金曜の夜は書き入れ時なんだよ!」
“金曜の夜は書き入れ時”
菱和はその言葉を聞いて、アタルに尋ねた
「‥‥あっちゃん、何のバイトしてんの?」
「バーテンダーだよ!お洒落なバーで、カクテル作ってんの!」
ユイはシェイカーを振る真似をした
「‥‥へぇ‥‥‥‥、めっちゃ似合う」
「ふっふっふ。だろ?お前、来年二十歳だよな?一回飲みに来いよ、ご馳走するぜ」
「うん、是非」
「じゃあ、またねー!」
「おー、お前らも気ぃ付けてなー」
アタルは足早に帰宅し、ユイと拓真は菱和の家へ向かった
***
幾度めかの、菱和の自宅での晩餐
大好きな音楽を良いだけ堪能した後の菱和の作る料理は、いずれも絶品だった
今宵も、期待せずには居られない
「少し時間かかっても大丈夫?」
「うん、勿論!どうせ明日学校休みだし、俺らも少しのんびりしてくわ」
「時間とか全然気にしないで!何時まででも待つから!」
「‥‥ん」
冷蔵庫の中身を物色し思案したところ、菱和はタンドリーチキンを作ることにした
余り物の挽き肉と玉ねぎでキーマカレーを、同じく余っていた野菜を使いサラダを作った
「めっちゃ良い匂い!」
「ふおぉー、贅沢にサラダ付きか。てか俺、キーマカレー大好き」
「俺もー!頂きまーす!」
スパイシーで香ばしい香りを放つタンドリーチキンは食欲を唆る
手が汚れることを全く気にせず、ユイと拓真は手掴みでチキンを頬張った
タンドリーチキンと同じくインド料理であるキーマカレーには、目玉焼きが乗っている
半熟の黄身を潰すと、とろりと流れ出る
『この組み合わせは反則だ』と、2人は大満足で夕餉を堪能した
菱和は早々に食事を済ませ、まだ食事中の2人を残し、キッチンでドリンクを作り始めた
ヨーグルトと牛乳、生クリームを撹拌し、黒砂糖を加える
再び撹拌して、氷の入ったグラスに注ぐ
「まだ腹に入りそうなら、どうぞ」
少しとろみのあるヨーグルトラッシーを、2人の皿の傍らに置いた
「何、これ?」
「ラッシー」
「‥‥うまあぁ!ヨーグルトだ!」
「甘さとか固さ、大丈夫?」
「うん、ちょうど良い。俺サラサラより少しドロッとしたラッシーのが好き。今日はインド尽くしかぁ。‥‥ひっしーって、形に拘るタイプ?」
「ん、形から入る。特に料理は」
「こういうのって、誰かから教わるの?」
「そういう時もあるけど、ここに住むようになってからはレシピ見て適当に」
「ふぅーん、てかレパートリー半端ないね!」
「‥‥やり出したらハマっちまって」
「得意料理ってあんの?」
「‥‥‥‥‥‥何だろ‥‥、考えたことなかったな」
「料理ってセンスだからなー。元々そういう才能あったのかもね。器用だし」
「‥‥‥‥別にフツーじゃねぇか」
「ひっしーって、お袋さん似?」
「‥‥多分」
「そっかぁ。お袋さんも、さぞや料理上手なんだろうなー」
2人はタンドリーチキンとキーマカレーを食べ終えた後、ラッシーをもう一杯お代わりし、漸く食事を終えた
いつものことながら、胃は八分目以上に膨れている
ユイと拓真は胃を落ち着かせる為、のんびりと寛いだ
絶品の料理で胃が満たされた後は、自然と眠気が襲ってくる
ユイは大きな欠伸をした
「くぁー‥‥‥‥」
「ユイー、洗い物ー。今日はお前の番だぞ」
「あー‥‥うん‥‥‥‥」
ユイは目を軽く擦り、眠たそうにしている
灰皿が置いてあるキッチンから煙草の煙を吐きながら、菱和がユイに声を掛けた
「‥‥寝不足?」
「‥‥うん、夕べ朝方まで弾いてたから」
「はー‥‥ほんとお前は見境無いんだから」
「毎日弾かなきゃ、腕が鈍っちゃうもん」
「んー、そうかもしんないけどさぁ‥‥」
「だいじょぶ、洗い物はちゃんとやるよ。アズ、御馳走様!超美味かった!」
「‥‥お粗末さんです」
また一つ欠伸をし、ユイは食器を片付け始めた
41 Fallin’ 【A SIDE】
少しずつ秋の風が混ざる、学校の屋上
ユイと拓真と菱和、そして上田は、最早すっかりいつものこととなってしまった『昼休憩は屋上に集う』習慣に倣い、毎日のように一緒に過ごした
輪になって話し込むユイと拓真と上田を、菱和がぼーっと景色を眺めながら静観している
最早、これも見慣れた構図
「どうだったん?スタジオ」
「いやー、超楽しかったね。全員大興奮!ひっしーのベース、ほんとヤバいわ」
「そりゃようござんしたねぇ。俺もお前らの曲聴くの楽しみなんだけど!次のマンスリー出るっしょ?」
「一応その予定だけど、あっちゃんが『曲が間に合わなかったらその次にする』って。でも、早くライヴ演りたくてウズウズしてるよ!」
「ははっ!じゃあさ、近いうち対バンしよーぜ!」
「そっか、演るって云ってたもんな。久々にやりますかー」
「おー。俺らも楽しみにしてんだぜ、お前らと同じライヴ出んの!」
「じゃあさ、合同ミーティングしなきゃね!」
「そうねー。あ、皆で飯食い行っか。この前行けんかったし」
「行く行くー!」
頬杖をついてぼーっとしている菱和の横に、ユイが並んできた
にこにこと、菱和に笑い掛ける
「‥‥楽しみだね!」
「ん」
菱和は怠そうに生返事をした
今までもそういったことは何度もあったが、“菱和はこういうキャラ”だと思っていたので、ユイは否定的に受け取りはしなかった
無愛想で無口な菱和の横に、空気が読めなくて騒がしいユイが並んでいる
一見相容れないように見える2人だが、お互いを補うように上手くバランスが取れていると、拓真も上田も思っていた
「なんか、コーラ飲みてぇな。拓真、コンビニ行くべ」
「一人で行けば良いじゃん」
「ついてきてよぉ、たくちゃあん‥‥俺ウサギさんだから、淋しいと死んじゃうの‥‥」
「じゃあいっそ召されろ。あと、気持ち悪い」
「んなこと云ってー。俺のこと世界一好きでしょ!ほら、チューしたげっから!」
「うげっ!やめろぉ!!」
上田は拓真に絡み出し、あれよあれよという間に屋上から出て行った
静かに、穏やかに流れていく時間
少しずつ秋の匂いが籠る風が、残暑を掻き消す
会話が無くとも、ユイは菱和が隣に居るだけで満足し、菱和もまた、口煩く話し掛けてくるユイを受け入れていた
「あ、もうそろ予鈴鳴る。教室戻ろ!」
「‥‥‥‥今日は、サボるわ」
「‥‥へ!?」
「なんか、かったりぃ」
「えー‥‥‥‥」
菱和は空を仰いで、軽く溜め息を吐いた
ユイは思い立ち、ぱん、と手を叩く
「‥‥よし!じゃあ俺も!」
「‥‥‥‥良いのかよ」
「うん!たまには良いでしょ。次の授業政経だし、俺もかったるい!」
「‥‥そ」
予鈴が鳴り、静かな屋上が益々静かになったように感じる
「なんか、ドキドキする‥‥」
「サボったこと無いのか」
「無いわけじゃないけど、久し振り過ぎて。皆授業してんのに、っていうか本来俺もその筈なのに。なんか変な感じ」
「‥‥案外悪くねぇだろ」
「‥うん!アズと一緒だしね!」
そう云って、ユイは菱和に笑い掛けた
ふと、菱和の動きが止まる
行き交う喧騒を置いてけぼりにしたまま、鼓動が聴こえる
心臓がザワザワとし出し、息苦しさを感じる
いつも以上に早い鼓動が、いつも決まって騒ぎ出す
そう、こいつが俺に笑い掛けたときに限って───
何なんだろう、これは
何でこいつは、俺にこんな顔が出来るんだろう
見る度に、変な気分になる
この気持ちは、一体何なんだろう
こいつの笑顔は──────
それがどういうものであるかわからない
今までに抱いたことの無い、不可思議な、複雑な、そして単純な感情
“触れてみたい”
衝動を抑え切れず、菱和は手を伸ばした
菱和の大きな手が、ユイの頬を包む
ユイは若干肩を竦めたが、自分を見つめる漆黒の目に捕らわれる
怪訝な顔をし、首を傾げた
「───‥‥‥‥アズ‥‥?」
───ああ、そっか
「んむっ!?」
頬を抓られ、変な声が出た
「‥‥‥‥、変な顔」
「なっ、何だよ!?そっちが抓ってきたんだろ!」
ユイは慌てて菱和の手を払い除ける
初めて触れたユイの肌
“触れたい”なんて、思ったこともなかった
何でそんなことをしたくなったのか、全くわからなかった
でも、確かに感じたかった
こいつの存在と、この感情が何なのかを
笑顔のみならず、ユイが見せる表情や仕草
ユイを形作っている全てのもの
その全てが、いつしか自分の中で特別なものになっていることに気付く
頬を抓ることで誤魔化すことしか出来なかったが、菱和は自らの心中にあった一つの感情をゆっくりと自覚した
“好き”なんだな、俺。こいつのこと───
40 40 aglio, olio e peperoncino
スタジオを後にした4人は、だらだらと帰路につく
空は暗くなっており、2時間ほど練習をした4人はすっかり空腹になっていた
「腹減ったなー、なんか食ってくか」
「賛成ー!」
「あっちゃん、奢り?」
「んなわけねぇだろボケ」
「‥‥何なら、またうち来るか?そしたらあっちゃんも、余計な金使わなくて済むだろうし」
菱和は前回3人でセッションをしたときと同様に、また夕飯を振る舞うつもりで云った
ユイは目をキラキラさせて喜んだ
「えー、またなんか作ってくれるの!?行く行くー!!」
「そういや、『料理上手い』っつってたっけ」
「病み上がりなのに、大丈夫?」
「ん、もう全然平気」
「前から思ってたけど、お前タフだよなぁ」
「‥‥自分でもそう思います」
「何ヶ月振りかな、アズの晩飯!」
3人は、菱和の自宅に向かうことにした
***
「なんか食いたいもんある?」
「んー‥‥今猛烈にしょっぱ辛いもん食いてぇんだよな」
「“しょっぱ辛い”‥‥‥‥ペペロンチーノとかで良い?」
「お、パスタか!良いねぇ!」
「お前らは?」
「俺、何でも良い!」
「パスタかー、カルボナーラが絶品だっただけに楽しみだなー」
3人は談笑しながら、菱和が料理を終えるのを暫し待つ
程なくして、オリーブオイルと大蒜が絡む香りが漂ってきた
ガーリックチップが油で跳ねる音が聴こえ、3人の食欲はより一層唆られた
ユイと拓真が前回のカルボナーラを大絶賛していたのは知っているが、未だ菱和の料理を口にしたことのないアタルは、果たして本当に美味いのかどうか半信半疑だった
アタルのお眼鏡に敵うかどうかはまだ定かではないが、菱和は怠そうに煙草を喫いながらさくさくと調理を進めていった
「頂きます!」
「‥‥どうぞ」
ユイと拓真は揃って手を合わせ、ペペロンチーノを口にした
前回同様、2人は菱和の味に絶賛した
「‥うんまぁ!!!サイコー!!」
「はー、塩加減絶妙だわ!今日もお代わりある?」
「あ、俺も俺も!」
「ん、多目に作ったから」
「‥ラッキー!」
2人の様子を見て、アタルもパスタを口に運んだ
数回咀嚼した後、その手が止まる
「‥‥あっちゃん、どしたの?」
ユイはパスタを頬張ったまま話し掛けた
どこか様子のおかしいアタルに、菱和も声を掛けた
「‥‥口に合わなかったすか‥?」
アタルは口の中の物を飲み込み、驚愕の顔で菱和を見た
「‥‥美味ぇ。‥‥‥‥多分今まで食った中でいちばん美味ぇ‥‥。お前、マジ何者?」
アタルの一言に安堵し、菱和は少しだけ口角を上げた
「‥‥フツーすよ」
3人は、瞬く間に目の前のペペロンチーノを平らげ、揃って菱和に“お代わり”を要求した
「スタジオの後にアズの料理食えるなんて、サイコーだね!」
「ああ、至福のときだなー。良いだけ演った後のこの味は反則だわ、ほんと美味いもん」
「‥‥お粗末様です」
「ねぇ、もしアズが良ければ、これからスタジオ帰り飯食ってっても良い?」
「それヤバいな。俺もその案賛成ー」
「‥‥あぁ。別にスタジオ終わりじゃなくても、飯くらいいつでも」
「ほんと!?じゃあ、今度から材料費払うね!」
「良いよ、要らねぇ」
「それは駄目!!ずぇーっっったい駄目!」
「そうそう、今日からちゃーんと払います」
「‥‥わかった」
「うん!ご馳走様でした!」
そう云って、ユイと拓真は食器を片付け始めた
話し合いの後、今回は拓真が後片付けをすることになった
早々に洗い物を済ませ、ユイと拓真は菱和の部屋で雑誌を読みながら談笑に耽っていた
菱和はキッチンの換気扇をつけ、煙草を喫い始めた
アタルもその横に並び、自分の煙草に火をつける
「お前、面倒見良いのな」
アタルは煙草を吹かしてそう云った
菱和がどういう人間なのか、関わるようになってからいちばん日が浅いアタルは未だわかりかねていたが、スタジオで時間を共にしてから現在までに抱いた菱和の印象を本人に伝える
菱和は俯きながら話し出した
「‥‥‥‥何が良いのか、どうすりゃ普通なのか、正直まだわかんなくて。でも自分が“楽しい”とか“これが良い”って思ったら、結局何でも良いのかなって。‥‥それだけす」
“コミュ障”と云いつつも自分の話をし出す菱和に、アタルは煙草を咥えたまま面食らった
幼い頃から一緒に過ごしてきたユイたちは既に関係性が構築されており、友達の家で食事をすることは決して特別なことではなかった
“これから”は菱和にとっても普通のことになってゆくのだろうが、“これまで”には考えられなかったこと
無表情で無愛想で無口
自他共に認める菱和の印象は一見冷たく見えるのだが、元々根は真面目で、年上を敬いアタルに敬語を使うことからもそれが窺い知れる
間違ったことを赦さず、硬派なところもある
菱和の担当であるベース
周りの音を聴き、決して邪魔をせず、地にしっかりと根を下ろし支える
目立たず地味ながらも重く厚いその音はバンドには必要不可欠であり、絶対に無くてはならないものだ
───“ぶっとくて、芯が強い”
菱和に抱いた印象と、パートである楽器が、アタルの頭の中でぴったりと重なった
「お前って、ベースみてぇな奴だな」
アタルは菱和の顔を覗き込んでそう云った
「‥‥どうせ学校でもあんな感じなんだろ、あいつら。うるせぇガキ共だけど、宜しく頼むぜ」
そして穏やかに笑い、菱和の肩を軽く叩いた
誰かに必要とされることなど皆無だと思っていたが、いつの間にか自分を頼ってくれる人間が何人も現れた
“バンド仲間”とは、実に不可解なもの
同じ音楽を奏でるという共通の目的で結ばれている関係性に過ぎない筈なのだが、そこから垣間見える人間性は、バンドを続けていく中で重要なものになっていく
まだお互いをよく知らない2人だが、何とかやっていけそうだと無意識のうちに確信し、喫いかけの煙草をゆっくりと味わった