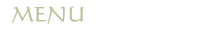NEW ENTRY
[PR]
113 “RIOT”
ユイは茹でダコになる前にと湯槽から上がり、菱和の洗髪をすることにした
下半身が見えるか見えないかのギリギリまで上がったところで、ユイは菱和の視線に気付いた
「‥‥見ないでよ。恥ずかしいから」
「‥“そこ”は見てねぇよ」
「も、良いから下向いててってば‥!」
「はいはい。終わるまでずっと目ぇ瞑ってます」
菱和は湯に浸かったまま肩から上を湯槽から出して凭れ掛かり、頭を下に垂らした
ユイはそわそわしつつ股をタオルで隠して椅子に座り、シャワーで菱和の髪を濡らしていった
「‥メッシュの色、だんだん落ちてきたね」
「あー‥‥‥‥。‥‥いい加減もう染めねぇと」
「これ、自分でやったの?」
「うん」
「へぇ‥‥すげぇ」
「簡単だよ、こんなの」
「そうなの?‥‥‥‥アズの髪って、真っ黒だね」
「だろ。なんか重くてつまんねぇからメッシュ入れたんだけど」
「真っ黒だから却って映えるよね。次は何色にする?」
「‥また同じ色で良いかな」
「ちょっと奇抜な色にしてよ、ピンクとか!」
「‥‥似合うと思ってんの?」
「思ってる!絶対似合う!」
「あっそ‥‥」
菱和は呆れたように生返事をしたが、ユイは楽しそうに洗髪を進めた
宣言通り、菱和はユイが洗髪を終えて湯槽に浸かるまで目を瞑ったままでいた
***
先に着替えを済ませた菱和は濡れた髪を軽くタオルで拭いてから一本に纏め、煙草を喫い始めた
項に垂れる水滴が、いつもの気だるい様子と相まって妖艶な雰囲気を醸し出す
髪を纏めている菱和を見るのは初めてのこと
いつもと違う印象に、ユイは若干照れたようにした
菱和は煙草を喫い終えると冷蔵庫から麦茶を出してコップに注ぎ、一口飲んでからユイに差し出した
「飲む?」
「ありがと。‥‥あ。ねぇ、さっきCD聴いてて、ジャケットがないの見つけたんだけど。結構古いやつ」
「?‥‥何だ、どれだろ」
ユイは足早に楽器が置いてある部屋へ向かい、件のものを取って戻ってきた
「これ」
「ああ‥‥それ、我妻のバンド」
「店長‥の?」
「あいつのプロ時代の」
「え!店長ってプロだったの!!?」
「‥‥知らなかったんだ」
「初めて聞いた!」
「もう解散して暫く経つけど、結構人気あったっぽい。これはデモだから、一応“レア”物だって自慢してた。‥聴いてみる?」
「うん!聴きたい!」
二人は楽器部屋に行き、我妻がバンドをやっていた時代の曲を聴くことにした
ケースを開けると、“RIOT demo”という字と共に曲名が走り書きされているCDRが入っていた
「‥りお、っと‥‥?バンドの、名前?」
「“らいおっと”。“暴動”って意味。でも、“バカ騒ぎ”って意味もあんだって。我妻は、そっちの方が気に入ってこの名前にしたって」
菱和がデッキにCDをセットし、ユイは再生されるのをわくわくしながら待つ
全てのパートが一斉に音を出す
出だしから歌が始まるとは思っていなかったユイはのっけから肩を竦めて驚き、音が耳に届くと同時に背筋に悪寒が走り、口内にぶわ、と味が広がった
頭に、耳に、口に
音を感じ取る器官の全てが、我妻のバンドの曲にあっという間に引き込まれる
お洒落で繊細な印象のギター
ツボを押さえつつ滑らかに動くベース
軽やかに全体を纏めるドラム
そして、生き生きと、朗に、全てを解放し歌うヴォーカル
一曲目は、爽やかなアップテンポの曲だった
楽器隊の他に、間奏部分にピアノと裏声のコーラス
軽くエコーの掛かる、奏者の感情を最大限に表現したギターソロ
風が吹き抜けて花びらが舞う花畑の情景が思い浮かぶと共に、フルーツ味のドロップのような甘く賑やかな味覚が口一杯に溢れる
ユイの口の中は条件反射で分泌された唾液がじわじわと出ていた
間延びしたギターの音が途切れると溜まった唾液を飲み込み、軽く唇を拭い、気が抜けたように感想を漏らす
「‥‥‥‥すげぇ‥‥鳥肌立っちゃった」
「良いよな。やりたいこと自由にやってる感じで」
「うん、どのパートもカッコイイ!もっと早くに知ってたかったなぁ‥‥‥‥勿体無いな、何で解散しちゃったんだろ‥‥」
菱和は一旦CDの再生を止め、低い声で呟いた
「‥‥メンバーの誰かが、亡くなったらしい。確か、ヴォーカルだったかな」
「え‥」
「『このヴォーカルが居ないバンドは有り得ない』って、メンバー全員一致で解散決めたんだってさ。でも、ギターの人もドラムの人も音楽関係の仕事してるって。我妻もそうだけど」
「そうなん、だ‥‥」
その声は終始明るく爽やかだったが、時折切なく、甘く、妖艶な雰囲気もあった
その全てが、鮮明に耳に焼き付いて離れない
今までユイが聴いてきた数々のバンドの中でもトップクラスと讃えたくなる程のそのヴォーカルに、“天才”と云っても過言ではない才能を感じた
若くしてヴォーカルが亡くなり、惜しまれつつもバンドは解散
人生の全てを音楽に捧げるつもりでいたバンドマンにとっては、苦渋の選択だったに違いない
拓真も、アタルも、そして菱和も、Hazeになくてはならない存在であり、バンドメンバーである以前に幼馴染みで、更に菱和とは恋仲だ
もし、自分が我妻と状況になったら───そんなことは考えられないし、想像したくもなかった
───ほんと、リアルタイムで聴いてたかったな‥‥
『あんたたちの音は、永遠に俺のもんだ』
我妻たちが奏でていた音は一生涯、亡くなったヴォーカルだけのものになった
ヴォーカリストとしてもバンドとしても、なんとも贅沢で残酷な現実
いつも笑顔で迎えてくれる楽器屋の店主、我妻
その笑顔の裏の哀しい過去を知り、ユイは少し胸が苦しくなった
- トラックバックURLはこちら